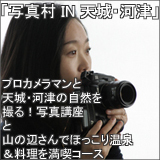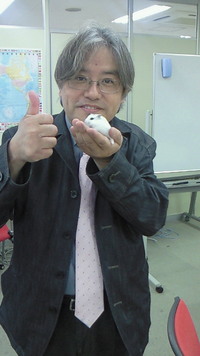フライング・ファミリー(浮遊する家族)
2007年10月11日
何日か前の日経新聞の記事です。
皆さんはどう思われますか?少し長文ですが、ちょっと面白い内容だと思いますのでお時間ございましたらお読みください。
「犯罪の温床と批判される出会い系サイト。子供が被害にあう例も目立ち、問題になっている。ただ世界を見渡せば、見知らぬ人同士を結びつける「マッチングサイト」は静かに増加。透明性を高めながら、新領域にも広がっている。
出版社勤務の相馬茜(仮名、27)は結婚を決めた。相手(33)との話はとんとん拍子。一月にメールを交換し二月に対面、「一ヵ月後にプロポーズされた」。
出会うきっかけは米系結婚情報サイト「マッチ・ドット・コム」。身長、年収、趣味などを隠さず入力。相手に望む条件を設定したら、まるで検索結果のように候補者が並んだ。登録できるのは18歳以上の未婚者だけ。
「互いに結婚が目的だから無駄がない」。
相馬は実際に相手と会って人柄などを互いに確認し、人生の伴侶をたぐり寄せた。
長く神聖なものとされてきた結婚。そんな聖域にもネット文明の波は及ぶ。
結婚サイトは世界に爆発的に増加。最大手のマッチ・ドット・コムでは年間40万組が家族として「成約」、日本でも84万人が登録、心理的抵抗は薄れる。
文明の進展は、社会の基本単位である家族のかたちを変える。農業文明では農作業を営む大家族が形作られた。工業文明では工場勤務が広がり、核家族化が進んだ。コミュニケーションの姿を一変させるネット文明も例外ではない。
「高知の果物もらったよ。にほひのよかー」
「おいしくてよかったね」
「うちにも買ってきてよ」--。
画面の中で会話が弾む。
高知に単身赴任する下川裕太(仮名、47)は家族内ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で雑談を楽しむ。
参加するのは千葉に住む妻と三人の子供、佐賀の義妹夫婦の計7人だ。
本当は顔を見て話したいけれど住まいも生活時間も別。「どうにかならないか」と思っていたらナノティ(静岡県焼津市)という会社が運営する家族向けSNSが目にとまった。登録した家族ならいつでも好きなことを書き込める。夜遅く帰ってもパソコンを立ち上げれば話題を共有できる。
日本の家族は今年、大きな転換点を迎える。少子高齢化や晩婚が進み、一人暮らしをする単独世帯の数が、夫婦と子供で住む標準世帯を抜くのだ。
放っておけばとまらぬ分裂。
「分散家族」をつなぎとめるのにネットが一役買う。
「足を机に乗せてたわよ。甘いんじゃない」。
東京に住む田中菜月(仮名、35)は娘(4)の癖を実母(65)に指摘された。同居しているわけではない。広島で暮らす母はパソコンから保育園のカメラに映る孫を毎日のように眺めている。
同園運営のポピンズコーポレーションは働く母親の不安を和らげようとカメラを導入した。専用ホームページに識別番号などを入れると園児の姿が映る。ところがふたを開けると「生きがいができた」など祖父母の反響が大きく驚いた。高齢化社会の裏側で、三世代がネット上でつながる”擬似大家族”が増える。
家族に新たな意思疎通の手立てをもたらしたネット。しかし「つながりやすさ」には落とし穴も潜む。
「えっ、また?」。
坂本里香(仮名、44)は五月、メール送信者の名前を見て驚いた。
三年前に別れた元カレ。誕生日になるとなぜかメールを送ってくる。覚えているというアピールなのか旧友に声をかける感覚なのか。交遊の痕跡が相手のパソコンに残り、こちらは忘れたいのに不意に向こうから手を伸ばしてくる。
自分の言いたいことだけを一方的に「送信」できるネット時代。
浮遊する家族が本当に「受信」しているかは分からない。それでも離ればなれの人たちは、ネットに新時代の「一つ屋根の下」の願いを託す。
歴史家アーノルド・トインビーは
「社会とは人間の間に張り巡らされた網目全体のこと」と指摘した。
ネットという網目の上で離合集散を繰り返すネット文明の家族たち。
きょうもメールが飛び交う。(敬称略)」
最後のトインビーの言葉は、私が以前お話しました「ITの今後10年~30年の動向について ④」に書いた内容に重なります。
皆さんはいかがお考えになりますでしょうか?
よろしかったらコメントください。ではまた。

皆さんはどう思われますか?少し長文ですが、ちょっと面白い内容だと思いますのでお時間ございましたらお読みください。
「犯罪の温床と批判される出会い系サイト。子供が被害にあう例も目立ち、問題になっている。ただ世界を見渡せば、見知らぬ人同士を結びつける「マッチングサイト」は静かに増加。透明性を高めながら、新領域にも広がっている。
出版社勤務の相馬茜(仮名、27)は結婚を決めた。相手(33)との話はとんとん拍子。一月にメールを交換し二月に対面、「一ヵ月後にプロポーズされた」。
出会うきっかけは米系結婚情報サイト「マッチ・ドット・コム」。身長、年収、趣味などを隠さず入力。相手に望む条件を設定したら、まるで検索結果のように候補者が並んだ。登録できるのは18歳以上の未婚者だけ。
「互いに結婚が目的だから無駄がない」。
相馬は実際に相手と会って人柄などを互いに確認し、人生の伴侶をたぐり寄せた。
長く神聖なものとされてきた結婚。そんな聖域にもネット文明の波は及ぶ。
結婚サイトは世界に爆発的に増加。最大手のマッチ・ドット・コムでは年間40万組が家族として「成約」、日本でも84万人が登録、心理的抵抗は薄れる。
文明の進展は、社会の基本単位である家族のかたちを変える。農業文明では農作業を営む大家族が形作られた。工業文明では工場勤務が広がり、核家族化が進んだ。コミュニケーションの姿を一変させるネット文明も例外ではない。
「高知の果物もらったよ。にほひのよかー」
「おいしくてよかったね」
「うちにも買ってきてよ」--。
画面の中で会話が弾む。
高知に単身赴任する下川裕太(仮名、47)は家族内ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で雑談を楽しむ。
参加するのは千葉に住む妻と三人の子供、佐賀の義妹夫婦の計7人だ。
本当は顔を見て話したいけれど住まいも生活時間も別。「どうにかならないか」と思っていたらナノティ(静岡県焼津市)という会社が運営する家族向けSNSが目にとまった。登録した家族ならいつでも好きなことを書き込める。夜遅く帰ってもパソコンを立ち上げれば話題を共有できる。
日本の家族は今年、大きな転換点を迎える。少子高齢化や晩婚が進み、一人暮らしをする単独世帯の数が、夫婦と子供で住む標準世帯を抜くのだ。
放っておけばとまらぬ分裂。
「分散家族」をつなぎとめるのにネットが一役買う。
「足を机に乗せてたわよ。甘いんじゃない」。
東京に住む田中菜月(仮名、35)は娘(4)の癖を実母(65)に指摘された。同居しているわけではない。広島で暮らす母はパソコンから保育園のカメラに映る孫を毎日のように眺めている。
同園運営のポピンズコーポレーションは働く母親の不安を和らげようとカメラを導入した。専用ホームページに識別番号などを入れると園児の姿が映る。ところがふたを開けると「生きがいができた」など祖父母の反響が大きく驚いた。高齢化社会の裏側で、三世代がネット上でつながる”擬似大家族”が増える。
家族に新たな意思疎通の手立てをもたらしたネット。しかし「つながりやすさ」には落とし穴も潜む。
「えっ、また?」。
坂本里香(仮名、44)は五月、メール送信者の名前を見て驚いた。
三年前に別れた元カレ。誕生日になるとなぜかメールを送ってくる。覚えているというアピールなのか旧友に声をかける感覚なのか。交遊の痕跡が相手のパソコンに残り、こちらは忘れたいのに不意に向こうから手を伸ばしてくる。
自分の言いたいことだけを一方的に「送信」できるネット時代。
浮遊する家族が本当に「受信」しているかは分からない。それでも離ればなれの人たちは、ネットに新時代の「一つ屋根の下」の願いを託す。
歴史家アーノルド・トインビーは
「社会とは人間の間に張り巡らされた網目全体のこと」と指摘した。
ネットという網目の上で離合集散を繰り返すネット文明の家族たち。
きょうもメールが飛び交う。(敬称略)」
最後のトインビーの言葉は、私が以前お話しました「ITの今後10年~30年の動向について ④」に書いた内容に重なります。
皆さんはいかがお考えになりますでしょうか?
よろしかったらコメントください。ではまた。
今日は久しぶりに何もせず・・・・
ずいぶん久しぶりのアップになっちゃって・・・・
今年は太宰治の生誕100周年です
信じたくはないが、戦争を起こしたい人がいるんじゃないのか!
蔵王の自然
ホンダ、F1撤退・・・・ほんとに寂しいねえ
ずいぶん久しぶりのアップになっちゃって・・・・
今年は太宰治の生誕100周年です
信じたくはないが、戦争を起こしたい人がいるんじゃないのか!
蔵王の自然
ホンダ、F1撤退・・・・ほんとに寂しいねえ