「生き方」の記事一覧
スポンサーサイト
イチローのWBCへの思いにすごく惹かれるものを感じます
イチローが本当に素直に純粋にWBCへ「SAMURAI JAPAN」を引っ張っていこうとしている姿に、見ているこちらもとても熱い気持ちを感じています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000002-spn-spo
彼はやはりすばらしい人間ですね。とってもピュアなイチローに感動すら覚えます。
まさに侍そのもの。
なんだかこちらも、よーしやったるか!という気にさせられます。
ケガを恐がってWBCへの出場を見合わせるプロ野球選手の気持ちも、その現実的な側面を考えると分からないでもないですが、しかしながら、イチローのこの日本人としての矜持を示そうとしている姿に、同じ日本人として、ジーンと熱いものを感じざるを得ません。
今度のWBCをチャンピョンとしての守りの姿勢ではなく、「もう一度奪い取ってやる」と言ったイチローの言葉に、こちらもカーッと燃え上がるものを感じます。
日本人全員でイチローを、SAMURAI JAPANを応援して、一緒にWBCを奪いとってやりましょう!
フレーフレー!イチロー!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000002-spn-spo
彼はやはりすばらしい人間ですね。とってもピュアなイチローに感動すら覚えます。
まさに侍そのもの。
なんだかこちらも、よーしやったるか!という気にさせられます。
ケガを恐がってWBCへの出場を見合わせるプロ野球選手の気持ちも、その現実的な側面を考えると分からないでもないですが、しかしながら、イチローのこの日本人としての矜持を示そうとしている姿に、同じ日本人として、ジーンと熱いものを感じざるを得ません。
今度のWBCをチャンピョンとしての守りの姿勢ではなく、「もう一度奪い取ってやる」と言ったイチローの言葉に、こちらもカーッと燃え上がるものを感じます。
日本人全員でイチローを、SAMURAI JAPANを応援して、一緒にWBCを奪いとってやりましょう!
フレーフレー!イチロー!
オバマ氏の勝利宣言(歴史に残る名演説)
言霊が人を動かす典型だと思います。
皆さん、その言葉の力をご覧ください。
http://news.goo.ne.jp/article/gooeditor/world/gooeditor-20081105-05.html
さあ、モーニングセミナーへ行ってこよっと。
皆さん、その言葉の力をご覧ください。
http://news.goo.ne.jp/article/gooeditor/world/gooeditor-20081105-05.html
さあ、モーニングセミナーへ行ってこよっと。
わが人生を語ってまいりました
うまく伝わったでしょうか?
本日の三島市倫理法人会のモーニングセミナーで、講師を勤めさせていただきました。
40分くらいの短いお話の中で、かいつまんで・・・・とくに最後の方は駆け足になってしまって・・・・・うまく伝わりましたでしょうか?
三島市倫理法人会の皆様、どうもありがとうございました。
私の拙いお話をしっかり聞いていただき、誠に感謝申し上げます。
私もいろんなところでお話する機会はあるのですが、意外にも・・・というか自分にとっても意外ですが・・・・自らの人生をお話することは今までほとんどありませんでした。
そういう意味では、自分にとっても新鮮で、少ししゃべりずらかったのですが、勉強になりました。
今後、またどこかでお話する機会があれば、もう少しうまくお話できるでしょう。
とまれ、本日はどうもありがとうございました。
本日の三島市倫理法人会のモーニングセミナーで、講師を勤めさせていただきました。
40分くらいの短いお話の中で、かいつまんで・・・・とくに最後の方は駆け足になってしまって・・・・・うまく伝わりましたでしょうか?
三島市倫理法人会の皆様、どうもありがとうございました。
私の拙いお話をしっかり聞いていただき、誠に感謝申し上げます。
私もいろんなところでお話する機会はあるのですが、意外にも・・・というか自分にとっても意外ですが・・・・自らの人生をお話することは今までほとんどありませんでした。
そういう意味では、自分にとっても新鮮で、少ししゃべりずらかったのですが、勉強になりました。
今後、またどこかでお話する機会があれば、もう少しうまくお話できるでしょう。
とまれ、本日はどうもありがとうございました。
日本の教育が変わる!(2人の巨人が出会った日!)
先日、大変うれしい出会いがありました。(というか、私がその介添え役をいたしました。)
弊社は、星槎グループという超巨大な教育グループと提携しています。
星槎グループは宮澤保夫という私立高校の教員が、1972年に創った塾からはじまりました。http://www.seisagroup.jp/menu1_group/index.html
そして、現在、星槎グループは、高校はもとより幼稚園、大学、中学、福祉専門学校、医療法人、農業生産法人、数々のNPO法人・・・・・。超巨大な教育グループに発展しています。
そしてそして、いよいよ教育事業として、最後に残った小学校を今度創ります。
これらすべてを、宮澤保夫という一人の人間がトップとして活動し、創り上げました。
日本の教育史において、一人の人間が、幼稚園~小学~中学~大学まで創り上げた例はありません。
宮澤保夫がはじめてとなります。
そういう意味では、教育界の超巨人です。そして、私は数年前に宮澤保夫会長にお会いし、その教育理念にほれ込み、弊社の経営理念ととても似通ったものを感じ、提携させていただきました。
それ以来、会長とは大変懇意にさせていただいております。いつもお話すると大変感動する話が多く、勉強になり刺激になり、私がひそかにお手本にさせていただいている唯一の人物です。大変尊敬しております。
彼はまさしく日本の教育を大きく変革できる唯一の人物である、と私は思っております。
その彼に、今回、これまた大変大きな人物をお引き合わせすることができました。
阿部進先生、そう、カバゴン先生、その人です。
先日来より、カバゴン先生とお会いしお話するたびに、この方もものすごくパワフルで、超巨大な人物であることは、すでにこのブログでもたびたびお話して参りました。http://katsu.i-ra.jp/e17575.html
http://katsu.i-ra.jp/e29323.html
http://katsu.i-ra.jp/e30721.html
私が宮澤会長にカバゴン先生をお引き合わせしたかったのは、両者の教育への熱い思い、そして星槎グループがこれから創る今までにない新しい小学校に、カバゴン先生の想いを生かしていただきたかったからです。
今回のお二人の超巨人の出会いは、私がいままで生きてきた中で、味わったことがない、震えがくるほどの感動的なものでした。
お二人とも非常に高い感性レベルを持っていることから、出会いの密度が常人とはおよそ及びがつきません。
交わす一つの言葉から瞬時にいくつもの内容が相手に伝わり、まさに一つを聞いて十を知るそのものでありました。
私はこの場に居れることがもううれしくてうれしくて・・・・。なんだか涙が出てきて止まりませんでした。
現在、星槎グループは大磯に超広大な土地を取得し、今までだれも見たことのない、広大な教育都市を建設する予定です。
少しお話を聞いていますが、もう本当に想像を絶する計画です。
そして、この計画の中に、カバゴン先生の熱い教育への想いが加味されます。
もう想像しただけでわくわくどきどきするようなお話です。
そして、その仲立ちをたまたまさせていただいたのが私であったことに、本当に本当に感動しています。
きっとこのお二人の出会いが、これから大きく起こるであろう教育の革命的変化の嚆矢となるでしょう。
教育は大きく変わる!変わらねばならない! そういう思いを強く強く感じた日でありました。
すばらしい出会いに感謝!そしてこの運命に乾杯です。
子供たちの未来に思いを馳せて。ではまた。
弊社は、星槎グループという超巨大な教育グループと提携しています。
星槎グループは宮澤保夫という私立高校の教員が、1972年に創った塾からはじまりました。http://www.seisagroup.jp/menu1_group/index.html
そして、現在、星槎グループは、高校はもとより幼稚園、大学、中学、福祉専門学校、医療法人、農業生産法人、数々のNPO法人・・・・・。超巨大な教育グループに発展しています。
そしてそして、いよいよ教育事業として、最後に残った小学校を今度創ります。
これらすべてを、宮澤保夫という一人の人間がトップとして活動し、創り上げました。
日本の教育史において、一人の人間が、幼稚園~小学~中学~大学まで創り上げた例はありません。
宮澤保夫がはじめてとなります。
そういう意味では、教育界の超巨人です。そして、私は数年前に宮澤保夫会長にお会いし、その教育理念にほれ込み、弊社の経営理念ととても似通ったものを感じ、提携させていただきました。
それ以来、会長とは大変懇意にさせていただいております。いつもお話すると大変感動する話が多く、勉強になり刺激になり、私がひそかにお手本にさせていただいている唯一の人物です。大変尊敬しております。
彼はまさしく日本の教育を大きく変革できる唯一の人物である、と私は思っております。
その彼に、今回、これまた大変大きな人物をお引き合わせすることができました。
阿部進先生、そう、カバゴン先生、その人です。
先日来より、カバゴン先生とお会いしお話するたびに、この方もものすごくパワフルで、超巨大な人物であることは、すでにこのブログでもたびたびお話して参りました。http://katsu.i-ra.jp/e17575.html
http://katsu.i-ra.jp/e29323.html
http://katsu.i-ra.jp/e30721.html
私が宮澤会長にカバゴン先生をお引き合わせしたかったのは、両者の教育への熱い思い、そして星槎グループがこれから創る今までにない新しい小学校に、カバゴン先生の想いを生かしていただきたかったからです。
今回のお二人の超巨人の出会いは、私がいままで生きてきた中で、味わったことがない、震えがくるほどの感動的なものでした。
お二人とも非常に高い感性レベルを持っていることから、出会いの密度が常人とはおよそ及びがつきません。
交わす一つの言葉から瞬時にいくつもの内容が相手に伝わり、まさに一つを聞いて十を知るそのものでありました。
私はこの場に居れることがもううれしくてうれしくて・・・・。なんだか涙が出てきて止まりませんでした。
現在、星槎グループは大磯に超広大な土地を取得し、今までだれも見たことのない、広大な教育都市を建設する予定です。
少しお話を聞いていますが、もう本当に想像を絶する計画です。
そして、この計画の中に、カバゴン先生の熱い教育への想いが加味されます。
もう想像しただけでわくわくどきどきするようなお話です。
そして、その仲立ちをたまたまさせていただいたのが私であったことに、本当に本当に感動しています。
きっとこのお二人の出会いが、これから大きく起こるであろう教育の革命的変化の嚆矢となるでしょう。
教育は大きく変わる!変わらねばならない! そういう思いを強く強く感じた日でありました。
すばらしい出会いに感謝!そしてこの運命に乾杯です。
子供たちの未来に思いを馳せて。ではまた。
ライフノート(デスノートじゃないよヾ(´▽`;)ゝ)
今日のモーニングセミナーはほんとに面白かったですねえ。
講師は木幡美麗(こはたみれい)さん。
ライフノートという、自分の人生を書き写すノートを作られた方です。
自分がいつ死んでもよいように、残った方々のために自分の人生を日頃から記録しておくことができるノートです。
詳しくはこちらのページ。
本日のセミナーの内容は、このノートを作ることになったご自分(木幡さん)の人生について。
そして、この方の人生が本当に数奇に富んだ人生でした。
波乱万丈といえばそのとおりなんですが、単なるそんな言葉では決して言い表せない・・・・強いて言えば・・・・超超ユニーク・・・・・奇想天外・・・・・なんで、こうなるの??・・・・というような人生なんです。とにかく、こう言っては失礼かもしれませんが、面白い!!
人生って深いなあ・・・・まだ自分の知っていることってほんとにちっぽけなことなんだなあ・・・・・人生の味ってこういうことかも・・・というような感想です。
なんだかもったいつけてるみたいでごめんなさい。
私が、今ここで、さっき聞いた木幡さんのお話を書いても、きっと百分の一も伝わらないと思いますが、記憶に残しておくために書いておきます。
今から数十年前のこと。竹中工務店に勤務されていた木幡さんは結婚されて、お子さんを一人儲けます。ご主人はサウジアラビラに単身赴任。(数十年前のサウジアラビアへの単身赴任ですから、かなり異例中の異例だったんでしょう)
木幡さんはお子さんがいたので、ご主人と一緒にサウジアラビアに行きたかったのですが、ご主人からOKが出ず、やむなく国内に留まります。ところが、問題はこれからで、ご主人のお兄さんが、ご主人の給与を一手に管理し、木幡さんに一銭のお金も渡してくれません。困った木幡さんは、ご主人と離婚することに。
さあ、どうやって食っていこうか・・・。
そこで、教師をやりたい、と思います。ところがそれまで、何も勉強などしてきていません。また、学校に入って勉強しようにもお金がまったくありません。そこで、なんと、通信教育で教員免許をとろうとします。おそらくかなり難しかったんだろうと思いますが、彼女は通信教育は本来2年かかるところを1年で教員免許を取得します。
そして、今度は職を得るために、いくつかの学校に自分を売り込みにいきます。その中で、産休補助教員の口があり、念願の教員へ。
と、ここまでは、すごい人生と思いますし、他人が決してまねできない、やろうと思ってもできない人生なんですが、彼女のもっとすごいところは、やっていることを徹底することです。
たとえば、教員としてプロフェッショナルに徹するために、英語教員であったことから、英語のベースになっている聖書を徹底的に勉強します。聖書がぼろぼろになるまで読むので、現在の聖書はなんと7冊目だそうです。旧約聖書はヘブライ語で書かれていて、新約聖書はギリシャ語からラテン語まで。40人の著者がいて・・・・というようなことまで勉強しつくしたそうです。
そして、ここまでプロに徹した教員の道(20年の経験)を、ある日、ぽっと捨てるんですね。それはなぜかというと、家を建てたいから大工になりたい、ということだけで。
ある時、道を歩いていたら、一生懸命ブレード(刃、ナイフ)を作っている職人(親方)がいました。実は、彼女は幼いころに父親の兄弟がナイフで刺されて殺されたことがあったそうです。それで、血糊のついたナイフを、警察が父親に見せているのを幼いj彼女が見てしまいました。あまりのショックで、以来、鋭利なものを見れなくなっていました。
ところが、親方の作っているブレードは、刃が柔らかいように見えて、不思議に怖くありませんでした。
彼女は親方に話しかけます。「なんでこの刃は怖くないんでしょうか?」。
親方は、「ナイフというのは道具なんで、本来は怖くないんだよ。怖いと感じるのは、ナイフで殺人が行われるのをイメージするからであって、本来の道具という観点からみれば、怖いものではなく役に立つもの、と見えるんだよ」と答えました。
そんなやりとりもあって、彼女は親方がブレード職人ということだけでなく大工であることがわかって、大工の見習いがやりたい、と伝えます。40過ぎで、しかも手に覚えのない、通りすがりの女性からいきなりそう言われても、当然親方は半信半疑であったそうですが、3日間現場の助手として連れまわして、彼女があきらめるふうでもなく一生懸命だったので、それから3年間、見習いとして雇ったそうです。教員から突然、大工見習いへ。なんという人生の転換でしょう。彼女は大工見習いも徹底的にやったことから大工用語もしっかり覚えました。
そして、そんな大工見習いもひょんなことから急転回します。
親方が突然倒れました。それも原因不明の病で。医者に行っても病名が分かりません。親方に身寄りの者がいなかったことから、彼女が身の回りのお世話をすることになります。しかも大工仕事、ブレード職人、そして、なんと親方は夜はテナーサックスプレイヤーとして、JAZZバンドにも参加していたそうですから、それらの仕事が彼女に覆いかぶさってきます。当然、彼女はそれらを一つ一つこなしていくわけです。そして、その合間に親方の病名を調べるために、ありとあらゆる医学辞典・文献を調べて、ようやく病気の原因を解明するという離れ業までやってのけるのですから、もう常人とは思えませんねえ。超スーパー、ウルトラ、ハイパー・・・・ま、いいや、とにかくすごい人です。
と、この後、大工の棟梁の仕事から平安葬祭に移るんですが、ここの経緯は時間がなくてお話されませんでした。きっとまた、とんでもない転回があったに違いありません。
そして、平安葬祭に移ってからも、超スーパーぶりは遺憾なく発揮されます。移って5ヶ月で、言わば新人の身ながら、社内トップのセールスレディになったそうです。年収は1500万。これを9年間キープしました。もう唖然。
そして、この仕事も突然、放り出すんですから、いったいこの人は何者なんでしょうか?
この最後の転回が、「ライフノート」作成が原因となっているわけです。
彼女の同僚が、犬にかまれて、ある日突然、これも原因不明の病に倒れます。いくつか病院を回りましたが、最終的には起き上がれなくなってしまいます。
彼女は自分の死期を悟ります。
そして彼女が木幡さんに言ったことは、「今まで生きてきた色々な思い出や、皆へのメッセージ、感謝の言葉や写真なんかも一緒にまとめられたらいいね。それにもしものときの希望や残したものの一覧表、大切な物入れの袋がついていると便利だよね。そんな、一つで全部できるものが欲しいよね。」
それに対して木幡さんは、「わかった。その希望を現実のものにするよ。きっとかなえるから。」と約束しました。
それから、木幡さんは、いろいろな文房具店をまわりますが、そのようなものはありません。
そこで・・・ここがもう普通じゃないと思いますが・・・・、ないなら自分で作ろうと思います。次から、ありとあらゆる業者を訪ね歩き、先の彼女の要望を伝えますが、皆一笑に付します。しかしながら、回っている中から木幡さんの熱意に動かされて、ある会社が協力を申し出て、様々な試行錯誤の末、「ライフノート」は出来上がります。病に倒れた彼女の要望を聞いたときから、わずか3ヶ月で。ほんまに・・・・この行動力は・・・・いったいなに!
そして、高給をもらっていた平安葬祭を、この「ライフノート」作成をきっかけにあっさりと辞めてしまうんですから。あいやー!!!( ̄□ ̄;)ギョッ
木幡さんは言います。「ライフノートは、日本をローマ滅亡のような有様にしないために、今の日本に必ず必要とされるものです。聖書から学んだことは、ローマ滅亡は、外からの攻撃ではなく、内から瓦解していったということです。その際に家族の崩壊が引き金になっています。日本は今、核家族化が極端に進み、家族崩壊が進んでいます。ライフノートは、ご自分の人生の記録を残された家族がいつでも見れるようにすることによって、家族間のつながりを密にします。これによって家族崩壊を防ぎます。」
ほんとに、ここまで木幡さんの人生の記録を若干、私も記述したことによって、そのさわりを疑似体験させていただきましたが、人生ってほんとに何が起こるかわかりませんね。また、木幡さんの人生を振り返ると、逆に人生って何でもできるんだなあ、と深く思います。
ほんまに、人の一生っておもろいでんなあ。へたなドラマよりはるかに面白いでっせー。
ということが、朝はよから実感できて、今日もハッピーですわ。
では皆さん、がんばりんしゃい。わてもがんばるさかい。いってらっしゃーい。

講師は木幡美麗(こはたみれい)さん。
ライフノートという、自分の人生を書き写すノートを作られた方です。
自分がいつ死んでもよいように、残った方々のために自分の人生を日頃から記録しておくことができるノートです。
詳しくはこちらのページ。
本日のセミナーの内容は、このノートを作ることになったご自分(木幡さん)の人生について。
そして、この方の人生が本当に数奇に富んだ人生でした。
波乱万丈といえばそのとおりなんですが、単なるそんな言葉では決して言い表せない・・・・強いて言えば・・・・超超ユニーク・・・・・奇想天外・・・・・なんで、こうなるの??・・・・というような人生なんです。とにかく、こう言っては失礼かもしれませんが、面白い!!
人生って深いなあ・・・・まだ自分の知っていることってほんとにちっぽけなことなんだなあ・・・・・人生の味ってこういうことかも・・・というような感想です。
なんだかもったいつけてるみたいでごめんなさい。
私が、今ここで、さっき聞いた木幡さんのお話を書いても、きっと百分の一も伝わらないと思いますが、記憶に残しておくために書いておきます。
今から数十年前のこと。竹中工務店に勤務されていた木幡さんは結婚されて、お子さんを一人儲けます。ご主人はサウジアラビラに単身赴任。(数十年前のサウジアラビアへの単身赴任ですから、かなり異例中の異例だったんでしょう)
木幡さんはお子さんがいたので、ご主人と一緒にサウジアラビアに行きたかったのですが、ご主人からOKが出ず、やむなく国内に留まります。ところが、問題はこれからで、ご主人のお兄さんが、ご主人の給与を一手に管理し、木幡さんに一銭のお金も渡してくれません。困った木幡さんは、ご主人と離婚することに。
さあ、どうやって食っていこうか・・・。
そこで、教師をやりたい、と思います。ところがそれまで、何も勉強などしてきていません。また、学校に入って勉強しようにもお金がまったくありません。そこで、なんと、通信教育で教員免許をとろうとします。おそらくかなり難しかったんだろうと思いますが、彼女は通信教育は本来2年かかるところを1年で教員免許を取得します。
そして、今度は職を得るために、いくつかの学校に自分を売り込みにいきます。その中で、産休補助教員の口があり、念願の教員へ。
と、ここまでは、すごい人生と思いますし、他人が決してまねできない、やろうと思ってもできない人生なんですが、彼女のもっとすごいところは、やっていることを徹底することです。
たとえば、教員としてプロフェッショナルに徹するために、英語教員であったことから、英語のベースになっている聖書を徹底的に勉強します。聖書がぼろぼろになるまで読むので、現在の聖書はなんと7冊目だそうです。旧約聖書はヘブライ語で書かれていて、新約聖書はギリシャ語からラテン語まで。40人の著者がいて・・・・というようなことまで勉強しつくしたそうです。
そして、ここまでプロに徹した教員の道(20年の経験)を、ある日、ぽっと捨てるんですね。それはなぜかというと、家を建てたいから大工になりたい、ということだけで。
ある時、道を歩いていたら、一生懸命ブレード(刃、ナイフ)を作っている職人(親方)がいました。実は、彼女は幼いころに父親の兄弟がナイフで刺されて殺されたことがあったそうです。それで、血糊のついたナイフを、警察が父親に見せているのを幼いj彼女が見てしまいました。あまりのショックで、以来、鋭利なものを見れなくなっていました。
ところが、親方の作っているブレードは、刃が柔らかいように見えて、不思議に怖くありませんでした。
彼女は親方に話しかけます。「なんでこの刃は怖くないんでしょうか?」。
親方は、「ナイフというのは道具なんで、本来は怖くないんだよ。怖いと感じるのは、ナイフで殺人が行われるのをイメージするからであって、本来の道具という観点からみれば、怖いものではなく役に立つもの、と見えるんだよ」と答えました。
そんなやりとりもあって、彼女は親方がブレード職人ということだけでなく大工であることがわかって、大工の見習いがやりたい、と伝えます。40過ぎで、しかも手に覚えのない、通りすがりの女性からいきなりそう言われても、当然親方は半信半疑であったそうですが、3日間現場の助手として連れまわして、彼女があきらめるふうでもなく一生懸命だったので、それから3年間、見習いとして雇ったそうです。教員から突然、大工見習いへ。なんという人生の転換でしょう。彼女は大工見習いも徹底的にやったことから大工用語もしっかり覚えました。
そして、そんな大工見習いもひょんなことから急転回します。
親方が突然倒れました。それも原因不明の病で。医者に行っても病名が分かりません。親方に身寄りの者がいなかったことから、彼女が身の回りのお世話をすることになります。しかも大工仕事、ブレード職人、そして、なんと親方は夜はテナーサックスプレイヤーとして、JAZZバンドにも参加していたそうですから、それらの仕事が彼女に覆いかぶさってきます。当然、彼女はそれらを一つ一つこなしていくわけです。そして、その合間に親方の病名を調べるために、ありとあらゆる医学辞典・文献を調べて、ようやく病気の原因を解明するという離れ業までやってのけるのですから、もう常人とは思えませんねえ。超スーパー、ウルトラ、ハイパー・・・・ま、いいや、とにかくすごい人です。
と、この後、大工の棟梁の仕事から平安葬祭に移るんですが、ここの経緯は時間がなくてお話されませんでした。きっとまた、とんでもない転回があったに違いありません。
そして、平安葬祭に移ってからも、超スーパーぶりは遺憾なく発揮されます。移って5ヶ月で、言わば新人の身ながら、社内トップのセールスレディになったそうです。年収は1500万。これを9年間キープしました。もう唖然。
そして、この仕事も突然、放り出すんですから、いったいこの人は何者なんでしょうか?
この最後の転回が、「ライフノート」作成が原因となっているわけです。
彼女の同僚が、犬にかまれて、ある日突然、これも原因不明の病に倒れます。いくつか病院を回りましたが、最終的には起き上がれなくなってしまいます。
彼女は自分の死期を悟ります。
そして彼女が木幡さんに言ったことは、「今まで生きてきた色々な思い出や、皆へのメッセージ、感謝の言葉や写真なんかも一緒にまとめられたらいいね。それにもしものときの希望や残したものの一覧表、大切な物入れの袋がついていると便利だよね。そんな、一つで全部できるものが欲しいよね。」
それに対して木幡さんは、「わかった。その希望を現実のものにするよ。きっとかなえるから。」と約束しました。
それから、木幡さんは、いろいろな文房具店をまわりますが、そのようなものはありません。
そこで・・・ここがもう普通じゃないと思いますが・・・・、ないなら自分で作ろうと思います。次から、ありとあらゆる業者を訪ね歩き、先の彼女の要望を伝えますが、皆一笑に付します。しかしながら、回っている中から木幡さんの熱意に動かされて、ある会社が協力を申し出て、様々な試行錯誤の末、「ライフノート」は出来上がります。病に倒れた彼女の要望を聞いたときから、わずか3ヶ月で。ほんまに・・・・この行動力は・・・・いったいなに!
そして、高給をもらっていた平安葬祭を、この「ライフノート」作成をきっかけにあっさりと辞めてしまうんですから。あいやー!!!( ̄□ ̄;)ギョッ
木幡さんは言います。「ライフノートは、日本をローマ滅亡のような有様にしないために、今の日本に必ず必要とされるものです。聖書から学んだことは、ローマ滅亡は、外からの攻撃ではなく、内から瓦解していったということです。その際に家族の崩壊が引き金になっています。日本は今、核家族化が極端に進み、家族崩壊が進んでいます。ライフノートは、ご自分の人生の記録を残された家族がいつでも見れるようにすることによって、家族間のつながりを密にします。これによって家族崩壊を防ぎます。」
ほんとに、ここまで木幡さんの人生の記録を若干、私も記述したことによって、そのさわりを疑似体験させていただきましたが、人生ってほんとに何が起こるかわかりませんね。また、木幡さんの人生を振り返ると、逆に人生って何でもできるんだなあ、と深く思います。
ほんまに、人の一生っておもろいでんなあ。へたなドラマよりはるかに面白いでっせー。
ということが、朝はよから実感できて、今日もハッピーですわ。
では皆さん、がんばりんしゃい。わてもがんばるさかい。いってらっしゃーい。

大切な人へ
「焦燥感」
えもいわれぬ焦燥感から、地団駄踏んでも晴れない心の底から、いつからこうなったんだろうか。
あの時の、いやその前の・・・。振り返った先から時間は過ぎていく。
・・・・けっこう私はがんばってきた。それなのに・・・・?
放物線上に浮かぶ軌跡。駆け上がりなだらかに落ちていく。
日の光、夜の闇。ふたたび、光は射すはずで。なぜかその事実が心に落ち着かない。
自分は性格に胡坐をかいてきたわけではない。変わろうと努力している。
でも・・・・。突然、涙が出る。くやしい、ひどい、苦しい。
今に見てろ。 でも、誰が見てるんだろうか。
もう忘れなければならない。そう思えば思うほど気持ちが高ぶる。
情けない。 いつからこうなってしまったんだろうか?
時間が解決する? じゃあ、何時間で解決するの、と問いかけている自分がみじめだ。
少しエネルギーを吐き出そう! 悩みのエネルギーを吐き出そう!
幻気球の世界の中で、意識を変えるんだ。
何かをきっかけに変えるんだ。-カエルンダ。
理由もなくカエルンダ。理もなくカエルンダ。
放物線のその先なんて、所詮見えるわけがない。
自然に戻れ!子に戻れ!土に戻れ!気に戻れ!
われに戻れ!性に戻れ!笑顔に戻れ!体に戻れ!
心の流れを取り戻せ。瞳の力を取り戻せ。
所詮、人生、日々流転。流れにまかせて、しゅらしゅしゅしゅ。
次第に景色が変化して、友の姿が見えてくる。仏の姿が見えてくる。
注)この散文詩は僕の友人の心象風景をイメージして書いてみました。
えもいわれぬ焦燥感から、地団駄踏んでも晴れない心の底から、いつからこうなったんだろうか。
あの時の、いやその前の・・・。振り返った先から時間は過ぎていく。
・・・・けっこう私はがんばってきた。それなのに・・・・?
放物線上に浮かぶ軌跡。駆け上がりなだらかに落ちていく。
日の光、夜の闇。ふたたび、光は射すはずで。なぜかその事実が心に落ち着かない。
自分は性格に胡坐をかいてきたわけではない。変わろうと努力している。
でも・・・・。突然、涙が出る。くやしい、ひどい、苦しい。
今に見てろ。 でも、誰が見てるんだろうか。
もう忘れなければならない。そう思えば思うほど気持ちが高ぶる。
情けない。 いつからこうなってしまったんだろうか?
時間が解決する? じゃあ、何時間で解決するの、と問いかけている自分がみじめだ。
少しエネルギーを吐き出そう! 悩みのエネルギーを吐き出そう!
幻気球の世界の中で、意識を変えるんだ。
何かをきっかけに変えるんだ。-カエルンダ。
理由もなくカエルンダ。理もなくカエルンダ。
放物線のその先なんて、所詮見えるわけがない。
自然に戻れ!子に戻れ!土に戻れ!気に戻れ!
われに戻れ!性に戻れ!笑顔に戻れ!体に戻れ!
心の流れを取り戻せ。瞳の力を取り戻せ。
所詮、人生、日々流転。流れにまかせて、しゅらしゅしゅしゅ。
次第に景色が変化して、友の姿が見えてくる。仏の姿が見えてくる。
注)この散文詩は僕の友人の心象風景をイメージして書いてみました。
九地の変 孫子の言葉
今までのバックナンバー
http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
http://katsu.i-ra.jp/e4115.html
http://katsu.i-ra.jp/c138.html
http://katsu.i-ra.jp/e6071.html
久しぶりに孫子の兵法です。
九地の変、屈伸の利、
人情の理、察せざるべからず。
戦場は変化が変化を生む。その連続である。
したがって変化を異常なもの、特別なもの、突発したものとして受け取るのではなく、変化することが常態なのだという認識に立たない限り、ついていけないのである。
このような「変化管理」をするためにはどうすればよいのか。
その手順を示したのがこの言葉である。
-状況の変化。
-変化への有効な対応の仕方。
-兵の心理。
この三つについて、将たる者は、よくよく見極めておかなければならないのである。
まず変化の態様を見定めることだ。予期していれば、たとえそれが未知のものであっても、比較的冷静に観察できる。状況は、どう変化するにしても、おのずからパターンがある。
それが九地である。以下、九地の説明。
散地 -なんらかの原因で、将兵の戦意を集中できないところ。ここでは戦わないこと。
軽地 -国境から少し敵地に入ったところ。落ち着かないから早く立ち去った方がよい。
争地 -敵味方ともに手に入れたい場所。利につられ、焦って攻めない方がよい。
交地 -双方から入りやすいところ。入り交じり混乱するから、部隊間の連絡を密にせよ。
衢地(くち)-諸勢力が錯綜しているところ。外交交渉を第一に心がけること。
重地 -敵国深く入り込み、心に重圧を受けやすいところ。略奪で発散させるがよい。
圮地(ひち)-険しい地形で行軍しにくいところ。早く通過してしまうこと。
囲地(いち)-出入り口は狭く、なかは囲まれている場所。戦闘よりも計略で戦う方がよい。
死地 -戦う以外に生きるすべのないところ。必死に戦うこと。
ついで、それに見合って屈し、あるいは伸びる。その際、兵士たちの心理を計算に入れることを忘れてはならないのである。
http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
http://katsu.i-ra.jp/e4115.html
http://katsu.i-ra.jp/c138.html
http://katsu.i-ra.jp/e6071.html
久しぶりに孫子の兵法です。
九地の変、屈伸の利、
人情の理、察せざるべからず。
戦場は変化が変化を生む。その連続である。
したがって変化を異常なもの、特別なもの、突発したものとして受け取るのではなく、変化することが常態なのだという認識に立たない限り、ついていけないのである。
このような「変化管理」をするためにはどうすればよいのか。
その手順を示したのがこの言葉である。
-状況の変化。
-変化への有効な対応の仕方。
-兵の心理。
この三つについて、将たる者は、よくよく見極めておかなければならないのである。
まず変化の態様を見定めることだ。予期していれば、たとえそれが未知のものであっても、比較的冷静に観察できる。状況は、どう変化するにしても、おのずからパターンがある。
それが九地である。以下、九地の説明。
散地 -なんらかの原因で、将兵の戦意を集中できないところ。ここでは戦わないこと。
軽地 -国境から少し敵地に入ったところ。落ち着かないから早く立ち去った方がよい。
争地 -敵味方ともに手に入れたい場所。利につられ、焦って攻めない方がよい。
交地 -双方から入りやすいところ。入り交じり混乱するから、部隊間の連絡を密にせよ。
衢地(くち)-諸勢力が錯綜しているところ。外交交渉を第一に心がけること。
重地 -敵国深く入り込み、心に重圧を受けやすいところ。略奪で発散させるがよい。
圮地(ひち)-険しい地形で行軍しにくいところ。早く通過してしまうこと。
囲地(いち)-出入り口は狭く、なかは囲まれている場所。戦闘よりも計略で戦う方がよい。
死地 -戦う以外に生きるすべのないところ。必死に戦うこと。
ついで、それに見合って屈し、あるいは伸びる。その際、兵士たちの心理を計算に入れることを忘れてはならないのである。
今ある事に、感謝して
以前、「プチ紳士を探せ」の「志賀内泰弘さん」をご紹介しました。 →ここをクリック
彼のメールマガジンを大変楽しみに読んでいるのですが、最新号は大変感動的な内容でしたので、ここにご紹介します。
すばらしい内容です。長文ですが、ぜひお読みください。心が動かされると思います。
「今ある事に、感謝して」
志賀内泰弘
先々週、金沢の四方健二さんの詩を紹介しました。
昨年、泉鏡花記念金沢市民文学賞を受賞している詩人です。
彼の詩は、あちこちを漂泊し、気ままに吟行するような印象を受けるのですが、
実は彼は30年以上、家からほとんど外に出たことがありません。
彼は7歳で進行性筋ジストロフィー症を発症して以来、
病床での生活を送っているのです。
手足の指先1本動かせません。
まったく寝たきりの状態です。
9月30日、四方君の詩の朗読会と講演会があると聞き、
金沢の市民芸術村パフォーミングスクエアへ行ってまいりました。
朗読は地元の女性アナウンサーさんが、
心をこめて読んでいただきました。
講演は、ステージの上の移動式ベッドから、本人が語りました。
・ ・・でも、彼は言葉を発することができません。
どうやって皆に伝えたのか。
本当に驚きました。
額に信号を伝えるためのコードを貼り付け、
瞼(まぶた)を開いたり閉じたりして、
パソコンに文字を書くのです。
それをパソコンの言語変換ソフトで、
再び音声に換えて、
講演をするわけです。
もちろん、時間がかかるので、その場ですぐに、
というわけにはいきません。
おそらく、何時間いや何日もかかって完成したものでしょう。
今日は、ぜひ。
ぜひ、ぜひ、皆さんにも講演を聞いていただきたく、
四方君の講演録を下記に披露させていただきます。
きっと皆さんの心に、優しさと元気をもたらしてくれることでしょう。
* * * * *
詩人 四方健二・講演録「生かされて生きる」
生きるとは、どういう事なのでしょうか。
あなたは今、生きていますか。
心の底から、生きていると言えますか。
胸に手を当ててみて下さい。
鼓動が響いてくると思います、温かな血流が伝わってくる事でしょう。
生きていれば、誰もがそうあります。
しかし、ただそれだけで、人は生きていると言えるのでしょうか。
人は、身体だけで生きているのではありません。
人には、心があります。身体と精神ともに息づいてこそ、
人は生きていると言えるのではないかと、私は思っています。
私は重度の身体障害者です。
進行性筋ジストロフィーという難病を背負っています。
進行性筋ジストロフィーとは、
全身の筋肉が萎縮し、破壊され、徐々にその機能を失っていく病気です。
今の私は、身体どころか、指ひとつ動かせません。
寝たきりの状態にあり、人工呼吸器がなくては生きていられません。
そんな私ではありますが、子供の頃には、息を切らして駆け回り、
夕方暗くなるまで、家に帰りつく事はありませんでした。
私が生まれたところは、自然豊かな能登の漁師町です。
遊ぶ場所には、事欠くことはありませんでした。
時を経て、私は中学生へと、高校生へと成長していきました。
学生の頃の私はといいますと。
心の趣くままに、何事にも情熱を傾けていました。
興味のある事には、次から次へとトライして。
時には、その情熱が、良からぬ興味に注がれた事もありましたが。
それはともかくとして。
その当時の私は、最も活動的で、最も活発に行動していました。
音楽サークルを立ち上げたり。
劇団に加わったり。アマチュア無線の交信にも勤しんでいましたし。
生徒会活動には、かなり熱を入れていたものでした。
しかし、進行性の病気とは、本当にやるせないものです。
どうあがこうと、病気の進行には抗えず。
歩けなくなり、車椅子へ。
そして、ついには寝たきりの生活を送る事になってしまいました。
進行性筋ジストロフィー。
この病気の本当に恐ろしいところは、その短命さにあるのです。
かつてこの病気は、二十歳までの命とされていました。
実際に、二十歳を迎える前に力尽き、亡くなっていく仲間。
人たちを、数多く見送ってきました。
その中でも、最も辛かったのは、親友の死でした。
それは、高等部二年生の初秋の事でした。
もう持たないと聞いてからの毎日の病室通い。
見舞うたびに、彼からの反応は鈍くなり、目からは光が失われていきました。
そんな親友を目の当たりにしておきながら。
私は彼に、何ひとつしてやれませんでした。
あまりにも、自分が情けなく思え。
無力感に苛まれたものでした。
また、この彼の死は、私に拭い去れない恐怖を植えつける事になりました。
「次は自分かもしれない」という、重苦しい思いが。
現実として、リアルに圧し掛かってきたのです。
今でも、それは重い影となって、私にまとわりついています。
それでも、現在では私たちを囲む医療環境が進歩し。
対症療法が功を奏すようになり、
命の期限は緩やかなものになったと言えるでしょう。
しかし、いくら対症療法が進んだとはいえ、
短命だという事には変わりはありません。
私自身も、十九歳の時に、重い呼吸不全に陥ってしまいました。
それは、命の危機を連想するまでに、深刻なものだったのです。
そんな私を救ってくれたのは、
当時導入されたばかりの体外式といわれる呼吸器でした。
この呼吸器によって、私は命を永らえることが出来たのです。
あの時、ひとつでも時の歯車が狂っていたら。
おそらく、十九歳の冬に私は死んでいた事でしょう。
そんな私も、今年で四十歳になります。
かつて、私の命は二十歳までだと言われていました。
それを思うと、四十歳という年齢が、大変重いものに思えてきます。
ここ二十年間の経験は、本当に貴重な経験ばかりだったように思います。
今、こうして四十歳になるまで生きてこられたことに、
大きな意味と、大きな喜びを感じています。
思い起こせば、よく仲間たちと話していたものでした。
「四十歳まで生きていられたら最高だ」と。
その夢であった年齢を、今年、私は迎えるわけですから、
なんとも不思議なものを感じます。
私は自発呼吸が出来ません。
気管を切開して、人工呼吸器を使用しています。
気管を切開したことで、私は声を失いました。
そのために、思うに任せない事も沢山あります。
ですが、これは生きていくため、仕方がありません。
それでも、時には、たまらない思いに囚われることがあります。
割り切っているはずなのですが、複雑な思いもそこにはあるのです。
夢の中での私は、いつも当たり前のように喋っています。
この夢こそが、私の複雑な心を物語っていると言えるのではないでしょうか。
さらに、私にはものを飲み込む力がありません。
必要な栄養や水分は、
全て鼻から入っているチューブを通して胃へと流し込んでいます。
身体を動かせない、声は出せない、飲めない、食べられない。
こうして挙げてみると、なかなか重いものがありますね。
人によっては、これを絶望だと言うのかもしれません。
しかし、私はそうは思っていません。
私には、充実した毎日があります。
絶望は陰へと追いやられ、心を支配することはありません。
とはいえ、この病気によって、私は多くのものを失いました。
心を許し合った仲間も、次々と倒れていきました。
わたし独りだけが生き残り。
時には、それを仲間への裏切りだと感じてしまう事さえあります。
それでも、失うことばかりではありませんでした。
筋ジストロフィーである事により、得られたものもあるのです。
これまでの私の人生には、身体的にも精神的にも辛い事が数多くありました。
不安と恐怖に押し潰されそうになった事も、幾度となくありました。
苦しい経験ではありましたが、逆にその苦境の時にこそ、
私は大切なものを得られたように思います。
先にも触れましたが、私は深刻な呼吸不全に陥った事がありました。
昼も夜も無く、ままならない呼吸に喘ぐばかりで、
心身ともに無残なまでに衰えてしまっていたのです。
抗えない苦痛と、絶望感に囚われ。「これまでか」と、
死を覚悟するまでに疲弊していました。
その日も、澱んだ薄暗い病室の中で。
私は、それ以上の闇に沈んでいました。
ふと何かに呼ばれたような気がして、視線を向けると。
そこには、忘れられた一輪挿しに、萎れた桔梗が残されていました。
私は、「自分と同じ運命か」と、悲観の眼差しで桔梗を眺めていました。
ところがです、朽ち果てるばかりだと思っていたその花が。
私の目の前で力強く蕾を開き、生きいきと花を咲かせたのです。
諦めることを知らず、与えられた命を誠実に全うしようとする姿勢に、
私の心は震えました。私の中で熱い力が湧き上がってくるのを感じたのです。
生きたいと、強く思いました。
すると、どうでしょう。
それまではくすんでいた世界が、
たちまち鮮やかさを取り戻していくでは、ありませんか。
苦しいばかりの毎日が続いて。
私は、気づかないうちに、
私自身の作った殻に閉じこもってしまっていたようです。
自分だけの世界しか見えなくなってしまい。
自分は孤独だと思い込んでしまっていたようです。
しかし、広い視野で周りがよく見えるようになると、
それは大きな間違いであったと気がつきました。
多くの人の力が、その真心が、苦しみに喘ぐ私を、
私の命を支えてくれていたのです。深く感謝しました。
それからというもの、呼吸不全との暗く孤独な戦いは。
家族や看護師さんたち、先生方との、共同戦線となりました。
体調の良い時は、共に喜び。苦しい時には、共に歯を食いしばり。
身体的には厳しい毎日でしたが、心は満たされていました。
幸せにさえ、思えていたものです。
私は支えてくださる皆さんの真心を追い風に、
心ある人たちと力を合わせる事で、この窮地を乗り切る事ができました。
私は、これまでの人生を通して、生かされている自分というものを、
強く意識するようになりました。
私は毎日、多くの人々に支えられて生きています。生かされています。
また、私は、自然と対峙するたびに、
自然の大きな懐に包まれている事を感じるのです。
生かされている安心感を覚えるのです。
私は、生きている事の喜びを、生かされていることの幸せを。
この身の全てで、この心の全てで受け止めて生きています。
だからこそ、何気ない毎日が嬉しいのです。愛おしいのです。
今ある事に、感謝して。与えられた日々を、精一杯生きる。
不平不満が無いとは言いません。嫉妬もすれば、妬みもします。
しかし、私は生きているのです。生かされているのです。
ありがたい事ではありませんか。
不平不満に取り付かれ、嫉妬や妬みに心を惑わせるなど。
この喜びにくらべると、本当に小さな事だと思えるのです。
私は日々、生きがいを咲かせ、希望を持って生きています。
そういう毎日が、私の人生を充実したものにしてくれているのです。
私は、生かされてここにいます。
生かされている事に感謝しつつ、自らも生きる姿勢を持って生きています。
そうしてこそ、豊かな人生を得られるのではないでしょうか。
私は詩作という生きがいを咲かせ、心豊かに、満たされた日々を送っています。
私は生きています。今は、自信を持ってそう言えます。
自分の確固たる意識を基に、私らしく、あるがままに生きています。
私が私であることに、感謝せずにはいられません。
私は幸せです。私は恵まれています。
この人生を与えてくれた全てのものに、全ての人々に、心から感謝しています。
私にも、明日がやってくるのです。
私は、幸せです。
* * * * *
もし、心に響いたら、波長が合いましたら、
お友達にも転送して多くの人に講演を聞いていただけたら幸いです。
四方さんのことを紹介している関連サイトは、
こちらをクリック
こちらもクリック
すばらしいですね。私たちは本当に「生かされている」のですね。今ある幸せに心底から感謝の気持ちが芽生えてきます。
すべてのものに「ありがとう」。
ではまた。

彼のメールマガジンを大変楽しみに読んでいるのですが、最新号は大変感動的な内容でしたので、ここにご紹介します。
すばらしい内容です。長文ですが、ぜひお読みください。心が動かされると思います。
「今ある事に、感謝して」
志賀内泰弘
先々週、金沢の四方健二さんの詩を紹介しました。
昨年、泉鏡花記念金沢市民文学賞を受賞している詩人です。
彼の詩は、あちこちを漂泊し、気ままに吟行するような印象を受けるのですが、
実は彼は30年以上、家からほとんど外に出たことがありません。
彼は7歳で進行性筋ジストロフィー症を発症して以来、
病床での生活を送っているのです。
手足の指先1本動かせません。
まったく寝たきりの状態です。
9月30日、四方君の詩の朗読会と講演会があると聞き、
金沢の市民芸術村パフォーミングスクエアへ行ってまいりました。
朗読は地元の女性アナウンサーさんが、
心をこめて読んでいただきました。
講演は、ステージの上の移動式ベッドから、本人が語りました。
・ ・・でも、彼は言葉を発することができません。
どうやって皆に伝えたのか。
本当に驚きました。
額に信号を伝えるためのコードを貼り付け、
瞼(まぶた)を開いたり閉じたりして、
パソコンに文字を書くのです。
それをパソコンの言語変換ソフトで、
再び音声に換えて、
講演をするわけです。
もちろん、時間がかかるので、その場ですぐに、
というわけにはいきません。
おそらく、何時間いや何日もかかって完成したものでしょう。
今日は、ぜひ。
ぜひ、ぜひ、皆さんにも講演を聞いていただきたく、
四方君の講演録を下記に披露させていただきます。
きっと皆さんの心に、優しさと元気をもたらしてくれることでしょう。
* * * * *
詩人 四方健二・講演録「生かされて生きる」
生きるとは、どういう事なのでしょうか。
あなたは今、生きていますか。
心の底から、生きていると言えますか。
胸に手を当ててみて下さい。
鼓動が響いてくると思います、温かな血流が伝わってくる事でしょう。
生きていれば、誰もがそうあります。
しかし、ただそれだけで、人は生きていると言えるのでしょうか。
人は、身体だけで生きているのではありません。
人には、心があります。身体と精神ともに息づいてこそ、
人は生きていると言えるのではないかと、私は思っています。
私は重度の身体障害者です。
進行性筋ジストロフィーという難病を背負っています。
進行性筋ジストロフィーとは、
全身の筋肉が萎縮し、破壊され、徐々にその機能を失っていく病気です。
今の私は、身体どころか、指ひとつ動かせません。
寝たきりの状態にあり、人工呼吸器がなくては生きていられません。
そんな私ではありますが、子供の頃には、息を切らして駆け回り、
夕方暗くなるまで、家に帰りつく事はありませんでした。
私が生まれたところは、自然豊かな能登の漁師町です。
遊ぶ場所には、事欠くことはありませんでした。
時を経て、私は中学生へと、高校生へと成長していきました。
学生の頃の私はといいますと。
心の趣くままに、何事にも情熱を傾けていました。
興味のある事には、次から次へとトライして。
時には、その情熱が、良からぬ興味に注がれた事もありましたが。
それはともかくとして。
その当時の私は、最も活動的で、最も活発に行動していました。
音楽サークルを立ち上げたり。
劇団に加わったり。アマチュア無線の交信にも勤しんでいましたし。
生徒会活動には、かなり熱を入れていたものでした。
しかし、進行性の病気とは、本当にやるせないものです。
どうあがこうと、病気の進行には抗えず。
歩けなくなり、車椅子へ。
そして、ついには寝たきりの生活を送る事になってしまいました。
進行性筋ジストロフィー。
この病気の本当に恐ろしいところは、その短命さにあるのです。
かつてこの病気は、二十歳までの命とされていました。
実際に、二十歳を迎える前に力尽き、亡くなっていく仲間。
人たちを、数多く見送ってきました。
その中でも、最も辛かったのは、親友の死でした。
それは、高等部二年生の初秋の事でした。
もう持たないと聞いてからの毎日の病室通い。
見舞うたびに、彼からの反応は鈍くなり、目からは光が失われていきました。
そんな親友を目の当たりにしておきながら。
私は彼に、何ひとつしてやれませんでした。
あまりにも、自分が情けなく思え。
無力感に苛まれたものでした。
また、この彼の死は、私に拭い去れない恐怖を植えつける事になりました。
「次は自分かもしれない」という、重苦しい思いが。
現実として、リアルに圧し掛かってきたのです。
今でも、それは重い影となって、私にまとわりついています。
それでも、現在では私たちを囲む医療環境が進歩し。
対症療法が功を奏すようになり、
命の期限は緩やかなものになったと言えるでしょう。
しかし、いくら対症療法が進んだとはいえ、
短命だという事には変わりはありません。
私自身も、十九歳の時に、重い呼吸不全に陥ってしまいました。
それは、命の危機を連想するまでに、深刻なものだったのです。
そんな私を救ってくれたのは、
当時導入されたばかりの体外式といわれる呼吸器でした。
この呼吸器によって、私は命を永らえることが出来たのです。
あの時、ひとつでも時の歯車が狂っていたら。
おそらく、十九歳の冬に私は死んでいた事でしょう。
そんな私も、今年で四十歳になります。
かつて、私の命は二十歳までだと言われていました。
それを思うと、四十歳という年齢が、大変重いものに思えてきます。
ここ二十年間の経験は、本当に貴重な経験ばかりだったように思います。
今、こうして四十歳になるまで生きてこられたことに、
大きな意味と、大きな喜びを感じています。
思い起こせば、よく仲間たちと話していたものでした。
「四十歳まで生きていられたら最高だ」と。
その夢であった年齢を、今年、私は迎えるわけですから、
なんとも不思議なものを感じます。
私は自発呼吸が出来ません。
気管を切開して、人工呼吸器を使用しています。
気管を切開したことで、私は声を失いました。
そのために、思うに任せない事も沢山あります。
ですが、これは生きていくため、仕方がありません。
それでも、時には、たまらない思いに囚われることがあります。
割り切っているはずなのですが、複雑な思いもそこにはあるのです。
夢の中での私は、いつも当たり前のように喋っています。
この夢こそが、私の複雑な心を物語っていると言えるのではないでしょうか。
さらに、私にはものを飲み込む力がありません。
必要な栄養や水分は、
全て鼻から入っているチューブを通して胃へと流し込んでいます。
身体を動かせない、声は出せない、飲めない、食べられない。
こうして挙げてみると、なかなか重いものがありますね。
人によっては、これを絶望だと言うのかもしれません。
しかし、私はそうは思っていません。
私には、充実した毎日があります。
絶望は陰へと追いやられ、心を支配することはありません。
とはいえ、この病気によって、私は多くのものを失いました。
心を許し合った仲間も、次々と倒れていきました。
わたし独りだけが生き残り。
時には、それを仲間への裏切りだと感じてしまう事さえあります。
それでも、失うことばかりではありませんでした。
筋ジストロフィーである事により、得られたものもあるのです。
これまでの私の人生には、身体的にも精神的にも辛い事が数多くありました。
不安と恐怖に押し潰されそうになった事も、幾度となくありました。
苦しい経験ではありましたが、逆にその苦境の時にこそ、
私は大切なものを得られたように思います。
先にも触れましたが、私は深刻な呼吸不全に陥った事がありました。
昼も夜も無く、ままならない呼吸に喘ぐばかりで、
心身ともに無残なまでに衰えてしまっていたのです。
抗えない苦痛と、絶望感に囚われ。「これまでか」と、
死を覚悟するまでに疲弊していました。
その日も、澱んだ薄暗い病室の中で。
私は、それ以上の闇に沈んでいました。
ふと何かに呼ばれたような気がして、視線を向けると。
そこには、忘れられた一輪挿しに、萎れた桔梗が残されていました。
私は、「自分と同じ運命か」と、悲観の眼差しで桔梗を眺めていました。
ところがです、朽ち果てるばかりだと思っていたその花が。
私の目の前で力強く蕾を開き、生きいきと花を咲かせたのです。
諦めることを知らず、与えられた命を誠実に全うしようとする姿勢に、
私の心は震えました。私の中で熱い力が湧き上がってくるのを感じたのです。
生きたいと、強く思いました。
すると、どうでしょう。
それまではくすんでいた世界が、
たちまち鮮やかさを取り戻していくでは、ありませんか。
苦しいばかりの毎日が続いて。
私は、気づかないうちに、
私自身の作った殻に閉じこもってしまっていたようです。
自分だけの世界しか見えなくなってしまい。
自分は孤独だと思い込んでしまっていたようです。
しかし、広い視野で周りがよく見えるようになると、
それは大きな間違いであったと気がつきました。
多くの人の力が、その真心が、苦しみに喘ぐ私を、
私の命を支えてくれていたのです。深く感謝しました。
それからというもの、呼吸不全との暗く孤独な戦いは。
家族や看護師さんたち、先生方との、共同戦線となりました。
体調の良い時は、共に喜び。苦しい時には、共に歯を食いしばり。
身体的には厳しい毎日でしたが、心は満たされていました。
幸せにさえ、思えていたものです。
私は支えてくださる皆さんの真心を追い風に、
心ある人たちと力を合わせる事で、この窮地を乗り切る事ができました。
私は、これまでの人生を通して、生かされている自分というものを、
強く意識するようになりました。
私は毎日、多くの人々に支えられて生きています。生かされています。
また、私は、自然と対峙するたびに、
自然の大きな懐に包まれている事を感じるのです。
生かされている安心感を覚えるのです。
私は、生きている事の喜びを、生かされていることの幸せを。
この身の全てで、この心の全てで受け止めて生きています。
だからこそ、何気ない毎日が嬉しいのです。愛おしいのです。
今ある事に、感謝して。与えられた日々を、精一杯生きる。
不平不満が無いとは言いません。嫉妬もすれば、妬みもします。
しかし、私は生きているのです。生かされているのです。
ありがたい事ではありませんか。
不平不満に取り付かれ、嫉妬や妬みに心を惑わせるなど。
この喜びにくらべると、本当に小さな事だと思えるのです。
私は日々、生きがいを咲かせ、希望を持って生きています。
そういう毎日が、私の人生を充実したものにしてくれているのです。
私は、生かされてここにいます。
生かされている事に感謝しつつ、自らも生きる姿勢を持って生きています。
そうしてこそ、豊かな人生を得られるのではないでしょうか。
私は詩作という生きがいを咲かせ、心豊かに、満たされた日々を送っています。
私は生きています。今は、自信を持ってそう言えます。
自分の確固たる意識を基に、私らしく、あるがままに生きています。
私が私であることに、感謝せずにはいられません。
私は幸せです。私は恵まれています。
この人生を与えてくれた全てのものに、全ての人々に、心から感謝しています。
私にも、明日がやってくるのです。
私は、幸せです。
* * * * *
もし、心に響いたら、波長が合いましたら、
お友達にも転送して多くの人に講演を聞いていただけたら幸いです。
四方さんのことを紹介している関連サイトは、
こちらをクリック
こちらもクリック
すばらしいですね。私たちは本当に「生かされている」のですね。今ある幸せに心底から感謝の気持ちが芽生えてきます。
すべてのものに「ありがとう」。
ではまた。

白骨の章
ちょっとしぶいお話で。
私は、経営者になってからお付き合いの関係もあり、様々な方々のご葬儀に参列することがあります。
あるご葬儀に参列した時、そこで、はじめて浄土真宗本願寺の蓮如上人の「白骨の章」を聞きました。すごく感動し、落涙しましたので、以下に写経ならぬ写文します。
「夫(それ)、人間の浮生(ふしょう)なる相を、つらつら観ずるに。
おほよそはかなきものは、この世の始中終(しちゅうじゅう)、まぼろしのごとくなる一期(いちご)なり。
されば、いまだ萬歳(まんざい)の人身をうけたりといふ事をきかず、一生すぎやすし。
いまにいたりてたれか百年の形体(ぎょうたい ただ、本当は骨へんに豊かという字です。)をたもつべきや、我やさき、人やさき、けふともしらずあすともしらず。
おくれさきだつ人は、もとのしづくすゑの露よりもしげしといへり。
されば、朝(あした)には紅顔ありて、夕(ゆうべ)には白骨となれる身なり。
すでに無常の風きたりぬれば、すなわちふたつのまなこたちまちにとぢ、ひとつのいきながくたへぬれば。
紅顔むなしく変じて、桃李(とうり)のよそほひをうしなひるときは、六親眷属(ろくしんけんぞく)あつまりて、なげきかなしめども、更にその甲斐あるべからず。
さてしもあるべきことならねばとて、野外におくりて夜半(よわ)のけむりとなしはてぬれば。
ただ白骨のみぞのこれり。
あはれといふも中々をろかなり。
されば人間のはかなき事は、老少不定のさかひなれば。
たれの人も、はやく後生の一大事を心にかけて。
阿弥陀仏をふかくたのみまゐらせて、念仏まうすべきものなり。
あなかしこあなかしこ。」
すごい文章ですね。本当に深い深い・・・・。
とくに、「ただ白骨のみぞのこれり。」「あはれといふも中々をろかなり。」というところで、はからずも落涙いたしました。
そして、この文章のすごいところは、この文を聞いた人の心理の変化を、まるで仏の御導きよろしく教えているところだと思います。
私は、「生身ひとつで生き抜く勇気・気迫」みたいな感性を得ました。
ただ、すぐ忘れるでしょうけどねそれも、ひとつの無常ということでいや、やっぱり言い訳でしょうか・・・・とほほ
よろしかったら参考にしてください。
なお、上記の文の口語訳は、さきほど探しましたら、以下のページに掲載されていました。
http://www.hokuriku.ne.jp/~yabumoto/yabuhp/10.htm
ではまた。

私は、経営者になってからお付き合いの関係もあり、様々な方々のご葬儀に参列することがあります。
あるご葬儀に参列した時、そこで、はじめて浄土真宗本願寺の蓮如上人の「白骨の章」を聞きました。すごく感動し、落涙しましたので、以下に写経ならぬ写文します。
「夫(それ)、人間の浮生(ふしょう)なる相を、つらつら観ずるに。
おほよそはかなきものは、この世の始中終(しちゅうじゅう)、まぼろしのごとくなる一期(いちご)なり。
されば、いまだ萬歳(まんざい)の人身をうけたりといふ事をきかず、一生すぎやすし。
いまにいたりてたれか百年の形体(ぎょうたい ただ、本当は骨へんに豊かという字です。)をたもつべきや、我やさき、人やさき、けふともしらずあすともしらず。
おくれさきだつ人は、もとのしづくすゑの露よりもしげしといへり。
されば、朝(あした)には紅顔ありて、夕(ゆうべ)には白骨となれる身なり。
すでに無常の風きたりぬれば、すなわちふたつのまなこたちまちにとぢ、ひとつのいきながくたへぬれば。
紅顔むなしく変じて、桃李(とうり)のよそほひをうしなひるときは、六親眷属(ろくしんけんぞく)あつまりて、なげきかなしめども、更にその甲斐あるべからず。
さてしもあるべきことならねばとて、野外におくりて夜半(よわ)のけむりとなしはてぬれば。
ただ白骨のみぞのこれり。
あはれといふも中々をろかなり。
されば人間のはかなき事は、老少不定のさかひなれば。
たれの人も、はやく後生の一大事を心にかけて。
阿弥陀仏をふかくたのみまゐらせて、念仏まうすべきものなり。
あなかしこあなかしこ。」
すごい文章ですね。本当に深い深い・・・・。
とくに、「ただ白骨のみぞのこれり。」「あはれといふも中々をろかなり。」というところで、はからずも落涙いたしました。
そして、この文章のすごいところは、この文を聞いた人の心理の変化を、まるで仏の御導きよろしく教えているところだと思います。
私は、「生身ひとつで生き抜く勇気・気迫」みたいな感性を得ました。
ただ、すぐ忘れるでしょうけどねそれも、ひとつの無常ということでいや、やっぱり言い訳でしょうか・・・・とほほ
よろしかったら参考にしてください。
なお、上記の文の口語訳は、さきほど探しましたら、以下のページに掲載されていました。
http://www.hokuriku.ne.jp/~yabumoto/yabuhp/10.htm
ではまた。

勝つためには五つのポイントがある 孫子の兵法
孫子の兵法です。
孫子は、勝つためのポイントとして、統率に関する次の五項目を挙げている。
すべてマネジメントの問題、いわゆる人の問題である。
1.戦うべきと戦うべからざるとを知る者は勝つ
トップの意思決定が第一。
情報(彼を知り己を知る)と七計(以下に記す)にもとづく判断力。
七計とは
主、いずれが道あるか、将、いずれが能あるか、
天地、いずれが得たるか、法令、いずれが行わるるか、
兵衆、いずれが強きか、士卒、いずれが練れたるか、
賞罰、いずれが明らかなるか、
われ、これをもって勝負を知る。
①トップは、どちらが明確な方針をもっているか。
②指導部は、どちらが有能か。
③時機および状況は、どちらが有利か。
④管理は、どちらが行き届いているか。
⑤第一線の働き手は、どちらがやる気をもっているか。
⑥中間リーダーは、どちらが経験を積んでいるか。
⑦業績評価は、どちらが公平的確に行われているか。
2.衆寡の用を識る者は勝つ
兵力に応じた運用法、つまりもっとも効率的な戦い方をすること。
3.上下の欲を同じうする者は勝つ
全メンバーの意思を同方向に向ける目標が設定されていること。
この言葉は、ふつう「君主と国民とが心を一つにすること」というように理解されている。
だが、君主と国民が「心」を一つにすることなど、できるはずがない。
それは、上司と部下、トップと社員、リーダーとメンバーの関係にしても同じであって、人は立場によって、それぞれの思惑を持っているのが当然である。
孫子は精神主義者ではなく、漠然と「心を一つにせよ」といっているのではない。
「欲」を同じくせよといっているのである。「欲」とは「・・・・・したい」ということである。
人によってちがう「心」を完全に一致させることは、夫婦、親子でもむずかしい。
しかし、ある特定の目標にむけて「・・・・したい」という欲望を一致させることはできる。
共通の目標を設定することは、共同行動の前提であり、それが成功の大きな条件となる。
組織を動かすリーダーは、メンバーの「心」をまるまる自分と同じようにしようなどという大それたことを考えるよりも、全員が参加し、やる気を起こすような目標を見出すことに力を注ぐがよい。
「意」は、やはり「心そのもの」ではなく、「心の向かう方向」のことである。
4.虞をもって不虞を待つ者は勝つ
「虞(ぐ)」は事前に万全の対応策を練ること。
つまり不確実性への対応であり、あらゆる可能性を仮定して、それに応じた代替策を作成しておくべき。
5.将、能にして、君、御せざる者は勝つ
有能な将を任命したら、これを信頼し、細かく干渉してはならない。
日露戦争に際し満州軍総司令官に任ぜられた元帥大山巌は、智将児玉源太郎を総参謀長に起用すると、作戦はすべて児玉にまかせた。
遼陽の会戦のときなど、ロシア軍の砲弾が司令部の近くに落下するほどで、児玉以下、必死になって作戦を練っていたが、隣室で寝ていた大山は悠然と顔を出し、「今日も戦争はごわすか」といったという。
児玉は思う存分力を発揮することができた。
神経質で、なんでも自分でやらなければ気がすまない上司の下では、部下はやる気を失ってしまう。
委ねた以上は思いきってやらせることだ。
これは決して「無責任」がよいということではない。
大山巌は実は緻密な人間であり、もちろん大綱をつかんでいたのである。
権限委譲は、組織管理において、古くて新しい今日的テーマである。
今までのバックナンバー
http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
http://katsu.i-ra.jp/e4115.html
http://katsu.i-ra.jp/c138.html
孫子は、勝つためのポイントとして、統率に関する次の五項目を挙げている。
すべてマネジメントの問題、いわゆる人の問題である。
1.戦うべきと戦うべからざるとを知る者は勝つ
トップの意思決定が第一。
情報(彼を知り己を知る)と七計(以下に記す)にもとづく判断力。
七計とは
主、いずれが道あるか、将、いずれが能あるか、
天地、いずれが得たるか、法令、いずれが行わるるか、
兵衆、いずれが強きか、士卒、いずれが練れたるか、
賞罰、いずれが明らかなるか、
われ、これをもって勝負を知る。
①トップは、どちらが明確な方針をもっているか。
②指導部は、どちらが有能か。
③時機および状況は、どちらが有利か。
④管理は、どちらが行き届いているか。
⑤第一線の働き手は、どちらがやる気をもっているか。
⑥中間リーダーは、どちらが経験を積んでいるか。
⑦業績評価は、どちらが公平的確に行われているか。
2.衆寡の用を識る者は勝つ
兵力に応じた運用法、つまりもっとも効率的な戦い方をすること。
3.上下の欲を同じうする者は勝つ
全メンバーの意思を同方向に向ける目標が設定されていること。
この言葉は、ふつう「君主と国民とが心を一つにすること」というように理解されている。
だが、君主と国民が「心」を一つにすることなど、できるはずがない。
それは、上司と部下、トップと社員、リーダーとメンバーの関係にしても同じであって、人は立場によって、それぞれの思惑を持っているのが当然である。
孫子は精神主義者ではなく、漠然と「心を一つにせよ」といっているのではない。
「欲」を同じくせよといっているのである。「欲」とは「・・・・・したい」ということである。
人によってちがう「心」を完全に一致させることは、夫婦、親子でもむずかしい。
しかし、ある特定の目標にむけて「・・・・したい」という欲望を一致させることはできる。
共通の目標を設定することは、共同行動の前提であり、それが成功の大きな条件となる。
組織を動かすリーダーは、メンバーの「心」をまるまる自分と同じようにしようなどという大それたことを考えるよりも、全員が参加し、やる気を起こすような目標を見出すことに力を注ぐがよい。
「意」は、やはり「心そのもの」ではなく、「心の向かう方向」のことである。
4.虞をもって不虞を待つ者は勝つ
「虞(ぐ)」は事前に万全の対応策を練ること。
つまり不確実性への対応であり、あらゆる可能性を仮定して、それに応じた代替策を作成しておくべき。
5.将、能にして、君、御せざる者は勝つ
有能な将を任命したら、これを信頼し、細かく干渉してはならない。
日露戦争に際し満州軍総司令官に任ぜられた元帥大山巌は、智将児玉源太郎を総参謀長に起用すると、作戦はすべて児玉にまかせた。
遼陽の会戦のときなど、ロシア軍の砲弾が司令部の近くに落下するほどで、児玉以下、必死になって作戦を練っていたが、隣室で寝ていた大山は悠然と顔を出し、「今日も戦争はごわすか」といったという。
児玉は思う存分力を発揮することができた。
神経質で、なんでも自分でやらなければ気がすまない上司の下では、部下はやる気を失ってしまう。
委ねた以上は思いきってやらせることだ。
これは決して「無責任」がよいということではない。
大山巌は実は緻密な人間であり、もちろん大綱をつかんでいたのである。
権限委譲は、組織管理において、古くて新しい今日的テーマである。

今までのバックナンバー
http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
http://katsu.i-ra.jp/e4115.html
http://katsu.i-ra.jp/c138.html
孫子の兵法 兵勢編
雑然と入り乱れていながら、しかし乱すことができない。はじめも終わりもなくつながっていて捉えどころがないと、逆に破ることができない。
久々に、「孫子の兵法」です。
(今までのバックナンバーはこちらです。)
http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
http://katsu.i-ra.jp/e4115.html
今回の話題は、私が「孫子の兵法」を読んで、一番びびった内容です。
何度も言う様に、この書は2400年~2500年前に書かれたものなんですよ。これは、本当にすごい!!

このIT全盛の時代、変化が秒速で進んでいる現代においても十二分に通じるお話です。
この書が、いかに普遍的な内容を書いているか。
人の世はいつの時代になっても変わらないところは、本当に変わらないものなんですね。
さて、冒頭の文章を読んでみてください。
ほぼ、文章どおりの意味なんですが、これは大変優れた組織論です。
組織というものは硬直したときに、すでに崩壊の道を辿っています。
一見、組織の中の個人を見ていると、勝手気ままに動いているようで、その実、まるでアメーバーのように組織が成り立っている。
こういう組織がもっとも強い組織です。とにかく敵にはその組織の正体がまったく分かりません。
まるで雲を捕まえるようなものです。まったくとらえどころがありません。
そして、変化に大変強い組織です。常に変化しています。
形式にとらわれない活力ある会社の形態は、常にこのような形態に自然となっていっています。
整然として、どこから見ても非の打ち所のない組織。これがもっとも危険な状態であるということを、2400年以上も前に、孫子は言っているのです。すごい書です。

孫子の兵法~敗軍の形~つづき
前回 → http://katsu.i-ra.jp/e4082.html
前日の続きで、「崩」と「乱」について述べます。
重要幹部が不平を抱いて、自分勝手に戦うような状態でありながら、トップは、部下の能力を正しく認識していないような場合。
トップが補佐役の気持ちをよく理解していないと、思いがけないとき、思いがけないことで、足もとをすくわれることになるかもしれない。
指導部の不一致-それは組織の「崩」を意味する。
この対策としては、「陥」の場合と同じく「下々を充実させる」、即ち、部下とのコミュニケーション、処遇、教育等々が必要だということである。
いうまでもなく「乱」(混乱の極み)である。
将の厳しさについては、「尉綾子(うつりょうし)」が次のように言っている。
「威は変ぜざるにあり。それ将は、上、天に制せられず、下、地に制せられず、中、人に制せられず。」
即ち、あらゆる干渉、横槍、制約、雑音に左右されることなく、信念を貫くこと、それが将の真の威厳に通ずる。
前日の続きで、「崩」と「乱」について述べます。
「大吏は怒りて服せず、敵に遭えばうらみて自ら戦い、将はその能を知らざるを崩という」。
重要幹部が不満を抱いていて勝手に戦い、しかも将は部下の能力を知らない。そうした状態は「崩」である。
重要幹部が不平を抱いて、自分勝手に戦うような状態でありながら、トップは、部下の能力を正しく認識していないような場合。
トップが補佐役の気持ちをよく理解していないと、思いがけないとき、思いがけないことで、足もとをすくわれることになるかもしれない。
指導部の不一致-それは組織の「崩」を意味する。
この対策としては、「陥」の場合と同じく「下々を充実させる」、即ち、部下とのコミュニケーション、処遇、教育等々が必要だということである。
「将の弱くして厳ならず、教道も明らかならずして、吏卒は常なく、兵を陳ぬること縦横なるを乱という」。
将が弱気で厳しさを欠き、方針も不明確で、幹部も兵士も動揺し、部隊の配置も混乱、こうした状態は「乱」である。
いうまでもなく「乱」(混乱の極み)である。
将の厳しさについては、「尉綾子(うつりょうし)」が次のように言っている。
「威は変ぜざるにあり。それ将は、上、天に制せられず、下、地に制せられず、中、人に制せられず。」
即ち、あらゆる干渉、横槍、制約、雑音に左右されることなく、信念を貫くこと、それが将の真の威厳に通ずる。
孫子の兵法~敗軍のかたち~
二日続けて、孫子を取り上げます。
本日は「敗軍のかたち」。
これは、現代におきかえると、さしずめ「事業失敗のパターン」というところでしょうか。
そういう目でみると、大変示唆に富んだ言葉です。
孫子は、敗軍のかたちとその原因を六つに分類。
そして、その原因を、誰のせいでもなく、将の責任、指導者の管理責任である、と言っています。
走 ・・・・ 敗走。兵力の集中と分散についての作戦を誤り、少数で大敵にぶつかった場合。
弛 ・・・・ 軍規のゆるみ (下の項参考)
陥 ・・・・ 戦力の空洞化 (下の項参考)
崩 ・・・・ 指導部の不一致 (これはまた別の機会に詳しく述べます。)
乱 ・・・・ 戦闘部隊の混乱 (これもまた別の機会に詳しく述べます。)
北 ・・・・ 戦線離脱。敵の兵力推定を誤った結果、弱兵が強兵にぶつかった場合。
-部下が強くて、幹部、指揮官が弱い。
そういうときに一つの組織が陥る状態を「弛」という。
-部下の方が能力あって、長は無能である場合。
-部下はやる気があって、長はやる気がない場合。
組織は正常な運営ができなくなる。
-幹部が強力(もしくは有能)であって、部下が弱い(無能な)場合。
こういうときには、その軍は「陥」(窮地に陥る)になる。
幹部が立派で有能だと、その組織全体がいかにもよくみえる。ところが内容は空洞化している。実践ではたちまち敗れてしまう。「もろい組織」。崩壊寸前の危機状態である。
「上にたつ者は、下々を充実させ、富ませるがよい。それによってのみ自分の立場も固まる。」(「易経」より)
(あらためて社員教育の重要さを認識します。管理職は、部下を育ててはじめて有能なんですね。)
「崩」と「乱」については、明日、述べたいと思います。では。
孫子の兵法シリーズ-将に五危あり → http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
本日は「敗軍のかたち」。
これは、現代におきかえると、さしずめ「事業失敗のパターン」というところでしょうか。
そういう目でみると、大変示唆に富んだ言葉です。
兵には走なるものあり、弛なるものあり、陥なるものあり、崩なるものあり、乱なるものあり、北なるものあり。およそこの六者は天の災にあらず、将の過ちなり。
孫子は、敗軍のかたちとその原因を六つに分類。
そして、その原因を、誰のせいでもなく、将の責任、指導者の管理責任である、と言っています。
走 ・・・・ 敗走。兵力の集中と分散についての作戦を誤り、少数で大敵にぶつかった場合。
弛 ・・・・ 軍規のゆるみ (下の項参考)
陥 ・・・・ 戦力の空洞化 (下の項参考)
崩 ・・・・ 指導部の不一致 (これはまた別の機会に詳しく述べます。)
乱 ・・・・ 戦闘部隊の混乱 (これもまた別の機会に詳しく述べます。)
北 ・・・・ 戦線離脱。敵の兵力推定を誤った結果、弱兵が強兵にぶつかった場合。
「卒の強くして吏の弱きを弛という」。
兵士が強くて指揮官が弱い状態は「弛」である。
-部下が強くて、幹部、指揮官が弱い。
そういうときに一つの組織が陥る状態を「弛」という。
-部下の方が能力あって、長は無能である場合。
-部下はやる気があって、長はやる気がない場合。
組織は正常な運営ができなくなる。
「吏の強くして卒の弱きを陥という。」
指揮官が強くて兵士が弱い状態は「陥」である。
-幹部が強力(もしくは有能)であって、部下が弱い(無能な)場合。
こういうときには、その軍は「陥」(窮地に陥る)になる。
幹部が立派で有能だと、その組織全体がいかにもよくみえる。ところが内容は空洞化している。実践ではたちまち敗れてしまう。「もろい組織」。崩壊寸前の危機状態である。
「上にたつ者は、下々を充実させ、富ませるがよい。それによってのみ自分の立場も固まる。」(「易経」より)
(あらためて社員教育の重要さを認識します。管理職は、部下を育ててはじめて有能なんですね。)
「崩」と「乱」については、明日、述べたいと思います。では。
孫子の兵法シリーズ-将に五危あり → http://katsu.i-ra.jp/e4050.html
孫子の兵法~将に五危あり~
将に五危あり。必死は殺さるべきなり。
必生は虜にさるべきなり。ふんそくは侮らるべきなり。
廉潔は辱しめらるべきなり。愛民は煩さるべきなり。
孫子の言葉には、現代にも通じる「知恵と謀(戦略)」が溢れています。
このブログでも折に触れて、孫子の言葉をテーマに、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。
今回は、「将の心得」を説いたものを挙げました。まさしく、現代のリーダー(経営者等々)に必要とされる「心得(精神状態)」です。
1.必死になり過ぎる者は危ない ・・・・ 心のゆとりを失い、対局の判断もできず犬死してしまう。
2.生に執着しすぎる者は危ない ・・・・ 臆病になって卑怯なふるまいをし、あげくの果ては捕虜にされてしまう。
3.いらだつ者は危ない ・・・・ 怒りっぽくなり、部下からも敵からも足元を見透かされる。
4.潔癖すぎる者は危ない ・・・・ 面子にこだわり、恥を気にして、実をとることを忘れる。
5.人情家は危ない ・・・・ そのために気を遣い、部下に同情しすぎて、厳しくなれない。
孫子曰く、「この五つは、将として持ってはならない欠陥であり、作戦の妨げとなる。軍を滅ぼし、将を死に追い込むのは、必ずこれが原因となっている。よくよく考えることだ」
皆さん、どうですか?
含蓄のある深い言葉ですね。私もこの五つの心得を考えさせられることが、普段の仕事上のあらゆる場面で遭遇します。
今から2400年~2500年前の知恵ですが、現代に十分過ぎるほど当てはまります。
うーん、忘れてはならない言葉です。
では。
南蔵院の林住職
先日、「伊豆八十八札所巡礼」のお話をしましたよね。
http://katsu.i-ra.jp/e1635.html
その巡礼ツアーの際に、バスの中で、「南蔵院の林住職」のビデオを見せられたのです。
私は「南蔵院の林住職」のことをそれまで一切知らなかったので、「なんだ。坊主の話か。ありがたいお話だろうけど、昨日、あまり寝てないので、おそらくバスの中で寝てしまうだろうなあ。」という、かなり不届きな心持で、見始めたのです。
そうしたところ、見始めたとたんに、どんどんどんどんどんどん・・・(どこまで続くの? )。
)。
引き寄せられるように見入ってしまい、なんて面白い住職だろう、と思ってしまいました。
となりにうちの中3の息子もいたのですが、彼も最初は「またうるさい話が始まりやがった」と思っていたのでしょう。PSPのゲームに夢中に。ところが、次第にビデオの話を、いやいやながら(親の前なので少しテレがあるのでしょう。態度は不承不承といった形なのですが)聞き始めていました。
住職の話は、お笑いあり涙ありの、しかも回転よくスピード感たっぷり。
60分の話があっという間に終わってしまった、という感じでした。
この林住職の話も、ぜひとも社員さんたちに聞かせてあげたい、と思い、早速ビデオを発注。実は昨日手元に届きました。
あとで聞いたのですが、今この林住職のビデオは非常によく売れているらしく、注文しても2週間ぐらいかかるかもしれないほどなんだそうです。
「人としてどう生きるか」を分かりやすく、大きく笑いころげながら聞ける内容です。
ご興味ある方は、「南蔵院」の公式HPをごらんになってみてください。
http://www.nanzoin.com/
ビデオの販売もしています。
ではまた。


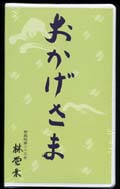
http://katsu.i-ra.jp/e1635.html
その巡礼ツアーの際に、バスの中で、「南蔵院の林住職」のビデオを見せられたのです。
私は「南蔵院の林住職」のことをそれまで一切知らなかったので、「なんだ。坊主の話か。ありがたいお話だろうけど、昨日、あまり寝てないので、おそらくバスの中で寝てしまうだろうなあ。」という、かなり不届きな心持で、見始めたのです。
そうしたところ、見始めたとたんに、どんどんどんどんどんどん・・・(どこまで続くの?
 )。
)。引き寄せられるように見入ってしまい、なんて面白い住職だろう、と思ってしまいました。
となりにうちの中3の息子もいたのですが、彼も最初は「またうるさい話が始まりやがった」と思っていたのでしょう。PSPのゲームに夢中に。ところが、次第にビデオの話を、いやいやながら(親の前なので少しテレがあるのでしょう。態度は不承不承といった形なのですが)聞き始めていました。
住職の話は、お笑いあり涙ありの、しかも回転よくスピード感たっぷり。
60分の話があっという間に終わってしまった、という感じでした。
この林住職の話も、ぜひとも社員さんたちに聞かせてあげたい、と思い、早速ビデオを発注。実は昨日手元に届きました。
あとで聞いたのですが、今この林住職のビデオは非常によく売れているらしく、注文しても2週間ぐらいかかるかもしれないほどなんだそうです。
「人としてどう生きるか」を分かりやすく、大きく笑いころげながら聞ける内容です。
ご興味ある方は、「南蔵院」の公式HPをごらんになってみてください。
http://www.nanzoin.com/
ビデオの販売もしています。
ではまた。


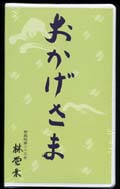
自分自身のルール
以前、お話していた「高橋歩」の「人生の地図」という本から。
http://katsu.i-ra.jp/e1237.html
あるOLの言葉
「私は、私自身の考える『美しい女』に少しでも近づくために生きてる気がする。
外見も能力も精神的なことも含めて、とにかく、『美しい女になるため』だけに、すべての時間を使ってるし、それ以外のことは、やらないようにしてる。それが、いくら楽しそうなことでも、お金が入ることでもね。いろんな誘惑に流されずに、完璧に自分を管理して、いつも輝いていたいもん。」
アイルトン・セナ
「自分が感じていることは、正しくないかもしれない。
もしかしたら、自分の五感すべてが、間違っているのかもしれない。
だから、常に自分をオープンにしておくんだ。
あらゆる情報や、たくさんの知識を、受け入れられるように。
耳を傾けて、新しい情報を、聞き逃さないように。
そうすれば人間も、マシンも、徐々に限界を越えていけると、僕は信じているんだ。」
武者小路実篤
「自分は一個の人間でありたい。
誰にも利用されない
誰にも頭をさげない
一個の人間でありたい。
他人を利用したり
他人をいびつにしたりしない
そのかわり自分もいびつにされない
一個の人間でありたい。
自分の最も深い泉から
最も新鮮な
生命の泉をくみとる
一個の人間でありたい。
誰もが見て
これでこそ人間だと思う
一個の人間でありたい。
一個の人間は
一個の人間でいいのではないか
一個の人間
独立人同志が
愛しあい、尊敬しあい、力をあわせる。
それは実に美しいことだ。
だが他人を利用して得をしようとするものは、いかに醜いか。
その醜さを本当に知るものが一個の人間。」
私は、この「自分自身のルール」というのが、もっとも大切だと、常日頃考えています。
また、どこかでお話したいと思いますが、「自分自身が、人の借り物ではない、ゼロベースから築き上げた、自分自身の価値観」、これがある人は、本当に強い。誰がなんと言おうと、支点が定まっています。
私もはやくそうなりたい、と思っています。
皆さんは、お持ちですか?
「自分自身のルール」を。

http://katsu.i-ra.jp/e1237.html
あるOLの言葉
「私は、私自身の考える『美しい女』に少しでも近づくために生きてる気がする。
外見も能力も精神的なことも含めて、とにかく、『美しい女になるため』だけに、すべての時間を使ってるし、それ以外のことは、やらないようにしてる。それが、いくら楽しそうなことでも、お金が入ることでもね。いろんな誘惑に流されずに、完璧に自分を管理して、いつも輝いていたいもん。」
アイルトン・セナ
「自分が感じていることは、正しくないかもしれない。
もしかしたら、自分の五感すべてが、間違っているのかもしれない。
だから、常に自分をオープンにしておくんだ。
あらゆる情報や、たくさんの知識を、受け入れられるように。
耳を傾けて、新しい情報を、聞き逃さないように。
そうすれば人間も、マシンも、徐々に限界を越えていけると、僕は信じているんだ。」
武者小路実篤
「自分は一個の人間でありたい。
誰にも利用されない
誰にも頭をさげない
一個の人間でありたい。
他人を利用したり
他人をいびつにしたりしない
そのかわり自分もいびつにされない
一個の人間でありたい。
自分の最も深い泉から
最も新鮮な
生命の泉をくみとる
一個の人間でありたい。
誰もが見て
これでこそ人間だと思う
一個の人間でありたい。
一個の人間は
一個の人間でいいのではないか
一個の人間
独立人同志が
愛しあい、尊敬しあい、力をあわせる。
それは実に美しいことだ。
だが他人を利用して得をしようとするものは、いかに醜いか。
その醜さを本当に知るものが一個の人間。」
私は、この「自分自身のルール」というのが、もっとも大切だと、常日頃考えています。
また、どこかでお話したいと思いますが、「自分自身が、人の借り物ではない、ゼロベースから築き上げた、自分自身の価値観」、これがある人は、本当に強い。誰がなんと言おうと、支点が定まっています。
私もはやくそうなりたい、と思っています。
皆さんは、お持ちですか?
「自分自身のルール」を。

もう一人、素敵な人物を
「高橋歩」という人もかなりユニークな生き方をしています。
世界を旅しながら(放浪しながら)、自然と出版と家族と自由を愛しています。
今流でいうと「超クール」な生き方ですね。すごく共感できるし、彼はかなりオシャレで粋な人だと思います。
彼のホームページもご覧になってみてください。
http://www.ayumu.ch/
このホームページの中の「プロフィール」にCaravanの曲が使われています。
静岡では御前崎で、レオナとかスピナビルがやっている「ウィンドブロー」でもよくCaravanが出てきますよね。
Caravanの曲もかなりオシャレですよ。
とにかく、「高橋歩」はCheck It Out です。

世界を旅しながら(放浪しながら)、自然と出版と家族と自由を愛しています。
今流でいうと「超クール」な生き方ですね。すごく共感できるし、彼はかなりオシャレで粋な人だと思います。
彼のホームページもご覧になってみてください。
http://www.ayumu.ch/
このホームページの中の「プロフィール」にCaravanの曲が使われています。
静岡では御前崎で、レオナとかスピナビルがやっている「ウィンドブロー」でもよくCaravanが出てきますよね。
Caravanの曲もかなりオシャレですよ。
とにかく、「高橋歩」はCheck It Out です。

”森”が先か、”木”が先か Ⅴ
昼間の常葉菊川の余韻も少しおさまりつつある今宵、いかがお過ごしでしょうか?
そろそろ思索の時間では・・・なんちゃって。そんなことはないですかね。
ま、ともかく、このシリーズ早く終わらせないと、皆さんのアクセスが減ってしまうので、とにかく、今回が最終回です。(やっぱりこういう地味な内容はなかなか人気がないですね )
)
大体、写真もなく内容がそんなに面白いものでもないのですから、ここまでお付き合いしてくださっている方が仮にいらっしゃったら、それはもうよほどの変人ですね。私と同じ偏屈おやじですよ、まったく。仲良くしましょ
さてさて、途中からこのシリーズを読み始めた方のために、バックナンバーを。
そもそものはじまり → http://katsu.i-ra.jp/e515.html
Ⅱ → http://katsu.i-ra.jp/e588.html
Ⅲ → http://katsu.i-ra.jp/e609.html
Ⅳ → http://katsu.i-ra.jp/e617.html
よくこんなに書くよね。まったく自分のためですから、ごめんなさい。
さあ、では最終回。はじめましょう。
前回までの話で、「われわれが他人との関係性をより深く認識し、将来に生かしていくために教育(学習)が必要」というところまでいきました。続けます。
私たちが目の前で見ているPCは、「今、現時点での私」が見ている形です。PCの形は、その人の性格や考え方、感じ方、価値観、知識等々によって、まったく異なったものとして映っているはずです。人によっては、目の前のPCを単なるモノとしてとらえているでしょうし、ある人によっては、そのPCの組成が中身がCPUが何々で、と認識した上で見ているでしょうし、単にPCを人間性のない冷たいもの、として見ている人、PCを自分の将来を切り開いてくれる頼もしい味方として見ている人もいます。それぞれの人には、まったく同じPCとしては見えていないはずです。
また、「今、現時点での私」が見ているPCと、「少し過去の私」「少し未来の私」が見ているPCも異なっているはずです。なぜなら、人間の性格や考え方、感じ方、価値観、知識等々は時間によって異なるからです。(これを成長と言い換えてもよいかもしれません。)
即ち、PCは、あなたが見ている「世間」です。そして、その「世間」はあなた自身です。
そして、その「世間」の見方に大きく影響を与えているのが、教育(学習)です。
われわれは、他人との関係性を深く認識し、「世間」の見方をよりよいものとして、または成熟したものとしていくために、そして、そのことを通してよりよく行動し幸せな豊かな時間を享受するために、教育(学習)が必要です。
私の発した質問が、最後は教育論になってしまったようで。決して我田引水ということではなく、私が考える一つの普遍的な「人の生き方」論として読んでいただければ幸いです。
なんだか、最後はわかりにくいお話になってしまったかもしれません。現時点での私の未熟さが現れているものと思います。とにかく、このテーマに終わりはありません。時間が経ち、私も年を経ていけば、その時点での価値観でお話していきます。また何年か経って、このテーマをもう一度探ってみることにしたいと思います。成長していればよいのですが、退歩していたりして・・・・あーっ
というところで、おやすみなさい
そろそろ思索の時間では・・・なんちゃって。そんなことはないですかね。
ま、ともかく、このシリーズ早く終わらせないと、皆さんのアクセスが減ってしまうので、とにかく、今回が最終回です。(やっぱりこういう地味な内容はなかなか人気がないですね
 )
)大体、写真もなく内容がそんなに面白いものでもないのですから、ここまでお付き合いしてくださっている方が仮にいらっしゃったら、それはもうよほどの変人ですね。私と同じ偏屈おやじですよ、まったく。仲良くしましょ

さてさて、途中からこのシリーズを読み始めた方のために、バックナンバーを。
そもそものはじまり → http://katsu.i-ra.jp/e515.html
Ⅱ → http://katsu.i-ra.jp/e588.html
Ⅲ → http://katsu.i-ra.jp/e609.html
Ⅳ → http://katsu.i-ra.jp/e617.html
よくこんなに書くよね。まったく自分のためですから、ごめんなさい。
さあ、では最終回。はじめましょう。
前回までの話で、「われわれが他人との関係性をより深く認識し、将来に生かしていくために教育(学習)が必要」というところまでいきました。続けます。
私たちが目の前で見ているPCは、「今、現時点での私」が見ている形です。PCの形は、その人の性格や考え方、感じ方、価値観、知識等々によって、まったく異なったものとして映っているはずです。人によっては、目の前のPCを単なるモノとしてとらえているでしょうし、ある人によっては、そのPCの組成が中身がCPUが何々で、と認識した上で見ているでしょうし、単にPCを人間性のない冷たいもの、として見ている人、PCを自分の将来を切り開いてくれる頼もしい味方として見ている人もいます。それぞれの人には、まったく同じPCとしては見えていないはずです。
また、「今、現時点での私」が見ているPCと、「少し過去の私」「少し未来の私」が見ているPCも異なっているはずです。なぜなら、人間の性格や考え方、感じ方、価値観、知識等々は時間によって異なるからです。(これを成長と言い換えてもよいかもしれません。)
即ち、PCは、あなたが見ている「世間」です。そして、その「世間」はあなた自身です。
そして、その「世間」の見方に大きく影響を与えているのが、教育(学習)です。
われわれは、他人との関係性を深く認識し、「世間」の見方をよりよいものとして、または成熟したものとしていくために、そして、そのことを通してよりよく行動し幸せな豊かな時間を享受するために、教育(学習)が必要です。
私の発した質問が、最後は教育論になってしまったようで。決して我田引水ということではなく、私が考える一つの普遍的な「人の生き方」論として読んでいただければ幸いです。
なんだか、最後はわかりにくいお話になってしまったかもしれません。現時点での私の未熟さが現れているものと思います。とにかく、このテーマに終わりはありません。時間が経ち、私も年を経ていけば、その時点での価値観でお話していきます。また何年か経って、このテーマをもう一度探ってみることにしたいと思います。成長していればよいのですが、退歩していたりして・・・・あーっ

というところで、おやすみなさい

”森”が先か、”木”が先か Ⅳ
おはようございます
今日はとにかく常葉菊川になってしまうでしょうから、朝の早い内に小難しい話をとっとと進めてまいりましょう!
とにかく、もうこのあたりまで進んでくると、なかなか読み手も少なくなってくるころでしょうから、ほとんど自分のために書いているようなものです。
ひょっとしてまだお付き合いして下さってくる方は、相当奇特な方で、どうもご愁傷さまというしかございません。どうせお付き合いくださっているのですから、どうぞ最後まで・・・南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・・・ちーん
さて、前回の記事(→http://katsu.i-ra.jp/e609.html)では、「物やひとは関係性の中で存在している」、という話をしたつもりですが、伝わっていますでしょうか?
そして、このことは、実は大変大きなことをわれわれに教えてくれているというお話をしました。
それはいったいなんでしょうか?
それは、つまりわれわれが幸せに(ここでは、芳醇な豊かな時間を過ごしていくために、と言い換えます)生きていくためには、教育(学習)が必要である、ということを示しています。
われわれは、他人との関係性の中で生きています。ということは、自らの将来は他人との関係性に大きく影響を受ける、ということです。
自分の将来は自分で決める。ある意味、当然のことなんですが、もう少し深く考えていくと、その将来を決める自分そのものが、他人との関係性の中にいるということです。
そして、この他人との関係性を認識し、自らの将来に生かしていければ、自分の思い描いた未来に近づくことができると私は思っています。
そして、そのために教育(学習)が必要です。われわれが他人との関係性をより深く認識し、将来に生かしていくために教育(学習)が必要です。
実は教育(学習)というのは、そのためにやっていると言って過言ではない、と思っています。
ということで、また続きます。常葉菊川~~~ガンバレー~~~~~~
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e639.html

今日はとにかく常葉菊川になってしまうでしょうから、朝の早い内に小難しい話をとっとと進めてまいりましょう!
とにかく、もうこのあたりまで進んでくると、なかなか読み手も少なくなってくるころでしょうから、ほとんど自分のために書いているようなものです。
ひょっとしてまだお付き合いして下さってくる方は、相当奇特な方で、どうもご愁傷さまというしかございません。どうせお付き合いくださっているのですから、どうぞ最後まで・・・南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏・・・・・・ちーん

さて、前回の記事(→http://katsu.i-ra.jp/e609.html)では、「物やひとは関係性の中で存在している」、という話をしたつもりですが、伝わっていますでしょうか?
そして、このことは、実は大変大きなことをわれわれに教えてくれているというお話をしました。
それはいったいなんでしょうか?
それは、つまりわれわれが幸せに(ここでは、芳醇な豊かな時間を過ごしていくために、と言い換えます)生きていくためには、教育(学習)が必要である、ということを示しています。
われわれは、他人との関係性の中で生きています。ということは、自らの将来は他人との関係性に大きく影響を受ける、ということです。
自分の将来は自分で決める。ある意味、当然のことなんですが、もう少し深く考えていくと、その将来を決める自分そのものが、他人との関係性の中にいるということです。
そして、この他人との関係性を認識し、自らの将来に生かしていければ、自分の思い描いた未来に近づくことができると私は思っています。
そして、そのために教育(学習)が必要です。われわれが他人との関係性をより深く認識し、将来に生かしていくために教育(学習)が必要です。
実は教育(学習)というのは、そのためにやっていると言って過言ではない、と思っています。
ということで、また続きます。常葉菊川~~~ガンバレー~~~~~~

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e639.html
”森”が先か、”木”が先か Ⅲ
明日、続きをと思っていましたが、おそらく明日は常葉菊川で忙しい( ?)でしょうから、今時間があったので、続きを書きます。お付き合いください。
?)でしょうから、今時間があったので、続きを書きます。お付き合いください。
前回は、「自分の性格や考え方、感じ方、価値観、は他人との関係性の中から備わってきたもの、と言える」というところまででした。(前回の記事→http://katsu.i-ra.jp/e588.html)
さて、先に皆さんに問うていたものに、もうひとつありました。忘れていると思いますから、再度質問します。
「皆さんが今見ているパソコンの形状は「パソコンそのもの」が持っているものでしょうか?」
この質問もなんだか人を食ったような質問で、よくわからないものなんですが、実は大変重要な質問です。
勘のいい方はもうお気づきと思いますが、前の問いと連動して考えていけば、この質問の答えも自ずと想像がつきます。
すなわち、あなたが見ているPCの形状は、PCそのものが持っているもの、ということではない、ということです。
これも、普通に常識的に考えれば、PCの形状はPCそのものの形ではないか、そのどこがおかしいのか、ということになります。
しかし、もう少し深く考えてみましょう!
あなたが見ているPCの形は、あなたの目を通して見ています。
即ち、PCの形は、PCそのものとあなたの目との相互作用(関係性)によって決定づけられています。
従って、あなたが見ているPCの形は、あなたとの関係においてのみ成立しているものであって、他の人には、あなたが見ているPCの形とまったく同じものが見えている、とは限らないのです。むしろ、私はまったく異なっているものと思っています。(もちろん、このことを証明することはできないのですが。)
そして、このことは、実は大変大きなことをわれわれに教えてくれています。
ということで、次にお話を進めていきたいのですが、このあとも実はかなり長文が続き、おそらく苦痛以外の何物でもない(え?すでにそうなっているって、ごめんなさい )ので、今度こそ明日にします。多謝。
)ので、今度こそ明日にします。多謝。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e617.html
 ?)でしょうから、今時間があったので、続きを書きます。お付き合いください。
?)でしょうから、今時間があったので、続きを書きます。お付き合いください。前回は、「自分の性格や考え方、感じ方、価値観、は他人との関係性の中から備わってきたもの、と言える」というところまででした。(前回の記事→http://katsu.i-ra.jp/e588.html)
さて、先に皆さんに問うていたものに、もうひとつありました。忘れていると思いますから、再度質問します。
「皆さんが今見ているパソコンの形状は「パソコンそのもの」が持っているものでしょうか?」
この質問もなんだか人を食ったような質問で、よくわからないものなんですが、実は大変重要な質問です。
勘のいい方はもうお気づきと思いますが、前の問いと連動して考えていけば、この質問の答えも自ずと想像がつきます。
すなわち、あなたが見ているPCの形状は、PCそのものが持っているもの、ということではない、ということです。
これも、普通に常識的に考えれば、PCの形状はPCそのものの形ではないか、そのどこがおかしいのか、ということになります。
しかし、もう少し深く考えてみましょう!
あなたが見ているPCの形は、あなたの目を通して見ています。
即ち、PCの形は、PCそのものとあなたの目との相互作用(関係性)によって決定づけられています。
従って、あなたが見ているPCの形は、あなたとの関係においてのみ成立しているものであって、他の人には、あなたが見ているPCの形とまったく同じものが見えている、とは限らないのです。むしろ、私はまったく異なっているものと思っています。(もちろん、このことを証明することはできないのですが。)
そして、このことは、実は大変大きなことをわれわれに教えてくれています。
ということで、次にお話を進めていきたいのですが、このあとも実はかなり長文が続き、おそらく苦痛以外の何物でもない(え?すでにそうなっているって、ごめんなさい
 )ので、今度こそ明日にします。多謝。
)ので、今度こそ明日にします。多謝。次へ → http://katsu.i-ra.jp/e617.html










