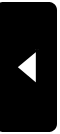「雑感」の記事一覧
スポンサーサイト
スピルバーグ氏について
もう皆さんよくご存知のスティーブン・スピルバーグ。
私の半生の中で、この人の影響は計り知れないものがあります。
私の青年時代から現代まで。
スピルバーグ氏がもたらした「映像マジック」は様々な形で、私の考え方、ものごとの捉え方、想像力、創造力、そして人生に影響を与えています。
私は今でもスピルバーグ氏のようになりたい、と心のどこかで思っています。
「激突」「続激突」「ジョーズ」「未知との遭遇」「1941」・・・「E.T.」「インディ・ジョーンズ」等々。
ありとあらゆる彼の作品を私は見て、そして影響を受けています。
彼の作品のすごいというか、言葉にもならないくらいすばらしいところは、私の言葉ではたった一つ。
Sense of Wonder・・・・この一言です。
もうびっくり。口をあーんぐりあけて・・・・・・の、この感覚。
最初に「激突」見たとき、「ジョーズ」見たとき、「未知との遭遇」見たとき、「E.T.」見たとき・・・・・・まったく今までの映画で見たこともなかった衝撃が私を襲いました。
とにかく、「すごい」んです。そして、それ以上語る言葉が思いつきません。
したがって、友人や知人に話す際は、「とにかく見るしかない」と言うしかない。
クリエイティブ(創造性)の最たるものが彼の中にエネルギッシュに詰まっている、もう創り出すことが楽しくて楽しくて仕方ない、という感じが見る人にもどんどん熱病のように伝わってきました。
彼の映画を見た後のすっきり感。踊りだすようなハイな気持ち。そして、「俺も絶対に彼のようになってやるんだ」と夢遊病のように、うわ言のように、独り言を話しながら、彷徨いながら、自宅に帰った道のりを今でも思い出します。
したがって、私の会社の名前は、こういった感性を引きずりながら、「アイ・クリエイティブ」という名前になっています。
ゆえに、スピルバーグという名前を見ると、その映画を見たくて仕方がなくなってくるのです。
だから、「トランスフォーマー」、見に行っちゃいました。一人で。
作品は面白かったですね。
でも悲しいかな、スピルバーグに備わっていた、Sense of Wonder を感じられなかった。
まあ、もっともこの映画に限らず、最近の彼の映画では、なかなかこのSense of Wonder を感じることが少なくなってきていました。「A.I.」くらいまでは彼のクリエイティブさに驚きと才能を感じていましたが、どうもここのところの映画は、スピルバーグでなくてもよいのでは、という映画が増えてきたような気がします。
これは決して、彼の創造性が衰えたわけでもないのかもしれません。やはり彼も私も、言いたくはありませんが、年をとってしまったのかもしれません。ちょっと寂しいですが。
それと同時に、彼がもっとも油の乗っていて、次々にSense of Wonder を繰り出していた時期と私の青春期が重なり合っていることに大変幸福を感じます。
現代のティーンエイジャーの人たちは、映画を見てSense of Wonder を感じることがあるのでしょうか?
強い衝撃を受け、自分の人生そのものに大きな影響を受けるような経験ってあるのでしょうか?
昨日の「トランスフォーマー」を見終わって帰ってくる道すがら、そんなことを思わず考えてしまいました。
どうなんでしょうか?またよかったら、ティーンエイジャーの方がいらっしゃったら、教えてください。よろしく。では。
私の半生の中で、この人の影響は計り知れないものがあります。
私の青年時代から現代まで。
スピルバーグ氏がもたらした「映像マジック」は様々な形で、私の考え方、ものごとの捉え方、想像力、創造力、そして人生に影響を与えています。
私は今でもスピルバーグ氏のようになりたい、と心のどこかで思っています。
「激突」「続激突」「ジョーズ」「未知との遭遇」「1941」・・・「E.T.」「インディ・ジョーンズ」等々。
ありとあらゆる彼の作品を私は見て、そして影響を受けています。
彼の作品のすごいというか、言葉にもならないくらいすばらしいところは、私の言葉ではたった一つ。
Sense of Wonder・・・・この一言です。
もうびっくり。口をあーんぐりあけて・・・・・・の、この感覚。
最初に「激突」見たとき、「ジョーズ」見たとき、「未知との遭遇」見たとき、「E.T.」見たとき・・・・・・まったく今までの映画で見たこともなかった衝撃が私を襲いました。
とにかく、「すごい」んです。そして、それ以上語る言葉が思いつきません。
したがって、友人や知人に話す際は、「とにかく見るしかない」と言うしかない。
クリエイティブ(創造性)の最たるものが彼の中にエネルギッシュに詰まっている、もう創り出すことが楽しくて楽しくて仕方ない、という感じが見る人にもどんどん熱病のように伝わってきました。
彼の映画を見た後のすっきり感。踊りだすようなハイな気持ち。そして、「俺も絶対に彼のようになってやるんだ」と夢遊病のように、うわ言のように、独り言を話しながら、彷徨いながら、自宅に帰った道のりを今でも思い出します。
したがって、私の会社の名前は、こういった感性を引きずりながら、「アイ・クリエイティブ」という名前になっています。
ゆえに、スピルバーグという名前を見ると、その映画を見たくて仕方がなくなってくるのです。
だから、「トランスフォーマー」、見に行っちゃいました。一人で。
作品は面白かったですね。
でも悲しいかな、スピルバーグに備わっていた、Sense of Wonder を感じられなかった。
まあ、もっともこの映画に限らず、最近の彼の映画では、なかなかこのSense of Wonder を感じることが少なくなってきていました。「A.I.」くらいまでは彼のクリエイティブさに驚きと才能を感じていましたが、どうもここのところの映画は、スピルバーグでなくてもよいのでは、という映画が増えてきたような気がします。
これは決して、彼の創造性が衰えたわけでもないのかもしれません。やはり彼も私も、言いたくはありませんが、年をとってしまったのかもしれません。ちょっと寂しいですが。
それと同時に、彼がもっとも油の乗っていて、次々にSense of Wonder を繰り出していた時期と私の青春期が重なり合っていることに大変幸福を感じます。
現代のティーンエイジャーの人たちは、映画を見てSense of Wonder を感じることがあるのでしょうか?
強い衝撃を受け、自分の人生そのものに大きな影響を受けるような経験ってあるのでしょうか?
昨日の「トランスフォーマー」を見終わって帰ってくる道すがら、そんなことを思わず考えてしまいました。
どうなんでしょうか?またよかったら、ティーンエイジャーの方がいらっしゃったら、教えてください。よろしく。では。
さあて・・・・参院選について独断・偏見
やっぱり自民党のぼろ負けでしたね。
これについて、マスコミ各社いろいろと論評されています。
私は凡人なので、私なりに自分の考えをまとめる意味で。
いろいろな観点があると思いますが、私は安部さんの視点と、われわれ生活者の視点のずれ、という視点でお話したいと思います。
先ほど、田原総一朗氏の以下の評論を読みました。
ここをクリック
ちょっと長いですが、面白いので、お時間ある方は読んでみてください。
私は、結構田原さんのいろいろな話は面白いし、私も同調することが多いので、よく読んでいます。
今回の若手官僚の話・・・財政赤字や少子化、環境問題、イラクや北朝鮮問題、これらの、今後の日本の針路を考えるに当たって、大変重要な問題が、今回の選挙ではまったく議論にならなくて、年金の問題、赤城農水大臣のお金の問題に終始した、今回の選挙。いったいこの国の、国民の問題意識はどうなっているのか。レベルが低すぎるのではないか。という若手官僚の問題意識。
ある一面、私はまったくもっともなことだと思います。
実際のところ、行政を担当する人間として、この問題意識は実は大変重要なことだと思います。
きっと彼は、日夜この問題にさらされて仕事を進めているのでしょう。
従って、彼にとっては、これらの問題・・・財政赤字や少子化、環境問題、イラクや北朝鮮問題、が生活レベルの問題となっているに違いありません。
では、翻って、われわれ国民の多くは、これらの問題が生活レベルに落とし込まれているでしょうか?
少なくとも私は違います。
私が、今一番、寝ても覚めても頭にあるのは、経営上の問題であり、家族の問題であり・・・・。
もちろん、イラクや北朝鮮問題、財政赤字・少子化、どれをとっても大変重要だと頭では分かっていますが、皮膚感覚として、それよりずっと重要なことが、身の回りのことであります。
明日を生きる、今日を生きることに必死になっている人々にとって、一番重要なことは、今の生活を少しでもよくしたいし、できる限り老後まで安心して過ごしたい、ということです。当然のことですが。
そして、そのために重要なことに、優先順位を付ければ、年金や景気、税金等の問題が、若手官僚が意識する問題より先にきます。
年金や景気、税金等の問題を先に解決しなければ、あとの問題を考えたくても考えられないのです。
私は、これが庶民感覚だと思います。
もちろん、これらの問題が行政依存していても解決できないことを、われわれは知っています。しかしながら、今回の年金問題や「政治とカネ」の問題は、良識ある国民が、先の問題に当たろうと、考え行動しようとする、前提となる、行政や政治家に対する信頼感を著しく損ねました。そこに、国民、いや私は怒っているんです。
この点において、先の若手官僚の感覚と私の感覚は大きくずれています。年金や景気、税金等の問題が取るに足らない問題では絶対にありません。そして、今回の参院選が決して争点なきものであったわけではありません。大変重要な生活感覚の争点があったと思っています。
若手官僚の感覚は、恐らく安部首相の感覚とほぼ同値ではないか、と想像しています。
安部さんのおっしゃっていることは、よくわかります。ただ、彼は庶民の、生活者の、感性を理解していなかった、と思っています。ここに、大きなずれがありました。
申し訳ありませんが、安部さんの言っていることが、どこか教科書的で、残念ながら私の「心」に響きませんでした。
もっと言うと、安部さんの言っていることは首尾一貫していなくて、どこか場当たり的で、「信用」できなかった。この点が、先の小泉さんと大きな違いです。小泉さんは、言っていることが首尾一貫しているように思えました。(実際はどうか分かりませんが。)彼はぶれなかった。しかしながら、安部さんはどんどん論点がずれていきました。そして、何より彼の人事が大きく失敗しています。人事の失敗は、リーダーシップの欠如です。彼がどんなに聞こえがいいことを言っても(実際に安部さんは大変話がうまいと思います)、行動が結果が、彼のリーダーシップの欠如を物語っています。
私は、とくに支持政党を持っているわけではありません。従って、前回の衆議院選挙は小泉さんを支持しましたし、今回は小沢さんを支持しました。
今回、私が思ったことは、そろそろ日本も政権交代が必要な時代になってきたのではないか、ということです。政権交代がないと、行政や政治家の失態はなくならないでしょう。お役人や政治家に緊張感が必要です。これは、われわれ経営者が経営しているときの緊張感と同じだと思います。経営は常に変化していかなければ、続きません。それは世の中が変化しているからです。
当然、政治も行政も変化しなければ、継続できません。そして、その変化のためには、恐らく常に政権交代できる環境にさらされていることが重要です。
決して自民党や民主党がまったくすぐれているわけではありません。それぞれ良い部分もあり、悪い部分もあるのが、政党・・・所詮、人間がやっていることですから。
だからこそ、適度な政権交代が必要です。そして、その時々で政党を選ぶことができる民主主義という制度が、人類が生み出したもっとも重要な智慧であります。
今回の参院選の結果は、本当に良かった。かろうじて日本は民主主義を守ることができた、と思っています。
今後の自民党、民主党の動きに期待が持てる内容になりました。今後の政治に興味を持っていきたいと思います。
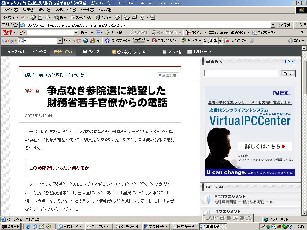
これについて、マスコミ各社いろいろと論評されています。
私は凡人なので、私なりに自分の考えをまとめる意味で。
いろいろな観点があると思いますが、私は安部さんの視点と、われわれ生活者の視点のずれ、という視点でお話したいと思います。
先ほど、田原総一朗氏の以下の評論を読みました。
ここをクリック
ちょっと長いですが、面白いので、お時間ある方は読んでみてください。
私は、結構田原さんのいろいろな話は面白いし、私も同調することが多いので、よく読んでいます。
今回の若手官僚の話・・・財政赤字や少子化、環境問題、イラクや北朝鮮問題、これらの、今後の日本の針路を考えるに当たって、大変重要な問題が、今回の選挙ではまったく議論にならなくて、年金の問題、赤城農水大臣のお金の問題に終始した、今回の選挙。いったいこの国の、国民の問題意識はどうなっているのか。レベルが低すぎるのではないか。という若手官僚の問題意識。
ある一面、私はまったくもっともなことだと思います。
実際のところ、行政を担当する人間として、この問題意識は実は大変重要なことだと思います。
きっと彼は、日夜この問題にさらされて仕事を進めているのでしょう。
従って、彼にとっては、これらの問題・・・財政赤字や少子化、環境問題、イラクや北朝鮮問題、が生活レベルの問題となっているに違いありません。
では、翻って、われわれ国民の多くは、これらの問題が生活レベルに落とし込まれているでしょうか?
少なくとも私は違います。
私が、今一番、寝ても覚めても頭にあるのは、経営上の問題であり、家族の問題であり・・・・。
もちろん、イラクや北朝鮮問題、財政赤字・少子化、どれをとっても大変重要だと頭では分かっていますが、皮膚感覚として、それよりずっと重要なことが、身の回りのことであります。
明日を生きる、今日を生きることに必死になっている人々にとって、一番重要なことは、今の生活を少しでもよくしたいし、できる限り老後まで安心して過ごしたい、ということです。当然のことですが。
そして、そのために重要なことに、優先順位を付ければ、年金や景気、税金等の問題が、若手官僚が意識する問題より先にきます。
年金や景気、税金等の問題を先に解決しなければ、あとの問題を考えたくても考えられないのです。
私は、これが庶民感覚だと思います。
もちろん、これらの問題が行政依存していても解決できないことを、われわれは知っています。しかしながら、今回の年金問題や「政治とカネ」の問題は、良識ある国民が、先の問題に当たろうと、考え行動しようとする、前提となる、行政や政治家に対する信頼感を著しく損ねました。そこに、国民、いや私は怒っているんです。
この点において、先の若手官僚の感覚と私の感覚は大きくずれています。年金や景気、税金等の問題が取るに足らない問題では絶対にありません。そして、今回の参院選が決して争点なきものであったわけではありません。大変重要な生活感覚の争点があったと思っています。
若手官僚の感覚は、恐らく安部首相の感覚とほぼ同値ではないか、と想像しています。
安部さんのおっしゃっていることは、よくわかります。ただ、彼は庶民の、生活者の、感性を理解していなかった、と思っています。ここに、大きなずれがありました。
申し訳ありませんが、安部さんの言っていることが、どこか教科書的で、残念ながら私の「心」に響きませんでした。
もっと言うと、安部さんの言っていることは首尾一貫していなくて、どこか場当たり的で、「信用」できなかった。この点が、先の小泉さんと大きな違いです。小泉さんは、言っていることが首尾一貫しているように思えました。(実際はどうか分かりませんが。)彼はぶれなかった。しかしながら、安部さんはどんどん論点がずれていきました。そして、何より彼の人事が大きく失敗しています。人事の失敗は、リーダーシップの欠如です。彼がどんなに聞こえがいいことを言っても(実際に安部さんは大変話がうまいと思います)、行動が結果が、彼のリーダーシップの欠如を物語っています。
私は、とくに支持政党を持っているわけではありません。従って、前回の衆議院選挙は小泉さんを支持しましたし、今回は小沢さんを支持しました。
今回、私が思ったことは、そろそろ日本も政権交代が必要な時代になってきたのではないか、ということです。政権交代がないと、行政や政治家の失態はなくならないでしょう。お役人や政治家に緊張感が必要です。これは、われわれ経営者が経営しているときの緊張感と同じだと思います。経営は常に変化していかなければ、続きません。それは世の中が変化しているからです。
当然、政治も行政も変化しなければ、継続できません。そして、その変化のためには、恐らく常に政権交代できる環境にさらされていることが重要です。
決して自民党や民主党がまったくすぐれているわけではありません。それぞれ良い部分もあり、悪い部分もあるのが、政党・・・所詮、人間がやっていることですから。
だからこそ、適度な政権交代が必要です。そして、その時々で政党を選ぶことができる民主主義という制度が、人類が生み出したもっとも重要な智慧であります。
今回の参院選の結果は、本当に良かった。かろうじて日本は民主主義を守ることができた、と思っています。
今後の自民党、民主党の動きに期待が持てる内容になりました。今後の政治に興味を持っていきたいと思います。
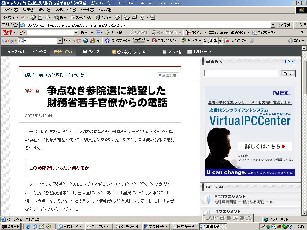
住所パワー
ブログ執筆、5人に1人
いつぞやの日経新聞に掲載されていました。
日本のインターネット利用者の5人に1人はブログを執筆しているそうです。
年代別では、12歳から19歳で、35.4%、20~24歳で、32.8%。すごい数ですね。みんな情報発信したいのですね。
また、ネットをどう利用していますか?という問いには、
日本では、「パソコンでのメール送受信(91.9%)」、「天気、地図、路線を調べる(83.5%)」、「知らない言葉や物事を調べる(80.7%)」でありました。
中国では、メッセンジャーソフトを使う人が72.4%。中国では知人との交流にネットを積極的に利用しているようです。
何をするときにネットが必要か?という問いには、
日本では、「趣味」に「必要」「ある程度必要」と答えた人が91.0%。「仕事」が81.6%。
アメリカでは、「仕事」「勉強」に「必要」「ある程度必要」と答えた人が9割を超え、実用面で必要と感じる人が突出して多い。
中国では、「友人関係の構築・維持」に必要と答えた人が80.4%とかなり高い数字。中国では仕事より友人との交流が盛んのようです。
同じメディアでも、国によってかなり状況が異なっていることが、この調査でもわかりますね。
皆さんは、どういう目的で、ネットを使っていますか?
また教えてください。では。
日本のインターネット利用者の5人に1人はブログを執筆しているそうです。
年代別では、12歳から19歳で、35.4%、20~24歳で、32.8%。すごい数ですね。みんな情報発信したいのですね。
また、ネットをどう利用していますか?という問いには、
日本では、「パソコンでのメール送受信(91.9%)」、「天気、地図、路線を調べる(83.5%)」、「知らない言葉や物事を調べる(80.7%)」でありました。
中国では、メッセンジャーソフトを使う人が72.4%。中国では知人との交流にネットを積極的に利用しているようです。
何をするときにネットが必要か?という問いには、
日本では、「趣味」に「必要」「ある程度必要」と答えた人が91.0%。「仕事」が81.6%。
アメリカでは、「仕事」「勉強」に「必要」「ある程度必要」と答えた人が9割を超え、実用面で必要と感じる人が突出して多い。
中国では、「友人関係の構築・維持」に必要と答えた人が80.4%とかなり高い数字。中国では仕事より友人との交流が盛んのようです。
同じメディアでも、国によってかなり状況が異なっていることが、この調査でもわかりますね。
皆さんは、どういう目的で、ネットを使っていますか?
また教えてください。では。
ITの今後10年~30年の動向について ⑱
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
第16回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html
さて、このシリーズ、いよいよ18回目です。
よく続けているなあ・・・・と呆れているあなた。 まったく、そのとおり
私自身が呆れています。もうこうなると意地ですかね
ということで、本日の課題は
「ボーダーレス社会によって、日本独自の文化・価値はどうなるのか?」。
もうなんだか、「IT革命」の話しがどこかへ飛んでいってしまったようですが、そもそもボーダーレス社会そのものが、「IT革命」によってもたらされたものですから。ちょっと思い出しておいてくださいね。
では「日本独自の文化・価値はどうなるのか?」ということですが、これには、いろいろな観点・見識から、様々な意見が語られると思います。
恐らく、ボーダーレス化によって、日本独自の文化・価値のいくつかの部分は消えていってしまうものもあるでしょう。大変残念なことですが。
例えば、「下町文化」。寅さんの世界ですね。もう消えている、と思われますが、まだまだ「下町情緒」の残っているところは多いですね。だが、そういった日本人独自の「人情文化」は、大変残念なことですが、どんどん消失されていくでしょう。本当に寂しいですね。
私の少年時代は、近所の「おいちゃん」「おばちゃん」からよく「かっちゃん、元気かい?」と、街を歩く度に声かけられて、「元気だよ」と何気なく答えていました。なんだか、街全体に大きな温かさがあったような気がします。大変寂しいですね。
では、なぜそういった文化が消失していくのか?
それは、なくても生きていけるからではないでしょうか。
また、その文化のよさを説明できないからではないでしょうか。
私は、60年代・70年代くらいまでの、日本の文化には、明示できない、説明できない、というか、説明したらそれで終わり、という文化が多くあったと思います。(この部分は、以前、「五木寛之氏の講演会」を聴いた際にも、私の感性が大きく刺激を受けたところです。五木氏の年代以前の方々が持っていた(とくに文化人、芸術家が持っていた)「日本人の名辞以前の感性空間」です。中原中也の詩の世界にもつながります。「『これが手だ』と、『手』といふ名辞を口にする前に感じてゐる手、その手が深く感じられてゐればよい」。これは大変深い内容なので、また中原中也の項でお伝えします。)
そういったものの多くは、一見不条理で理屈に合わない、ある一面からみれば正しくないものでさえあったと思っています。
例えば、日本の「粋」の文化や、落語の世界・・・・落語は語っているじゃないか、と言ったら、それはちょっと違う。私は、その世界を疑似体験させてもらっていると思っています。言ってみれば、「言葉そのものに意味や価値があるのではなく、言葉が発する雰囲気・情感に意味や価値がある」といった世界です。従って、その価値は言葉では説明できない・・・・。
そして、そういった明示できない、現代で言うと「かっこよくてクールな」文化は、80年代・90年代になって、世の中が情報化社会に突入していくと同時に次第に消えていきました。
ただ、現代社会においても、かろうじてそういった文化の名残が残っています。例えば、男と女がデートで呑みに行って、割り勘より男が「おごる」ということに拘りを示すとか、いわゆるさりげなく「男」としての矜持を示すといった部分にね。(と言っておきながら私にはその拘りがないですから、女性の方、ご勘弁を・・・・ )
)
実は、こういった価値観が「IT革命」にとっては、もっとも弱い部分なんです。言葉にできない文化は、「IT革命」で扱うことができないものですから。
従って、「IT革命」「ボーダーレス社会」の到来によって、今後、日本の、言葉にできない文化はどんどん消えていってしまうでしょう。
では、全ての日本独自の文化・価値は消えていくのか、というと、もちろん、そんなことは絶対にありません。日本人が生きている限りは。
次回は、「ボーダーレス社会が進んでいっても、残りさらに強くなっていく日本文化」についてお話を進めていきたいと思います。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e6037.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
第16回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html
さて、このシリーズ、いよいよ18回目です。
よく続けているなあ・・・・と呆れているあなた。 まったく、そのとおり

私自身が呆れています。もうこうなると意地ですかね

ということで、本日の課題は
「ボーダーレス社会によって、日本独自の文化・価値はどうなるのか?」。
もうなんだか、「IT革命」の話しがどこかへ飛んでいってしまったようですが、そもそもボーダーレス社会そのものが、「IT革命」によってもたらされたものですから。ちょっと思い出しておいてくださいね。
では「日本独自の文化・価値はどうなるのか?」ということですが、これには、いろいろな観点・見識から、様々な意見が語られると思います。
恐らく、ボーダーレス化によって、日本独自の文化・価値のいくつかの部分は消えていってしまうものもあるでしょう。大変残念なことですが。
例えば、「下町文化」。寅さんの世界ですね。もう消えている、と思われますが、まだまだ「下町情緒」の残っているところは多いですね。だが、そういった日本人独自の「人情文化」は、大変残念なことですが、どんどん消失されていくでしょう。本当に寂しいですね。
私の少年時代は、近所の「おいちゃん」「おばちゃん」からよく「かっちゃん、元気かい?」と、街を歩く度に声かけられて、「元気だよ」と何気なく答えていました。なんだか、街全体に大きな温かさがあったような気がします。大変寂しいですね。
では、なぜそういった文化が消失していくのか?
それは、なくても生きていけるからではないでしょうか。
また、その文化のよさを説明できないからではないでしょうか。
私は、60年代・70年代くらいまでの、日本の文化には、明示できない、説明できない、というか、説明したらそれで終わり、という文化が多くあったと思います。(この部分は、以前、「五木寛之氏の講演会」を聴いた際にも、私の感性が大きく刺激を受けたところです。五木氏の年代以前の方々が持っていた(とくに文化人、芸術家が持っていた)「日本人の名辞以前の感性空間」です。中原中也の詩の世界にもつながります。「『これが手だ』と、『手』といふ名辞を口にする前に感じてゐる手、その手が深く感じられてゐればよい」。これは大変深い内容なので、また中原中也の項でお伝えします。)
そういったものの多くは、一見不条理で理屈に合わない、ある一面からみれば正しくないものでさえあったと思っています。
例えば、日本の「粋」の文化や、落語の世界・・・・落語は語っているじゃないか、と言ったら、それはちょっと違う。私は、その世界を疑似体験させてもらっていると思っています。言ってみれば、「言葉そのものに意味や価値があるのではなく、言葉が発する雰囲気・情感に意味や価値がある」といった世界です。従って、その価値は言葉では説明できない・・・・。
そして、そういった明示できない、現代で言うと「かっこよくてクールな」文化は、80年代・90年代になって、世の中が情報化社会に突入していくと同時に次第に消えていきました。
ただ、現代社会においても、かろうじてそういった文化の名残が残っています。例えば、男と女がデートで呑みに行って、割り勘より男が「おごる」ということに拘りを示すとか、いわゆるさりげなく「男」としての矜持を示すといった部分にね。(と言っておきながら私にはその拘りがないですから、女性の方、ご勘弁を・・・・
 )
)実は、こういった価値観が「IT革命」にとっては、もっとも弱い部分なんです。言葉にできない文化は、「IT革命」で扱うことができないものですから。
従って、「IT革命」「ボーダーレス社会」の到来によって、今後、日本の、言葉にできない文化はどんどん消えていってしまうでしょう。
では、全ての日本独自の文化・価値は消えていくのか、というと、もちろん、そんなことは絶対にありません。日本人が生きている限りは。
次回は、「ボーダーレス社会が進んでいっても、残りさらに強くなっていく日本文化」についてお話を進めていきたいと思います。
ではまた。

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e6037.html

修善寺の「菊屋」さんのこと
日経新聞に、修善寺の老舗旅館「菊屋」さんの記事が掲載されていました。以下に、記事の要旨を記載します。
どうですか?皆さん。
このお話はいろいろ示唆に富んだ教訓を含んでいます。
もちろん、単なる旅館の再生ということでも大変勉強になるのですが、実は、今、この「経営と所有の分離」ということが、静岡県東部地区のどの市町村でも頭を抱えている「中心市街地の活性化」という問題に関しても、ソリューションの一つとして脚光を浴びつつあります。(財源確保の手法として、日本版BID(Bussiness Improvement District?)という手法も考えられ始めました。)
少し長くなってしまったので、そのお話はどこかで進めるとして、私がお話したいのは、市街地や各店舗、旅館等々、地域の活性化において、地域の発想・知識・ノウハウだけでは限界がある、ということです。
時代はどんどん変わってきています。伝統や、今までの考えにしがみついていても、問題解決には決してつながらない事例が多いということ。
外部の知恵・ノウハウ・資金を入れることに臆病になっていると、いつの間にか時代から大きく取り残され、内向きの発想に支配され、「動かないことがよいこと」=「ゆで蛙現象」になってしまいますよ、ということをお伝えしたいと思います。
ではまた。

「菊屋」さんは、バブル崩壊後経営が悪化し、2005年に自主再建を断念しました。
その後、ビジネスホテル運営のノウハウを持っている共立メンテナンスが運営を引き継ぎ、伝統に変化を加えた再生プランでよみがえりました。
「菊屋」は夏目漱石が吐血した「修善寺の大患」の舞台になるなど、多くの文豪が訪れる由緒ある旅館でした。当時は、文豪に「新聞小説を書いてもらい、名前を売る、画期的な宣伝手法」をとっていました。(今流で言うと、メディアにパブリシティでどんどん取り上げてもらうマーケティング手法ですね。)
先人は桜並木等街づくりを行い、明治から大正にかけて、修善寺温泉を先進リゾート地に育てた。
ただし、その後は「過去の遺産を食い潰してきた」。
十五代目当主の野田治久さんは、25年前に、大学卒業後他の旅館修行を終えて戻ったが、「菊屋は自分でも泊まりたくない大変古臭い旅館」になっていた。
約一万三千平方メートルの敷地を観光センターなど温泉街の中核施設に変え、旅館は取り壊し近くに新築するという野田さんの大胆な構想に、母親らは「伝統を守れ」と猛反対。
やむなく耐火工事などに四億を投じたが、客の目に付く改装は後手に回った。なじみ客は高齢化、新規顧客の開拓もままならず、バブル崩壊後は赤字経営。
自主再建断念のきっかけは、2004年10月の台風22号。ケヤキの大木が倒れ漱石ゆかりの部屋を壊すなど壊滅的被害を受けた。
年間一千万近くかかる庭木の手入れをおろそかにした「しっぺ返し」と映り、「手をかけられないなら終わりだ」と、覚悟を決めた。
台風後に、以前から旅館経営に関心あり、旅館運営受託の打診をされていた共立メンテナンスに直ちに連絡をとり、一ヶ月ほどで経営から身を引き、二十年契約で土地建物を賃貸に。
共立メンテナンスはさっそく数億円かけて大改装。壊れた部屋を露天風呂付き客室に変えたり、カーペットなど内装も一新。2006年7月に「湯回廊 菊屋」としてリニューアル開館。
部屋だしの食事をレストランに切り替え、共立メンテナンスが開発したシステムを使い、インターネットで集客。
それから一年。週末は満室続きで稼働率は65%に達し、今年の4月からは単月黒字に転換した。営業利益率は10%を確保。「利益で再投資するメドもついた」と新支配人。
ただ、「新しい客室で若年層は増えたが、基本は菊屋の伝統」であるとのこと。壁にかかる古い柱時計も廃止ではなく、顧客にどう価値を伝えるかを検討している。
新しい仕組みを加えて、伝統を生かす----。
外部の力による旅館再生を目の当たりにした野田さんは、「温泉街再生にも外の力が必要だ」と痛感、外部資本を取り入れた遊休地活用などに奔走している。
修善寺温泉の宿泊客数は2005年度の54万人を底に、2006年度は57万人に回復。温泉街には福岡県からどら焼き店が出店するなど、「外資ブーム」を予感させる動きもある。
どうですか?皆さん。
このお話はいろいろ示唆に富んだ教訓を含んでいます。
もちろん、単なる旅館の再生ということでも大変勉強になるのですが、実は、今、この「経営と所有の分離」ということが、静岡県東部地区のどの市町村でも頭を抱えている「中心市街地の活性化」という問題に関しても、ソリューションの一つとして脚光を浴びつつあります。(財源確保の手法として、日本版BID(Bussiness Improvement District?)という手法も考えられ始めました。)
少し長くなってしまったので、そのお話はどこかで進めるとして、私がお話したいのは、市街地や各店舗、旅館等々、地域の活性化において、地域の発想・知識・ノウハウだけでは限界がある、ということです。
時代はどんどん変わってきています。伝統や、今までの考えにしがみついていても、問題解決には決してつながらない事例が多いということ。
外部の知恵・ノウハウ・資金を入れることに臆病になっていると、いつの間にか時代から大きく取り残され、内向きの発想に支配され、「動かないことがよいこと」=「ゆで蛙現象」になってしまいますよ、ということをお伝えしたいと思います。
ではまた。

Def Techのマイクロさんは下田に住んでいるんですね
私も少し芸能ネタを 
昨日、ミュージックステーションを見ていたら、Def Techのマイクロさんが出てて、下田の話をしているので、へえーっと思ってみていました。
Def Techの「My Way」を私もGeneration Gap を感じつつも案外気持ちよく聴いていましたので、「2LDKの部屋(駐車場付)に住んでいる」という話に、随分と身近に感じました。
首都圏から近い伊豆には、多くのクリエーターたちにとって、「生活と仕事(創作)」をうまく両立させる絶好の場所なのかもしれませんね。
ここにもこの地域の活性化のヒントがあるかもしれません。では。


昨日、ミュージックステーションを見ていたら、Def Techのマイクロさんが出てて、下田の話をしているので、へえーっと思ってみていました。
Def Techの「My Way」を私もGeneration Gap を感じつつも案外気持ちよく聴いていましたので、「2LDKの部屋(駐車場付)に住んでいる」という話に、随分と身近に感じました。
首都圏から近い伊豆には、多くのクリエーターたちにとって、「生活と仕事(創作)」をうまく両立させる絶好の場所なのかもしれませんね。
ここにもこの地域の活性化のヒントがあるかもしれません。では。

さあ、選挙戦はじまりましたね
皆さん、いよいよ選挙戦突入ですね。
自民党、民主党はじめ各党のマニフェストも出揃いました!
YAHOOのページで各党のマニフェストの内容がつかめます。
各党のHPの作り方は、やはり資金力のある自民党が一番うまいですが、でも内容が一番重要ですからね。どうなりますやら・・・・。

今回の参院選は、今後の日本の状況を占う大変大きな意味のある選挙だと思います。
皆さん、必ず投票に行きましょう!
ご自身の考えを必ず1票に託しましょう!
以上、かっちゃん選挙管理委員会からの公私混同報でした
自民党、民主党はじめ各党のマニフェストも出揃いました!
YAHOOのページで各党のマニフェストの内容がつかめます。
各党のHPの作り方は、やはり資金力のある自民党が一番うまいですが、でも内容が一番重要ですからね。どうなりますやら・・・・。

今回の参院選は、今後の日本の状況を占う大変大きな意味のある選挙だと思います。
皆さん、必ず投票に行きましょう!
ご自身の考えを必ず1票に託しましょう!
以上、かっちゃん選挙管理委員会からの公私混同報でした

ITの今後10年~30年の動向について ⑰
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
さて、「日本市場の国際化」のお話でした。
ちょっとここのところ、このシリーズは、話が難しくなってきまして恐縮です。
また、ITの話がどこかいっちゃってるなあ、とお思いの方・・・・・・あなたは正解です!
ITの話だと思って、クリックしたのにーー。これじゃあ詐欺だ なんて。しまいにはクリックを返せ、なんて
なんて。しまいにはクリックを返せ、なんて
ただ、ITの今後10年~30年のことを考えていくということは、もうこれは社会の根底から考えていくことに等しいことですから、どうぞご勘弁のほどを。
さて、法人企業と株主との関係のお話です。
この問題は古くて新しいテーマで、株式会社という形態が生まれてからずっと続いている、「会社は誰のものか」という問答に直結するわけですが。
欧米では「株主のもの」という帰結がほぼ一般的であるのですが(もちろん、細かく言えば、アメリカとヨーロッパでは若干、その論調は異なります。)、日本の場合は、この問題の答えが、株式会社が生まれてからずーっと現代まで、相変わらずはっきりしません。
そして、どちらかと言えば、日本の場合、「株式会社は、経営者を含む従業員のもの」という価値観が根強かった。ただ、市場経済の中、この価値観はかなりゆがんだ日本の市場社会を作り出していました。昨今の「西武」「ダイエー」・・・・等々の経営者が引き起こす数々の事件は、すべてこの価値観から生まれてきている、と私は思っています。そして、前回お話した「M&A」に対する過剰防衛の問題も根っこは同じです。
実は私どもの会社には、私と少しの血縁関係もないまったくのあかの他人の株主の方々が、出資をしてくださっております。
これは、会社設立当初からの私の方針でした。
会社設立の時は、有限会社でしたが、法人であることは間違いないですから、私は、法人であるということは、すでに私企業ではない、という意識で設立いたしました。
即ち、法人ということはその設立段階からすでに公企業である、という意識です。
会社の経営者というのは、「経営」という機能を会社に提供している人であって、会社は経営者の持ち物でない、というのは当然のことです。
会社は株主のものであって、経営者のものではありません。
従って、その会社が自らの経営理念に従って、社会に貢献し、人々に便益を提供していくことにご賛同し、ご支援いただけるのであれば、どのような方に出資していただいても、というか、出来る限り多くの方にご出資賜れば、「みんなの会社」という意識で見ていただけ、より経営基盤が磐石なものとなると思っています。
現在、ご出資していただいている株主の方々には大変感謝しておりますし、早く株主の皆様のご期待にお応えしたい、と常にある緊張感の中で経営を行っております。(他人資本が入っていると、経営者の経営にある緊張感が生まれ、経営のチェック機能を果すと思っております。)
従って、経営者は株主の皆さんへの経営状態および経営方針の説明責任を持っています。これは大変重要な責任だと思っております。
私のこのような感覚は、日本の経済界においては長い間、異端であったのかもしれません。
日本の会社の株主総会は、どう考えても長らく株主軽視の総会でありました。
ところが、日本市場がオープン化されるに従って、昨今の株主総会は次第に「株主尊重」の雰囲気が出て参りました。
そして、この風土は、今後30年の間にどんどん欧米化されてくると思われます。先ほどお話した、西武の堤オーナー、ダイエーの中内オーナー等々の問題は、その根っこに、結局、法人と株主の関係を「自分勝手な解釈で」捻じ曲げて、自分の都合のよいように考えたことから始まっています。
経営者は常に会社にとって、最善の経営能力を提供できるように努めるべきだと思っています。ただ、経営者は次のことも覚悟しておかなければならないでしょう。
それは、「自分より会社にとって、もっとよい経営能力を提供できる者が現れたときは、躊躇なくその者と交代すべきである」ということです。
堤オーナーも中内オーナーもこの点を大きく見誤ったと思います。
また前回お話しましたように、経営者が自分の保身のために、TOBの防衛策を練るのは、大いに間違っています。会社の価値、即ち株主にとっての価値を向上させるためには、常にその時点でもっとも能力ある経営者が経営にあたることが一番重要なポイントです。これができなければ、その会社は次第に衰退していくでしょう。
そして、以上のような価値観は、必ずしも上場企業だけの話しではありません。われわれ中小企業もまったく同じです。法人である限り、株主と会社の関係は常にそうあるべきです。そのことが会社を強くするし、会社を永続させる智恵となります。
「ボーダーレス社会」は、以上の価値観をより一層深く広く浸透させて、「日本独自のルール」を消滅させていくでしょう。
では、「日本独自の価値」や「日本独自の文化」、そして「日本の存在理由・価値」はどうなっていくのか?
この点を次回述べていきたいと思います。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e6034.html
以下は任天堂株主総会の写真だそうです。

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
さて、「日本市場の国際化」のお話でした。
ちょっとここのところ、このシリーズは、話が難しくなってきまして恐縮です。
また、ITの話がどこかいっちゃってるなあ、とお思いの方・・・・・・あなたは正解です!
ITの話だと思って、クリックしたのにーー。これじゃあ詐欺だ
 なんて。しまいにはクリックを返せ、なんて
なんて。しまいにはクリックを返せ、なんて
ただ、ITの今後10年~30年のことを考えていくということは、もうこれは社会の根底から考えていくことに等しいことですから、どうぞご勘弁のほどを。

さて、法人企業と株主との関係のお話です。
この問題は古くて新しいテーマで、株式会社という形態が生まれてからずっと続いている、「会社は誰のものか」という問答に直結するわけですが。
欧米では「株主のもの」という帰結がほぼ一般的であるのですが(もちろん、細かく言えば、アメリカとヨーロッパでは若干、その論調は異なります。)、日本の場合は、この問題の答えが、株式会社が生まれてからずーっと現代まで、相変わらずはっきりしません。
そして、どちらかと言えば、日本の場合、「株式会社は、経営者を含む従業員のもの」という価値観が根強かった。ただ、市場経済の中、この価値観はかなりゆがんだ日本の市場社会を作り出していました。昨今の「西武」「ダイエー」・・・・等々の経営者が引き起こす数々の事件は、すべてこの価値観から生まれてきている、と私は思っています。そして、前回お話した「M&A」に対する過剰防衛の問題も根っこは同じです。
実は私どもの会社には、私と少しの血縁関係もないまったくのあかの他人の株主の方々が、出資をしてくださっております。
これは、会社設立当初からの私の方針でした。
会社設立の時は、有限会社でしたが、法人であることは間違いないですから、私は、法人であるということは、すでに私企業ではない、という意識で設立いたしました。
即ち、法人ということはその設立段階からすでに公企業である、という意識です。
会社の経営者というのは、「経営」という機能を会社に提供している人であって、会社は経営者の持ち物でない、というのは当然のことです。
会社は株主のものであって、経営者のものではありません。
従って、その会社が自らの経営理念に従って、社会に貢献し、人々に便益を提供していくことにご賛同し、ご支援いただけるのであれば、どのような方に出資していただいても、というか、出来る限り多くの方にご出資賜れば、「みんなの会社」という意識で見ていただけ、より経営基盤が磐石なものとなると思っています。
現在、ご出資していただいている株主の方々には大変感謝しておりますし、早く株主の皆様のご期待にお応えしたい、と常にある緊張感の中で経営を行っております。(他人資本が入っていると、経営者の経営にある緊張感が生まれ、経営のチェック機能を果すと思っております。)
従って、経営者は株主の皆さんへの経営状態および経営方針の説明責任を持っています。これは大変重要な責任だと思っております。
私のこのような感覚は、日本の経済界においては長い間、異端であったのかもしれません。
日本の会社の株主総会は、どう考えても長らく株主軽視の総会でありました。
ところが、日本市場がオープン化されるに従って、昨今の株主総会は次第に「株主尊重」の雰囲気が出て参りました。
そして、この風土は、今後30年の間にどんどん欧米化されてくると思われます。先ほどお話した、西武の堤オーナー、ダイエーの中内オーナー等々の問題は、その根っこに、結局、法人と株主の関係を「自分勝手な解釈で」捻じ曲げて、自分の都合のよいように考えたことから始まっています。
経営者は常に会社にとって、最善の経営能力を提供できるように努めるべきだと思っています。ただ、経営者は次のことも覚悟しておかなければならないでしょう。
それは、「自分より会社にとって、もっとよい経営能力を提供できる者が現れたときは、躊躇なくその者と交代すべきである」ということです。
堤オーナーも中内オーナーもこの点を大きく見誤ったと思います。
また前回お話しましたように、経営者が自分の保身のために、TOBの防衛策を練るのは、大いに間違っています。会社の価値、即ち株主にとっての価値を向上させるためには、常にその時点でもっとも能力ある経営者が経営にあたることが一番重要なポイントです。これができなければ、その会社は次第に衰退していくでしょう。
そして、以上のような価値観は、必ずしも上場企業だけの話しではありません。われわれ中小企業もまったく同じです。法人である限り、株主と会社の関係は常にそうあるべきです。そのことが会社を強くするし、会社を永続させる智恵となります。
「ボーダーレス社会」は、以上の価値観をより一層深く広く浸透させて、「日本独自のルール」を消滅させていくでしょう。
では、「日本独自の価値」や「日本独自の文化」、そして「日本の存在理由・価値」はどうなっていくのか?
この点を次回述べていきたいと思います。
ではまた。

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e6034.html
以下は任天堂株主総会の写真だそうです。

ITの今後10年~30年の動向について ⑯
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
さて、このシリーズも4月26日から始まって、2ヶ月以上経過してしまいました。
長~~いシリーズに、皆さん、よくお付き合いくださってありがとうございます。
今日は昨日に引き続き「ボーダーレス化」もしくは「グローバル化」(流行の欧米化 ではないですよ)
ではないですよ)
ここで、前回の復習をいたしましょう。
えっと、何でしたっけ。「国が消えると桶屋が儲かる」って話し・・・・ではないと 。これまた失礼いたしました。(植木等ばりで・・・これが分かると相当の年齢で・・・あ、いやお呼びでないってことですよ。ね。
。これまた失礼いたしました。(植木等ばりで・・・これが分かると相当の年齢で・・・あ、いやお呼びでないってことですよ。ね。 )
)
「国が消えるとボーダーレス社会になり、資産価値が減るので投資した方がいいですよ」という証券会社まがいのことを言っていたんですよね。
それで、今回は、「国が消えると、日本独自のルール(商慣習等)はどうなるのか?」というところからお話ししていきたい、と思います。
そして、この部分は言うのは大変簡単です。
即ち、残念ながら「日本独自のルールは消えていく」ということです。(これはあくまでも事実を伝えています。このことに対する価値観は、当然、別です。)
ボーダーレス社会は間違いなく、市場が国を超えてオープンになっていくわけですから、海外投資家もどんどん日本市場に入ってきます(入ってきています)。このような状態で、日本独自の商慣習が維持できるわけがありません。
ちょっと前の、ニッポン放送vsライブドア、楽天vsTBSのTOB合戦から、「M&A」ということは日常茶飯事になってきました。これからどんどん「M&A」「TOB」は今以上に進みます。
そして、ここでの大きな問題は、「TOB」「M&A」というよりも、「TOB」への過剰防衛でしょう。そもそも株式を上場しているというのは、会社そのものを、ある意味、商品化しているわけですから、会社そのものを売り買いの対象とみることは当然のことです。TOBする側が、現経営者以上の能力があり、株主にとってより会社の価値を高める事業プランと実行力があれば、当然TOBは成立しなければなりません。これが市場原理です。TOBへの過剰防衛は、株主への背信行為であり、市場原理への重大な挑戦と思います。(「グリーンメーラー」や「乗っ取りや」は別ですが。ただ、そのような存在は市場原理により消えていく運命にあります。)
ま、何にせよ、このような問題、恐らく、底流にあるのは、日本独自の商慣習VS世界の商慣習、ではないか、と思いますが、今後数多く発生すると思います。がしかし、全体のトレンドはもはや逆戻りはありえません。
今後30年で、日本市場はほぼ世界市場化されていくでしょう!
そして、私がお話ししたいのは、この「日本独自のルールが次第に消えていく」という事態は、何も上場企業だけの話しではない、ということです。(誤解のないように。非上場企業がTOBされるよ、という話しではありませんから。そんなことは不可能ですから。)
私がお話ししたいのは、法人企業と株主との関係です。
ということで、この先はまた長くなりますので、また今度。では
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
さて、このシリーズも4月26日から始まって、2ヶ月以上経過してしまいました。
長~~いシリーズに、皆さん、よくお付き合いくださってありがとうございます。
今日は昨日に引き続き「ボーダーレス化」もしくは「グローバル化」(流行の欧米化
 ではないですよ)
ではないですよ)ここで、前回の復習をいたしましょう。
えっと、何でしたっけ。「国が消えると桶屋が儲かる」って話し・・・・ではないと
 。これまた失礼いたしました。(植木等ばりで・・・これが分かると相当の年齢で・・・あ、いやお呼びでないってことですよ。ね。
。これまた失礼いたしました。(植木等ばりで・・・これが分かると相当の年齢で・・・あ、いやお呼びでないってことですよ。ね。 )
)「国が消えるとボーダーレス社会になり、資産価値が減るので投資した方がいいですよ」という証券会社まがいのことを言っていたんですよね。
それで、今回は、「国が消えると、日本独自のルール(商慣習等)はどうなるのか?」というところからお話ししていきたい、と思います。
そして、この部分は言うのは大変簡単です。
即ち、残念ながら「日本独自のルールは消えていく」ということです。(これはあくまでも事実を伝えています。このことに対する価値観は、当然、別です。)
ボーダーレス社会は間違いなく、市場が国を超えてオープンになっていくわけですから、海外投資家もどんどん日本市場に入ってきます(入ってきています)。このような状態で、日本独自の商慣習が維持できるわけがありません。
ちょっと前の、ニッポン放送vsライブドア、楽天vsTBSのTOB合戦から、「M&A」ということは日常茶飯事になってきました。これからどんどん「M&A」「TOB」は今以上に進みます。
そして、ここでの大きな問題は、「TOB」「M&A」というよりも、「TOB」への過剰防衛でしょう。そもそも株式を上場しているというのは、会社そのものを、ある意味、商品化しているわけですから、会社そのものを売り買いの対象とみることは当然のことです。TOBする側が、現経営者以上の能力があり、株主にとってより会社の価値を高める事業プランと実行力があれば、当然TOBは成立しなければなりません。これが市場原理です。TOBへの過剰防衛は、株主への背信行為であり、市場原理への重大な挑戦と思います。(「グリーンメーラー」や「乗っ取りや」は別ですが。ただ、そのような存在は市場原理により消えていく運命にあります。)
ま、何にせよ、このような問題、恐らく、底流にあるのは、日本独自の商慣習VS世界の商慣習、ではないか、と思いますが、今後数多く発生すると思います。がしかし、全体のトレンドはもはや逆戻りはありえません。
今後30年で、日本市場はほぼ世界市場化されていくでしょう!
そして、私がお話ししたいのは、この「日本独自のルールが次第に消えていく」という事態は、何も上場企業だけの話しではない、ということです。(誤解のないように。非上場企業がTOBされるよ、という話しではありませんから。そんなことは不可能ですから。)
私がお話ししたいのは、法人企業と株主との関係です。
ということで、この先はまた長くなりますので、また今度。では

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html

ITの今後10年~30年の動向について ⑮
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
さあ、ついにシリーズ第15弾にまでなってしまいました。
本当は前回で終了の予定だったのですが、意外とこの項目の内容が思っていたよりあったので、本日まで伸びてしまいました。ごめんなさい。
今日はきっと最終回になるかなあ(?(^^;)
前回、「IT革命が進むと、国が消える」という「ボーダーレス社会」のより一層深化した姿を、どちらかといえば、企業サイドからお話ししました。
今日は、その後半部分。もう少し大きく、社会の視点から、「ボーダーレス社会」を眺めてみましょう。そして、われわれの身近な生活の変化を考えてみましょう。
さて皆さん、唐突ですが、資産をお持ちですか?
(いきなりなんという挑戦的な・・・・ でも私は資産をまったく持っていないので、資産もっている人と仲良くなっとかないと・・・ね
でも私は資産をまったく持っていないので、資産もっている人と仲良くなっとかないと・・・ね という話しではなく)
という話しではなく)
もし資産お持ちの方で、その資産価値を減らしたくない方は、これからはどんどん投資をしてください。
(もちろん、そんなことは人に言われなくても百も承知でしょうが )
)
すなわち、
「IT革命」が進んで「ボーダーレス社会」になると、今後、「日本の資産価値」は「海外の資産価値」に比べて相対的に減っていきますよ、という話しです。(これも当然皆さん、お分かりでしょうが、再確認したいと思います。)
きっと、われわれ日本人はこの点において、もっとも勉強しておかなければならないのかもしれません。そして、その際の勉強の対象は、もう一度、アメリカではないでしょうか?
なぜか?
それは、アメリカの戦後50年の間に起きた、「資産価値の相対的な目減り」が、われわれにとって意味あるからです。
思い出してください、終戦直後からその後の10年間位のことを。(といっても、私は当然生まれていませんので、よく分かりませんが・・・ホント?、生まれてたんじゃないの・・・・いや絶対にありません、ハイ )
)
その頃、わが日本から見れば、アメリカははるかに進んだ国でした。「あこがれの社会」だったはずです。みんな、誰しもアメリカに行き住んでみたい、と思っていたはずです。
そして、恐らくその頃のアメリカの資産の相対的価値は、世界の半分位あったのではないでしょうか?(私は専門家ではないので、このあたりはまったくの勘で言っています。無責任な数字ですみません。また、今回の稿は、ITの話というより金融のお話が多いので、門外漢の私がお話するのはお門違いも甚だしいのですが、私個人の独断と偏見、ということでお許しください。できれば、これを読んだ専門家の方からご意見いただきたい位であります。)
その後、(私も生まれて・・・ホント? しつこい )わが日本は高度成長を走ります。そして、いつしか「あこがれのアメリカ」が手の届く範囲になり、あの「あこがれの象徴」だったロックフェラーセンターを日本人が買うという時代になったわけです。恐らく現在のアメリカの資産の相対的価値は世界の4分の一位になっていると思います。(かなりいい加減ですが・・・)
)わが日本は高度成長を走ります。そして、いつしか「あこがれのアメリカ」が手の届く範囲になり、あの「あこがれの象徴」だったロックフェラーセンターを日本人が買うという時代になったわけです。恐らく現在のアメリカの資産の相対的価値は世界の4分の一位になっていると思います。(かなりいい加減ですが・・・)
そして、現在、われわれ日本が戦後たどった道を、中国・ロシア・ブラジル・インド(BRICSと言われてますね)をはじめとした国々が突っ走っています。(恐らく日本がたどった50年の道を彼らは25年~30年位で走るのではないでしょうか?これはまさに「IT革命」の成果なんですがね・・・ )
)
と、どうなるでしょうか。お分かりですね。今後、30年で日本の「相対的価値」はどんどん下がっていくということです。これは、この50年、アメリカがたどった道なんです。そして、このことは絶対に避けて通ることの出来ない道・・・。必ずやってくるでしょう。(気が付くと、あなたの家のとなりの土地をブラジル人が持っていたということは十分に起こりうることです。 )
)
では、アメリカの人々はこの50年の間、この「資産価値の目減り」にどのように対処してきたのでしょうか?
もうお分かりですね。「投資」をしてきたのです。
当たり前のことですが、「資産」をそのまま何もせずに持っていても、その「価値」が減るのであれば、その「資産」を使って「投資」するしかありません。彼らは「海外」に「投資」してきたのです。(もちろん、アメリカの国外に、ということです。)
それでは、皆さん、「投資」ということに関してどう思いますか?
われわれ日本人は本当に投資が苦手ですよね。というか、余りにも金融の知識を持っていないので、「よく分からない」というのが実感ではないでしょうか。これも戦後教育の大きな欠陥です。(実は私もこのあたりは大変苦手で・・・とほほ )
)
でも、このままではわれわれの資産価値が目減りしていくことになります。
寝かせている資産のある方は、どんどん海外に出向いていって、もしくは海外の情報をいろいろな形で得て、海外への投資を企ててみてはいかがでしょうか?(もちろん、国内への投資も必要なことですが、海外への投資の方がはるかに重要です。)
また、個人だけで投資を行うことに限界があることから、様々な形での投資ファンドがもっと拡がることになるでしょう。(実は、この世界は「ITそのもの」です。今、もっとも大きなビジネスチャンスはここにあります。)
また、教育も大きく変えていかなければなりません。金融関連の教育を中学・高校の時点からやっていきたいですね。今後、増えてくる様々な「投資ファンド」と教育の有機的連携が進んでくるでしょう。きっと新しい金融教育サービスが生まれてくるものと思います。
ということで、またまた長くなってしまいました。
本当は今日が最後のつもりで・・・(何?もう聞き飽きたって・・・結局、また続くんだろって・・・・そのとおりです。 )
)
まだ、実はいくつかお話ししていきたいことが残っています。
例えば、「ボーダーレス化」や今日のお話の「ファンド」によって「日本の伝統・文化・価値」「日本独自の商慣習等」はどうなっていくのか、といった点など。
それでは、また次回に続きを。(もう、最終回と言わないほうがよいかな。 )
)
ではまた
次回へ → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
さあ、ついにシリーズ第15弾にまでなってしまいました。
本当は前回で終了の予定だったのですが、意外とこの項目の内容が思っていたよりあったので、本日まで伸びてしまいました。ごめんなさい。
今日はきっと最終回になるかなあ(?(^^;)
前回、「IT革命が進むと、国が消える」という「ボーダーレス社会」のより一層深化した姿を、どちらかといえば、企業サイドからお話ししました。
今日は、その後半部分。もう少し大きく、社会の視点から、「ボーダーレス社会」を眺めてみましょう。そして、われわれの身近な生活の変化を考えてみましょう。
さて皆さん、唐突ですが、資産をお持ちですか?
(いきなりなんという挑戦的な・・・・
 でも私は資産をまったく持っていないので、資産もっている人と仲良くなっとかないと・・・ね
でも私は資産をまったく持っていないので、資産もっている人と仲良くなっとかないと・・・ね という話しではなく)
という話しではなく)もし資産お持ちの方で、その資産価値を減らしたくない方は、これからはどんどん投資をしてください。
(もちろん、そんなことは人に言われなくても百も承知でしょうが
 )
)すなわち、
「IT革命」が進んで「ボーダーレス社会」になると、今後、「日本の資産価値」は「海外の資産価値」に比べて相対的に減っていきますよ、という話しです。(これも当然皆さん、お分かりでしょうが、再確認したいと思います。)
きっと、われわれ日本人はこの点において、もっとも勉強しておかなければならないのかもしれません。そして、その際の勉強の対象は、もう一度、アメリカではないでしょうか?
なぜか?
それは、アメリカの戦後50年の間に起きた、「資産価値の相対的な目減り」が、われわれにとって意味あるからです。
思い出してください、終戦直後からその後の10年間位のことを。(といっても、私は当然生まれていませんので、よく分かりませんが・・・ホント?、生まれてたんじゃないの・・・・いや絶対にありません、ハイ
 )
)その頃、わが日本から見れば、アメリカははるかに進んだ国でした。「あこがれの社会」だったはずです。みんな、誰しもアメリカに行き住んでみたい、と思っていたはずです。
そして、恐らくその頃のアメリカの資産の相対的価値は、世界の半分位あったのではないでしょうか?(私は専門家ではないので、このあたりはまったくの勘で言っています。無責任な数字ですみません。また、今回の稿は、ITの話というより金融のお話が多いので、門外漢の私がお話するのはお門違いも甚だしいのですが、私個人の独断と偏見、ということでお許しください。できれば、これを読んだ専門家の方からご意見いただきたい位であります。)
その後、(私も生まれて・・・ホント? しつこい
 )わが日本は高度成長を走ります。そして、いつしか「あこがれのアメリカ」が手の届く範囲になり、あの「あこがれの象徴」だったロックフェラーセンターを日本人が買うという時代になったわけです。恐らく現在のアメリカの資産の相対的価値は世界の4分の一位になっていると思います。(かなりいい加減ですが・・・)
)わが日本は高度成長を走ります。そして、いつしか「あこがれのアメリカ」が手の届く範囲になり、あの「あこがれの象徴」だったロックフェラーセンターを日本人が買うという時代になったわけです。恐らく現在のアメリカの資産の相対的価値は世界の4分の一位になっていると思います。(かなりいい加減ですが・・・)そして、現在、われわれ日本が戦後たどった道を、中国・ロシア・ブラジル・インド(BRICSと言われてますね)をはじめとした国々が突っ走っています。(恐らく日本がたどった50年の道を彼らは25年~30年位で走るのではないでしょうか?これはまさに「IT革命」の成果なんですがね・・・
 )
)と、どうなるでしょうか。お分かりですね。今後、30年で日本の「相対的価値」はどんどん下がっていくということです。これは、この50年、アメリカがたどった道なんです。そして、このことは絶対に避けて通ることの出来ない道・・・。必ずやってくるでしょう。(気が付くと、あなたの家のとなりの土地をブラジル人が持っていたということは十分に起こりうることです。
 )
)では、アメリカの人々はこの50年の間、この「資産価値の目減り」にどのように対処してきたのでしょうか?
もうお分かりですね。「投資」をしてきたのです。
当たり前のことですが、「資産」をそのまま何もせずに持っていても、その「価値」が減るのであれば、その「資産」を使って「投資」するしかありません。彼らは「海外」に「投資」してきたのです。(もちろん、アメリカの国外に、ということです。)
それでは、皆さん、「投資」ということに関してどう思いますか?
われわれ日本人は本当に投資が苦手ですよね。というか、余りにも金融の知識を持っていないので、「よく分からない」というのが実感ではないでしょうか。これも戦後教育の大きな欠陥です。(実は私もこのあたりは大変苦手で・・・とほほ
 )
)でも、このままではわれわれの資産価値が目減りしていくことになります。
寝かせている資産のある方は、どんどん海外に出向いていって、もしくは海外の情報をいろいろな形で得て、海外への投資を企ててみてはいかがでしょうか?(もちろん、国内への投資も必要なことですが、海外への投資の方がはるかに重要です。)
また、個人だけで投資を行うことに限界があることから、様々な形での投資ファンドがもっと拡がることになるでしょう。(実は、この世界は「ITそのもの」です。今、もっとも大きなビジネスチャンスはここにあります。)
また、教育も大きく変えていかなければなりません。金融関連の教育を中学・高校の時点からやっていきたいですね。今後、増えてくる様々な「投資ファンド」と教育の有機的連携が進んでくるでしょう。きっと新しい金融教育サービスが生まれてくるものと思います。
ということで、またまた長くなってしまいました。
本当は今日が最後のつもりで・・・(何?もう聞き飽きたって・・・結局、また続くんだろって・・・・そのとおりです。
 )
)まだ、実はいくつかお話ししていきたいことが残っています。
例えば、「ボーダーレス化」や今日のお話の「ファンド」によって「日本の伝統・文化・価値」「日本独自の商慣習等」はどうなっていくのか、といった点など。
それでは、また次回に続きを。(もう、最終回と言わないほうがよいかな。
 )
)ではまた

次回へ → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html

ITの今後10年~30年の動向について ⑭
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
さて、「国」が消えていくお話です。
まず、「国」が消えていく、とはどういうことか、です。
「国」が消える、ということは国境の壁が低くなり、終いにはなくなることで、ヒトとモノの行き来が国の単位を超えて、自由になるということを指します。
この、いわゆる「ボーダーレス社会」ということは、多くの識者が新聞・書物等でお話ししていることですが、これからの30年はこのことがより一層進み、われわれの身近な生活のレベルまで深くそして広く浸透してくることになります。
今までは、「ボーダーレス社会」をどこか他人事のように、考えられる余裕がありましたが、これからは、まさに「自分事」となって、あらゆる生活の諸断面に降り注いでくるでしょう。
われわれは、仕事、生活、教育、環境等のあらゆる身近な場面で、国際化を意識することになります。
そして、そのことによって、われわれは「日本国民」とほぼ同等のレベルで「世界市民」を意識することになります。(正確に言うと「意識させられます。」)
例えば、私は、現在、静岡県東部地区を中心に事業を展開し、仕事を行っているわけですが、従来ですと、仕事上の競合相手は、同じ地域の事業者である比重が高かったわけです。ところが、これからは同じ地域の事業者と同等のレベルで、日本国内の、そして、世界各国の事業者を考えていかなければ事業の継続はできません。
そして、このことは私たちの業界だけの話しではなく、ありとあらゆる全ての事業者にとっても共通の話題です。これからの、あなたの街の八百屋さんは、世界中の市場の情報を手に入れていないと、商売ができなくなるかもしれません。(商店街に足を運ぶ顧客のみを相手にしているだけでは、ジリ貧状態がさらに深刻に進みます。)
事業者からみれば、「ボーダーレス社会」は過酷な競争を強いることになります。
消費者からみれば、「ボーダーレス社会」は「よりよい商品・サービスをより安く」手に入れることを可能にします。
ごく身近な消費行動から国内と海外のきびしい比較選別が始まります。
国内の教育サービスより、海外の教育サービスの方が、より高品質でより低価格であれば、顧客はいとも簡単に、海外のサービスを選択します。
このように、事業者にとっては、「ボーダーレス社会」は大変大きなデメリットしかもたらさないように思えますが、実は違います。
私は、「ボーダーレス社会」は事業者に大変大きなチャンスも同時にもたらすと思っています。
「ボーダーレス社会」は、日本の地方の中小零細企業を、いきなり「世界企業」にするチャンスをもたらします。もちろんチャンスは、日本だけでなく、中小零細企業だけでなく、あらゆる国々の、ありとあらゆる業態の企業に等しく与えられます。
「よりよい商品・サービスをより安く」提供できた企業には、「世界市場」が与えられます。
重要なことは、「消費者のニーズを、潜在化しているものも含めて、『人間が欲するもの』という普遍化したレベルでとらえ、それに応える商品・サービスを開発すること」。
例えば、教育事業に関してですが、「日本国内の大学合格を目的とした受験市場」に特化した商品・サービスであれば、その市場は海外には存在しません。ところが、その商品・サービスを、教育の本質(普遍性)に立脚し、即ち、「人間の脳力開発」に根ざしたものとし、例えば「認知症予防」「アルツハイマー予防」のために資する商品・サービス開発を行い、「よりよい商品・サービス」を「より安く」提供できたとしたら、対象市場は国内だけではなく「世界市場」となります。(もちろん、この場合においても、中小企業の事業展開の戦略としては、まずニッチな部分から起こしていった方がよいように思いますが。)
実は、これとよく似た具体的な事業展開は、「公文式学習」です。
皆さん、よくご存知のとおり、「公文式学習」の市場は世界に広がっています。「公文式学習」がいかに普遍的なものか、お分かりですね。どの国においても、「人間の能力開発」という視点で、基本的にはほぼ同じサービスを展開しています。
ここでも、「IT革命」が「本質的で普遍的な商品・サービス」を求めていることが分かります。
ところが、この「普遍性」や「普遍的なもの・こと」を事象からとらえることが、日本人はもっとも弱いのです。これは、まさしく戦後教育のもっとも大きな問題点だと思っています。
さて、今日がこのシリーズの最終回のつもりで書き進めてきましたが、実はまだお話ししたいことの半分しか述べていません。(え、まだあるの・・・・ )
)
従って、当初の予定にはなかったのですが、次回、「国が消えると私たちの生活はどうなるか?」をお贈りします。(もう飽きた ・・・・まあ、そう言わずお付き合いの程を
・・・・まあ、そう言わずお付き合いの程を )
)
では、また。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
さて、「国」が消えていくお話です。
まず、「国」が消えていく、とはどういうことか、です。
「国」が消える、ということは国境の壁が低くなり、終いにはなくなることで、ヒトとモノの行き来が国の単位を超えて、自由になるということを指します。
この、いわゆる「ボーダーレス社会」ということは、多くの識者が新聞・書物等でお話ししていることですが、これからの30年はこのことがより一層進み、われわれの身近な生活のレベルまで深くそして広く浸透してくることになります。
今までは、「ボーダーレス社会」をどこか他人事のように、考えられる余裕がありましたが、これからは、まさに「自分事」となって、あらゆる生活の諸断面に降り注いでくるでしょう。
われわれは、仕事、生活、教育、環境等のあらゆる身近な場面で、国際化を意識することになります。
そして、そのことによって、われわれは「日本国民」とほぼ同等のレベルで「世界市民」を意識することになります。(正確に言うと「意識させられます。」)
例えば、私は、現在、静岡県東部地区を中心に事業を展開し、仕事を行っているわけですが、従来ですと、仕事上の競合相手は、同じ地域の事業者である比重が高かったわけです。ところが、これからは同じ地域の事業者と同等のレベルで、日本国内の、そして、世界各国の事業者を考えていかなければ事業の継続はできません。
そして、このことは私たちの業界だけの話しではなく、ありとあらゆる全ての事業者にとっても共通の話題です。これからの、あなたの街の八百屋さんは、世界中の市場の情報を手に入れていないと、商売ができなくなるかもしれません。(商店街に足を運ぶ顧客のみを相手にしているだけでは、ジリ貧状態がさらに深刻に進みます。)
事業者からみれば、「ボーダーレス社会」は過酷な競争を強いることになります。
消費者からみれば、「ボーダーレス社会」は「よりよい商品・サービスをより安く」手に入れることを可能にします。
ごく身近な消費行動から国内と海外のきびしい比較選別が始まります。
国内の教育サービスより、海外の教育サービスの方が、より高品質でより低価格であれば、顧客はいとも簡単に、海外のサービスを選択します。
このように、事業者にとっては、「ボーダーレス社会」は大変大きなデメリットしかもたらさないように思えますが、実は違います。
私は、「ボーダーレス社会」は事業者に大変大きなチャンスも同時にもたらすと思っています。
「ボーダーレス社会」は、日本の地方の中小零細企業を、いきなり「世界企業」にするチャンスをもたらします。もちろんチャンスは、日本だけでなく、中小零細企業だけでなく、あらゆる国々の、ありとあらゆる業態の企業に等しく与えられます。
「よりよい商品・サービスをより安く」提供できた企業には、「世界市場」が与えられます。
重要なことは、「消費者のニーズを、潜在化しているものも含めて、『人間が欲するもの』という普遍化したレベルでとらえ、それに応える商品・サービスを開発すること」。
例えば、教育事業に関してですが、「日本国内の大学合格を目的とした受験市場」に特化した商品・サービスであれば、その市場は海外には存在しません。ところが、その商品・サービスを、教育の本質(普遍性)に立脚し、即ち、「人間の脳力開発」に根ざしたものとし、例えば「認知症予防」「アルツハイマー予防」のために資する商品・サービス開発を行い、「よりよい商品・サービス」を「より安く」提供できたとしたら、対象市場は国内だけではなく「世界市場」となります。(もちろん、この場合においても、中小企業の事業展開の戦略としては、まずニッチな部分から起こしていった方がよいように思いますが。)
実は、これとよく似た具体的な事業展開は、「公文式学習」です。
皆さん、よくご存知のとおり、「公文式学習」の市場は世界に広がっています。「公文式学習」がいかに普遍的なものか、お分かりですね。どの国においても、「人間の能力開発」という視点で、基本的にはほぼ同じサービスを展開しています。
ここでも、「IT革命」が「本質的で普遍的な商品・サービス」を求めていることが分かります。
ところが、この「普遍性」や「普遍的なもの・こと」を事象からとらえることが、日本人はもっとも弱いのです。これは、まさしく戦後教育のもっとも大きな問題点だと思っています。
さて、今日がこのシリーズの最終回のつもりで書き進めてきましたが、実はまだお話ししたいことの半分しか述べていません。(え、まだあるの・・・・
 )
)従って、当初の予定にはなかったのですが、次回、「国が消えると私たちの生活はどうなるか?」をお贈りします。(もう飽きた
 ・・・・まあ、そう言わずお付き合いの程を
・・・・まあ、そう言わずお付き合いの程を )
)では、また。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html

ITの今後10年~30年の動向について ⑬
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
さて、いよいよこのシリーズも大団円(^_^;;?
四つ目の予測に入ります。
IT革命が進んでいくと、最終的には何が消えていくのか?
皆さん、考えてくれましたか?
いったい何が消えるのでしょうか???
お金(現金)ですか?
そうですね、ITが進化すれば「お金(現金)」からネット上での「バーチャルマネー」に次第に変わっていくものと思われますね。ただ、われわれの実物経済がある限り、なかなか「お金(現金)」の存在を完全に消し去るのは難しいでしょうね。(ただ、私の財布からはどんどん消えていっていますが・・・とほほ )
)
緑(自然環境)ですか?
確かに、これは大変ゆゆしき問題ですね。実際に30年後に、自然はどうなっているのでしょうか・・・・・・?
ただ、この環境問題はITだけの話しではないですから、今回のテーマからは外していきたいと思います。
心でしょうか?
「心が消えていく」・・・うーん。恐い話しですね。でもこれもITだけの問題ではないですね。
では・・・・・・はてさて、いったい何が消えていくのか?
実は・・・・・・・・・・・
実は「人間」が消えていく・・・・(@o@)
えっ!!!・・・・・・なんちゃって。
うそだピョーン。 (コノ )
)
失礼しました。もう一度仕切りなおして・・・
「IT革命」が進展すると・・・・(ドラムロールスタート。シーン№4! 3、2、1・・・「カチンコ」)
それは・・・・・ » 続きを読む
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
さて、いよいよこのシリーズも大団円(^_^;;?
四つ目の予測に入ります。
IT革命が進んでいくと、最終的には何が消えていくのか?
皆さん、考えてくれましたか?
いったい何が消えるのでしょうか???
お金(現金)ですか?
そうですね、ITが進化すれば「お金(現金)」からネット上での「バーチャルマネー」に次第に変わっていくものと思われますね。ただ、われわれの実物経済がある限り、なかなか「お金(現金)」の存在を完全に消し去るのは難しいでしょうね。(ただ、私の財布からはどんどん消えていっていますが・・・とほほ
 )
)緑(自然環境)ですか?
確かに、これは大変ゆゆしき問題ですね。実際に30年後に、自然はどうなっているのでしょうか・・・・・・?
ただ、この環境問題はITだけの話しではないですから、今回のテーマからは外していきたいと思います。
心でしょうか?
「心が消えていく」・・・うーん。恐い話しですね。でもこれもITだけの問題ではないですね。
では・・・・・・はてさて、いったい何が消えていくのか?
実は・・・・・・・・・・・
実は「人間」が消えていく・・・・(@o@)
えっ!!!・・・・・・なんちゃって。
うそだピョーン。 (コノ
 )
)失礼しました。もう一度仕切りなおして・・・
「IT革命」が進展すると・・・・(ドラムロールスタート。シーン№4! 3、2、1・・・「カチンコ」)
それは・・・・・ » 続きを読む
ITの今後10年~30年の動向について ⑫
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
またまた時間が経ってしまいましたが、このシリーズは続けなければ・・・・・。
前回、学校の役割が再構築されるお話をしました。
今回は、学校の役割が再構築されると、教師と生徒の役割がまったく現在と異なってくることをお話しします。
教師=教える人、生徒=教わる人、という図式とはまったく異なり、生徒は自らの目的・目標に従って、知識を得、学習を進めていきます。
教師は、その環境設定および支援者(サポーター)、もしくはメンター(先達者)およびコンサルタントです。
また、「優秀な教師」と「そうでない教師」の間には大きな差が開きます。「IT革命」によって、「優秀な教師」の授業は、どの学校の生徒でも受けられるようになります。従って、「優秀な教師」には多くの生徒が集まり、「そうでない教師」にはまったく生徒がいない、という事態が発生する可能性があります。即ち、教師が淘汰されていく時代がやってくる、ということです。(プロ・ワーカーならぬ「プロ教師」が今以上に求められてきます。)
そして、このことからも「どの学校」よりも「どの先生」に習ったか、が大きく意味をもつことがわかります。
これからは「学閥」ではなく、「先生閥」かもしれません。
「学校」が消えていく予測の意味・・・・お分かりいただけたでしょうか?
さて、次回がこのシリーズの最終回、とします。(そうしないと、皆さん、飽きますからね)
最終回の次回は、四つ目の予測です。
さあ、何が消えていくのでしょうか?
よかったら考えてみてください。
では、皆さん、また明日。アテブレーベ。オブリガード。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
またまた時間が経ってしまいましたが、このシリーズは続けなければ・・・・・。
前回、学校の役割が再構築されるお話をしました。
今回は、学校の役割が再構築されると、教師と生徒の役割がまったく現在と異なってくることをお話しします。
教師=教える人、生徒=教わる人、という図式とはまったく異なり、生徒は自らの目的・目標に従って、知識を得、学習を進めていきます。
教師は、その環境設定および支援者(サポーター)、もしくはメンター(先達者)およびコンサルタントです。
また、「優秀な教師」と「そうでない教師」の間には大きな差が開きます。「IT革命」によって、「優秀な教師」の授業は、どの学校の生徒でも受けられるようになります。従って、「優秀な教師」には多くの生徒が集まり、「そうでない教師」にはまったく生徒がいない、という事態が発生する可能性があります。即ち、教師が淘汰されていく時代がやってくる、ということです。(プロ・ワーカーならぬ「プロ教師」が今以上に求められてきます。)
そして、このことからも「どの学校」よりも「どの先生」に習ったか、が大きく意味をもつことがわかります。
これからは「学閥」ではなく、「先生閥」かもしれません。
「学校」が消えていく予測の意味・・・・お分かりいただけたでしょうか?
さて、次回がこのシリーズの最終回、とします。(そうしないと、皆さん、飽きますからね)
最終回の次回は、四つ目の予測です。
さあ、何が消えていくのでしょうか?
よかったら考えてみてください。
では、皆さん、また明日。アテブレーベ。オブリガード。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html

ITの今後10年~30年の動向について ⑪
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
さあ、みなさん、独断と偏見による予測。
いよいよ三つ目の予測をしてみたいと思います。
「IT革命」が進むと何が消えていくのでしょうか?
これまで「パソコン」「会社」と消えていくシリーズはつながりましたが、三つ目は何が消えていくか?
それは・・・・・・
「学校」が消えていくでしょう
ということです。
さあ、「パソコン」「会社」の次は、「学校」でした
(しかし、「パソコン」がなくなって、「学校」がなくなるって・・・・「パソコンスクール」の経営者が言う言葉じゃないよね。ちょっと商売換えでもしようかなあ・・・ )
)
では、「学校」が消え~るとは、どういうことでしょうか?
それは、「IT革命」が進んでいくことによって、「学ぶ場所が必ずしも学校である必要がなくなる」ということです。
「IT革命」によって、学習はあらゆる場所で可能になります。
少し、長文ですが、弊社の「M-net市民大学」の「学長挨拶」を読んでみてください。
http://www.mnet-c-univ.jp/about2_long.html
ふう・・・ちょっと長すぎて疲れましたか?
この挨拶文、うちのスタッフからも不評で、長すぎるんですよね。しかし、私は天邪鬼だから、変えないんです。(こう見えても意外と頑固なところも・・・・ね あったようです。ハイ )
)
ただ、言いたいことは分かってもらえますかね。前回の「会社」の場合と同じく、「学校」の機能もその本質を鋭く問われて、その機能に相応しい場所・時間に取って代わられる、ということです。
学校は「集団生活を学ぶ場」として再構築されます。
これからは「東大卒業」ということよりも、「どこの大学の何先生に学び、どの程度の成績であったか」がもっと価値があります。(誰ですか、「どこの大学のどの女の子と付き合い、どのような付き合い方だったかがもっとも・・・・」と言っているのは )
)
そして、中学高校大学での勉強以上に、卒業してからの学習が重要視されると思います。仕事を得てからの学習がもっとも価値があるでしょう!(本来、「学習」というのはその目的のためにあるのですから)
さて、次回はこのように学校の役割が再構築されてくると、教師と生徒の役割がまったく現在と異なってくる、ということをお話しします。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
さあ、みなさん、独断と偏見による予測。
いよいよ三つ目の予測をしてみたいと思います。
「IT革命」が進むと何が消えていくのでしょうか?
これまで「パソコン」「会社」と消えていくシリーズはつながりましたが、三つ目は何が消えていくか?
それは・・・・・・
「学校」が消えていくでしょう
ということです。
さあ、「パソコン」「会社」の次は、「学校」でした
(しかし、「パソコン」がなくなって、「学校」がなくなるって・・・・「パソコンスクール」の経営者が言う言葉じゃないよね。ちょっと商売換えでもしようかなあ・・・
 )
)では、「学校」が消え~るとは、どういうことでしょうか?
それは、「IT革命」が進んでいくことによって、「学ぶ場所が必ずしも学校である必要がなくなる」ということです。
「IT革命」によって、学習はあらゆる場所で可能になります。
少し、長文ですが、弊社の「M-net市民大学」の「学長挨拶」を読んでみてください。
http://www.mnet-c-univ.jp/about2_long.html
ふう・・・ちょっと長すぎて疲れましたか?
この挨拶文、うちのスタッフからも不評で、長すぎるんですよね。しかし、私は天邪鬼だから、変えないんです。(こう見えても意外と頑固なところも・・・・ね あったようです。ハイ
 )
)ただ、言いたいことは分かってもらえますかね。前回の「会社」の場合と同じく、「学校」の機能もその本質を鋭く問われて、その機能に相応しい場所・時間に取って代わられる、ということです。
学校は「集団生活を学ぶ場」として再構築されます。
これからは「東大卒業」ということよりも、「どこの大学の何先生に学び、どの程度の成績であったか」がもっと価値があります。(誰ですか、「どこの大学のどの女の子と付き合い、どのような付き合い方だったかがもっとも・・・・」と言っているのは
 )
)そして、中学高校大学での勉強以上に、卒業してからの学習が重要視されると思います。仕事を得てからの学習がもっとも価値があるでしょう!(本来、「学習」というのはその目的のためにあるのですから)
さて、次回はこのように学校の役割が再構築されてくると、教師と生徒の役割がまったく現在と異なってくる、ということをお話しします。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html

「IZU photo」さんの写真、すばらしいですね
一昨日から、この「イーラ」を見る楽しみが、また増えました。
本当に写真って説得力ありますね。すばらしいと思います。
結構癒されていますよ。
kiyoさん、ぜひどんどん作品掲載してください。
僕はファンになってしまいましたよ。
http://kiyo.i-ra.jp/
それにしても僕のブログは本当に文章ばかりで見栄えよくないねえ・・・・
本当に写真って説得力ありますね。すばらしいと思います。
結構癒されていますよ。
kiyoさん、ぜひどんどん作品掲載してください。
僕はファンになってしまいましたよ。
http://kiyo.i-ra.jp/
それにしても僕のブログは本当に文章ばかりで見栄えよくないねえ・・・・

ITの今後10年~30年の動向について ⑩
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
さて、前回のお話からかなり時間が経ってしまいました。ごめんなさい。
では、早速、前回の続きからお話を進めてまいりましょう。
「仕事」を行う主体が「個人」に戻っていく過程をこれから10年~30年くらいかけて、われわれは経験していくわけですが、その際、「会社」はどうなっていくのでしょうか?
「会社」は本当に消えていくのだろうか?
もちろん、従来の形態の「会社」はなくなっていくでしょう!
では、「会社」は必要ないのか?
それは、ノン(いいえ)です。
「会社」の存在は、次のようなものとして変質していくのではないでしょうか?
ひとつめは、「消費者」と「プロ・ワーカー」を結びつける「仲介」としての存在です。「プロ・ワーカー」は製品やサービスの供給者ではありますが、「マーケティング」の機能がありません。それは引き続き、「会社」が行っていくものと思われます。ただし、「プロ・ワーカー」の中には、「マーケティング」機能そのものを供給するものもいます。従って、「会社」と「プロ・ワーカー」との関係は固定的なものでなく、かなり柔軟で流動的なものと想像できます。
ふたつめは、「会社」は、「人とのふれあいの場」「コミュニケーションの場」として、存在します。この機能は、社会を成立させるための大変重要な機能です。社会を成立させるものは、「コミュニケーション」です。また、「仕事」も「コミュニケーション」の中で成立していきます。
すでに、何度もお話ししていますように、「われわれは、他人との関係性の中で生きています。」
「コミュニケーション」はわれわれを存在づける、大変重要な機能です。
みっつめは、「会社」は、「資金集め」の大変大きなツールです。これは、最近、「ファンド」の役割が大きくなってきているので、改めて「会社」のその機能が脚光を浴びてきていることからわかると思います。
ただ、このこと自体は何ら新しいことでもありません。
「会社」が世の中に生まれた時に持っていた、というか、そのために「会社」は生まれたのですから、その本来的な機能があらわれているだけです。
つまり、「会社」はそれ自体が「商品」です。これを否定することはできません。これは、「会社」の本来的な機能です。その意味では、「会社」は「株主」のものであることは、当然のことなんです。
問題になっているのは、「商品」である「会社」を運用する「人間のオペレーションの問題」です。
資本主義社会である限り、「会社」の「商品性」は否定することはできません。(ちょっと話がずれていくので、この部分はまた別の機会にでもお話してみたいと思います。)
ということで、「なあんだ、結局、「会社」が消えるというのはうそじゃないか」という声が、痛いほど聞こえてきます。
「えへへ」とごまかしていきたいのですが、少しは言い訳を。
それは、現在の「会社」の機能の多くが消えていく、ということが言いたかっただけで・・・・(「じゃあ、そう言えばいいじゃないか」・・・・「まあまあ(日本的ごまかしで・・)」)
このように、「IT革命」はあらゆるものの本質的存在を鋭く問うていきます。
「会社」「社会」「仕事」・・・そして「個人」。
そして、その本質的存在に応えられないものは、消えていく運命にあります。
さて、次回は3つめの予想を行います。
ひとつめは、「パソコン」が消えていき、ふたつめは「会社」が消える話をしました。
では、次は何が消えていくのでしょうか?
よろしかったらお考え下さい。ではまた
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
さて、前回のお話からかなり時間が経ってしまいました。ごめんなさい。
では、早速、前回の続きからお話を進めてまいりましょう。
「仕事」を行う主体が「個人」に戻っていく過程をこれから10年~30年くらいかけて、われわれは経験していくわけですが、その際、「会社」はどうなっていくのでしょうか?
「会社」は本当に消えていくのだろうか?
もちろん、従来の形態の「会社」はなくなっていくでしょう!
では、「会社」は必要ないのか?
それは、ノン(いいえ)です。
「会社」の存在は、次のようなものとして変質していくのではないでしょうか?
ひとつめは、「消費者」と「プロ・ワーカー」を結びつける「仲介」としての存在です。「プロ・ワーカー」は製品やサービスの供給者ではありますが、「マーケティング」の機能がありません。それは引き続き、「会社」が行っていくものと思われます。ただし、「プロ・ワーカー」の中には、「マーケティング」機能そのものを供給するものもいます。従って、「会社」と「プロ・ワーカー」との関係は固定的なものでなく、かなり柔軟で流動的なものと想像できます。
ふたつめは、「会社」は、「人とのふれあいの場」「コミュニケーションの場」として、存在します。この機能は、社会を成立させるための大変重要な機能です。社会を成立させるものは、「コミュニケーション」です。また、「仕事」も「コミュニケーション」の中で成立していきます。
すでに、何度もお話ししていますように、「われわれは、他人との関係性の中で生きています。」
「コミュニケーション」はわれわれを存在づける、大変重要な機能です。
みっつめは、「会社」は、「資金集め」の大変大きなツールです。これは、最近、「ファンド」の役割が大きくなってきているので、改めて「会社」のその機能が脚光を浴びてきていることからわかると思います。
ただ、このこと自体は何ら新しいことでもありません。
「会社」が世の中に生まれた時に持っていた、というか、そのために「会社」は生まれたのですから、その本来的な機能があらわれているだけです。
つまり、「会社」はそれ自体が「商品」です。これを否定することはできません。これは、「会社」の本来的な機能です。その意味では、「会社」は「株主」のものであることは、当然のことなんです。
問題になっているのは、「商品」である「会社」を運用する「人間のオペレーションの問題」です。
資本主義社会である限り、「会社」の「商品性」は否定することはできません。(ちょっと話がずれていくので、この部分はまた別の機会にでもお話してみたいと思います。)
ということで、「なあんだ、結局、「会社」が消えるというのはうそじゃないか」という声が、痛いほど聞こえてきます。
「えへへ」とごまかしていきたいのですが、少しは言い訳を。
それは、現在の「会社」の機能の多くが消えていく、ということが言いたかっただけで・・・・(「じゃあ、そう言えばいいじゃないか」・・・・「まあまあ(日本的ごまかしで・・)」)

このように、「IT革命」はあらゆるものの本質的存在を鋭く問うていきます。
「会社」「社会」「仕事」・・・そして「個人」。
そして、その本質的存在に応えられないものは、消えていく運命にあります。
さて、次回は3つめの予想を行います。
ひとつめは、「パソコン」が消えていき、ふたつめは「会社」が消える話をしました。
では、次は何が消えていくのでしょうか?
よろしかったらお考え下さい。ではまた

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html

ニコニコ動画~もう動画の時代ですね
皆さんはもうご存知でしょうか? ニコニコ動画。
もう知っている人はかなり知っているし、はまっていると思います。
私はどうしてもこの手はオクテで、ようやく先日知りました。
知らない人は、YAHOOで文字通り「ニコニコ動画」と検索すれば、すぐに突き当たります。
「YouTube」も面白いですが、日本人にはこちらの方がいいかもしれません。
先日、このニコニコ動画で「NHK ドキュメント地球時間 JAZZ ジャズよ 永遠なれ」という番組を見ました。
私は本当にJAZZが好きで、前の会社に20年前に転職した際は、JAZZ好きが嵩じてSAXを買って、ヤマハの教室で習っていました。(またどこかで、このことは書きます。)
このブログでも以前にJAZZのことについて書きましたね。
http://katsu.i-ra.jp/e483.html
先のNHKの番組は以前見ていたのですが、その際、録画するのを忘れて、またどこかで見れたらなあ、とずーっと思い続けていたものでした。
それをおそらく7、8年ぶりに見ることができたのだと思います。
感激しました。
もう本当にインターネットは動画の時代に突入していくんですね。こういったことがあると実感します。
ニコニコ動画は例の2ちゃんねるをはじめた人がプロデュースしていますから、ちょっと著作権のことを考えると法律すれすれか、完璧に違法のものも結構あるようです。
YouTubeもそうですが、ね。
またアダルトの映像がやはり多い、ということ。
93、4年ころから、インターネットがなぜこんなに世の中に広まったかというと、結局、アダルト情報がもっともはやく広範囲に流通したからで・・・・どうしてもこの部分は否定できないことです。
(私も男ですから、ごく自然な感情として、やはり興味ありますから。学長がこんなこと言ったらまずいかなあ(^^;))
動画情報も世間一般に流布していくのは、どうしてもこの部分からになると思います。
ただ、ニコニコ動画の中には、当然アダルトだけではなく、大変広範囲に動画が集まっています。
先のNHKの番組も結構ありそうです。(ただ、これも厳密にいえば、著作権違反ですよね。)
結構貴重な動画を見ることができるかもしれません。
この著作権と見る方のニーズ、および、「創作」との関係は大変微妙なバランス感覚が必要です。
最近では、「クリエイティブ・コモンズ」という考え方もありますが、著作権を厳密に運用すればするほど「創作」のパワーが減衰していく、という考え方もあるかもしれないなあ、とニコニコ動画を見ていて思ってしまうほど、大変ユニークな動画、新たな発想の動画がたくさんあります。
クリエイティブな感性をかなり刺激されそうです。(ただ、そうでないものもたくさんありますが・・・・・玉石混交。)
そして、見る方のニーズははてしがない。人間って本当に好奇心旺盛で・・・これがビジネスを作っているんですから仕方がない。もっともっと知りたいし、もっともっと見たいのですね。
ただ、昨今の犯罪とか事件を見ていると、ほうっておくと限度のない自分の心・欲望に対して、何らかのバランス感覚やコントロールする心理学的手法を教育していく必要があると、切に思います。
(単純に欲望を押さえつけるのではなく、否定するのではなく、その欲望を認めたうえで、うまく自然な心の動きの中で制御していく手法を身につける必要があると思います。)
このブログの中でも、どこかでそういったテーマに基づくお話をしてみたいとは思います。
ということで、今日は(というか今日も、ですが )とりとめのない話になってしまいました。
)とりとめのない話になってしまいました。
ではまた。

もう知っている人はかなり知っているし、はまっていると思います。
私はどうしてもこの手はオクテで、ようやく先日知りました。
知らない人は、YAHOOで文字通り「ニコニコ動画」と検索すれば、すぐに突き当たります。
「YouTube」も面白いですが、日本人にはこちらの方がいいかもしれません。
先日、このニコニコ動画で「NHK ドキュメント地球時間 JAZZ ジャズよ 永遠なれ」という番組を見ました。
私は本当にJAZZが好きで、前の会社に20年前に転職した際は、JAZZ好きが嵩じてSAXを買って、ヤマハの教室で習っていました。(またどこかで、このことは書きます。)
このブログでも以前にJAZZのことについて書きましたね。
http://katsu.i-ra.jp/e483.html
先のNHKの番組は以前見ていたのですが、その際、録画するのを忘れて、またどこかで見れたらなあ、とずーっと思い続けていたものでした。
それをおそらく7、8年ぶりに見ることができたのだと思います。
感激しました。
もう本当にインターネットは動画の時代に突入していくんですね。こういったことがあると実感します。
ニコニコ動画は例の2ちゃんねるをはじめた人がプロデュースしていますから、ちょっと著作権のことを考えると法律すれすれか、完璧に違法のものも結構あるようです。
YouTubeもそうですが、ね。
またアダルトの映像がやはり多い、ということ。
93、4年ころから、インターネットがなぜこんなに世の中に広まったかというと、結局、アダルト情報がもっともはやく広範囲に流通したからで・・・・どうしてもこの部分は否定できないことです。
(私も男ですから、ごく自然な感情として、やはり興味ありますから。学長がこんなこと言ったらまずいかなあ(^^;))
動画情報も世間一般に流布していくのは、どうしてもこの部分からになると思います。
ただ、ニコニコ動画の中には、当然アダルトだけではなく、大変広範囲に動画が集まっています。
先のNHKの番組も結構ありそうです。(ただ、これも厳密にいえば、著作権違反ですよね。)
結構貴重な動画を見ることができるかもしれません。
この著作権と見る方のニーズ、および、「創作」との関係は大変微妙なバランス感覚が必要です。
最近では、「クリエイティブ・コモンズ」という考え方もありますが、著作権を厳密に運用すればするほど「創作」のパワーが減衰していく、という考え方もあるかもしれないなあ、とニコニコ動画を見ていて思ってしまうほど、大変ユニークな動画、新たな発想の動画がたくさんあります。
クリエイティブな感性をかなり刺激されそうです。(ただ、そうでないものもたくさんありますが・・・・・玉石混交。)
そして、見る方のニーズははてしがない。人間って本当に好奇心旺盛で・・・これがビジネスを作っているんですから仕方がない。もっともっと知りたいし、もっともっと見たいのですね。
ただ、昨今の犯罪とか事件を見ていると、ほうっておくと限度のない自分の心・欲望に対して、何らかのバランス感覚やコントロールする心理学的手法を教育していく必要があると、切に思います。
(単純に欲望を押さえつけるのではなく、否定するのではなく、その欲望を認めたうえで、うまく自然な心の動きの中で制御していく手法を身につける必要があると思います。)
このブログの中でも、どこかでそういったテーマに基づくお話をしてみたいとは思います。
ということで、今日は(というか今日も、ですが
 )とりとめのない話になってしまいました。
)とりとめのない話になってしまいました。ではまた。
ITの今後10年~30年の動向について ⑨
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
さて、前回は、「個人」が「組織」より力をもつ時代がやってくる、というお話をしました。
そして、そのときにわれわれは
「何のために『仕事』をするのか?」
ということを鋭く問われるようになります。
皆さんは、どのようにお答えになりますか?
かなり本質的、根源的に問われます。
そして、この質問は次の質問と同値です。
「その仕事をするあなたは何者ですか?」
当然、その問いに対する答えはそれぞれにあるでしょうが、唯一言えることは、「そもそも人間は仕事によって、自らの存在を証明する動物である」ということです。(こういう個人のことを、私は「プロフェッショナル・ワーカー」(略して「プロ・ワーカー」と呼んでいます。)
自己の存在を証明するのは、「会社」ではなく、「仕事」ですね。当然ですが。
そして、このこと自体は何も目新しいことではありません。
世の中に、「会社」という存在が現れたのは、人類史からみれば、ごく最近です。
人が「会社」の中で「仕事」を行うようになったのは、ほんの400年程度の歴史です。
この400年の歴史の中で、「仕事」を行う主体が、「個人」から「会社」へ次第に次第にシフトしていきました。
そして、その結果、われわれはいつしか「個人」より「会社」「組織」を優先させるように、意識が変わっていきました。「会社」のために「仕事」を行う「会社人間」、「社会」の構成要素として、「組織」を優先させる「組織社会」が・・・・・。こうして「個人」は阻害されていったのです。
「個人」のために「仕事」を行うことを、社会は「わがまま」で「無責任」であると糾弾するようになりました。
一流企業に所属することが、自己の存在を証明することであるかのように、世の中全体が「錯覚」を起こし、「個人」は「組織」の中に埋没していったのです。
さて、歴史はいつも繰り返します。
「会社」が主体となっていく400年の歴史過程を経て、ここに「IT革命」が起こりました。
「IT革命」は「仕事」を行う主体を、もう一度、「会社」「組織」から「個人」に戻します。
われわれが本来もっているであろうはずの意識が再認識されてくるでしょう。
曰く、
「仕事を行うことが、自らの存在を社会に対して証明する唯一の行為である。」
「われわれは自らの存在を証明するために、仕事を行っている。」
という意識。
ただ、誤解しないでいただきたいのは、「仕事」の主体が「個人」になっても、一人で仕事ができる分野はそんなに多くはありません。
「仕事」は相変わらず、何人かの複数の「プロ・ワーカー」たちとの「グループワーク」になります。ということは、「仕事」を遂行する上でのスキルとして最も重要なものは、「コミュニケーション能力」であることは、これからも一切変わらない、と思います。
さて、ここまで話を進めていくと、いよいよ気になってくる質問が出てまいります。
それは・・・・・・・
では、「会社」はどうなってしまうのか?
ということ。
次回は、この話題を進めていきましょう。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
さて、前回は、「個人」が「組織」より力をもつ時代がやってくる、というお話をしました。
そして、そのときにわれわれは
「何のために『仕事』をするのか?」
ということを鋭く問われるようになります。
皆さんは、どのようにお答えになりますか?
かなり本質的、根源的に問われます。
そして、この質問は次の質問と同値です。
「その仕事をするあなたは何者ですか?」
当然、その問いに対する答えはそれぞれにあるでしょうが、唯一言えることは、「そもそも人間は仕事によって、自らの存在を証明する動物である」ということです。(こういう個人のことを、私は「プロフェッショナル・ワーカー」(略して「プロ・ワーカー」と呼んでいます。)
自己の存在を証明するのは、「会社」ではなく、「仕事」ですね。当然ですが。
そして、このこと自体は何も目新しいことではありません。
世の中に、「会社」という存在が現れたのは、人類史からみれば、ごく最近です。
人が「会社」の中で「仕事」を行うようになったのは、ほんの400年程度の歴史です。
この400年の歴史の中で、「仕事」を行う主体が、「個人」から「会社」へ次第に次第にシフトしていきました。
そして、その結果、われわれはいつしか「個人」より「会社」「組織」を優先させるように、意識が変わっていきました。「会社」のために「仕事」を行う「会社人間」、「社会」の構成要素として、「組織」を優先させる「組織社会」が・・・・・。こうして「個人」は阻害されていったのです。
「個人」のために「仕事」を行うことを、社会は「わがまま」で「無責任」であると糾弾するようになりました。
一流企業に所属することが、自己の存在を証明することであるかのように、世の中全体が「錯覚」を起こし、「個人」は「組織」の中に埋没していったのです。
さて、歴史はいつも繰り返します。
「会社」が主体となっていく400年の歴史過程を経て、ここに「IT革命」が起こりました。
「IT革命」は「仕事」を行う主体を、もう一度、「会社」「組織」から「個人」に戻します。
われわれが本来もっているであろうはずの意識が再認識されてくるでしょう。
曰く、
「仕事を行うことが、自らの存在を社会に対して証明する唯一の行為である。」
「われわれは自らの存在を証明するために、仕事を行っている。」
という意識。
ただ、誤解しないでいただきたいのは、「仕事」の主体が「個人」になっても、一人で仕事ができる分野はそんなに多くはありません。
「仕事」は相変わらず、何人かの複数の「プロ・ワーカー」たちとの「グループワーク」になります。ということは、「仕事」を遂行する上でのスキルとして最も重要なものは、「コミュニケーション能力」であることは、これからも一切変わらない、と思います。
さて、ここまで話を進めていくと、いよいよ気になってくる質問が出てまいります。
それは・・・・・・・
では、「会社」はどうなってしまうのか?
ということ。
次回は、この話題を進めていきましょう。
ではまた。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html

ITの今後10年~30年の動向について ⑧
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
さて、ここのところ、この「ITシリーズ」のことをすっかり忘れていまして、続編が今日になってしまいました。すみません
前回、「ITの今後10年~30年の動向」の二つ目の予測をするというお話をしました。
一つ目の予測では、「IT革命」の主役である「パソコン」が消えていく、ということでしたが、二つ目はどういった予測でしょうか?
それは・・・・・
「IT革命」によって起こる「社会変革・動向」として、10年~30年の間に、
「会社」が消えていくでしょう
ということです。
かなり大胆な独断と偏見に満ちた予測なので、何を荒唐無稽な、といって一笑に付されてしまいそうなお話です。一笑に付す前に、今しばらくお付き合いのほどを。
「会社が消える」・・・、どういうことでしょうか?
それは、「IT革命」が進んでいくことで、「会社」と「個人」の関係が劇的に変化していくことを示しています。
これからの「会社」と「個人」の関係は、「会社という枠組み(場)」と「個人という仕事主体者」との契約関係に移行していくと思われます。
「IT革命」、「ブロードバンド(通信)革命」が一層進むことで、会社の内と外の壁がどんどん低くなって、そしてなくなっていくでしょう。
そして、内と外の壁がなくなれば、仕事は最も効率のよい最適な場所に移ります。自宅での仕事、客先での仕事、移動中での仕事・・・。
即ち、仕事の多くは会社の外で行われます。
いわゆるSOHO、テレワーク、マイクロビジネスといった形態が、一般の会社にまで広がるイメージです。
今までの会社・仕事のあり方の常識が大きく変わります。
個人にとって、会社が単位ではなく、仕事が単位となります。
個人は会社と1対1ではありません。個人は仕事と1対1であります。そういう意味では、個人が複数の会社に同時に勤めることは、ごく普通のオフィス風景となっているでしょう。当然、正社員という区別はもはや何の意味もなくなっていると思われます。個人と仕事のあり方が本質的に問われます。
先日、ブログ村の記事の際に、「アルファ・ブロガー」のお話をしました。
http://katsu.i-ra.jp/e2142.html
これまでの社会の主役は、企業や組織でした。ところが、ネットの世界では、企業も個人も同列で扱われていくことを、この「アルファ・ブロガー」の存在は示しています。
これからは、「日本一・世界一の自動車会社のトヨタに所属する部長・課長のAさん」よりも、トヨタに所属していようが他の会社・組織に所属していようが関係なく、「特異な能力・才能、情報、的確な価値観や見識、を持って主体的に行動しているBさん」の方が力をもつ時代がやってくるでしょう。
真の意味で、「組織」より「個人」が力をもつ時代がやってきます。
ここに、先の「アルファ・ブロガー」以外に、その兆しをあらわす、もう一つの例があります。
以下の記事をご覧下さい。
(個人アニメ作家にFlashがくれた“力”)(クリックしてください)
この記事の中の「フロッグマン」さんは、「映画・テレビ業界」という大きな組織に所属した制作スタッフの一人でありましたが、その「組織」を飛び出し、「個人の力」で「自分の事業」を展開しています。
これを、単なる「アニメ作家」の話だけでとらえていては、少しアンテナが低いのではないか、と思っています。
これからは、このような「組織」ではなく「個人」で勝負する人々が一般の事務系の職場までどんどん拡がってくると、私は思っています。
ただ、誤解の無いように。私は「組織」を飛び出せ、という話をしているのでは決してありません。
「組織」に依存した「個人」では、もはや満足な「仕事」ができなくなる、というお話をしています。
そして、このように「会社」と「個人」の関係が大きく変動を遂げていく中で、われわれに改めて、するどく問い掛けてくる、質問があります。
それは・・・・・
「われわれは何のために『仕事』をするのか?」
ということ。
さて、皆さんは何のために「仕事」をしていますか?
次回は、この問いかけを中心に、もっと「会社」と「個人」、そして「仕事」との関係をお話していきたい、と思います。
今日も長くなってしまいました。すみません。では、また今度。
次へ → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html

第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
さて、ここのところ、この「ITシリーズ」のことをすっかり忘れていまして、続編が今日になってしまいました。すみません

前回、「ITの今後10年~30年の動向」の二つ目の予測をするというお話をしました。
一つ目の予測では、「IT革命」の主役である「パソコン」が消えていく、ということでしたが、二つ目はどういった予測でしょうか?
それは・・・・・
「IT革命」によって起こる「社会変革・動向」として、10年~30年の間に、
「会社」が消えていくでしょう
ということです。
かなり大胆な独断と偏見に満ちた予測なので、何を荒唐無稽な、といって一笑に付されてしまいそうなお話です。一笑に付す前に、今しばらくお付き合いのほどを。
「会社が消える」・・・、どういうことでしょうか?
それは、「IT革命」が進んでいくことで、「会社」と「個人」の関係が劇的に変化していくことを示しています。
これからの「会社」と「個人」の関係は、「会社という枠組み(場)」と「個人という仕事主体者」との契約関係に移行していくと思われます。
「IT革命」、「ブロードバンド(通信)革命」が一層進むことで、会社の内と外の壁がどんどん低くなって、そしてなくなっていくでしょう。
そして、内と外の壁がなくなれば、仕事は最も効率のよい最適な場所に移ります。自宅での仕事、客先での仕事、移動中での仕事・・・。
即ち、仕事の多くは会社の外で行われます。
いわゆるSOHO、テレワーク、マイクロビジネスといった形態が、一般の会社にまで広がるイメージです。
今までの会社・仕事のあり方の常識が大きく変わります。
個人にとって、会社が単位ではなく、仕事が単位となります。
個人は会社と1対1ではありません。個人は仕事と1対1であります。そういう意味では、個人が複数の会社に同時に勤めることは、ごく普通のオフィス風景となっているでしょう。当然、正社員という区別はもはや何の意味もなくなっていると思われます。個人と仕事のあり方が本質的に問われます。
先日、ブログ村の記事の際に、「アルファ・ブロガー」のお話をしました。
http://katsu.i-ra.jp/e2142.html
これまでの社会の主役は、企業や組織でした。ところが、ネットの世界では、企業も個人も同列で扱われていくことを、この「アルファ・ブロガー」の存在は示しています。
これからは、「日本一・世界一の自動車会社のトヨタに所属する部長・課長のAさん」よりも、トヨタに所属していようが他の会社・組織に所属していようが関係なく、「特異な能力・才能、情報、的確な価値観や見識、を持って主体的に行動しているBさん」の方が力をもつ時代がやってくるでしょう。
真の意味で、「組織」より「個人」が力をもつ時代がやってきます。
ここに、先の「アルファ・ブロガー」以外に、その兆しをあらわす、もう一つの例があります。
以下の記事をご覧下さい。
(個人アニメ作家にFlashがくれた“力”)(クリックしてください)
この記事の中の「フロッグマン」さんは、「映画・テレビ業界」という大きな組織に所属した制作スタッフの一人でありましたが、その「組織」を飛び出し、「個人の力」で「自分の事業」を展開しています。
これを、単なる「アニメ作家」の話だけでとらえていては、少しアンテナが低いのではないか、と思っています。
これからは、このような「組織」ではなく「個人」で勝負する人々が一般の事務系の職場までどんどん拡がってくると、私は思っています。
ただ、誤解の無いように。私は「組織」を飛び出せ、という話をしているのでは決してありません。
「組織」に依存した「個人」では、もはや満足な「仕事」ができなくなる、というお話をしています。
そして、このように「会社」と「個人」の関係が大きく変動を遂げていく中で、われわれに改めて、するどく問い掛けてくる、質問があります。
それは・・・・・
「われわれは何のために『仕事』をするのか?」
ということ。
さて、皆さんは何のために「仕事」をしていますか?
次回は、この問いかけを中心に、もっと「会社」と「個人」、そして「仕事」との関係をお話していきたい、と思います。
今日も長くなってしまいました。すみません。では、また今度。

次へ → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html