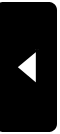「雑感」の記事一覧
スポンサーサイト
小沢さんの辞任は大変残念です
せっかく二大政党制が築かれて、日本の政治がようやくまともになってきたかなあと思われた矢先の辞任は大変惜しい。
また、前のように自民党の一党支配が続くようでは、日本の政治、そして国家の先行きはかなり暗いものと思われます。
年金・社会保険庁の問題、政治と金の問題、防衛省のスキャンダル、新テロ特措法案(給油新法)等々。従来の自民党一党支配の状況では表に出てこなかった問題ばかりです。今回出てきている問題はどれも長年の自民党一党支配の状況下に置かれた官僚・行政の緩みから出てきています。自民党と官僚の馴れ合い・もたれあいの構図が招いているといっても過言ではないでしょう。これが政権交代が常に起こりうる状況であれば、官僚は常に一定の緊張感におかれるでしょう。
この国の政治は絶対に二大政党制に、常に政権交代が起こりうる状況を作らないと、官僚のいいようにされてしまいます。政治と行政・官僚に一定の緊張感がなければ、人・組織は緩みます。
私は必ずしも民主党のみを応援しているわけではありません。自民党も民主党もどちらも国民・国家に対してよかれという方向に動いているものに対して応援します。
現時点では、実質的な二大政党制を築くことがこの国にとってもっとも急務のことであると思われますから民主党を応援しますが、本来どちらの党に対しても是々非々でいることが私のスタイルです。
しかし、今回の事態はがっかりと言うしかありません。民主党のイメージダウン、政権担当能力に疑問符がつくことは間違いないでしょう!
そのことがもたらすこと。それはこの国の歩みが10年、20年後退することにつながります。
そして、最終的にわれわれ国民がそのツケを払わされることになります。
私は、民主党にどんどん財政削減を大胆に切り込んでもらいたかった。
弊社は経営革新法の認定を受けておりますから、行政の補助金を得て監督官庁とお付き合いしながら事業を進めた経験もあり、現在はある省とお付き合いさせていただいておりますが、行政の仕事の進め方や様々なシステムには大変無駄があるように思っております。
まだまだ予算を削減することはできます。
行政の事業やワークフローの洗い出し、そして分析を行えば、またちょっと古い言葉ですが、ビジネスプロセスリエンジニアリング(BPR)を行えば、かなりの無駄や非効率が見えてきます。
そういった観点で、行政にメスを入れることができるのは自民党では難しいでしょう!
なぜなら、すでに行政・官僚とある運命共同体的な桎梏があり、お互いにとって得にならないことをすることができないからです。(そういった視点すらないと言えます。)
日産がカルロスゴーンによってV字回復を描けたのは、社内の人間と桎梏のない人間がトップに立ったからです。
日本の政治も一度本格的な政権交代をしなければならない時期に近づいているでしょう!それまでこの国をここまでに成長させた自民党と行政・官僚には評価を与えることはできますが、そのシステムではこれから先の激動の世界を乗り切ることは難しい。
また、アメリカに対しても自民党のままでは「扱いやすい国」と思われて、適当に言いようにあしらわれるのがおちです。今回のテロ特措法のアメリカの対応ぶりに明確に現れています。民主党が参議院で多数になった途端に、手のひらを返したように情報開示をするアメリカの対応に疑念が残ります。
これに対して日本の報道機関があまり問題にしないのも、政府のマスコミ操作の影を感じます。
まあ、ともかく世界を見渡してみても戦後一度も本格的な政権交代がない(細川・羽田政権がありますが、あれは暫定的といえるでしょう)先進国は日本くらいなものですよ。
そういう意味ではおかしな国です。われわれ国民は、少しグローバルな視点でこの国を見ていく必要があると思います。そのことがわれわれ自身の生活を向上させる大きな道筋であることを、そろそろ私たち一人ひとりが認識していく時期になってきていると思います。
この国はかなりおかしな状況にあるんですよ、という視点が大変重要です。
ではまた。

また、前のように自民党の一党支配が続くようでは、日本の政治、そして国家の先行きはかなり暗いものと思われます。
年金・社会保険庁の問題、政治と金の問題、防衛省のスキャンダル、新テロ特措法案(給油新法)等々。従来の自民党一党支配の状況では表に出てこなかった問題ばかりです。今回出てきている問題はどれも長年の自民党一党支配の状況下に置かれた官僚・行政の緩みから出てきています。自民党と官僚の馴れ合い・もたれあいの構図が招いているといっても過言ではないでしょう。これが政権交代が常に起こりうる状況であれば、官僚は常に一定の緊張感におかれるでしょう。
この国の政治は絶対に二大政党制に、常に政権交代が起こりうる状況を作らないと、官僚のいいようにされてしまいます。政治と行政・官僚に一定の緊張感がなければ、人・組織は緩みます。
私は必ずしも民主党のみを応援しているわけではありません。自民党も民主党もどちらも国民・国家に対してよかれという方向に動いているものに対して応援します。
現時点では、実質的な二大政党制を築くことがこの国にとってもっとも急務のことであると思われますから民主党を応援しますが、本来どちらの党に対しても是々非々でいることが私のスタイルです。
しかし、今回の事態はがっかりと言うしかありません。民主党のイメージダウン、政権担当能力に疑問符がつくことは間違いないでしょう!
そのことがもたらすこと。それはこの国の歩みが10年、20年後退することにつながります。
そして、最終的にわれわれ国民がそのツケを払わされることになります。
私は、民主党にどんどん財政削減を大胆に切り込んでもらいたかった。
弊社は経営革新法の認定を受けておりますから、行政の補助金を得て監督官庁とお付き合いしながら事業を進めた経験もあり、現在はある省とお付き合いさせていただいておりますが、行政の仕事の進め方や様々なシステムには大変無駄があるように思っております。
まだまだ予算を削減することはできます。
行政の事業やワークフローの洗い出し、そして分析を行えば、またちょっと古い言葉ですが、ビジネスプロセスリエンジニアリング(BPR)を行えば、かなりの無駄や非効率が見えてきます。
そういった観点で、行政にメスを入れることができるのは自民党では難しいでしょう!
なぜなら、すでに行政・官僚とある運命共同体的な桎梏があり、お互いにとって得にならないことをすることができないからです。(そういった視点すらないと言えます。)
日産がカルロスゴーンによってV字回復を描けたのは、社内の人間と桎梏のない人間がトップに立ったからです。
日本の政治も一度本格的な政権交代をしなければならない時期に近づいているでしょう!それまでこの国をここまでに成長させた自民党と行政・官僚には評価を与えることはできますが、そのシステムではこれから先の激動の世界を乗り切ることは難しい。
また、アメリカに対しても自民党のままでは「扱いやすい国」と思われて、適当に言いようにあしらわれるのがおちです。今回のテロ特措法のアメリカの対応ぶりに明確に現れています。民主党が参議院で多数になった途端に、手のひらを返したように情報開示をするアメリカの対応に疑念が残ります。
これに対して日本の報道機関があまり問題にしないのも、政府のマスコミ操作の影を感じます。
まあ、ともかく世界を見渡してみても戦後一度も本格的な政権交代がない(細川・羽田政権がありますが、あれは暫定的といえるでしょう)先進国は日本くらいなものですよ。
そういう意味ではおかしな国です。われわれ国民は、少しグローバルな視点でこの国を見ていく必要があると思います。そのことがわれわれ自身の生活を向上させる大きな道筋であることを、そろそろ私たち一人ひとりが認識していく時期になってきていると思います。
この国はかなりおかしな状況にあるんですよ、という視点が大変重要です。
ではまた。

ピロリ菌って大変なんですね
日曜日の日経新聞を見ていたら、なあんと現在の私の状況にもっと密接に関連する「ピロリ菌」について掲載されていました。
ピロリ菌って潰瘍だけでなく、胃ガンにも関連するんですね。
現在、50歳以上の日本人の6割以上がピロリ菌に感染していて、感染者は胃潰瘍だけでなく胃ガンにもなりやすいとする研究報告が相次いでいるようです。その結果、予防目的で除菌する人が増えているとのこと。すごいですねえ。
群馬県沼田市の飯田武一さん(67)は昨年末、近くの公民館でピロリ菌の感染有無を調べる尿検査を受けた。胃の調子は良好だったが、検査は陽性。病院で薬をもらい一週間飲んだところ除菌できた。「がんのリスクがひとつ減って安心しました」と喜ぶ。
沼田市の利根保険生活協同組合は、数年前からピロリ菌除菌の啓蒙活動に取り組んでいる。地域の集まり「班会」に利根中央病院の検査技師が出向き、ピロリ菌について説明し、その場で検査する。
ピロリ菌除菌が保険適用になるのは胃か十二指腸に潰瘍がある場合だけ。飯田さんのようなケースは自己負担になる。
費用は病院や検査の種類などで異なり、五千円から三万円程度だ。保険診療と一緒には実施できないため、利根中央病院では自費診療の窓口を設けている。担当の大野順弘医長は「ピロリ菌がいれば必ず胃炎は起きている。除菌で胃炎はよくなり胃ガンリスクも下がる」と話す。
一般的にピロリ菌除菌は胃酸を抑える薬と二種類の抗菌薬を一週間服用する。これで八割が除菌できるが、できなかったら薬を変えてもう一度除菌する。
服薬中は下痢や、味覚が変わるなどの副作用が起きることがある。(ちなみに私は現在服薬中ですが、あまり副作用はおきていません。)
ごくまれに薬剤過敏症で入院が必要になる人もいる。
また、除菌後は胃の粘膜が回復して胃酸が強くなるため、約一割の人に逆流性食道炎が起きる。(えーって感じです。これはお医者様に確認しておかないと・・・・。)
(中略)
ピロリ菌が胃ガンリスクを高めるという点では、専門家の意見は一致する。だが、いつ除菌すればどの程度胃ガンを防ぐことができるのかは、決着がついていない。症状や期待される効果、コストや副作用を考え、各自が判断するしかない。
ピロリ菌の検査は、人間ドックなどで受けることも可能。除菌は消化器の専門医に相談するとよい。社会保険滋賀病院(滋賀県大津市)の中島滋美検診部長が三月、専門医にアンケート調査したところ、胃ガン予防を含めて七割弱は保険外で除菌した経験があった。
「専門医の間では保険外の除菌が一般的になってきている」(中島部長)
ということです。こういう記事をみると心配になる方も多いと思います。気になる方は、お近くの消化器系の病院にお尋ねになられてはいかがでしょうか?
私も今薬を投用していますが、副作用等あまり先生から詳しく聞いてこなかったので、今度行った際にしっかりと聞いてこようと思います。
情報がなければないで困るし、あったらあったで困る、そんなケースですね。まったく・・・・・・゜゜・(×_×)・゜゜・。
では。
ピロリ菌って潰瘍だけでなく、胃ガンにも関連するんですね。
現在、50歳以上の日本人の6割以上がピロリ菌に感染していて、感染者は胃潰瘍だけでなく胃ガンにもなりやすいとする研究報告が相次いでいるようです。その結果、予防目的で除菌する人が増えているとのこと。すごいですねえ。
群馬県沼田市の飯田武一さん(67)は昨年末、近くの公民館でピロリ菌の感染有無を調べる尿検査を受けた。胃の調子は良好だったが、検査は陽性。病院で薬をもらい一週間飲んだところ除菌できた。「がんのリスクがひとつ減って安心しました」と喜ぶ。
沼田市の利根保険生活協同組合は、数年前からピロリ菌除菌の啓蒙活動に取り組んでいる。地域の集まり「班会」に利根中央病院の検査技師が出向き、ピロリ菌について説明し、その場で検査する。
ピロリ菌除菌が保険適用になるのは胃か十二指腸に潰瘍がある場合だけ。飯田さんのようなケースは自己負担になる。
費用は病院や検査の種類などで異なり、五千円から三万円程度だ。保険診療と一緒には実施できないため、利根中央病院では自費診療の窓口を設けている。担当の大野順弘医長は「ピロリ菌がいれば必ず胃炎は起きている。除菌で胃炎はよくなり胃ガンリスクも下がる」と話す。
一般的にピロリ菌除菌は胃酸を抑える薬と二種類の抗菌薬を一週間服用する。これで八割が除菌できるが、できなかったら薬を変えてもう一度除菌する。
服薬中は下痢や、味覚が変わるなどの副作用が起きることがある。(ちなみに私は現在服薬中ですが、あまり副作用はおきていません。)
ごくまれに薬剤過敏症で入院が必要になる人もいる。
また、除菌後は胃の粘膜が回復して胃酸が強くなるため、約一割の人に逆流性食道炎が起きる。(えーって感じです。これはお医者様に確認しておかないと・・・・。)
(中略)
ピロリ菌が胃ガンリスクを高めるという点では、専門家の意見は一致する。だが、いつ除菌すればどの程度胃ガンを防ぐことができるのかは、決着がついていない。症状や期待される効果、コストや副作用を考え、各自が判断するしかない。
ピロリ菌の検査は、人間ドックなどで受けることも可能。除菌は消化器の専門医に相談するとよい。社会保険滋賀病院(滋賀県大津市)の中島滋美検診部長が三月、専門医にアンケート調査したところ、胃ガン予防を含めて七割弱は保険外で除菌した経験があった。
「専門医の間では保険外の除菌が一般的になってきている」(中島部長)
ということです。こういう記事をみると心配になる方も多いと思います。気になる方は、お近くの消化器系の病院にお尋ねになられてはいかがでしょうか?
私も今薬を投用していますが、副作用等あまり先生から詳しく聞いてこなかったので、今度行った際にしっかりと聞いてこようと思います。
情報がなければないで困るし、あったらあったで困る、そんなケースですね。まったく・・・・・・゜゜・(×_×)・゜゜・。
では。
無意識の世界Ⅶ
第1回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
第5回 → http://katsu.i-ra.jp/e10851.html
第6回 → http://katsu.i-ra.jp/e11026.html
さあ、このシリーズ、今回が最終回であります。
前回、父との出会い、という不可思議な終わり方でありました。
そもそも私にとって父というのはどういう存在であるか。
多くの皆さんにとって父と出会うことは特別な出来事でもなんでもないはずですよね。
ところがこのシリーズの第4回を読んでいただいている方にはよくお分かりのように、私には父がいないのです。父は私が1歳の時に他界しているわけです。
したがって、この、皆さんにとってはなんでもない、父と出会うということが、私にとって、本当に本当に深い深いことだったのです。
そもそも私の実感からして、父の存在は、私の意識の中にはまったくありません。父の写真はありますが、その写真に何の愛着も感慨も湧きません。そして、これは母が本当に偉かったんだと、今になってつくづく思うことは、父がいなくて困ったという思い出が少しも私の中にありません。(だからこそ、逆に言えば、母から「生きるプライド」を得ているわけですが。)
確かに、伊勢湾台風以降、家の中に男は私一人ですから、よく小学生の頃は、身近に男の手本がいないことから、「こんな時に、またはあんな時に男はどういう風に思い、判断し、行動するのか」が気になって仕方がなかった思い出があります。近所の友達のお父さんをよく一生懸命見ていた頃もありました。
このことは結構、潜在意識に影響を及ぼしていますが、この「男の手本がない」ということと、「父がいなくて困った」ということは私の意識の中ではまったく結びついていません。
そもそも「父がいなくて困った」という意識そのものがまったくないのです。
即ち、私の意識の中に「父」はいないのです。
その父とはじめて出会っている-
戸惑いと共に、なぜだ、と頭の中で声がこだましています-
すると同時に、父の声が、
「かつひろ、お父さんはお前に謝るために、ここに来たんだよ。」
「お父さんは、ず~っとお前のそばにいたかった。そして、いろいろなことをお前に教えてやりたかったんだ。でも、こんなことがあって、それができなくなってしまって、ごめんよ。
でも、お父さんはお前のことをず~っと愛してるぞ。」
・・・・・・・・・・・・・・・。
嗚咽が聞こえました-
だれ?誰が泣いている?
気がつくと、私はぼろぼろ涙を流していました。
そして、
「お父さん、ありがとう、ありがとう」 と何度も何度も叫んでいました。
この体験があってから、私の気持ちは、すう~っと無音の静寂に置かれ、心が真の安らぎを求めてきて、ようやくそれが得られた思いがしました。
何か、ず~っと溜まっていた、心の中の澱が取り除かれて、軽くなって、そしてすごく気持ちがよかった。午後のまどろみの中の安寧と、胸一杯の幸福感で満たされていました。
現在は、この時の思いが常に心の中にあるわけではありませんが、何かあの時、私の人生の大きなメルクマールがあり、あの時点から私の人生の羅針盤が少しずつ角度を変えてきている気がしています。
また、なぜ私がクリエイティブなもの、創造的なものを求めているか、がよーくわかりました。
先ほどの「男の手本がない」ということ。
このことで、私は自分の所作や考え方、もっといえば男としての生き方を自分で創り上げてきました。
私は生をうけて生きてくる過程で、いろいろなもの・ことを自ら創り上げてきた人生だったのです。
そして今、私がはっきり言えるのは、
私の意思決定の背後に、母と、そして父の存在があるということ。
ようやく、私の心の中に、母と父の並んだ写真が自然な形で収まりました。
皆さん、どうですか。
皆さんの潜在意識の中にもきっと素晴らしい宝物が隠されているはずですよ。
ぜひ、その宝探しをはじめられてみては。
皆さんの探し求めていた幸せが、きっとそこにはあるはずです。
さあ、私の潜在意識の旅は、これでひとまず終わりとします。
潜在意識の旅に果てはありませんから、まだ、この続きはあるのですが、どこかでお話するかもしれませんし、しないかもしれません。か・ぜ・ま・か・せ。
興が乗ったらお話することにしましょう。ではまた、潜在意識の深海探検に。アディオス、アミーゴ。

第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
第5回 → http://katsu.i-ra.jp/e10851.html
第6回 → http://katsu.i-ra.jp/e11026.html
さあ、このシリーズ、今回が最終回であります。
前回、父との出会い、という不可思議な終わり方でありました。
そもそも私にとって父というのはどういう存在であるか。
多くの皆さんにとって父と出会うことは特別な出来事でもなんでもないはずですよね。
ところがこのシリーズの第4回を読んでいただいている方にはよくお分かりのように、私には父がいないのです。父は私が1歳の時に他界しているわけです。
したがって、この、皆さんにとってはなんでもない、父と出会うということが、私にとって、本当に本当に深い深いことだったのです。
そもそも私の実感からして、父の存在は、私の意識の中にはまったくありません。父の写真はありますが、その写真に何の愛着も感慨も湧きません。そして、これは母が本当に偉かったんだと、今になってつくづく思うことは、父がいなくて困ったという思い出が少しも私の中にありません。(だからこそ、逆に言えば、母から「生きるプライド」を得ているわけですが。)
確かに、伊勢湾台風以降、家の中に男は私一人ですから、よく小学生の頃は、身近に男の手本がいないことから、「こんな時に、またはあんな時に男はどういう風に思い、判断し、行動するのか」が気になって仕方がなかった思い出があります。近所の友達のお父さんをよく一生懸命見ていた頃もありました。
このことは結構、潜在意識に影響を及ぼしていますが、この「男の手本がない」ということと、「父がいなくて困った」ということは私の意識の中ではまったく結びついていません。
そもそも「父がいなくて困った」という意識そのものがまったくないのです。
即ち、私の意識の中に「父」はいないのです。
その父とはじめて出会っている-
戸惑いと共に、なぜだ、と頭の中で声がこだましています-
すると同時に、父の声が、
「かつひろ、お父さんはお前に謝るために、ここに来たんだよ。」
「お父さんは、ず~っとお前のそばにいたかった。そして、いろいろなことをお前に教えてやりたかったんだ。でも、こんなことがあって、それができなくなってしまって、ごめんよ。
でも、お父さんはお前のことをず~っと愛してるぞ。」
・・・・・・・・・・・・・・・。
嗚咽が聞こえました-
だれ?誰が泣いている?
気がつくと、私はぼろぼろ涙を流していました。
そして、
「お父さん、ありがとう、ありがとう」 と何度も何度も叫んでいました。
この体験があってから、私の気持ちは、すう~っと無音の静寂に置かれ、心が真の安らぎを求めてきて、ようやくそれが得られた思いがしました。
何か、ず~っと溜まっていた、心の中の澱が取り除かれて、軽くなって、そしてすごく気持ちがよかった。午後のまどろみの中の安寧と、胸一杯の幸福感で満たされていました。
現在は、この時の思いが常に心の中にあるわけではありませんが、何かあの時、私の人生の大きなメルクマールがあり、あの時点から私の人生の羅針盤が少しずつ角度を変えてきている気がしています。
また、なぜ私がクリエイティブなもの、創造的なものを求めているか、がよーくわかりました。
先ほどの「男の手本がない」ということ。
このことで、私は自分の所作や考え方、もっといえば男としての生き方を自分で創り上げてきました。
私は生をうけて生きてくる過程で、いろいろなもの・ことを自ら創り上げてきた人生だったのです。
そして今、私がはっきり言えるのは、
私の意思決定の背後に、母と、そして父の存在があるということ。
ようやく、私の心の中に、母と父の並んだ写真が自然な形で収まりました。
皆さん、どうですか。
皆さんの潜在意識の中にもきっと素晴らしい宝物が隠されているはずですよ。
ぜひ、その宝探しをはじめられてみては。
皆さんの探し求めていた幸せが、きっとそこにはあるはずです。
さあ、私の潜在意識の旅は、これでひとまず終わりとします。
潜在意識の旅に果てはありませんから、まだ、この続きはあるのですが、どこかでお話するかもしれませんし、しないかもしれません。か・ぜ・ま・か・せ。
興が乗ったらお話することにしましょう。ではまた、潜在意識の深海探検に。アディオス、アミーゴ。

無意識の世界Ⅵ
第1回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
第5回 → http://katsu.i-ra.jp/e10851.html
なんか台風が近づいているということで、どんな小さな台風でもいやですね~~~~~(ノ≧ρ≦)ノいやじゃぁぁぁぁって感じですね(ちょっと大げさ?)
このシリーズの第4回を読まれた方は、私のこの気持ちがご理解いただけると思います。
さて、前回までに、人の人生に大きく影響を及ぼしているのが潜在意識であり、私はある体験を通して、この潜在意識をインスパイアされて、母との関係がより明確になったというお話をしました。
また、人が行動を含めた意思決定の変革を行うには、潜在意識にメスを入れた「深い気づき」が必要である、という体験談もご提供しました。
前回、私が深く気づいたものは、母が私に深く影響を与え、いつしか私の意思決定・行動のベースになっていた、「生きるプライド」であり、そこからくる「他者への感謝そして大きな愛情」でありました。このことが私そのものであり、生き方となっていたわけです。
そして、これで何の過不足もないと思っていたわけです。もちろん、この事実に気づいたことは私の大きな財産になり、今後の意思決定や問題対処行動等のベースを作ってくれましたので、自己変革の旅はここで終わってもよかったのです。が、しかし・・・・。
なぜかもう少し自分の潜在意識を探ってみたくなりました、というか探らなくてはだめなんじゃないか、という気持ちが起きてきました。
それですぐさま次なる研修を受けてみたわけです。
そして、その研修で気づいたことは・・・・・・・・・・・・・・・。
私が生まれてからこの方、一度も意識すらしたことがなかったもの、いやことだったのです。
いったいどういうことだったのか?
そのお話をする前に、まず研修の現場シーンに移りましょう!
(カメラOK? ハーイ、カチッ(ガチンコのつもり(^^)))
その男は、突然、私の目の前に、生身の姿で現れました。
最初は、それが誰か分かりませんでした。
その男は私に向かって、一生懸命に涙ながらに叫んでいました。
「かつひろ(私の名前です)、私はお前に会いたかったんだよ。」
「お前を一人ぼっちにさせて、悪かったなあ。」
「お前のことを誰よりも気にしていたんだよ。」
いったい、この男は誰なんだ?
心なしか私に姿が似ていますが、私は今までその男に一度も会ったことがありませんでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
その男は、父でした。
はじめて私は父と顔を合わせました。
(このシリーズはここまで書くだけでかなり疲れます。このつづきは次回とさせていただきます。では。)
→ http://katsu.i-ra.jp/e11049.html

第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
第5回 → http://katsu.i-ra.jp/e10851.html
なんか台風が近づいているということで、どんな小さな台風でもいやですね~~~~~(ノ≧ρ≦)ノいやじゃぁぁぁぁって感じですね(ちょっと大げさ?)
このシリーズの第4回を読まれた方は、私のこの気持ちがご理解いただけると思います。
さて、前回までに、人の人生に大きく影響を及ぼしているのが潜在意識であり、私はある体験を通して、この潜在意識をインスパイアされて、母との関係がより明確になったというお話をしました。
また、人が行動を含めた意思決定の変革を行うには、潜在意識にメスを入れた「深い気づき」が必要である、という体験談もご提供しました。
前回、私が深く気づいたものは、母が私に深く影響を与え、いつしか私の意思決定・行動のベースになっていた、「生きるプライド」であり、そこからくる「他者への感謝そして大きな愛情」でありました。このことが私そのものであり、生き方となっていたわけです。
そして、これで何の過不足もないと思っていたわけです。もちろん、この事実に気づいたことは私の大きな財産になり、今後の意思決定や問題対処行動等のベースを作ってくれましたので、自己変革の旅はここで終わってもよかったのです。が、しかし・・・・。
なぜかもう少し自分の潜在意識を探ってみたくなりました、というか探らなくてはだめなんじゃないか、という気持ちが起きてきました。
それですぐさま次なる研修を受けてみたわけです。
そして、その研修で気づいたことは・・・・・・・・・・・・・・・。
私が生まれてからこの方、一度も意識すらしたことがなかったもの、いやことだったのです。
いったいどういうことだったのか?
そのお話をする前に、まず研修の現場シーンに移りましょう!
(カメラOK? ハーイ、カチッ(ガチンコのつもり(^^)))
その男は、突然、私の目の前に、生身の姿で現れました。
最初は、それが誰か分かりませんでした。
その男は私に向かって、一生懸命に涙ながらに叫んでいました。
「かつひろ(私の名前です)、私はお前に会いたかったんだよ。」
「お前を一人ぼっちにさせて、悪かったなあ。」
「お前のことを誰よりも気にしていたんだよ。」
いったい、この男は誰なんだ?
心なしか私に姿が似ていますが、私は今までその男に一度も会ったことがありませんでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
その男は、父でした。
はじめて私は父と顔を合わせました。
(このシリーズはここまで書くだけでかなり疲れます。このつづきは次回とさせていただきます。では。)
→ http://katsu.i-ra.jp/e11049.html

F1エンジン開発、10年間の完全凍結へ
さっき、YAHOOみてびっくりしました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000001-rcg-moto
えーーーーー、これってどうなのーーーー??????
ちょっとまってよ。これじゃあ、ぜんぜん面白くないじゃん。
なんだよーーー。どんだけーーーーー。
FIAもばかなことしてくれるぜい。これじゃあ、ホンダもトヨタもフェラーリも、参戦している意味ないじゃん。
やめるところ出てくるんじゃないの。それともメーカーサイドに何か他の面白みがあるのだろうか・・・・もちろんエンジンだけじゃないから、シャシーやタイヤや諸々。でもエンジンが一番開発者としては面白いところだろうし。エンジニアとしてはモチベーション下がるんじゃないの。
これはファンとしても困ったなあ。どうなの。このレギュレーションは???
えーーーーー、これってどうなのーーーー??????
ちょっとまってよ。これじゃあ、ぜんぜん面白くないじゃん。
なんだよーーー。どんだけーーーーー。
FIAもばかなことしてくれるぜい。これじゃあ、ホンダもトヨタもフェラーリも、参戦している意味ないじゃん。
やめるところ出てくるんじゃないの。それともメーカーサイドに何か他の面白みがあるのだろうか・・・・もちろんエンジンだけじゃないから、シャシーやタイヤや諸々。でもエンジンが一番開発者としては面白いところだろうし。エンジニアとしてはモチベーション下がるんじゃないの。
これはファンとしても困ったなあ。どうなの。このレギュレーションは???
無意識の世界Ⅴ
第1回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
さて前回、私の母のイメージを次のように伝えました。
「強い母」=「尊敬の対象」≒「少し距離のある対象」。
しかし、長らくこのイメージは私の顕在意識から消えていました。日常の生活に追われていく中で、また実家の四日市に住む母と離れて生活していることから、母のイメージは私の日常には存在しませんでした。
また、前回お話したように、母の生活は波乱万丈であったと思われますが、「強い母」の防波堤により世間の荒波が我が家ではさざなみとなっていたことから(当然、そういったことにその時点でまったく気づいていないことから)、私の人生と母の人生がオーバーラップすることはまったくなかったのです。
私は「自分の人生」を一生懸命に生きていると思っていました。自分で考え判断し、自分で行動し反省してまた動く。このことに何の不思議も感じませんでした。自分は自分の足で立っているのですから当然のこと。そのことに何ら疑念も生じなかったのです。
とくにその時点まで、人生において大きくつまづくといったことがなかったことから、私は自分が行っている「結果」に大きな疑念を抱くことはなかったのです。「原因」を遡及する必要性がなかった。
しかし、その時点で私は大きくつまづいていました。何かがおかしい。どうしていくべきか。何かを変えなければ。このままではとりかえしのつかないことになる。どうしたらいいのか。
私は知らず知らず、またその時点では意識すら感じず、どうやら大きな「迷い」の渦中に入っていったのです。
そんな中、前にお話しましたように、私は友人に誘われるまま、ある研修に参加することになったわけです。
人生とか運命というのは、あるとき面白い操作をするようです。私の友人は当然、その時点で私の深い悩みを知っていたわけでもなく、もちろん私自身もそんなに深い悩みとその時点では気づいていません。ところがそういう時点で、その研修に、まるで参加すべくして参加していくわけですから、人生には無駄はまったくないですね。人間は自分が思っている以上に必要としているものに必ず出会っていくものだと、現在の私は確信しています。その時点での私には気づくすべもありませんでしたが。
さて、その研修の中で、私が行っていること、考えて決断していることはどこかおかしいんだと気づき始めます。そして、そのおかしい部分は、どうも私の性格に起因しているようだ・・・・私の性格とは・・・・・私の性格(人格)の90%近くがどうも無意識(潜在意識)で形成されているようだぞ・・・・じゃあ、この潜在意識ってなにものだ?
そして、母が現れました。目の前の母は幼いころの私と妹を抱いて泣いていました。母のつらく苦しい姿が浮かび上がってきました。それでも母は私と妹をすやすや寝かせて荒波に立ち向かっていました。
「お母さん、ありがとう。僕はお母さんのおかげでここまで来たんだ。」という言葉を私は夢中になって叫んでいたように思います。
そして・・・・・・・・。しっかりと認識しました。
私が現在、生きていく上での、大きなプライドの源泉は、間違いなくこの「強い母」にある。
あの「強い母」によって、今日まで生かされた。
このことが、私の大きな「プライド(誇り)」となっている。
ここで、母の人生と私の人生がオーバーラップしました。連続とか継続という言葉で置き換えてもよいかもしれません。
そして、そのことが同時に、母への「感謝」から他者への「感謝」へ。
「生かされていることの感謝の源泉」につながっていきます。
私が生きていく上での支柱に近いもの、「プライド」が母から与えられた大変重要な財産であったということは、私の思考・行動・感性の原点をつかんだことであり、ここで私は先の「結果」に対する「原因」を得ました。これは当然、「正」の遺産だけでなく、「負」の遺産も受け継いでいます。したがって、自分の思考・行動・感性を分析し変革するきっかけを得ることになるわけです。
ここまで書いてくると、なんだか大層なことを経験したように書いてあるが、結局当たり前のことを書いているだけではないの、と思われる方々もいらっしゃるでしょう。
そうですね。文章で書くと何も意外性がある内容でも、不可思議な現象を描写しているわけでも、難解な世界を紐解いているわけでもありません。ごくごく普通のことを、私が体験したままに書いています。
しかし、この何気なく書いた「体験」が大きなポイントだとご理解ください。
そうです。ここでは「理解」ではありません。あくまでも「体験」なんです。
実際に母は、そのとき私の目の前に現れ、私と妹の二人の幼子を抱えて荒波に立ち向かっていたのです。
これらのことは「生身の実体験」として知覚されます。そして、実はこのことが大変重要なことで、「生身の実体験」ですから、潜在意識に深く認識され、意思決定や行動を変革しようとするエネルギーにつながっていきます。
本や人から聞いた話では、この「変革するエネルギー」につながりません。
ここが、本や人から聞いた話と潜在意識に深くメスを入れた場合との大きな差となります。
残念ながら、どんなにいい本を読み、人からどんなにいい話を聞いても、結局、その人の意思決定や行動を変えていくのは、なかなか容易なことではありません。もちろん、それができる人も、少数ですが、いらっしゃいます。そういう方は、本や話だけで、ご自分の潜在意識までメスを入れた「深い気づき」が得られる方です。
しかし、なかなか普通の方では、そこまではほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。ただ、本を読むことやいい話を聞くことは大切です。「深い気づき」まではいかないにしても、知識や情報を得なければ、「深い気づき」にたどり着くことは不可能ですから。
われわれ、(といって皆さんを私と同レベルというには大変恐縮ですが、ほんの少数の天才を除けば、われわれはほぼ同レベルである、という意味合いでご理解ください。)多くの凡人は、何か「深い気づき」が得られる、特殊なシチュエーション(状況)設定が必要です。
そういう意味では、心理学をベースにしたプロの手による状況設定(場)が必要です。
とにかく、研修を終わってみれば、大変面白いものであり、私の意識の中では「このままではいけない。何か行動を起こさなくては」、と強くインスパイアされていました。
そして、この研修から私の変革の旅は始まったのです。
この研修によって「母」の存在を強く意識し、潜在意識を深くインスパイアされ、すごい研修だなあ、と思ったのですが、実はそれが全然大したものではない、単なる始まりに過ぎなかったのだ、と気づくのに大して時間はかかりませんでした。
実は、このあとにもっと「深い気づき」につながる「体験」をすることになるのです。
次からは、その「体験」についてお話をしていきます。よろしかったらお付き合いください。
ちょっと長文になってしまってすみません。
ではまた次回に。謝謝。
あ、そうそう、ちょっと蛇足で。
やっぱり母への感謝の気持ちを。日頃、恥ずかしくてあまり口に出して言えませんので、このブログに残しておきましょう 。
。
「お母さん、あなたは本当に強かった。すばらしい母親でした。そして、私はあなたの子供でいられて本当に幸せです。
心から心から、 ありがとう。」
ではでは。 → http://katsu.i-ra.jp/e11026.html

第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
第4回 → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
さて前回、私の母のイメージを次のように伝えました。
「強い母」=「尊敬の対象」≒「少し距離のある対象」。
しかし、長らくこのイメージは私の顕在意識から消えていました。日常の生活に追われていく中で、また実家の四日市に住む母と離れて生活していることから、母のイメージは私の日常には存在しませんでした。
また、前回お話したように、母の生活は波乱万丈であったと思われますが、「強い母」の防波堤により世間の荒波が我が家ではさざなみとなっていたことから(当然、そういったことにその時点でまったく気づいていないことから)、私の人生と母の人生がオーバーラップすることはまったくなかったのです。
私は「自分の人生」を一生懸命に生きていると思っていました。自分で考え判断し、自分で行動し反省してまた動く。このことに何の不思議も感じませんでした。自分は自分の足で立っているのですから当然のこと。そのことに何ら疑念も生じなかったのです。
とくにその時点まで、人生において大きくつまづくといったことがなかったことから、私は自分が行っている「結果」に大きな疑念を抱くことはなかったのです。「原因」を遡及する必要性がなかった。
しかし、その時点で私は大きくつまづいていました。何かがおかしい。どうしていくべきか。何かを変えなければ。このままではとりかえしのつかないことになる。どうしたらいいのか。
私は知らず知らず、またその時点では意識すら感じず、どうやら大きな「迷い」の渦中に入っていったのです。
そんな中、前にお話しましたように、私は友人に誘われるまま、ある研修に参加することになったわけです。
人生とか運命というのは、あるとき面白い操作をするようです。私の友人は当然、その時点で私の深い悩みを知っていたわけでもなく、もちろん私自身もそんなに深い悩みとその時点では気づいていません。ところがそういう時点で、その研修に、まるで参加すべくして参加していくわけですから、人生には無駄はまったくないですね。人間は自分が思っている以上に必要としているものに必ず出会っていくものだと、現在の私は確信しています。その時点での私には気づくすべもありませんでしたが。
さて、その研修の中で、私が行っていること、考えて決断していることはどこかおかしいんだと気づき始めます。そして、そのおかしい部分は、どうも私の性格に起因しているようだ・・・・私の性格とは・・・・・私の性格(人格)の90%近くがどうも無意識(潜在意識)で形成されているようだぞ・・・・じゃあ、この潜在意識ってなにものだ?
そして、母が現れました。目の前の母は幼いころの私と妹を抱いて泣いていました。母のつらく苦しい姿が浮かび上がってきました。それでも母は私と妹をすやすや寝かせて荒波に立ち向かっていました。
「お母さん、ありがとう。僕はお母さんのおかげでここまで来たんだ。」という言葉を私は夢中になって叫んでいたように思います。
そして・・・・・・・・。しっかりと認識しました。
私が現在、生きていく上での、大きなプライドの源泉は、間違いなくこの「強い母」にある。
あの「強い母」によって、今日まで生かされた。
このことが、私の大きな「プライド(誇り)」となっている。
ここで、母の人生と私の人生がオーバーラップしました。連続とか継続という言葉で置き換えてもよいかもしれません。
そして、そのことが同時に、母への「感謝」から他者への「感謝」へ。
「生かされていることの感謝の源泉」につながっていきます。
私が生きていく上での支柱に近いもの、「プライド」が母から与えられた大変重要な財産であったということは、私の思考・行動・感性の原点をつかんだことであり、ここで私は先の「結果」に対する「原因」を得ました。これは当然、「正」の遺産だけでなく、「負」の遺産も受け継いでいます。したがって、自分の思考・行動・感性を分析し変革するきっかけを得ることになるわけです。
ここまで書いてくると、なんだか大層なことを経験したように書いてあるが、結局当たり前のことを書いているだけではないの、と思われる方々もいらっしゃるでしょう。
そうですね。文章で書くと何も意外性がある内容でも、不可思議な現象を描写しているわけでも、難解な世界を紐解いているわけでもありません。ごくごく普通のことを、私が体験したままに書いています。
しかし、この何気なく書いた「体験」が大きなポイントだとご理解ください。
そうです。ここでは「理解」ではありません。あくまでも「体験」なんです。
実際に母は、そのとき私の目の前に現れ、私と妹の二人の幼子を抱えて荒波に立ち向かっていたのです。
これらのことは「生身の実体験」として知覚されます。そして、実はこのことが大変重要なことで、「生身の実体験」ですから、潜在意識に深く認識され、意思決定や行動を変革しようとするエネルギーにつながっていきます。
本や人から聞いた話では、この「変革するエネルギー」につながりません。
ここが、本や人から聞いた話と潜在意識に深くメスを入れた場合との大きな差となります。
残念ながら、どんなにいい本を読み、人からどんなにいい話を聞いても、結局、その人の意思決定や行動を変えていくのは、なかなか容易なことではありません。もちろん、それができる人も、少数ですが、いらっしゃいます。そういう方は、本や話だけで、ご自分の潜在意識までメスを入れた「深い気づき」が得られる方です。
しかし、なかなか普通の方では、そこまではほぼ不可能と考えた方がよいでしょう。ただ、本を読むことやいい話を聞くことは大切です。「深い気づき」まではいかないにしても、知識や情報を得なければ、「深い気づき」にたどり着くことは不可能ですから。
われわれ、(といって皆さんを私と同レベルというには大変恐縮ですが、ほんの少数の天才を除けば、われわれはほぼ同レベルである、という意味合いでご理解ください。)多くの凡人は、何か「深い気づき」が得られる、特殊なシチュエーション(状況)設定が必要です。
そういう意味では、心理学をベースにしたプロの手による状況設定(場)が必要です。
とにかく、研修を終わってみれば、大変面白いものであり、私の意識の中では「このままではいけない。何か行動を起こさなくては」、と強くインスパイアされていました。
そして、この研修から私の変革の旅は始まったのです。
この研修によって「母」の存在を強く意識し、潜在意識を深くインスパイアされ、すごい研修だなあ、と思ったのですが、実はそれが全然大したものではない、単なる始まりに過ぎなかったのだ、と気づくのに大して時間はかかりませんでした。
実は、このあとにもっと「深い気づき」につながる「体験」をすることになるのです。
次からは、その「体験」についてお話をしていきます。よろしかったらお付き合いください。
ちょっと長文になってしまってすみません。
ではまた次回に。謝謝。
あ、そうそう、ちょっと蛇足で。
やっぱり母への感謝の気持ちを。日頃、恥ずかしくてあまり口に出して言えませんので、このブログに残しておきましょう
 。
。「お母さん、あなたは本当に強かった。すばらしい母親でした。そして、私はあなたの子供でいられて本当に幸せです。
心から心から、 ありがとう。」
ではでは。 → http://katsu.i-ra.jp/e11026.html

F1 ハミルトン負けたんだね
そうだ!京都へ行こう・・・・・行きたいなあ
なんだか、JRのかばん持ちのようなキャッチですみません (;^^)\( ̄ ̄)/ヾ(TT;)
こんな晴天の秋空には、やはり京都へ行きたくなりますねえ。
私は結構放浪癖があり、昔(というかちょい昔σ(^_^;)アセアセ...)、学生のころ(高校生のころ)、よく一人で京都へ泊まりで行っていました。
三重の四日市の生まれですから、関西本線の急行「平安」で一本。すぐに京都に着いてしまいます。
運賃も安いし。
金閣寺、銀閣寺、平安神宮はもちろん、よーく哲学の道を一人で歩いていました。
南禅寺の湯豆腐も結構食べたなあ・・・。
清水寺もよく行きましたが、京都はどこに行っても多くの観光客がいるので、私がよく一人になりたいなあと思って行ったのは、清水寺の奥の清閑寺。
あまり人がいないので、のんびり一人で佇んでいました。
嵐山・渡月橋から保津峡下り。紅葉のころはよく回りました。
そして、私が京都でもっとも好きなところは、大原の三千院と寂光院。冬の三千院はすばらしかった。
ずいぶん昔は観覧時間もルーズに管理(?)されていたのか、私は観光客が押し寄せる前に入らせてもらって縁台に一人で。
庭園と往生極楽院の美しい姿を見て、素敵な時間・空間を満喫していました。
そのころは貧乏旅行で、あまり素敵な旅館とか贅沢なこともできませんでしたが時間は贅沢に使っていた気がします。(今も決して裕福ではありませんがσ(^_^;)
さて、これから京都をまわるならこんな食べ歩きはできないかなあ、と思っています。
朝は龍安寺の西源院で湯豆腐を。
昼は吉田山荘の葉皿料理。夜は祇園丸山から鴨川沿いのザ・リバー・オリエンタル。
そして泊まりは俵屋旅館。
どこかのガイドに出てきそうなコースですが、いずれはこんな風に京都の一夜を過ごせたらなあ、と思っているんですが・・・・・。当分無理ですね・゜゜・(×_×)・゜゜・。

こんな晴天の秋空には、やはり京都へ行きたくなりますねえ。
私は結構放浪癖があり、昔(というかちょい昔σ(^_^;)アセアセ...)、学生のころ(高校生のころ)、よく一人で京都へ泊まりで行っていました。
三重の四日市の生まれですから、関西本線の急行「平安」で一本。すぐに京都に着いてしまいます。
運賃も安いし。
金閣寺、銀閣寺、平安神宮はもちろん、よーく哲学の道を一人で歩いていました。
南禅寺の湯豆腐も結構食べたなあ・・・。
清水寺もよく行きましたが、京都はどこに行っても多くの観光客がいるので、私がよく一人になりたいなあと思って行ったのは、清水寺の奥の清閑寺。
あまり人がいないので、のんびり一人で佇んでいました。
嵐山・渡月橋から保津峡下り。紅葉のころはよく回りました。
そして、私が京都でもっとも好きなところは、大原の三千院と寂光院。冬の三千院はすばらしかった。
ずいぶん昔は観覧時間もルーズに管理(?)されていたのか、私は観光客が押し寄せる前に入らせてもらって縁台に一人で。
庭園と往生極楽院の美しい姿を見て、素敵な時間・空間を満喫していました。
そのころは貧乏旅行で、あまり素敵な旅館とか贅沢なこともできませんでしたが時間は贅沢に使っていた気がします。(今も決して裕福ではありませんがσ(^_^;)
さて、これから京都をまわるならこんな食べ歩きはできないかなあ、と思っています。
朝は龍安寺の西源院で湯豆腐を。
昼は吉田山荘の葉皿料理。夜は祇園丸山から鴨川沿いのザ・リバー・オリエンタル。
そして泊まりは俵屋旅館。
どこかのガイドに出てきそうなコースですが、いずれはこんな風に京都の一夜を過ごせたらなあ、と思っているんですが・・・・・。当分無理ですね・゜゜・(×_×)・゜゜・。

無意識の世界Ⅳ
第1回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
さて前回は、「私」のベースが「母親」にあって、そこから「深い気づき」が得られたお話をしました。
何人かの方からお問い合わせがあり、結構私のブログを読んでくださっている方がたくさんいらっしゃるんだなあと、あらためて思いました。今一度、「母への思い」を再確認された方もいらっしゃたかもしれません。結局のところ、自らの行動や思いの源泉が「母」にあり(実はそれだけではありませんが、そのお話はもっと先に延ばします)、われわれの行動を変革しようとすれば、「母」の存在を抜きには語れないという、ごくごく当然のお話をしたにすぎないわけですが、このお話が「無意識の世界」を開く扉になることを今一度確認していただければ、と思います。
これから「私の気づき」のお話をしてまいりますが、その前に、私はじめ私の家族が置かれた環境についてお話していく必要があります。ちょっとテーマから離れますが、このお話をしておかないと、「私の気づき」のお話が理解していただけないと思いますので、しばらくお付き合いください。
さて、皆さん、人には自分自身の力ではどうしようもならないことが起こるものですね。
昭和34年9月26日--。
我が家にも起こりました、そのどうしようもならないことが・・・・・。
920ミリバール、今で言うと920hPa。超大型の台風、のちに伊勢湾台風と命名された、その超自然現象は、その日の夜に紀伊半島に上陸し、翌日日本海へ。死者・行方不明者は5,098人、負傷者39,000人。
その死者の中の4人はわが家族でした。私の父、祖父、叔父、そして姉でした。7人+0.5人(母のお腹に妹がいました)の家族が、翌日は3人+0.5人となっていました。母、祖母、妹、そして私です。
その時点で、母28歳、祖母56歳、妹0歳、私は1歳でした。
われわれ家族の運命は、この日を境に一変しました。とくに28歳の母の人生は・・・・・。
28歳の母がその後、どのような思いで現在までの人生の糸を紡いできたのか、その真の気持ちは私には想像すらできませんが、きっとかなり厳しい気持ちの中でいたのだと思います。
私がその立場でいたら、きっととうの昔に人生を終えていたかもしれません。
私には、不思議なのですが、母は私にその時の気持ちをほとんど語ったことがありません。
私には、「強い母」のイメージしか残っていません。
もっと正確に言いましょう!
「強い母」=「尊敬の対象」≒「少し距離のある対象」。
といったところが、私の母に対する心象風景でした。
さあ、以上のお話を前提として、テーマに戻りましょう!
と、思いましたが、すでに結構長くなってしまいましたので、続きは次回にしたいと思います。
(え、これからなのに・・・・なあんて思ってくれる人はいませんね )
)
では次回に、チャオ
→ http://katsu.i-ra.jp/e10851.html

第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
第3回 → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
さて前回は、「私」のベースが「母親」にあって、そこから「深い気づき」が得られたお話をしました。
何人かの方からお問い合わせがあり、結構私のブログを読んでくださっている方がたくさんいらっしゃるんだなあと、あらためて思いました。今一度、「母への思い」を再確認された方もいらっしゃたかもしれません。結局のところ、自らの行動や思いの源泉が「母」にあり(実はそれだけではありませんが、そのお話はもっと先に延ばします)、われわれの行動を変革しようとすれば、「母」の存在を抜きには語れないという、ごくごく当然のお話をしたにすぎないわけですが、このお話が「無意識の世界」を開く扉になることを今一度確認していただければ、と思います。
これから「私の気づき」のお話をしてまいりますが、その前に、私はじめ私の家族が置かれた環境についてお話していく必要があります。ちょっとテーマから離れますが、このお話をしておかないと、「私の気づき」のお話が理解していただけないと思いますので、しばらくお付き合いください。
さて、皆さん、人には自分自身の力ではどうしようもならないことが起こるものですね。
昭和34年9月26日--。
我が家にも起こりました、そのどうしようもならないことが・・・・・。
920ミリバール、今で言うと920hPa。超大型の台風、のちに伊勢湾台風と命名された、その超自然現象は、その日の夜に紀伊半島に上陸し、翌日日本海へ。死者・行方不明者は5,098人、負傷者39,000人。
その死者の中の4人はわが家族でした。私の父、祖父、叔父、そして姉でした。7人+0.5人(母のお腹に妹がいました)の家族が、翌日は3人+0.5人となっていました。母、祖母、妹、そして私です。
その時点で、母28歳、祖母56歳、妹0歳、私は1歳でした。
われわれ家族の運命は、この日を境に一変しました。とくに28歳の母の人生は・・・・・。
28歳の母がその後、どのような思いで現在までの人生の糸を紡いできたのか、その真の気持ちは私には想像すらできませんが、きっとかなり厳しい気持ちの中でいたのだと思います。
私がその立場でいたら、きっととうの昔に人生を終えていたかもしれません。
私には、不思議なのですが、母は私にその時の気持ちをほとんど語ったことがありません。
私には、「強い母」のイメージしか残っていません。
もっと正確に言いましょう!
「強い母」=「尊敬の対象」≒「少し距離のある対象」。
といったところが、私の母に対する心象風景でした。
さあ、以上のお話を前提として、テーマに戻りましょう!
と、思いましたが、すでに結構長くなってしまいましたので、続きは次回にしたいと思います。
(え、これからなのに・・・・なあんて思ってくれる人はいませんね
 )
)では次回に、チャオ

→ http://katsu.i-ra.jp/e10851.html

無意識の世界Ⅲ
第1回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
前回、人間の意識には潜在意識と顕在意識があり、その人の将来は潜在意識に大きく影響を受ける、という話をしました。
従って、潜在意識を顕在化する作業が大変重要なわけです。
では、この潜在意識を顕在化する作業とはどんな作業か?
ちょっとここでは私のお話がずれてしまうので触れませんが、がんばれば誰にでもできる簡単なものかというと、とてもそんなものではありません。
非常に高度な知識と経験と技術をもった人間によるサポートが必要です。
従って、残念ながらご自身の力でできる方は、ほとんどいないのではないでしょうか。プロの手が必要です。
私は、ある企業の研修を受講して、この作業が可能になりました。私もプロの手を借りたわけです。
私は、その研修を通して「深い気づき」を得ました。
潜在意識を顕在化する作業というのは、結局、この「深い気づき」を得る作業ととらえてよいと思われます。
今から数年前、私は経営上、かなり深い悩みを抱えていました。
そんな折、私の友人から誘われて、この研修を受講しました。
研修の最初の方ではあまり深い問題意識もなく、ただ漠然と研修のスケジュールに乗って受講していたのですが、進むに従って、次第に自分の経営のこと、ひいては自分の性格のこと、意思決定、行動パターン、危機感の持ち方と、ありとあらゆるところに問題意識を持ち始めていました。
なぜ、自分はこのような問題行動をとるのだろうか?なぜ自分はこんな風に考えてしまうのだろうか?
どうしてアクション(行動)がとれないのか?自分の意思はどうして弱いのか・・・・・・?
そして、その過程の中で、自分の潜在意識の中を深く探り始めるようになっていくわけです。
私は何者なのか・・・・・どういう人間なんだろうか・・・・・わたしは・・・・・・そういう言えば幼かったころ、こんなことが好きだったなあ・・・・・・あの子はどうしているかなあ・・・・・・なんであの頃喧嘩したんだっけ・・・・・・・・
という感じで、どんどん自分の来し方を遡っていき、精神深くまでダイブしていきます。
すると、眼前に一人の人物が現れてきました。
誰あろう、私の母親であります。
母親との幼い頃の思い出。ふれあい。しかられたこと。不愉快だったこと。楽しかったこと。
そうです。
私の性格、意思決定、行動パターンの背後にあるもの・・・・・それは、やはり母親なんですね。
「私」を形作っているもの。それはよくも悪くも「母親」なんです。
そして、ここから様々な「気づき」が私を訪れます。
それらは次回にお話しましょう! → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
ではまた。

第2回 → http://katsu.i-ra.jp/e10339.html
前回、人間の意識には潜在意識と顕在意識があり、その人の将来は潜在意識に大きく影響を受ける、という話をしました。
従って、潜在意識を顕在化する作業が大変重要なわけです。
では、この潜在意識を顕在化する作業とはどんな作業か?
ちょっとここでは私のお話がずれてしまうので触れませんが、がんばれば誰にでもできる簡単なものかというと、とてもそんなものではありません。
非常に高度な知識と経験と技術をもった人間によるサポートが必要です。
従って、残念ながらご自身の力でできる方は、ほとんどいないのではないでしょうか。プロの手が必要です。
私は、ある企業の研修を受講して、この作業が可能になりました。私もプロの手を借りたわけです。
私は、その研修を通して「深い気づき」を得ました。
潜在意識を顕在化する作業というのは、結局、この「深い気づき」を得る作業ととらえてよいと思われます。
今から数年前、私は経営上、かなり深い悩みを抱えていました。
そんな折、私の友人から誘われて、この研修を受講しました。
研修の最初の方ではあまり深い問題意識もなく、ただ漠然と研修のスケジュールに乗って受講していたのですが、進むに従って、次第に自分の経営のこと、ひいては自分の性格のこと、意思決定、行動パターン、危機感の持ち方と、ありとあらゆるところに問題意識を持ち始めていました。
なぜ、自分はこのような問題行動をとるのだろうか?なぜ自分はこんな風に考えてしまうのだろうか?
どうしてアクション(行動)がとれないのか?自分の意思はどうして弱いのか・・・・・・?
そして、その過程の中で、自分の潜在意識の中を深く探り始めるようになっていくわけです。
私は何者なのか・・・・・どういう人間なんだろうか・・・・・わたしは・・・・・・そういう言えば幼かったころ、こんなことが好きだったなあ・・・・・・あの子はどうしているかなあ・・・・・・なんであの頃喧嘩したんだっけ・・・・・・・・
という感じで、どんどん自分の来し方を遡っていき、精神深くまでダイブしていきます。
すると、眼前に一人の人物が現れてきました。
誰あろう、私の母親であります。
母親との幼い頃の思い出。ふれあい。しかられたこと。不愉快だったこと。楽しかったこと。
そうです。
私の性格、意思決定、行動パターンの背後にあるもの・・・・・それは、やはり母親なんですね。
「私」を形作っているもの。それはよくも悪くも「母親」なんです。
そして、ここから様々な「気づき」が私を訪れます。
それらは次回にお話しましょう! → http://katsu.i-ra.jp/e10661.html
ではまた。

無意識の世界Ⅱ
前回 → http://katsu.i-ra.jp/e10289.html
さて、ではその潜在意識って、どういったものなんでしょうか?
(これからのお話は、心理学の専門家でもない私が、皆さんと一緒に、潜在意識を勉強していくために書いていますので、専門家の方から見れば間違いが結構あるかもしれません。その際はどんどんご指摘ください。よろしくお願い申し上げます。)
それは、ご自分の幼児期に体験したことがほとんどです。幼い頃に感じたこと、嫌だったことや嬉しかったこと。こういったものの積み重ねが潜在意識を多重に形作っていきます。
また、皆さん、ジョハリの4つの窓、ということを聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
所謂、自己を、自分から見た場合と他人から見た場合で、マトリックスにして考える方法論です。
一つ目の窓は、自分は分かっていて、他人にも知られている自己です。(開放の窓)
二つ目の窓は、自分は分からなくて、他人は知っている自己です。(盲点の窓)
三つ目の窓は、自分は分かっていて、他人には知られていない自己です。(秘密の窓)
そして、四つ目の窓が、自分も他人も分かっていない自己です。(未知の窓)
このジョハリの窓で考えると、4つ目の、未知の窓が潜在意識の世界だと思われます。
そして、この未知の窓が大きな領域を占める方は、大変思考も幼く、言動も不安定です。逆に、開放の窓が大きい方は、どちらかと言えば落ち着いていて、あまり裏表がなく、見たままの人です。(ちょっと面白みがないかもしれませんが、付き合っていて安心できる相手です。)
人間の成長は、このジョハリの窓で言えば、未知の窓の領域を小さくし、開放の窓を大きくしていく過程と言えるかもしれません。
さて、皆さんはこの4つの窓で、どの窓が一番大きいでしょうか?
開放の窓ですか、盲点の窓ですか、それとも・・・ヒ・ミ・ツの窓ですか?
未知の窓が大きそうだと思われる方(というか、思っている方はすでに未知の窓は小さいと思われるのですが・・・)は、潜在意識にメスを入れていかなければなりません。
そして、ご自身の将来を変えていきたい、ご自分の性格を変えていきたい、と思われている方も、潜在意識にメスを入れる必要があります。
ご自分の言動の原因は、他ならぬご自身の潜在意識が作っているのですから。
即ち、ご自身の潜在意識を顕在化しない限り、ご自身の言動(性格)の原因は掴めません。ということは、ご自身を変えることはできない、ということです。
逆に、潜在意識を顕在化させ意識下に置いたとき、ご自身を変えるチャンスを得ることができます。
人間は、90%の潜在意識が意識しているように人生を送っていきます。
皆さん、ご自身がやれていることって、事前に「なんかやれそうだ」って思っていないですか?
そして逆に、自分ができていないことは、事前に「恐らく自分にはできないだろう」ってぼんやり思っている・・・・・・まだやる前に。
従って、ご自身が目標を立てて、「人生をあんな風に生きてみたい」と思ったときに、実はすでにご自身の潜在意識が原因を作り結果を(自分の意図とは異なり)勝手に生み出している可能性があります。
その結果が「自分が目標を達成することはありえない」というものであったとしたら・・・・・。
ここに、ご自分の潜在意識にメスを入れる意味があります。
自分の性格はどうして、こうなっているのか。自分はなぜ、こういったものが好きなのか。自分はどうして、こういった時に、このように意思決定するのか。
実は、これら全てに、そうなる原因があります。
それが、潜在意識です。
私は、ある出来事を通して、そのことに気づかされました。
次回は、そのことに触れていきましょう! → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
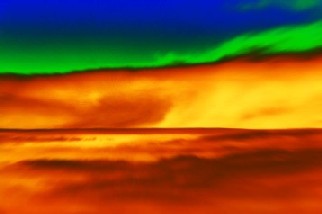
さて、ではその潜在意識って、どういったものなんでしょうか?
(これからのお話は、心理学の専門家でもない私が、皆さんと一緒に、潜在意識を勉強していくために書いていますので、専門家の方から見れば間違いが結構あるかもしれません。その際はどんどんご指摘ください。よろしくお願い申し上げます。)
それは、ご自分の幼児期に体験したことがほとんどです。幼い頃に感じたこと、嫌だったことや嬉しかったこと。こういったものの積み重ねが潜在意識を多重に形作っていきます。
また、皆さん、ジョハリの4つの窓、ということを聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
所謂、自己を、自分から見た場合と他人から見た場合で、マトリックスにして考える方法論です。
一つ目の窓は、自分は分かっていて、他人にも知られている自己です。(開放の窓)
二つ目の窓は、自分は分からなくて、他人は知っている自己です。(盲点の窓)
三つ目の窓は、自分は分かっていて、他人には知られていない自己です。(秘密の窓)
そして、四つ目の窓が、自分も他人も分かっていない自己です。(未知の窓)
このジョハリの窓で考えると、4つ目の、未知の窓が潜在意識の世界だと思われます。
そして、この未知の窓が大きな領域を占める方は、大変思考も幼く、言動も不安定です。逆に、開放の窓が大きい方は、どちらかと言えば落ち着いていて、あまり裏表がなく、見たままの人です。(ちょっと面白みがないかもしれませんが、付き合っていて安心できる相手です。)
人間の成長は、このジョハリの窓で言えば、未知の窓の領域を小さくし、開放の窓を大きくしていく過程と言えるかもしれません。
さて、皆さんはこの4つの窓で、どの窓が一番大きいでしょうか?
開放の窓ですか、盲点の窓ですか、それとも・・・ヒ・ミ・ツの窓ですか?
未知の窓が大きそうだと思われる方(というか、思っている方はすでに未知の窓は小さいと思われるのですが・・・)は、潜在意識にメスを入れていかなければなりません。
そして、ご自身の将来を変えていきたい、ご自分の性格を変えていきたい、と思われている方も、潜在意識にメスを入れる必要があります。
ご自分の言動の原因は、他ならぬご自身の潜在意識が作っているのですから。
即ち、ご自身の潜在意識を顕在化しない限り、ご自身の言動(性格)の原因は掴めません。ということは、ご自身を変えることはできない、ということです。
逆に、潜在意識を顕在化させ意識下に置いたとき、ご自身を変えるチャンスを得ることができます。
人間は、90%の潜在意識が意識しているように人生を送っていきます。
皆さん、ご自身がやれていることって、事前に「なんかやれそうだ」って思っていないですか?
そして逆に、自分ができていないことは、事前に「恐らく自分にはできないだろう」ってぼんやり思っている・・・・・・まだやる前に。
従って、ご自身が目標を立てて、「人生をあんな風に生きてみたい」と思ったときに、実はすでにご自身の潜在意識が原因を作り結果を(自分の意図とは異なり)勝手に生み出している可能性があります。
その結果が「自分が目標を達成することはありえない」というものであったとしたら・・・・・。
ここに、ご自分の潜在意識にメスを入れる意味があります。
自分の性格はどうして、こうなっているのか。自分はなぜ、こういったものが好きなのか。自分はどうして、こういった時に、このように意思決定するのか。
実は、これら全てに、そうなる原因があります。
それが、潜在意識です。
私は、ある出来事を通して、そのことに気づかされました。
次回は、そのことに触れていきましょう! → http://katsu.i-ra.jp/e10363.html
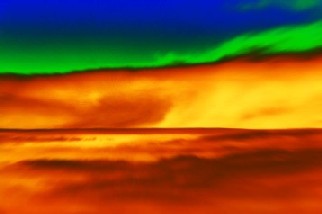
無意識の世界
皆さんは、ご自分の言動、意思決定は、ご自身の意識下(顕在意識)で行われていると思ってますよね。(もし思っていないとすれば、相当の心理学フリークでしょうね。)
当然、自分で思っているから言葉も出るし考え判断する。思っていなければ、考えないですものね。至極当たり前の話です。
でも、思っているかどうか、分からないまま物事を選んでいるってことないですか?
私は、道を歩いていて右か左か迷ったときは、よく何気なく右を選んでいます。上か下かの場合は、上を選ぶことが多いし、黒か白かといったら白を選んでいます。
このように、あまり積極的ではないのですが、なんとなく何かを選んでいることって、結構多くありませんか?
ありますよね。で、これって何かな?ということなんです。
ここで、心理学を少しでもかじった方は、それは無意識、というか潜在意識なんだよ、とおっしゃるでしょう。
そうなんですよね。私は心理学の専門家ではありませんが、よくいろいろな本で知見するのは、「われわれの意思決定や価値判断の際、潜在意識が大変大きな影響力をもっている」という事実です。
われわれの意識は、顕在意識と潜在意識があり、顕在意識は全意識の10%にすぎない、と言われています。ということは、残りの90%は潜在意識なんですね。
われわれの意思決定や価値判断、そして行動は、この90%の潜在意識によって、大変大きく管理されている、と言っても過言ではありません。
ということは、ご自分の将来の鍵は、この90%の潜在意識が握っている、ということなんです。
芥川龍之介氏曰く・・・・
「運命はその人の性格の中にあり」。(「侏儒(しゅじゅ)の言葉」より
これから何回かにわたって、皆さんとこの「無意識の世界」をさまよってみたいと思います。
ではまた次回に。→ http://katsu.i-ra.jp/e10339.html

当然、自分で思っているから言葉も出るし考え判断する。思っていなければ、考えないですものね。至極当たり前の話です。
でも、思っているかどうか、分からないまま物事を選んでいるってことないですか?
私は、道を歩いていて右か左か迷ったときは、よく何気なく右を選んでいます。上か下かの場合は、上を選ぶことが多いし、黒か白かといったら白を選んでいます。
このように、あまり積極的ではないのですが、なんとなく何かを選んでいることって、結構多くありませんか?
ありますよね。で、これって何かな?ということなんです。
ここで、心理学を少しでもかじった方は、それは無意識、というか潜在意識なんだよ、とおっしゃるでしょう。
そうなんですよね。私は心理学の専門家ではありませんが、よくいろいろな本で知見するのは、「われわれの意思決定や価値判断の際、潜在意識が大変大きな影響力をもっている」という事実です。
われわれの意識は、顕在意識と潜在意識があり、顕在意識は全意識の10%にすぎない、と言われています。ということは、残りの90%は潜在意識なんですね。
われわれの意思決定や価値判断、そして行動は、この90%の潜在意識によって、大変大きく管理されている、と言っても過言ではありません。
ということは、ご自分の将来の鍵は、この90%の潜在意識が握っている、ということなんです。
芥川龍之介氏曰く・・・・
「運命はその人の性格の中にあり」。(「侏儒(しゅじゅ)の言葉」より
これから何回かにわたって、皆さんとこの「無意識の世界」をさまよってみたいと思います。
ではまた次回に。→ http://katsu.i-ra.jp/e10339.html

フライング・ファミリー(浮遊する家族)
何日か前の日経新聞の記事です。
皆さんはどう思われますか?少し長文ですが、ちょっと面白い内容だと思いますのでお時間ございましたらお読みください。
「犯罪の温床と批判される出会い系サイト。子供が被害にあう例も目立ち、問題になっている。ただ世界を見渡せば、見知らぬ人同士を結びつける「マッチングサイト」は静かに増加。透明性を高めながら、新領域にも広がっている。
出版社勤務の相馬茜(仮名、27)は結婚を決めた。相手(33)との話はとんとん拍子。一月にメールを交換し二月に対面、「一ヵ月後にプロポーズされた」。
出会うきっかけは米系結婚情報サイト「マッチ・ドット・コム」。身長、年収、趣味などを隠さず入力。相手に望む条件を設定したら、まるで検索結果のように候補者が並んだ。登録できるのは18歳以上の未婚者だけ。
「互いに結婚が目的だから無駄がない」。
相馬は実際に相手と会って人柄などを互いに確認し、人生の伴侶をたぐり寄せた。
長く神聖なものとされてきた結婚。そんな聖域にもネット文明の波は及ぶ。
結婚サイトは世界に爆発的に増加。最大手のマッチ・ドット・コムでは年間40万組が家族として「成約」、日本でも84万人が登録、心理的抵抗は薄れる。
文明の進展は、社会の基本単位である家族のかたちを変える。農業文明では農作業を営む大家族が形作られた。工業文明では工場勤務が広がり、核家族化が進んだ。コミュニケーションの姿を一変させるネット文明も例外ではない。
「高知の果物もらったよ。にほひのよかー」
「おいしくてよかったね」
「うちにも買ってきてよ」--。
画面の中で会話が弾む。
高知に単身赴任する下川裕太(仮名、47)は家族内ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で雑談を楽しむ。
参加するのは千葉に住む妻と三人の子供、佐賀の義妹夫婦の計7人だ。
本当は顔を見て話したいけれど住まいも生活時間も別。「どうにかならないか」と思っていたらナノティ(静岡県焼津市)という会社が運営する家族向けSNSが目にとまった。登録した家族ならいつでも好きなことを書き込める。夜遅く帰ってもパソコンを立ち上げれば話題を共有できる。
日本の家族は今年、大きな転換点を迎える。少子高齢化や晩婚が進み、一人暮らしをする単独世帯の数が、夫婦と子供で住む標準世帯を抜くのだ。
放っておけばとまらぬ分裂。
「分散家族」をつなぎとめるのにネットが一役買う。
「足を机に乗せてたわよ。甘いんじゃない」。
東京に住む田中菜月(仮名、35)は娘(4)の癖を実母(65)に指摘された。同居しているわけではない。広島で暮らす母はパソコンから保育園のカメラに映る孫を毎日のように眺めている。
同園運営のポピンズコーポレーションは働く母親の不安を和らげようとカメラを導入した。専用ホームページに識別番号などを入れると園児の姿が映る。ところがふたを開けると「生きがいができた」など祖父母の反響が大きく驚いた。高齢化社会の裏側で、三世代がネット上でつながる”擬似大家族”が増える。
家族に新たな意思疎通の手立てをもたらしたネット。しかし「つながりやすさ」には落とし穴も潜む。
「えっ、また?」。
坂本里香(仮名、44)は五月、メール送信者の名前を見て驚いた。
三年前に別れた元カレ。誕生日になるとなぜかメールを送ってくる。覚えているというアピールなのか旧友に声をかける感覚なのか。交遊の痕跡が相手のパソコンに残り、こちらは忘れたいのに不意に向こうから手を伸ばしてくる。
自分の言いたいことだけを一方的に「送信」できるネット時代。
浮遊する家族が本当に「受信」しているかは分からない。それでも離ればなれの人たちは、ネットに新時代の「一つ屋根の下」の願いを託す。
歴史家アーノルド・トインビーは
「社会とは人間の間に張り巡らされた網目全体のこと」と指摘した。
ネットという網目の上で離合集散を繰り返すネット文明の家族たち。
きょうもメールが飛び交う。(敬称略)」
最後のトインビーの言葉は、私が以前お話しました「ITの今後10年~30年の動向について ④」に書いた内容に重なります。
皆さんはいかがお考えになりますでしょうか?
よろしかったらコメントください。ではまた。

皆さんはどう思われますか?少し長文ですが、ちょっと面白い内容だと思いますのでお時間ございましたらお読みください。
「犯罪の温床と批判される出会い系サイト。子供が被害にあう例も目立ち、問題になっている。ただ世界を見渡せば、見知らぬ人同士を結びつける「マッチングサイト」は静かに増加。透明性を高めながら、新領域にも広がっている。
出版社勤務の相馬茜(仮名、27)は結婚を決めた。相手(33)との話はとんとん拍子。一月にメールを交換し二月に対面、「一ヵ月後にプロポーズされた」。
出会うきっかけは米系結婚情報サイト「マッチ・ドット・コム」。身長、年収、趣味などを隠さず入力。相手に望む条件を設定したら、まるで検索結果のように候補者が並んだ。登録できるのは18歳以上の未婚者だけ。
「互いに結婚が目的だから無駄がない」。
相馬は実際に相手と会って人柄などを互いに確認し、人生の伴侶をたぐり寄せた。
長く神聖なものとされてきた結婚。そんな聖域にもネット文明の波は及ぶ。
結婚サイトは世界に爆発的に増加。最大手のマッチ・ドット・コムでは年間40万組が家族として「成約」、日本でも84万人が登録、心理的抵抗は薄れる。
文明の進展は、社会の基本単位である家族のかたちを変える。農業文明では農作業を営む大家族が形作られた。工業文明では工場勤務が広がり、核家族化が進んだ。コミュニケーションの姿を一変させるネット文明も例外ではない。
「高知の果物もらったよ。にほひのよかー」
「おいしくてよかったね」
「うちにも買ってきてよ」--。
画面の中で会話が弾む。
高知に単身赴任する下川裕太(仮名、47)は家族内ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で雑談を楽しむ。
参加するのは千葉に住む妻と三人の子供、佐賀の義妹夫婦の計7人だ。
本当は顔を見て話したいけれど住まいも生活時間も別。「どうにかならないか」と思っていたらナノティ(静岡県焼津市)という会社が運営する家族向けSNSが目にとまった。登録した家族ならいつでも好きなことを書き込める。夜遅く帰ってもパソコンを立ち上げれば話題を共有できる。
日本の家族は今年、大きな転換点を迎える。少子高齢化や晩婚が進み、一人暮らしをする単独世帯の数が、夫婦と子供で住む標準世帯を抜くのだ。
放っておけばとまらぬ分裂。
「分散家族」をつなぎとめるのにネットが一役買う。
「足を机に乗せてたわよ。甘いんじゃない」。
東京に住む田中菜月(仮名、35)は娘(4)の癖を実母(65)に指摘された。同居しているわけではない。広島で暮らす母はパソコンから保育園のカメラに映る孫を毎日のように眺めている。
同園運営のポピンズコーポレーションは働く母親の不安を和らげようとカメラを導入した。専用ホームページに識別番号などを入れると園児の姿が映る。ところがふたを開けると「生きがいができた」など祖父母の反響が大きく驚いた。高齢化社会の裏側で、三世代がネット上でつながる”擬似大家族”が増える。
家族に新たな意思疎通の手立てをもたらしたネット。しかし「つながりやすさ」には落とし穴も潜む。
「えっ、また?」。
坂本里香(仮名、44)は五月、メール送信者の名前を見て驚いた。
三年前に別れた元カレ。誕生日になるとなぜかメールを送ってくる。覚えているというアピールなのか旧友に声をかける感覚なのか。交遊の痕跡が相手のパソコンに残り、こちらは忘れたいのに不意に向こうから手を伸ばしてくる。
自分の言いたいことだけを一方的に「送信」できるネット時代。
浮遊する家族が本当に「受信」しているかは分からない。それでも離ればなれの人たちは、ネットに新時代の「一つ屋根の下」の願いを託す。
歴史家アーノルド・トインビーは
「社会とは人間の間に張り巡らされた網目全体のこと」と指摘した。
ネットという網目の上で離合集散を繰り返すネット文明の家族たち。
きょうもメールが飛び交う。(敬称略)」
最後のトインビーの言葉は、私が以前お話しました「ITの今後10年~30年の動向について ④」に書いた内容に重なります。
皆さんはいかがお考えになりますでしょうか?
よろしかったらコメントください。ではまた。
F1、見たいなあ!
あまりイーラではお話されていないので、ちょっと(?)F1の話題を。
最近のF1は少し見る機会(時間)がなくてあまり見ていないのですが、80年代後半~90年代前半まで、特にセナが大変好きだったので、よくF1を見ていました。
90年には鈴鹿に見に行って、プロストとセナの一騎打ちを、少しだけ直接見ることができました。
なぜ少しだけかって?
これは90年の鈴鹿のレース結果をご存知の方ならよくお分かりだと思いますが、あの第1コーナーのセナとプロストの接触がなければ、もちろんずっとセナプロ対決を大興奮しながら見ていたでしょうが、スタートしてわずか数秒後に二人の対決は終わっていました。
せっかくセナを見に行ったのに・・・・ととても悔しい思いをしていました。
しかも私の席は鈴鹿のヘアピンの席。フォーメーションラップの際に、プロストとセナがとてつもないエグゾーストノートを響かせて、目の前を走っていったので、もうわくわくしっぱなしで、今か今かと本レースを待っていました。
ところが、待てど暮らせど・・・・・・ とほほ
とほほ
がっくり。あとはもうレースを真剣に見るというより、浴びるように でして
でして
ただ、このレースでは亜久里が日本人としてはじめて3位に入って表彰台に立っていたことを思い出します。(私はそのことよりはるかにセナを見れなかった悔しさのほうが強かったですが。)
さあ、御殿場で富士スピードウエイでやってますね。ハミルトンがPPだそうですね。
久しぶりにF1観戦に力を入れてみようかな。
とにかくF1というのは、マシンが好きな人にはたまりませんね。
僕も結構メカに夢中になっていました。新しい技術が出るとその解説本に首っ引きに。
あーあ、わくわくしますね。F1見たーい。
今回、友人が抽選に当たって見に行っています。うらやましいなあ。
明日はどういう結果になるのでしょうか?
楽しみです。ではでは。
最近のF1は少し見る機会(時間)がなくてあまり見ていないのですが、80年代後半~90年代前半まで、特にセナが大変好きだったので、よくF1を見ていました。
90年には鈴鹿に見に行って、プロストとセナの一騎打ちを、少しだけ直接見ることができました。
なぜ少しだけかって?
これは90年の鈴鹿のレース結果をご存知の方ならよくお分かりだと思いますが、あの第1コーナーのセナとプロストの接触がなければ、もちろんずっとセナプロ対決を大興奮しながら見ていたでしょうが、スタートしてわずか数秒後に二人の対決は終わっていました。
せっかくセナを見に行ったのに・・・・ととても悔しい思いをしていました。
しかも私の席は鈴鹿のヘアピンの席。フォーメーションラップの際に、プロストとセナがとてつもないエグゾーストノートを響かせて、目の前を走っていったので、もうわくわくしっぱなしで、今か今かと本レースを待っていました。
ところが、待てど暮らせど・・・・・・
 とほほ
とほほ
がっくり。あとはもうレースを真剣に見るというより、浴びるように
 でして
でして
ただ、このレースでは亜久里が日本人としてはじめて3位に入って表彰台に立っていたことを思い出します。(私はそのことよりはるかにセナを見れなかった悔しさのほうが強かったですが。)
さあ、御殿場で富士スピードウエイでやってますね。ハミルトンがPPだそうですね。
久しぶりにF1観戦に力を入れてみようかな。
とにかくF1というのは、マシンが好きな人にはたまりませんね。
僕も結構メカに夢中になっていました。新しい技術が出るとその解説本に首っ引きに。
あーあ、わくわくしますね。F1見たーい。
今回、友人が抽選に当たって見に行っています。うらやましいなあ。
明日はどういう結果になるのでしょうか?
楽しみです。ではでは。
やっぱりセカンドライフは面白いですね
ネットの世界では日本はなかなかのもの?
先日、日経新聞の記事を見ていたら、こんな情報がありました。
私の他の情報入手先からも同様の情報を得ていたので、おそらく確かな情報なんだと思います。
でも、「えっ て感じ」ですよね。
て感じ」ですよね。
皆さんもツィッターという簡易ブログ(ミニブログ)をご存知ですよね。
今、そのツイッターでへんなことが起きている?
毎日、日本の夜明けと同時に日本ユーザがメッセージを投稿し始めて、事実上の公用語が英語から日本語に切り替わってしまうそうです。
ツイッター社はパソコンや携帯からのメールを受付け、インターネットを通して世界に発信しています。サイトの説明は英語ですが、口コミによって日本で人気が急上昇。「日本時間」では日本のユーザが世界のユーザを席巻しているということです。
また、米テクノラティの調査によると、昨年10月-12月期に世界のブログでもっとも使われた言語は、なんと、日本語だそうです。
記事では、ユーチューブにも言及しています。
なんでも「ユーチューブは、米についでユーザが多い日本を戦略的な市場ととらている」そうな・・・。日本で携帯向け新サービスを開発し世界展開を狙うそうです。
シリコンバレーの米ネットベンチャー企業にとっては、「日本はお得意様」ということか?
これでもって「日本はなかなかのもの」とは言えないでしょうが、日本はネットの世界では相変わらず大きな市場であることを証明しているのでは・・・・。
筆者が言っていますが、「そろそろ米のモノマネを脱するときではないか」。
まったく同感です。
弊社も「アイ・クリエイティブ」という名前に違わず独創的な、世の中にないものを生み出していかなければ、と思っています。
がんばろっと

私の他の情報入手先からも同様の情報を得ていたので、おそらく確かな情報なんだと思います。
でも、「えっ
 て感じ」ですよね。
て感じ」ですよね。皆さんもツィッターという簡易ブログ(ミニブログ)をご存知ですよね。
今、そのツイッターでへんなことが起きている?
毎日、日本の夜明けと同時に日本ユーザがメッセージを投稿し始めて、事実上の公用語が英語から日本語に切り替わってしまうそうです。
ツイッター社はパソコンや携帯からのメールを受付け、インターネットを通して世界に発信しています。サイトの説明は英語ですが、口コミによって日本で人気が急上昇。「日本時間」では日本のユーザが世界のユーザを席巻しているということです。
また、米テクノラティの調査によると、昨年10月-12月期に世界のブログでもっとも使われた言語は、なんと、日本語だそうです。
記事では、ユーチューブにも言及しています。
なんでも「ユーチューブは、米についでユーザが多い日本を戦略的な市場ととらている」そうな・・・。日本で携帯向け新サービスを開発し世界展開を狙うそうです。
シリコンバレーの米ネットベンチャー企業にとっては、「日本はお得意様」ということか?
これでもって「日本はなかなかのもの」とは言えないでしょうが、日本はネットの世界では相変わらず大きな市場であることを証明しているのでは・・・・。
筆者が言っていますが、「そろそろ米のモノマネを脱するときではないか」。
まったく同感です。
弊社も「アイ・クリエイティブ」という名前に違わず独創的な、世の中にないものを生み出していかなければ、と思っています。
がんばろっと


軽度の発達障害を抱えた子どもたちへの支援セミナーの感想
以前お話しました「軽度の発達障害を抱えた子どもたちへの支援~学校と家庭の連携による個別指導計画の有効活用~」のセミナーの感想です。
いつもこういったセミナーは、あまり静岡県内では行われていないことから、参加者が30名~40名いらっしゃるのですが、今回は9月の各種イベントと重なったためか、10名ほどの参加でありました。
ただ、セミナーの内容は、手前味噌で恐縮ですが、いつもどおり大変充実したものであり、セミナー終了後の相談会・懇親会は、受講生と講師との会話・交流がずっと続き、会場の予約時間をすぎても受講生が帰らないということがまま発生しております。それもかなり熱気を帯びたお話が多く、受講生のご父兄や先生の抱えているものの問題の深さが察せられます。
(でも結構皆さん明るいんですけど・・・・・この天然の明るさに、われわれも救われているところです(^^))
みんなで話しているとどんな内容でも、どこか楽しく、少し癒される感じがします。
今回は、高校の現役の先生が最後まで残ってくださり、あるクラスの軽度発達障害と思われる生徒をとりまく、他の生徒そして教師の様々な問題・悩みをお話下さいました。学校現場はまさに闘いです。
担任の教師の悩み・とまどいが手に取るようにわかります。
このブログを見てくださっている皆さんにとっても聞きなじみがないであろう「軽度発達障害」。
現場の先生方もほぼ皆さんと同じ認識だと思っていただいてもよいのかもしれません。
この障害という名称をつけてよいものかどうかも迷う「軽度発達障害」。
われわれは、この問題を「M-netアビニオンスクール」で考え始めて5年が経ちます。そして、われわれと提携している星槎グループは、もうこの問題と35年も闘っています。
この問題に適切に対処するためには、まず「情報」が必要です。
「情報」もなしに対処すると、大変な事態を招きます。
従って、まず現場の先生方にお願いしたいのは、まずは情報収集を必ず行ってほしいということ。
それがないと、生兵法は大怪我のもとです。
「軽度発達障害」の生徒は、もちろん病気では決してありませんので、一見、普通の生徒と大差ありません。先生は思わず普通の生徒と同様の対応しがちになります。これが大変大きな過ちとなります。
次に先生が誤りがちになるのは、「障害者」として扱おうとすることです。「軽度発達障害」というのは、先ほども少しお話したように、「障害」と名づけてよいものかどうかさえためらわれるものです。
実は、これも結構あることなんですが、その子の親が「軽度発達障害」に気づいていないケースも結構あります。この際、親御さんにどのようにしてこのことを伝えるべきか?これも大変大きな問題です。「障害」という名称に大変神経質になるのもこの場合が多いのです。
今回の高校教師の先生の例もこのケースでした。そして担任の先生は、「障害」として扱いそうになっていると思われました。
重要なことは、「どんなケースも生徒が主役である」ということです。
「軽度発達障害」にも「診断ツール」があります。「WISC-3」というものが代表的なものですが、ここでも問題なことは、指導に当たっては「WISC-3」にとらわれすぎてもいけないということです。「WISC-3」は客観的な診断データとして、重要な参考指標となりますが、決して「WISC-3」中心に考え指導してはいけない。大事なのは「その生徒をしっかり見ること」です。
という具合に、実は「軽度発達障害」の児童に対応するには、「その子の身になって」「その子の特性を活かした形で」「どうやって育成していくか」が大変重要であります。
このように書くと、なんだ軽度発達障害の話ではないじゃないか、という慧眼の持ち主がいらっしゃるでしょう!
そのとおりです。
実は「普通の生徒」に対しても本当は、「軽度発達障害の生徒」に対応することと、ある意味同じことを、指導者側は本来考え対応していかなければならないはずなんです。ただ、現実の様々な問題があり、それができえていないのが「現実の教育」です。いわゆるどこかで「手抜き」をしていかないと、「現実の教育」は回っていきません。
ところが、「軽度発達障害」の生徒を前にした時に、一番やってはいけないのは、この「手抜き」なんです。この「手抜き」を行った際に、必ず後で「つけ」が回ってきます。
これが「軽度発達障害」の生徒を前にした際の教育です。そして、すべてケースバイケースです。どこかの理論や知識がそのまま適用できることは、ほとんどまれでしょう!ただし、情報としてインプットすることはとても重要なことですが。
すべて、その生徒とともに「共育」するしかありません。教師側は「謙虚さ」と「一手間」を要求されます。
この点において、星槎グループは日本国内において、もっとも「情報」「ノウハウ」を持っています。そして、われわれ「M-netアビニオンスクール」は星槎グループと手を携えて、日夜この問題に取り組んでいます。
この問題に悩まれている先生方、そしてご父兄の方々には、早くわれわれの存在を知っていただきたいと切に思います。
なぜなら「軽度発達障害」の問題に対処するには、その生徒が年齢的に幼ければ幼いほど効果が大きいからです。実は高校より中学、もっと言えば小学生高学年から、親御さんも指導者もその子の「軽度発達障害」の状況を的確に把握し「共育」を行えば、ある意味「普通の生徒」以上の成長を促すことも可能です。かの「ヘレンケラー女史」も「軽度発達障害」ではなかったか、と言われています。彼女には「サリバン先生」という大変優秀な「共育者」が傍らにいました。そのことで「ヘレンケラー女史」という偉大な人物が生まれたのです。
われわれは「サリバン先生」にはとてもなれないと思いますが、少しでもその姿に近づきたいと思っています。
ぜひとも多くの方にわれわれの存在を知っていただきたい。
最後は、セミナーの感想とは思えない形になってしまいましたが、これもいつものかっちゃんの風任せ、ですね
よろしくご容赦くださいませませ
ではまた。
いつもこういったセミナーは、あまり静岡県内では行われていないことから、参加者が30名~40名いらっしゃるのですが、今回は9月の各種イベントと重なったためか、10名ほどの参加でありました。
ただ、セミナーの内容は、手前味噌で恐縮ですが、いつもどおり大変充実したものであり、セミナー終了後の相談会・懇親会は、受講生と講師との会話・交流がずっと続き、会場の予約時間をすぎても受講生が帰らないということがまま発生しております。それもかなり熱気を帯びたお話が多く、受講生のご父兄や先生の抱えているものの問題の深さが察せられます。
(でも結構皆さん明るいんですけど・・・・・この天然の明るさに、われわれも救われているところです(^^))
みんなで話しているとどんな内容でも、どこか楽しく、少し癒される感じがします。
今回は、高校の現役の先生が最後まで残ってくださり、あるクラスの軽度発達障害と思われる生徒をとりまく、他の生徒そして教師の様々な問題・悩みをお話下さいました。学校現場はまさに闘いです。
担任の教師の悩み・とまどいが手に取るようにわかります。
このブログを見てくださっている皆さんにとっても聞きなじみがないであろう「軽度発達障害」。
現場の先生方もほぼ皆さんと同じ認識だと思っていただいてもよいのかもしれません。
この障害という名称をつけてよいものかどうかも迷う「軽度発達障害」。
われわれは、この問題を「M-netアビニオンスクール」で考え始めて5年が経ちます。そして、われわれと提携している星槎グループは、もうこの問題と35年も闘っています。
この問題に適切に対処するためには、まず「情報」が必要です。
「情報」もなしに対処すると、大変な事態を招きます。
従って、まず現場の先生方にお願いしたいのは、まずは情報収集を必ず行ってほしいということ。
それがないと、生兵法は大怪我のもとです。
「軽度発達障害」の生徒は、もちろん病気では決してありませんので、一見、普通の生徒と大差ありません。先生は思わず普通の生徒と同様の対応しがちになります。これが大変大きな過ちとなります。
次に先生が誤りがちになるのは、「障害者」として扱おうとすることです。「軽度発達障害」というのは、先ほども少しお話したように、「障害」と名づけてよいものかどうかさえためらわれるものです。
実は、これも結構あることなんですが、その子の親が「軽度発達障害」に気づいていないケースも結構あります。この際、親御さんにどのようにしてこのことを伝えるべきか?これも大変大きな問題です。「障害」という名称に大変神経質になるのもこの場合が多いのです。
今回の高校教師の先生の例もこのケースでした。そして担任の先生は、「障害」として扱いそうになっていると思われました。
重要なことは、「どんなケースも生徒が主役である」ということです。
「軽度発達障害」にも「診断ツール」があります。「WISC-3」というものが代表的なものですが、ここでも問題なことは、指導に当たっては「WISC-3」にとらわれすぎてもいけないということです。「WISC-3」は客観的な診断データとして、重要な参考指標となりますが、決して「WISC-3」中心に考え指導してはいけない。大事なのは「その生徒をしっかり見ること」です。
という具合に、実は「軽度発達障害」の児童に対応するには、「その子の身になって」「その子の特性を活かした形で」「どうやって育成していくか」が大変重要であります。
このように書くと、なんだ軽度発達障害の話ではないじゃないか、という慧眼の持ち主がいらっしゃるでしょう!
そのとおりです。
実は「普通の生徒」に対しても本当は、「軽度発達障害の生徒」に対応することと、ある意味同じことを、指導者側は本来考え対応していかなければならないはずなんです。ただ、現実の様々な問題があり、それができえていないのが「現実の教育」です。いわゆるどこかで「手抜き」をしていかないと、「現実の教育」は回っていきません。
ところが、「軽度発達障害」の生徒を前にした時に、一番やってはいけないのは、この「手抜き」なんです。この「手抜き」を行った際に、必ず後で「つけ」が回ってきます。
これが「軽度発達障害」の生徒を前にした際の教育です。そして、すべてケースバイケースです。どこかの理論や知識がそのまま適用できることは、ほとんどまれでしょう!ただし、情報としてインプットすることはとても重要なことですが。
すべて、その生徒とともに「共育」するしかありません。教師側は「謙虚さ」と「一手間」を要求されます。
この点において、星槎グループは日本国内において、もっとも「情報」「ノウハウ」を持っています。そして、われわれ「M-netアビニオンスクール」は星槎グループと手を携えて、日夜この問題に取り組んでいます。
この問題に悩まれている先生方、そしてご父兄の方々には、早くわれわれの存在を知っていただきたいと切に思います。
なぜなら「軽度発達障害」の問題に対処するには、その生徒が年齢的に幼ければ幼いほど効果が大きいからです。実は高校より中学、もっと言えば小学生高学年から、親御さんも指導者もその子の「軽度発達障害」の状況を的確に把握し「共育」を行えば、ある意味「普通の生徒」以上の成長を促すことも可能です。かの「ヘレンケラー女史」も「軽度発達障害」ではなかったか、と言われています。彼女には「サリバン先生」という大変優秀な「共育者」が傍らにいました。そのことで「ヘレンケラー女史」という偉大な人物が生まれたのです。
われわれは「サリバン先生」にはとてもなれないと思いますが、少しでもその姿に近づきたいと思っています。
ぜひとも多くの方にわれわれの存在を知っていただきたい。
最後は、セミナーの感想とは思えない形になってしまいましたが、これもいつものかっちゃんの風任せ、ですね

よろしくご容赦くださいませませ

ではまた。
プチ紳士を探せ
かつて先輩経営者の方から教えていただいた「志賀内泰弘さん」をご紹介します。
彼は、ちょっとした良いこと、良い話を、あまり無理せず自分の手の届く範囲で、全国の皆さんに「プチ紳士」という形で広める活動をされています。
彼のモットーは、「Give&Give」。
「Give&Take」ではありません、「Give&Give」です。
私はこの言葉に大変感動しました。それ以来、彼のメールマガジンを購読し、時に心を動かされ、時に癒されています。かつて中小企業家同友会で、志賀内さんを三島にお呼びして講演していただきました。大変体がやせている方で、一見ひ弱そうに見えるのですが、どうしてどうして。
大変パワフルな方です。そして、すごく純粋。
とにかく「世の中にちょっとでいいから自分の生活の延長で、少しだけよいことをし、よい話を、ほんの少しの勇気でいいので、他の方に与えていきましょう!そして、そのことによって、少しずつ世の中が明るくなり幸せになっていけばいいのではないか」、という想いで一杯の方でした。
彼のホームページをご覧下さい。「プチ紳士を探せ」のHPです。
ご賛同される方は、彼のメールマガジンの購読者になってあげてください。
「中高年の太陽」さんのブログに触発されて、志賀内さんを思い出しました。中高年の太陽さん、ありがとうございました。
ではまた。

彼は、ちょっとした良いこと、良い話を、あまり無理せず自分の手の届く範囲で、全国の皆さんに「プチ紳士」という形で広める活動をされています。
彼のモットーは、「Give&Give」。
「Give&Take」ではありません、「Give&Give」です。
私はこの言葉に大変感動しました。それ以来、彼のメールマガジンを購読し、時に心を動かされ、時に癒されています。かつて中小企業家同友会で、志賀内さんを三島にお呼びして講演していただきました。大変体がやせている方で、一見ひ弱そうに見えるのですが、どうしてどうして。
大変パワフルな方です。そして、すごく純粋。
とにかく「世の中にちょっとでいいから自分の生活の延長で、少しだけよいことをし、よい話を、ほんの少しの勇気でいいので、他の方に与えていきましょう!そして、そのことによって、少しずつ世の中が明るくなり幸せになっていけばいいのではないか」、という想いで一杯の方でした。
彼のホームページをご覧下さい。「プチ紳士を探せ」のHPです。
ご賛同される方は、彼のメールマガジンの購読者になってあげてください。
「中高年の太陽」さんのブログに触発されて、志賀内さんを思い出しました。中高年の太陽さん、ありがとうございました。
ではまた。

静岡茶を世界ブランドにする方法(大前研一氏)
静岡県民の皆さん! 自分たちの常識を疑いましょう!
それまでの常識が何の意味ももたないことに早く気づくべきです。
まずは、大前研一氏の「静岡茶はブランドでない」という箴言に耳を傾けてみましょう!
この記事をお読みください。
どうですか?
反論される方はいらっしゃるでしょうか?
私は、改めて彼の慧眼に恐れ入りました。
私は、まったくそのとおりだと思います。静岡茶はブランドでもなんでもないと思います。高級茶でも、どうしてもほしいと思えるお茶でもありません、残念ながら
本当に悔しいのですが、大前氏の言うことは、まったくそのとおりだと思います。
(誤解しないで欲しいのは、これは一生懸命においしいお茶を作ろうとしている県内のお茶農家の方々を否定しているのでは一切ありません。恐らく大前氏もまったくそういう趣旨で言っているのではありません。このままでいると静岡茶というものが消滅してしまう危機感を感じる・・・・またやり方によっては、大きなブランド形成のチャンスとみて、お話されています。)
私は、このお話を「静岡のお茶」から「伊豆の観光」に置き換えて見ることができると思っています。
「伊豆の観光」も残念ながらブランド形成にはなっていません。
「湯布院」のようなブランドからみると、「伊豆」のブランド価値ははるかに低いと思います。
やはり「伊豆」は広すぎる!!
このままではブランド形成にはつながらない、と思います。
私は観光事業のプロではないので、よく分かりませんが、伊豆地域の観光に強いブランド価値を形成しようとすれば、どこかある一地域に、アイデア、資源、想い、ストーリー、資金を集中させる必要があるように思います。
集中戦略をとらなければ、私は「伊豆地域全般」で地盤沈下していくような気がしています。
逆にある地域に資源を集中させることで、その地域はもちろんのこと、周辺地域も同時に潤っていくのではないでしょうか?
そろそろわれわれのこれまでの常識を廃して、新たな観光戦略を考える時期にきているような気がしています。
皆さん、いかがお考えでしょうか?

それまでの常識が何の意味ももたないことに早く気づくべきです。
まずは、大前研一氏の「静岡茶はブランドでない」という箴言に耳を傾けてみましょう!
この記事をお読みください。
どうですか?
反論される方はいらっしゃるでしょうか?
私は、改めて彼の慧眼に恐れ入りました。
私は、まったくそのとおりだと思います。静岡茶はブランドでもなんでもないと思います。高級茶でも、どうしてもほしいと思えるお茶でもありません、残念ながら

本当に悔しいのですが、大前氏の言うことは、まったくそのとおりだと思います。
(誤解しないで欲しいのは、これは一生懸命においしいお茶を作ろうとしている県内のお茶農家の方々を否定しているのでは一切ありません。恐らく大前氏もまったくそういう趣旨で言っているのではありません。このままでいると静岡茶というものが消滅してしまう危機感を感じる・・・・またやり方によっては、大きなブランド形成のチャンスとみて、お話されています。)
私は、このお話を「静岡のお茶」から「伊豆の観光」に置き換えて見ることができると思っています。
「伊豆の観光」も残念ながらブランド形成にはなっていません。
「湯布院」のようなブランドからみると、「伊豆」のブランド価値ははるかに低いと思います。
やはり「伊豆」は広すぎる!!
このままではブランド形成にはつながらない、と思います。
私は観光事業のプロではないので、よく分かりませんが、伊豆地域の観光に強いブランド価値を形成しようとすれば、どこかある一地域に、アイデア、資源、想い、ストーリー、資金を集中させる必要があるように思います。
集中戦略をとらなければ、私は「伊豆地域全般」で地盤沈下していくような気がしています。
逆にある地域に資源を集中させることで、その地域はもちろんのこと、周辺地域も同時に潤っていくのではないでしょうか?
そろそろわれわれのこれまでの常識を廃して、新たな観光戦略を考える時期にきているような気がしています。
皆さん、いかがお考えでしょうか?

ITの今後10年~30年の動向について ⑲
第1回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1442.html
第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
第16回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
第17回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e6034.html
さあて、皆さん、4ヶ月弱にわたって、この回で19回となったこのシリーズ、実は今回が最終回です。と、いいますか、このシリーズは続けていくとどれだけでも続いていってしまいますから、この辺でひとまず大団円を迎えさせることにします。(ま、無理強いですが、一区切り。)
前回から1ヶ月近く経ってしまいましたので、少し振り返りますと、「ボーダーレス社会によって、日本独自の文化・価値の中で、名辞以前の感性空間等、言葉に表しにくい文化・価値が消えていってしまうだろう。」というお話をしていました。
そして、最終回の今回は、ボーダーレス社会の中で残り、さらに強くなっていく、日本独自の文化・価値についてお話してまいります。
さて、日本人が、それがないと生きていけない、生きてても意味がない、と思える文化・価値、または諸外国からみても、それが日本および日本人だと強く思えるもの。これは「ボーダーレス社会」になっても必ず残ります。
むしろ、「ボーダーレス社会」になればなるほど強く意識され、日本人のメンタリティに強く強く刻まれていくでしょう。日本人のアイデンティティ、存在理由(レゾンデートル)ですから。
例えば、能・歌舞伎・雅楽・華道・茶道・落語・漫才等々の芸能、日本画・陶器等々の芸術。他日本映画等の娯楽、前回のお話の「寅さんの世界」も全てが消えていくわけではありません。その映像世界は、日本人の心のよりどころとして残っていくでしょう。他にも、学術世界等、日本文化・価値と思われるものはたくさんあります。もちろん、漫画、アニメ等のポップカルチャーも。
そして、これらは全て残り、これらの文化・価値を土台にした、新たな日本独自の文化・価値を築いていくものと思われます。
従って、半ば結論的に言いますと、ボーダーレス社会に突入して、「日本独自の文化・価値」の中で消えていくものはあるが、残っていくものもあり、残ったものはさらに強く「日本的なもの」を表現していくために発展していくでしょう、というお話ししてみればごくごく当たり前の結論に落ち着くのでした。(なんだ、最後だけ聞いておけば、よかったんだ・・・・しっ )
)
そして、このボーダーレス社会のもたらすものは、大きな国際協調の社会です。
サミットや国連をみてもお分かりのように、もはや一国で処理できる問題はどんどん少なくなってきています。環境問題・エネルギー問題等々。
とくに、ここ10年間で超巨大な存在になってきたファンド。もう一国のGDPを超えた存在になりつつあり、ファンドの動きが国際経済に多大な影響を及ぼすようになってきています。
国際的に協調し合わなければ、解決できない問題ばかりです。
今後、30年はどんどんこの傾向が強まっていき、恐らく一国の政治家の相対的な地位はどんどん下がっていくでしょう。
そして、この傾向が強まる過程で危惧するのは、文化摩擦・衝突です。
現在のイスラム文化VS欧米文化をみても分かります。
経済摩擦ならば、ある程度の智恵で回避できるのですが、文化摩擦は大変根っこが深いことから、その解消にはかなり時間がかかるでしょう。
恐らくその解消には、最終的にはお互いの人々の交流(往来)しかないと思われます。
ということは、ボーダーレス社会が進めば進むほど、一時的にその摩擦と衝突は激しくなりますが、大きく数十年の過程の中で、互いの理解が進んでいくということ。
そして、その際に大変重要なことは「和・調和」の普遍的な価値観の醸成です。
即ち、日本人が古来から持っている、普遍的な価値観です。(私は、他者理解と自己主張のバランスではないか、と思っていますが。)
これからの30年は、日本人は大きく海外に飛び出し、この価値観の伝道師となって、国際的な役割を担うべきです。
それが、日本および日本人が負わされた宿命(カルマ)ではないでしょうか?
大国際協調時代、というか宇宙時代、といった方が未来志向のような感じがしますが、この時代における日本および日本人の役割は大変重要なものがあると私は確信しています。
なんだか、最後はITからどんどん離れていって、私の価値観を一方的に伝えているような感じになって、大変恐縮です。
振り返ってみれば、このITシリーズ。ITの進展によって、「パソコン」が消え、「会社」が消え、「学校」が消え、最後に「国」が消えていくお話をしました。
最終的に、このITの進展は、単に便利な世界を開いていくだけでなく、様々な問題点を提示し、われわれの価値観の一大転換を図っていくものであります。が、結局、その先は、なあんだ、よく考えたら、われわれ人類が、自然が、世界が、本来持っているそのものの意味を深化させ、より本来的なものを求めていく動きであることがわかります。
結局、悩み悩み一周回って、もとの位置に戻ってくるような感覚がありますが、実はそのもとの位置が、以前の位置から遥かに高い位置になっている、そんな感覚なんです。
もう一度、「自分」と「世界」の関係を深く深く探ってみてください。
結局、そのことがITの進化なんだと思います。
そして、その先に必ず世界平和が待っているはず、と私は信じています。
なんだか、ようやくシリーズの最終回のような雰囲気になってきましたね。え?何?無理やり終わらせてるだけじゃん・・・・・・・そのとおり!!ピンポンです。シリーズの大団円です。(あー、よかったよかった、ようやく終わりだよ。ふう )
)
では、皆さん、さような・・・・
あ、ちょっと待って待って。そう言えば、このシリーズの⑤の冒頭(http://katsu.i-ra.jp/e1771.html)で、「なぜ、この動向予測が数年先ではなく、10年~30年になっているのか」という宿題を皆さんに出していましたよね。
皆さん、そのわけが分かりましたか。
え?なになに・・・数年先だと間違ったことが言えないけど、10年~30年ならば、少々大胆なこと言ってごまかしても大丈夫だから・・・・・・・・そうですね。確かにそうですね。(ん、スルドイ )
)
でも私がこうした一番の理由は・・・・
10年~30年経てば、皆さんがこの話しを忘れてしまうから、ですよ 。
。
じゃあ、皆さん、よかったら10年~30年後に、この同じ話題で、この話しを検証してみたいと思います。
但し、皆さんと私が覚えていたら、ね 。
。
では、皆さん、10年~30年後に。謝謝。再見。


第2回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1540.html
第3回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1662.html
第4回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1703.html
第5回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1771.html
第6回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1885.html
第7回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e1940.html
第8回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2295.html
第9回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e2479.html
第10回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3452.html
第11回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e3603.html
第12回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4128.html
第13回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4178.html
第14回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4216.html
第15回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4974.html
第16回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e4996.html
第17回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e5080.html
前回のお話 → http://katsu.i-ra.jp/e6034.html
さあて、皆さん、4ヶ月弱にわたって、この回で19回となったこのシリーズ、実は今回が最終回です。と、いいますか、このシリーズは続けていくとどれだけでも続いていってしまいますから、この辺でひとまず大団円を迎えさせることにします。(ま、無理強いですが、一区切り。)
前回から1ヶ月近く経ってしまいましたので、少し振り返りますと、「ボーダーレス社会によって、日本独自の文化・価値の中で、名辞以前の感性空間等、言葉に表しにくい文化・価値が消えていってしまうだろう。」というお話をしていました。
そして、最終回の今回は、ボーダーレス社会の中で残り、さらに強くなっていく、日本独自の文化・価値についてお話してまいります。
さて、日本人が、それがないと生きていけない、生きてても意味がない、と思える文化・価値、または諸外国からみても、それが日本および日本人だと強く思えるもの。これは「ボーダーレス社会」になっても必ず残ります。
むしろ、「ボーダーレス社会」になればなるほど強く意識され、日本人のメンタリティに強く強く刻まれていくでしょう。日本人のアイデンティティ、存在理由(レゾンデートル)ですから。
例えば、能・歌舞伎・雅楽・華道・茶道・落語・漫才等々の芸能、日本画・陶器等々の芸術。他日本映画等の娯楽、前回のお話の「寅さんの世界」も全てが消えていくわけではありません。その映像世界は、日本人の心のよりどころとして残っていくでしょう。他にも、学術世界等、日本文化・価値と思われるものはたくさんあります。もちろん、漫画、アニメ等のポップカルチャーも。
そして、これらは全て残り、これらの文化・価値を土台にした、新たな日本独自の文化・価値を築いていくものと思われます。
従って、半ば結論的に言いますと、ボーダーレス社会に突入して、「日本独自の文化・価値」の中で消えていくものはあるが、残っていくものもあり、残ったものはさらに強く「日本的なもの」を表現していくために発展していくでしょう、というお話ししてみればごくごく当たり前の結論に落ち着くのでした。(なんだ、最後だけ聞いておけば、よかったんだ・・・・しっ
 )
)そして、このボーダーレス社会のもたらすものは、大きな国際協調の社会です。
サミットや国連をみてもお分かりのように、もはや一国で処理できる問題はどんどん少なくなってきています。環境問題・エネルギー問題等々。
とくに、ここ10年間で超巨大な存在になってきたファンド。もう一国のGDPを超えた存在になりつつあり、ファンドの動きが国際経済に多大な影響を及ぼすようになってきています。
国際的に協調し合わなければ、解決できない問題ばかりです。
今後、30年はどんどんこの傾向が強まっていき、恐らく一国の政治家の相対的な地位はどんどん下がっていくでしょう。
そして、この傾向が強まる過程で危惧するのは、文化摩擦・衝突です。
現在のイスラム文化VS欧米文化をみても分かります。
経済摩擦ならば、ある程度の智恵で回避できるのですが、文化摩擦は大変根っこが深いことから、その解消にはかなり時間がかかるでしょう。
恐らくその解消には、最終的にはお互いの人々の交流(往来)しかないと思われます。
ということは、ボーダーレス社会が進めば進むほど、一時的にその摩擦と衝突は激しくなりますが、大きく数十年の過程の中で、互いの理解が進んでいくということ。
そして、その際に大変重要なことは「和・調和」の普遍的な価値観の醸成です。
即ち、日本人が古来から持っている、普遍的な価値観です。(私は、他者理解と自己主張のバランスではないか、と思っていますが。)
これからの30年は、日本人は大きく海外に飛び出し、この価値観の伝道師となって、国際的な役割を担うべきです。
それが、日本および日本人が負わされた宿命(カルマ)ではないでしょうか?
大国際協調時代、というか宇宙時代、といった方が未来志向のような感じがしますが、この時代における日本および日本人の役割は大変重要なものがあると私は確信しています。
なんだか、最後はITからどんどん離れていって、私の価値観を一方的に伝えているような感じになって、大変恐縮です。
振り返ってみれば、このITシリーズ。ITの進展によって、「パソコン」が消え、「会社」が消え、「学校」が消え、最後に「国」が消えていくお話をしました。
最終的に、このITの進展は、単に便利な世界を開いていくだけでなく、様々な問題点を提示し、われわれの価値観の一大転換を図っていくものであります。が、結局、その先は、なあんだ、よく考えたら、われわれ人類が、自然が、世界が、本来持っているそのものの意味を深化させ、より本来的なものを求めていく動きであることがわかります。
結局、悩み悩み一周回って、もとの位置に戻ってくるような感覚がありますが、実はそのもとの位置が、以前の位置から遥かに高い位置になっている、そんな感覚なんです。
もう一度、「自分」と「世界」の関係を深く深く探ってみてください。
結局、そのことがITの進化なんだと思います。
そして、その先に必ず世界平和が待っているはず、と私は信じています。
なんだか、ようやくシリーズの最終回のような雰囲気になってきましたね。え?何?無理やり終わらせてるだけじゃん・・・・・・・そのとおり!!ピンポンです。シリーズの大団円です。(あー、よかったよかった、ようやく終わりだよ。ふう
 )
)では、皆さん、さような・・・・
あ、ちょっと待って待って。そう言えば、このシリーズの⑤の冒頭(http://katsu.i-ra.jp/e1771.html)で、「なぜ、この動向予測が数年先ではなく、10年~30年になっているのか」という宿題を皆さんに出していましたよね。
皆さん、そのわけが分かりましたか。
え?なになに・・・数年先だと間違ったことが言えないけど、10年~30年ならば、少々大胆なこと言ってごまかしても大丈夫だから・・・・・・・・そうですね。確かにそうですね。(ん、スルドイ
 )
)でも私がこうした一番の理由は・・・・
10年~30年経てば、皆さんがこの話しを忘れてしまうから、ですよ
 。
。じゃあ、皆さん、よかったら10年~30年後に、この同じ話題で、この話しを検証してみたいと思います。
但し、皆さんと私が覚えていたら、ね
 。
。では、皆さん、10年~30年後に。謝謝。再見。