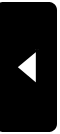「雑感」の記事一覧
スポンサーサイト
うーん、残念。AMI号乗船できず・・・
27日にAMI号乗船できると心躍っていましが、仕事が入りました。
なんとも残念・・・・・Σ( ̄⊥ ̄lll)・・・・・
ま、仕方ないね。また、いつでも乗れますからね。
さ、それよりも21日が重要です!
21日は、また一部上場の超巨大企業への2回目のプレゼンです。
前回、好評でしたので、今回は、さらに進化したものを見せないと・・・・・。
うーん、どうなりますか。
なんとも残念・・・・・Σ( ̄⊥ ̄lll)・・・・・
ま、仕方ないね。また、いつでも乗れますからね。
さ、それよりも21日が重要です!
21日は、また一部上場の超巨大企業への2回目のプレゼンです。
前回、好評でしたので、今回は、さらに進化したものを見せないと・・・・・。
うーん、どうなりますか。
イーラはすばらしい仲間ですね
前回の記事にたくさんの方から励ましのコメントをいただき、大変感謝申し上げます。
感激しています。
ありがとうございます。
ようやく実家から帰ってまいりました。
皆さんの励ましのお陰で、母の手術は大成功。術後の結果も良好で、大手術の割には、もう明日から歩行が可能なくらいになっています。
昨夜は、私も母と同じ病院の一室で一夜を過ごしました。
が、私の手はほとんど必要なく、看護婦さんが30分ごとに部屋に来て介護してくださるので、私は母のベッドの横の小さな長机に毛布と掛け布団と枕を運んでもらい、グーグーと高いびきをかいて寝ていたようです。(母によると)
母の容態は手術前とまったく異なり、以前の気丈な状況に戻り、元気を急速に回復している様子。もうすっかり心配はいりません。
ほんとうによかったよかった・・・(^^)。ほっと安堵しました。
かえって、私は妹から、兄貴は寝に帰っってきたと思われ・・・・えへへ・・・普段の睡眠不足がすっかり解消されたのでした(笑)。
また、一部上場企業へのプレゼンも大成功でして、次回のミーティングでさらに案件を詰めていくことになりました。これは面白いことになりそうです。
まあ、なんとか二つの案件がうまく運んだのも、イーラの皆さんの応援の賜物です。
イーラってほんとにいい仲間ですね。
本当に本当にありがとう・・・・・多謝多謝。
これからもよろしくお願い申し上げます。
感激しています。
ありがとうございます。
ようやく実家から帰ってまいりました。
皆さんの励ましのお陰で、母の手術は大成功。術後の結果も良好で、大手術の割には、もう明日から歩行が可能なくらいになっています。
昨夜は、私も母と同じ病院の一室で一夜を過ごしました。
が、私の手はほとんど必要なく、看護婦さんが30分ごとに部屋に来て介護してくださるので、私は母のベッドの横の小さな長机に毛布と掛け布団と枕を運んでもらい、グーグーと高いびきをかいて寝ていたようです。(母によると)
母の容態は手術前とまったく異なり、以前の気丈な状況に戻り、元気を急速に回復している様子。もうすっかり心配はいりません。
ほんとうによかったよかった・・・(^^)。ほっと安堵しました。
かえって、私は妹から、兄貴は寝に帰っってきたと思われ・・・・えへへ・・・普段の睡眠不足がすっかり解消されたのでした(笑)。
また、一部上場企業へのプレゼンも大成功でして、次回のミーティングでさらに案件を詰めていくことになりました。これは面白いことになりそうです。
まあ、なんとか二つの案件がうまく運んだのも、イーラの皆さんの応援の賜物です。
イーラってほんとにいい仲間ですね。
本当に本当にありがとう・・・・・多謝多謝。
これからもよろしくお願い申し上げます。
うーん、どうも落ち着かない・・・・・
今日は、大きな出来事が二つ。
一つ目は、一部上場、超大手企業へのプレゼンが、10時からある。これは、もちろん、弊社にとって大変大きなチャンス。
二つ目は、私事。母の大きな手術が、本日あり。医師はそんなに大きな問題にはならないだろう、とは言っているらしいが、やはり心配。
この二つの出来事。一見、つながりのないような気もするが・・・・・。なぜ、よりによって本日なのか。
ということで、本日は午前のプレゼンが終わり次第、急遽、実家へ帰省。
何事もなければよいが・・・・。
一つ目は、一部上場、超大手企業へのプレゼンが、10時からある。これは、もちろん、弊社にとって大変大きなチャンス。
二つ目は、私事。母の大きな手術が、本日あり。医師はそんなに大きな問題にはならないだろう、とは言っているらしいが、やはり心配。
この二つの出来事。一見、つながりのないような気もするが・・・・・。なぜ、よりによって本日なのか。
ということで、本日は午前のプレゼンが終わり次第、急遽、実家へ帰省。
何事もなければよいが・・・・。
テーマ=「楽しみの可能性」
「楽しいという価値観は人それぞれだと思う。
たとえば、人は笑っていても楽しいとは限らない。
人は、そして自分は何が楽しいと思っているのかを、写真を撮ることで確認してみたい。
風景、人、動物、物体、いろいろなものを撮る中で、自分の楽しみの可能性を探ってみたいと思う。」
あれ、いったい何?と思われた方もいらっしゃるでしょう!
実は今日は、写真講座上級編の初日でした。(あとで今日の状況写真はアップします。)
タラチャン(多々良講師)にいろいろわかりやすく講義してもらって大変楽しい内容でした。
そして、本日の一番のポイントは、「何のために写真を撮るか」です。
すなわち、「自分は何をテーマに写真を撮るか」。これを文章にしてみようということでした。
そこで、冒頭の文章になったわけです。
さて、このテーマで私は写真を撮っていくわけですが、果たしてテーマについていけるかどうか・・・。
まあ、文章だけはかっこつけましたが、きっと写真はかなり低レベルでしょう。
でもそんときはそんとき。テーマの中の可能性が低かったということで、逃げをうつわけで。
要するにまずかったときのことも考えたテーマでした。
なんだか軟弱やなあ。
・・・・・とにかく撮ってみます。ブログにもアップしますので、皆さん、よろしくご指導ください。
ではまた。
追伸:そろそろ一眼レフ買わんといかんねえ。
たとえば、人は笑っていても楽しいとは限らない。
人は、そして自分は何が楽しいと思っているのかを、写真を撮ることで確認してみたい。
風景、人、動物、物体、いろいろなものを撮る中で、自分の楽しみの可能性を探ってみたいと思う。」
あれ、いったい何?と思われた方もいらっしゃるでしょう!
実は今日は、写真講座上級編の初日でした。(あとで今日の状況写真はアップします。)
タラチャン(多々良講師)にいろいろわかりやすく講義してもらって大変楽しい内容でした。
そして、本日の一番のポイントは、「何のために写真を撮るか」です。
すなわち、「自分は何をテーマに写真を撮るか」。これを文章にしてみようということでした。
そこで、冒頭の文章になったわけです。
さて、このテーマで私は写真を撮っていくわけですが、果たしてテーマについていけるかどうか・・・。
まあ、文章だけはかっこつけましたが、きっと写真はかなり低レベルでしょう。
でもそんときはそんとき。テーマの中の可能性が低かったということで、逃げをうつわけで。
要するにまずかったときのことも考えたテーマでした。
なんだか軟弱やなあ。
・・・・・とにかく撮ってみます。ブログにもアップしますので、皆さん、よろしくご指導ください。
ではまた。
追伸:そろそろ一眼レフ買わんといかんねえ。
憧れの温泉地「由布院」の秘密
阿部進先生(通称カバゴン)
本当にすごい先生に会った。これぞホンモノと言える人である。
今回は2回目の出会いであったが、前回より遥かに長く2人でお話する機会があった。
彼と半日お話し、大仁から三島駅まで私の車で彼をお送りした間もずっと彼とお話した。
教育の話、社会の話、時代の話、そして齢77歳の彼が教育を社会を変革しようと試みている活動について。
大変感銘した。
彼の名は、阿部進。通称カバゴン先生である。
私より上の世代の方は、よーくご存知の名前であろう。1970年代のテレビ・マスコミにはしょっちゅう出ていた。売れっ子の教育評論家である。詳細はWikiPediaのこのページか彼のHPをご覧あれ。
彼の見識の高さはすばらしく、現代社会の、そして現代教育の病根をするどく抉っている。人間関係の疎の部分、そこからくる教育のひずみ、地域としての教育力の欠如・・・。
そして、彼はその問題意識をベースに、その解決策を、松田道雄というコンセプトクリエーターが考え出した「だがしや楽校」に「カバゴン」という地域通貨(エコマネーetc)を連携させる形で提示する。
彼が考える「だがしや楽校」、それは「カバゴン」という仮想マネーからはじまる。
いわゆる昔懐かしい駄菓子屋なんだが、この駄菓子屋、今までのものとチョト違う。
お金で駄菓子が買えるお店ではない。では何で買うか。それが「カバゴン」である。1カバゴン=1円の仮想マネー。
「カバゴン」は、子供たちの遊び(昔ながらの、地域で皆がやった、手や体を使い、土や自然に触れ合った遊び)、学習(子供に対して親・先生・地域のおじさん・おばさん・おじいちゃん・おばあちゃんが教える勉強)、仕事(子供がやる親や地域の人たちのお手伝い・介護やお使い等々)、に参加した場合の対価として支払われる。
そして、そのカバゴンで、駄菓子が買える。(「やおきん」という駄菓子の卸会社が全面的に支援している。)
駄菓子はどれも1円、5円、10円、20円・・・・・高くても400円くらいの大変安いもの。普通の駄菓子屋では置いても儲けにはつながらない。だから普通の駄菓子屋にはない。ここに子供たちを魅了するポイントがある。
私は、2回、「だがしや楽校」を経験させてもらった。つまり、駄菓子屋の店番を2回(半日×2回だから1日)させてもらった。
どの子も「1カバゴン」をもって駄菓子1個と交換するときの笑顔笑顔・・・・。お父さんお母さんから1円もらっても少しもうれしいと思わないであろう「現代っ子」(実はこの「現代っ子」という言葉は、阿部先生の造語からはじまって日本全国に広がった)。その子たちが、1カバゴンをもらって嬉々としている。おそらく「現代っ子」は、今では1万円もらってもニコともしないのではないか?
そのお金に対するありがたみが、カバゴンで見事によみがえっている。しかも、そのカバゴンは、子供たちが本来おこなうべき、遊び、学習、仕事、を子供たち本来の自然な形で行わせている。「現代っ子」が身の丈にふさわしい通貨の価値をともなって。
カバゴン先生の考える「だがしや楽校」は地域活性化のキーになる可能性が十分にあると、私は思っている。三島、沼津、富士、富士宮、御殿場、修善寺、草薙・・・・・等々。私が現在、事業展開を行っている各地域で、商店街が疲弊しているのを何度も目の当たりにしている。各商店街に人は寄らずシャッター街はもう日常の光景に溶け込んでいる。
私が教育事業を始めるきっかけの一つに、街に子供の姿を取り戻したい、という思いもあった。子供が街にあふれれば、当然、その親の姿が街に現れる。親が現れれば、街で買い物をはじめる。よい商品、商店の口コミがはじまる。商店街に駄菓子屋があれば、そして「だがしや楽校」が「カバゴン」を伴って機能すれば・・・・・。子供たちが嬉々として、遊び、学び、働く、「カバゴン」をもって。介護が必要な方には、「カバゴン」を介して、子供たちがサポートしはじめる。そして、子供と大人の会話がはじまる。
そんな夢のような光景をカバゴン先生は、まさに現実のものにしようとしている。もう横浜のいくつかの区では、「カバゴン」が運用されつつあり、成功事例が出てきている。
私は、そんなカバゴン先生がとても魅力的に思えた。大きな感銘を抱いた。そして、私も「だがしや楽校」をこの静岡に広めたいと思った。社の事業としてもサポートできないか、と考えている。
「だがしや楽校」は子供の将来を大きく変える。そのことは、日本の将来を変えることに必ずつながる・・・。
カバゴン先生の活動、だがしや楽校の活動の詳細はこちらをクリック。

今回は2回目の出会いであったが、前回より遥かに長く2人でお話する機会があった。
彼と半日お話し、大仁から三島駅まで私の車で彼をお送りした間もずっと彼とお話した。
教育の話、社会の話、時代の話、そして齢77歳の彼が教育を社会を変革しようと試みている活動について。
大変感銘した。
彼の名は、阿部進。通称カバゴン先生である。
私より上の世代の方は、よーくご存知の名前であろう。1970年代のテレビ・マスコミにはしょっちゅう出ていた。売れっ子の教育評論家である。詳細はWikiPediaのこのページか彼のHPをご覧あれ。
彼の見識の高さはすばらしく、現代社会の、そして現代教育の病根をするどく抉っている。人間関係の疎の部分、そこからくる教育のひずみ、地域としての教育力の欠如・・・。
そして、彼はその問題意識をベースに、その解決策を、松田道雄というコンセプトクリエーターが考え出した「だがしや楽校」に「カバゴン」という地域通貨(エコマネーetc)を連携させる形で提示する。
彼が考える「だがしや楽校」、それは「カバゴン」という仮想マネーからはじまる。
いわゆる昔懐かしい駄菓子屋なんだが、この駄菓子屋、今までのものとチョト違う。
お金で駄菓子が買えるお店ではない。では何で買うか。それが「カバゴン」である。1カバゴン=1円の仮想マネー。
「カバゴン」は、子供たちの遊び(昔ながらの、地域で皆がやった、手や体を使い、土や自然に触れ合った遊び)、学習(子供に対して親・先生・地域のおじさん・おばさん・おじいちゃん・おばあちゃんが教える勉強)、仕事(子供がやる親や地域の人たちのお手伝い・介護やお使い等々)、に参加した場合の対価として支払われる。
そして、そのカバゴンで、駄菓子が買える。(「やおきん」という駄菓子の卸会社が全面的に支援している。)
駄菓子はどれも1円、5円、10円、20円・・・・・高くても400円くらいの大変安いもの。普通の駄菓子屋では置いても儲けにはつながらない。だから普通の駄菓子屋にはない。ここに子供たちを魅了するポイントがある。
私は、2回、「だがしや楽校」を経験させてもらった。つまり、駄菓子屋の店番を2回(半日×2回だから1日)させてもらった。
どの子も「1カバゴン」をもって駄菓子1個と交換するときの笑顔笑顔・・・・。お父さんお母さんから1円もらっても少しもうれしいと思わないであろう「現代っ子」(実はこの「現代っ子」という言葉は、阿部先生の造語からはじまって日本全国に広がった)。その子たちが、1カバゴンをもらって嬉々としている。おそらく「現代っ子」は、今では1万円もらってもニコともしないのではないか?
そのお金に対するありがたみが、カバゴンで見事によみがえっている。しかも、そのカバゴンは、子供たちが本来おこなうべき、遊び、学習、仕事、を子供たち本来の自然な形で行わせている。「現代っ子」が身の丈にふさわしい通貨の価値をともなって。
カバゴン先生の考える「だがしや楽校」は地域活性化のキーになる可能性が十分にあると、私は思っている。三島、沼津、富士、富士宮、御殿場、修善寺、草薙・・・・・等々。私が現在、事業展開を行っている各地域で、商店街が疲弊しているのを何度も目の当たりにしている。各商店街に人は寄らずシャッター街はもう日常の光景に溶け込んでいる。
私が教育事業を始めるきっかけの一つに、街に子供の姿を取り戻したい、という思いもあった。子供が街にあふれれば、当然、その親の姿が街に現れる。親が現れれば、街で買い物をはじめる。よい商品、商店の口コミがはじまる。商店街に駄菓子屋があれば、そして「だがしや楽校」が「カバゴン」を伴って機能すれば・・・・・。子供たちが嬉々として、遊び、学び、働く、「カバゴン」をもって。介護が必要な方には、「カバゴン」を介して、子供たちがサポートしはじめる。そして、子供と大人の会話がはじまる。
そんな夢のような光景をカバゴン先生は、まさに現実のものにしようとしている。もう横浜のいくつかの区では、「カバゴン」が運用されつつあり、成功事例が出てきている。
私は、そんなカバゴン先生がとても魅力的に思えた。大きな感銘を抱いた。そして、私も「だがしや楽校」をこの静岡に広めたいと思った。社の事業としてもサポートできないか、と考えている。
「だがしや楽校」は子供の将来を大きく変える。そのことは、日本の将来を変えることに必ずつながる・・・。
カバゴン先生の活動、だがしや楽校の活動の詳細はこちらをクリック。

相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち・・・
本当に日本の株、世界の株はどうなってしまったのでしょうか?
アメリカのサブプライムローンから始まった、この悲観の連鎖は大きなリセッション(世界同時不況)の兆しなんでしょうか?
ま、おそらくその答えは誰も出せないと思います。これこそ神のみぞ知る。運を天にまかせるしかなさそうです。
株式投資をやられている方は、おそらく今は天を仰いでいるでしょう!
おお・・・神よ、どうしてわれをこのように苦しめ給うのか?
でも、ここでわれわれ人類は次の言葉に象徴される叡智ももっていることに気づかなければ・・・・。
曰く。
「相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟する」
まさに、この世に漂う悲観の中にこそ、ひそかに相場が形成されつつあるのかもしれません。長期投資をお考えの諸兄は、まさに今が買いのタイミング??いやいや、私は相場師ではないのでよく分かりませんが、その時機が近づいているように思います。
なんにしましても日本の超低金利の中、また年金事情がいよいよ不透明になりつつある今、やはりわれわれの資産を少しでも守り、または守るべき資産を持ち合わせていない私のような人間でも、今後の蓄えを少しでも積み上げていくためには・・・・・。
やはり投資しかありません。
日比谷公園の設計で知られる本多静六博士の「おカネ」訓をご紹介します。
一、金儲けは理屈でなくて、実際である。
計画でなくて、努力である。
予算でなくて、結果である。
一、絶対安全のみ期していては、いかなる投資にも、手も足も出ない。
一、好景気、楽観時代には思い切った勤倹貯蓄。
不景気、悲観時代には思い切った投資。
博士が1950年に著した「私の財産告白」よりの言葉です。
さらに、博士はこの書の中で、「四分の一貯金法」なるものを紹介しています。
貯金=通常収入×1/4+臨時収入×10/10
この数式が四分の一貯金法。
月給などの四分の一と賞与などの全額を貯金に回し、発生した利子も通常収入として四分の一を貯金に残す。
堅実な生活の勧めとして、「七割五分の生活」として伝えています。
しかし、四分の一貯金は単なる倹約ではなく、投資をはじめるための「雪だるまの芯」(=原資)づくりの意味。
先の書によれば、博士は蓄えたお金でまず私鉄株に投資。その後、投資先はガスや製紙、紡績、銀行など三十以上の業種にわたります。
博士曰く、「それぞれ優良株を選んで危険の分散に心がけた」。すなわち、今で言うポートフォリオ理論です。
博士は25歳のときから四分の一貯金をはじめました。
それに先立つドイツ留学で指導を受けた教授から言われた次の言葉がきっかけになっています。
「財産がなければ精神の独立はおぼつかない」。
われわれも見習いたいものです。(いや、もう皆さんはやってらっしゃるでしょうから、私自身への戒めとしてブログに残しておくことにします。あーあ、がんばろっとヾ(´ε`;)ゝ ふぅ。。。)

アメリカのサブプライムローンから始まった、この悲観の連鎖は大きなリセッション(世界同時不況)の兆しなんでしょうか?
ま、おそらくその答えは誰も出せないと思います。これこそ神のみぞ知る。運を天にまかせるしかなさそうです。
株式投資をやられている方は、おそらく今は天を仰いでいるでしょう!
おお・・・神よ、どうしてわれをこのように苦しめ給うのか?
でも、ここでわれわれ人類は次の言葉に象徴される叡智ももっていることに気づかなければ・・・・。
曰く。
「相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟する」
まさに、この世に漂う悲観の中にこそ、ひそかに相場が形成されつつあるのかもしれません。長期投資をお考えの諸兄は、まさに今が買いのタイミング??いやいや、私は相場師ではないのでよく分かりませんが、その時機が近づいているように思います。
なんにしましても日本の超低金利の中、また年金事情がいよいよ不透明になりつつある今、やはりわれわれの資産を少しでも守り、または守るべき資産を持ち合わせていない私のような人間でも、今後の蓄えを少しでも積み上げていくためには・・・・・。
やはり投資しかありません。
日比谷公園の設計で知られる本多静六博士の「おカネ」訓をご紹介します。
一、金儲けは理屈でなくて、実際である。
計画でなくて、努力である。
予算でなくて、結果である。
一、絶対安全のみ期していては、いかなる投資にも、手も足も出ない。
一、好景気、楽観時代には思い切った勤倹貯蓄。
不景気、悲観時代には思い切った投資。
博士が1950年に著した「私の財産告白」よりの言葉です。
さらに、博士はこの書の中で、「四分の一貯金法」なるものを紹介しています。
貯金=通常収入×1/4+臨時収入×10/10
この数式が四分の一貯金法。
月給などの四分の一と賞与などの全額を貯金に回し、発生した利子も通常収入として四分の一を貯金に残す。
堅実な生活の勧めとして、「七割五分の生活」として伝えています。
しかし、四分の一貯金は単なる倹約ではなく、投資をはじめるための「雪だるまの芯」(=原資)づくりの意味。
先の書によれば、博士は蓄えたお金でまず私鉄株に投資。その後、投資先はガスや製紙、紡績、銀行など三十以上の業種にわたります。
博士曰く、「それぞれ優良株を選んで危険の分散に心がけた」。すなわち、今で言うポートフォリオ理論です。
博士は25歳のときから四分の一貯金をはじめました。
それに先立つドイツ留学で指導を受けた教授から言われた次の言葉がきっかけになっています。
「財産がなければ精神の独立はおぼつかない」。
われわれも見習いたいものです。(いや、もう皆さんはやってらっしゃるでしょうから、私自身への戒めとしてブログに残しておくことにします。あーあ、がんばろっとヾ(´ε`;)ゝ ふぅ。。。)

今年も毎週火曜日朝5:55
今年も始まりました。
沼津市倫理法人会のモーニングセミナー。
本日は池田病院の院長先生のお話で、いつものように大変勉強になりました。
倫理法人会という会は本当にすばらしい会です。
経営者の皆さんが、いつも一生懸命に勉強し努力している姿は、私も本当に刺激を受け触発されます。
この倫理法人会は、現在、どんどん会員が増えておりまして、今春はいよいよ伊豆長岡にも作ろうという動きになってきました。
どうやら私もその役員として働くことになりそうです。
この会は決して経営者の方だけでなく、基本的にはどなたでも入会できますので、社員の方でも、もしご興味があれば、一度、モーニングセミナーにオブザーバーとして遠慮なくご参加ください。
実は昨年後半からもうすでに月に2回程度、伊豆長岡で、モーニングセミナーを朝6時から開催しております。私も参加しております。
また、開催の日時等決まりましたら、このブログでもお知らせします。
お近くの方だけでなく、広く伊豆地域の方々はお集まりいただくと、「倫理法人会ってどんな活動しているか」が大変よくご理解いただけると思います。→こちらをクリックしてください
また、大変勉強になる倫理活動と同時に、経営者の方にとっては人脈を広げる大きなチャンスになります。
この会は、商売は商売としてどんどんやっていこう、という趣旨でもありますから、そういう意味ではお仕事のチャンスが、限りなく広がります。(倫理法人会は、全国の4万社以上が所属している組織ですから、しかも倫理法人会の会員は結びつきも深いので、全国のどの会員ともお近づきになるチャンスはあります。)
よろしかったらどんどんご参加ください。
お待ちしています。
p.s.決して「宗教団体」ではありませんので、そこは誤解なさらないようにお願い申し上げます。

沼津市倫理法人会のモーニングセミナー。
本日は池田病院の院長先生のお話で、いつものように大変勉強になりました。
倫理法人会という会は本当にすばらしい会です。
経営者の皆さんが、いつも一生懸命に勉強し努力している姿は、私も本当に刺激を受け触発されます。
この倫理法人会は、現在、どんどん会員が増えておりまして、今春はいよいよ伊豆長岡にも作ろうという動きになってきました。
どうやら私もその役員として働くことになりそうです。
この会は決して経営者の方だけでなく、基本的にはどなたでも入会できますので、社員の方でも、もしご興味があれば、一度、モーニングセミナーにオブザーバーとして遠慮なくご参加ください。
実は昨年後半からもうすでに月に2回程度、伊豆長岡で、モーニングセミナーを朝6時から開催しております。私も参加しております。
また、開催の日時等決まりましたら、このブログでもお知らせします。
お近くの方だけでなく、広く伊豆地域の方々はお集まりいただくと、「倫理法人会ってどんな活動しているか」が大変よくご理解いただけると思います。→こちらをクリックしてください
また、大変勉強になる倫理活動と同時に、経営者の方にとっては人脈を広げる大きなチャンスになります。
この会は、商売は商売としてどんどんやっていこう、という趣旨でもありますから、そういう意味ではお仕事のチャンスが、限りなく広がります。(倫理法人会は、全国の4万社以上が所属している組織ですから、しかも倫理法人会の会員は結びつきも深いので、全国のどの会員ともお近づきになるチャンスはあります。)
よろしかったらどんどんご参加ください。
お待ちしています。
p.s.決して「宗教団体」ではありませんので、そこは誤解なさらないようにお願い申し上げます。
そういえば、高校サッカーの話題がないっすね
やはりイーラは県東部なので、ちょっと縁遠いのかなあ・・・・・。
でも34大会ぶりの決勝進出なんですよね。
静岡県民としては、やっぱり応援しちゃいますよね!!
14日、藤枝東、ガンバレー

でも34大会ぶりの決勝進出なんですよね。
静岡県民としては、やっぱり応援しちゃいますよね!!
14日、藤枝東、ガンバレー

新年おめでとう 今年はいよいよ宇宙ステーション
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
今年はいよいよ宇宙ステーション「きぼう」が建設されます。→http://www.jaxa.jp/
2月には、土井さんがシャトルに搭乗して、船内保管室の打ち上げ。
4月には、星出さんが搭乗して、船内実験室が打ち上げ。船内での利用実験が開始します。
そして、なんと今年の後半から、若田さんが、「きぼう」で、日本人初の宇宙長期滞在に挑みます。
2009年初め、3回目の船外実験プラットフォームと船外パレット打ち上げ。若田さん帰還。
2010年、国際宇宙ステーションが完成します。
土井さんは「きぼうは日本の技術の粋を集めた美しい実験棟。国際宇宙ステーション(ISS)の中で、日本の存在感が示せると思う」と語っています。
なんだか、わくわくしますね。若田さんの宇宙長期滞在が実現し、ISSが完成すれば、宇宙がもっとわれわれの身近になってきます。
ISSの見取り図をみますと、「きぼう」は、ロシアやアメリカの実験棟についでの大きさ。欧州より大きいんですね。下が「きぼう」がISSにドッキングした際のイメージ図です。

2008年はいよいよ宇宙時代の到来です。
皆さん、今年は空の向こうを眺めていてくださいね。
今年も┌|*゜o゜|┘よ┌|*゜0゜|┘ろ┌|*゜-゜|┘し┌|*゜。゜|┘く♪ねー
今年はいよいよ宇宙ステーション「きぼう」が建設されます。→http://www.jaxa.jp/
2月には、土井さんがシャトルに搭乗して、船内保管室の打ち上げ。
4月には、星出さんが搭乗して、船内実験室が打ち上げ。船内での利用実験が開始します。
そして、なんと今年の後半から、若田さんが、「きぼう」で、日本人初の宇宙長期滞在に挑みます。
2009年初め、3回目の船外実験プラットフォームと船外パレット打ち上げ。若田さん帰還。
2010年、国際宇宙ステーションが完成します。
土井さんは「きぼうは日本の技術の粋を集めた美しい実験棟。国際宇宙ステーション(ISS)の中で、日本の存在感が示せると思う」と語っています。
なんだか、わくわくしますね。若田さんの宇宙長期滞在が実現し、ISSが完成すれば、宇宙がもっとわれわれの身近になってきます。
ISSの見取り図をみますと、「きぼう」は、ロシアやアメリカの実験棟についでの大きさ。欧州より大きいんですね。下が「きぼう」がISSにドッキングした際のイメージ図です。

2008年はいよいよ宇宙時代の到来です。
皆さん、今年は空の向こうを眺めていてくださいね。
今年も┌|*゜o゜|┘よ┌|*゜0゜|┘ろ┌|*゜-゜|┘し┌|*゜。゜|┘く♪ねー
今年の締めくくり「歎異抄と現代」
さて、今年は皆さんにとってどんな年だったでしょうか?
今年も例年にたがわずいろいろな事件や事故、出来事がありました。
「偽」の年と言われましたが、それは何も今年が特別そうだったわけではなく、90年代後半から21世紀に入って、この日本のあちらこちらに見受けられたことだったのではないか、という気がします。
自分も含めた日本人が「大きく動揺・混乱しているさま」が見受けられます。80年代の日本は、今から振り返ると「自信にあふれていた」のではないでしょうか?(見せ掛けの「自信」だったと思いますが・・・。)
わずか十数年でこの国は自信だけではなく、「心」を失いつつある気がします。
きっとこの国は大きく変革しなければならないタイミングに差し掛かっているにもかかわらず、変革の意気地がなくただいたずらにその場しのぎを行い貴重な時間が無駄に過ぎていってしまっている。そういう気がします。
もちろん、他人事でなく自分も含めて、のことですが。
さて、このような状況の中で、今年も様々な方々にお会いしました。そして、その出会いを通して「心」に残った言葉は何か、と考えましたところ、この方の言葉がもっとも残っています。
五木寛之氏の言葉の数々
「世界の精神状況が躁の時代から鬱の時代に入った」
「欝を悲しいもの、否定的なもの、ととらえるのはどうか」
「悲しいですか、という挨拶もあっていいのではないか」
「弱い人間というのは、むしろうたれづよく、『あーあ』と嘆息することはむしろごく自然な感性である」
最近、氏が発端となってブームになったものがあります。
それは、「歎異抄(たんにしょう)」。ご存知の方は多いと思います。親鸞の教えが書かれた「日本の聖書」です。
私の実家も浄土真宗に帰依していますから、私も幼時から親鸞の教えを、その意味も分からぬまま唱えておりました。
そして、物心がつき、人生の拠って立つものや世の中のことわりを探しはじめた際に、すこーしずつ気になり始めた人物が、やはり親鸞その人でありました。
日本人が自信を失い、心をなくしつつある今、「歎異抄」がブームになりつつあるということは、私の中で大変符合し合点するものがあります。
私は思います。「日本人の心のよりどころは歎異抄ではないか」。
その昔、日本の哲学者、西田幾多郎は空襲の火災を前に、ほかの書物が燃え尽きても「歎異抄」さえ残ればいいと言い切ったそうです。
歎異抄こそ日本の原点。われわれが世界に誇るべき日本人の普遍的価値観だと思われます。まさに日本人が取り戻すべき「心」がここにあります。
西田幾多郎は「哲学の動機は人生の悲哀でなければならない」と言ったそうですが、昔から日本人の心の態様は人生の悲哀を切り捨てるものではなく、人生の中に内包され共にありそれに備え対峙し過ごしていく価値観がありました。
アメリカを中心とした昨今のグローバリズムや市場経済の流れにおいて、もっとも重要なことは「負を切り捨て、正に変えていくこと」ではなく、「負を負として内包しともにありともに歩む心の態様」ではないか、と思っております。
キリスト教的世界観が限界となり、人々の心の支柱が流動化し不安定化している現代、日本人の果たすべき役割は大変重要なものがあると思っています。
われわれ日本人はわが国を世界から俯瞰し、日本という国が果たすべき役割、また世界に伝えなければならない『心の伝道師』としての日本人の働きについて気づくべきです。
私もこのような問題意識から起業したものですから、起業から10年たった来年に向けて大きく行動していかなければ、と思っています。
手始めに、この年末年始は今までと違いこの三島に残り(というのは、例年は実家の三重県に帰省していましたから)、来年大きく行わなければならない事業の計画書を作成します。年末年始は休んでいられなくなっちゃった・゜゜・(×_×)・゜゜・。 ビエーン
来年はいよいよわが社の雌雄を決すべき年と考えて行動していくこととします。
なんだか、最後は私の決意表明みたいになってしまいましたが、さあ、皆さんは今年はどんな年でしたか?そして、来年はどんな年にしてみたいとお思いですか?
ということで、本年いろいろとお世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。

今年も例年にたがわずいろいろな事件や事故、出来事がありました。
「偽」の年と言われましたが、それは何も今年が特別そうだったわけではなく、90年代後半から21世紀に入って、この日本のあちらこちらに見受けられたことだったのではないか、という気がします。
自分も含めた日本人が「大きく動揺・混乱しているさま」が見受けられます。80年代の日本は、今から振り返ると「自信にあふれていた」のではないでしょうか?(見せ掛けの「自信」だったと思いますが・・・。)
わずか十数年でこの国は自信だけではなく、「心」を失いつつある気がします。
きっとこの国は大きく変革しなければならないタイミングに差し掛かっているにもかかわらず、変革の意気地がなくただいたずらにその場しのぎを行い貴重な時間が無駄に過ぎていってしまっている。そういう気がします。
もちろん、他人事でなく自分も含めて、のことですが。
さて、このような状況の中で、今年も様々な方々にお会いしました。そして、その出会いを通して「心」に残った言葉は何か、と考えましたところ、この方の言葉がもっとも残っています。
五木寛之氏の言葉の数々
「世界の精神状況が躁の時代から鬱の時代に入った」
「欝を悲しいもの、否定的なもの、ととらえるのはどうか」
「悲しいですか、という挨拶もあっていいのではないか」
「弱い人間というのは、むしろうたれづよく、『あーあ』と嘆息することはむしろごく自然な感性である」
最近、氏が発端となってブームになったものがあります。
それは、「歎異抄(たんにしょう)」。ご存知の方は多いと思います。親鸞の教えが書かれた「日本の聖書」です。
私の実家も浄土真宗に帰依していますから、私も幼時から親鸞の教えを、その意味も分からぬまま唱えておりました。
そして、物心がつき、人生の拠って立つものや世の中のことわりを探しはじめた際に、すこーしずつ気になり始めた人物が、やはり親鸞その人でありました。
日本人が自信を失い、心をなくしつつある今、「歎異抄」がブームになりつつあるということは、私の中で大変符合し合点するものがあります。
私は思います。「日本人の心のよりどころは歎異抄ではないか」。
その昔、日本の哲学者、西田幾多郎は空襲の火災を前に、ほかの書物が燃え尽きても「歎異抄」さえ残ればいいと言い切ったそうです。
歎異抄こそ日本の原点。われわれが世界に誇るべき日本人の普遍的価値観だと思われます。まさに日本人が取り戻すべき「心」がここにあります。
西田幾多郎は「哲学の動機は人生の悲哀でなければならない」と言ったそうですが、昔から日本人の心の態様は人生の悲哀を切り捨てるものではなく、人生の中に内包され共にありそれに備え対峙し過ごしていく価値観がありました。
アメリカを中心とした昨今のグローバリズムや市場経済の流れにおいて、もっとも重要なことは「負を切り捨て、正に変えていくこと」ではなく、「負を負として内包しともにありともに歩む心の態様」ではないか、と思っております。
キリスト教的世界観が限界となり、人々の心の支柱が流動化し不安定化している現代、日本人の果たすべき役割は大変重要なものがあると思っています。
われわれ日本人はわが国を世界から俯瞰し、日本という国が果たすべき役割、また世界に伝えなければならない『心の伝道師』としての日本人の働きについて気づくべきです。
私もこのような問題意識から起業したものですから、起業から10年たった来年に向けて大きく行動していかなければ、と思っています。
手始めに、この年末年始は今までと違いこの三島に残り(というのは、例年は実家の三重県に帰省していましたから)、来年大きく行わなければならない事業の計画書を作成します。年末年始は休んでいられなくなっちゃった・゜゜・(×_×)・゜゜・。 ビエーン
来年はいよいよわが社の雌雄を決すべき年と考えて行動していくこととします。
なんだか、最後は私の決意表明みたいになってしまいましたが、さあ、皆さんは今年はどんな年でしたか?そして、来年はどんな年にしてみたいとお思いですか?
ということで、本年いろいろとお世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。

メリークリスマス!(ミシュランつづき)
私は仏教徒(?)ですが、メリークリスマス、ですね
さて、先日、ミシュランガイド東京の話をしましたが、その際、東京の三ツ星レストランがどこなのか?という話をしました。
ようやくわかりました。もう知っている人は知っていると思いますが。
以下の8レストランです。
店名 所在地 料理の種類
かんだ 港区 日本料理
カンテサンス 港区 現代風フランス料理
小十 中央区 日本料理
ジョエル・ロブション 目黒区 現代風フランス料理
すきや橋 次郎 中央区 日本料理 寿司
鮨 水谷 中央区 日本料理 寿司
濱田家 中央区 日本料理
ロオジエ 中央区 フランス料理
という具合です。今日のイブは、きっともう何日も前からのお客様の予約で一杯でしょうね。
一度でいいから、こういうイブのような日に、この三ツ星レストランで食事をしたいものです。
あーあ、いつになることやら・・・・・・
ということで、皆さん、素敵なクリマスイブの夜をお過ごしください。
Merry Christmas


さて、先日、ミシュランガイド東京の話をしましたが、その際、東京の三ツ星レストランがどこなのか?という話をしました。
ようやくわかりました。もう知っている人は知っていると思いますが。
以下の8レストランです。
店名 所在地 料理の種類
かんだ 港区 日本料理
カンテサンス 港区 現代風フランス料理
小十 中央区 日本料理
ジョエル・ロブション 目黒区 現代風フランス料理
すきや橋 次郎 中央区 日本料理 寿司
鮨 水谷 中央区 日本料理 寿司
濱田家 中央区 日本料理
ロオジエ 中央区 フランス料理
という具合です。今日のイブは、きっともう何日も前からのお客様の予約で一杯でしょうね。
一度でいいから、こういうイブのような日に、この三ツ星レストランで食事をしたいものです。
あーあ、いつになることやら・・・・・・

ということで、皆さん、素敵なクリマスイブの夜をお過ごしください。
Merry Christmas


ミシュランガイド東京
もう皆さん、ご存知ですよね。「ミシュランガイド東京」が発刊されました。大変な人気だそうですね。
ところで昨日、「第12回静岡アジア・太平洋学術フォーラム」に参加してきました。このフォーラムは、実は静岡で開かれる国際会議としては超一流だと思っています。まず東京でもなかなかお目にかかれない、一流の学術関係者、評論家、経営者が一同に会して、アジア・太平洋の国際問題を語り合いディスカッションします。私は3年前の第10回から参加していますが、第10回、第11回、そして今回とも大満足。こんな上質の会議が無料で聞けるなんて。しかも誰でも参加できるんですよ。静岡県は相当がんばっていると思います。このフォーラムに関するお話はまた別途ご紹介します。非常に有意義なお話でしたので、ぜひとも皆さんにご紹介しようと思いますから、またの機会に、よろしかったら私のブログをごらんになってみてください。
さて、今日お話したいことは「ミシュランガイド東京」のことです。なぜ、「第12回静岡アジア・太平洋学術フォーラム」のお話をしたか、といいますと、その国際会議の中で、国際比較として「ミシュランガイド東京」のデータが紹介されました。
以下にご紹介します。
地名 一ツ星以上のレストランの数 三ツ星レストランの数
TOKYO 191 8
PARIS 97 10
NEWYORK 54 3
LONDON 50 1
SANFRANCISCO 42 1
ということで、東京の数はすごいですね。
東京の食のレベルはかなり高いといえるのかもしれません。
また、昨今の国際的な和食ブームと符合します。
ちなみに国際会議の中で中国の食についても触れていましたが、「ミシュラン」ではまったく評価されていなかったのではないか、ということでした(「ミシュラン」の評価がすべてというわけではないでしょうが・・。)
こういうデータをみますと、やはり三ツ星レストランがどこか気になりますね。
「ミシュランガイド東京」が売れるわけです。

ところで昨日、「第12回静岡アジア・太平洋学術フォーラム」に参加してきました。このフォーラムは、実は静岡で開かれる国際会議としては超一流だと思っています。まず東京でもなかなかお目にかかれない、一流の学術関係者、評論家、経営者が一同に会して、アジア・太平洋の国際問題を語り合いディスカッションします。私は3年前の第10回から参加していますが、第10回、第11回、そして今回とも大満足。こんな上質の会議が無料で聞けるなんて。しかも誰でも参加できるんですよ。静岡県は相当がんばっていると思います。このフォーラムに関するお話はまた別途ご紹介します。非常に有意義なお話でしたので、ぜひとも皆さんにご紹介しようと思いますから、またの機会に、よろしかったら私のブログをごらんになってみてください。
さて、今日お話したいことは「ミシュランガイド東京」のことです。なぜ、「第12回静岡アジア・太平洋学術フォーラム」のお話をしたか、といいますと、その国際会議の中で、国際比較として「ミシュランガイド東京」のデータが紹介されました。
以下にご紹介します。
地名 一ツ星以上のレストランの数 三ツ星レストランの数
TOKYO 191 8
PARIS 97 10
NEWYORK 54 3
LONDON 50 1
SANFRANCISCO 42 1
ということで、東京の数はすごいですね。
東京の食のレベルはかなり高いといえるのかもしれません。
また、昨今の国際的な和食ブームと符合します。
ちなみに国際会議の中で中国の食についても触れていましたが、「ミシュラン」ではまったく評価されていなかったのではないか、ということでした(「ミシュラン」の評価がすべてというわけではないでしょうが・・。)
こういうデータをみますと、やはり三ツ星レストランがどこか気になりますね。
「ミシュランガイド東京」が売れるわけです。

富士掃除に学ぶ会
先日、「ピカ沼津」のお話をしましたが、そう言えば、すっかり忘れていましたが、10月27日(土)に町立長泉北中学校で、「富士掃除に学ぶ会」というのがあって、そちらにも参加していました。
こちらは、倫理法人会とは違って、元イエローハット社長の鍵山秀三郎さんの呼びかけからはじまった、「日本を美しくする会」が主催されている活動です。
さあ、掃除をするのですが、どこを掃除するのか、分かりますか?
もうご存知の方はよーくわかっていらっしゃると思いますが・・・・・そうですね。
トイレです。そして、この会は、トイレを素手で磨いていくんですね。もちろん、雑巾は必要ですが。
私も昔、ある研修に参加して、トイレを、3ヶ月間毎日素手で磨いておりました。トイレを素手で磨いていると、結構、いろいろなことに気づくんですね、汚れとともに。たとえば、どうやったら掃除を効率化できるだろうか、トイレの形状はこんな風になっているんだ、とか。
新しい発見があります。もちろん、自分自身の再発見も。
自分の意思の継続、行動力、克己心等々。
たかがトイレ掃除、されどトイレ掃除。日常の行動の先に、自己革新があります。不連続ではないんですね。当然のことですが、日常の連続が営みとなり、そして経営にも反映されてくる・・・・・・。
そして、「日本を美しくする会」で、よく言われていますが、こんな方もトイレ掃除をやってらっしゃるのですね。以下、引用です。
ということで、私は今はほとんどやっていませんので、「富士掃除に学ぶ会」に出かけたわけです。会には200人くらい参加されておりました。(遠くは九州とか東北から駆けつけてきている人もいました。)
長泉北中学校のトイレも結構汚れていましたが、皆で3時間集中して一心不乱になってやりました。
本当に見違えるように、きれいになりました。トイレとは思えないほどです。すごいですね。(本当は写真があればよーくわかるんでしょうけど、あいにく撮るのをまったく忘れてやっていました。)
終わったあとは、皆で弁当を食べて、見ず知らずの人たちが楽しく会話を交わします。
大変気持ちのいい体験をさせていただきました。また、会が開催されるときは、このブログでご案内を差し上げます。皆さんもよろしかったらご参加されてはいかがでしょうか?
追伸:「人んちのトイレを掃除するより自分んちのトイレや庭を掃除しろよ」という妻の罵声をあびながら・・・・ヾ(´▽`;)ゝ
こちらは、倫理法人会とは違って、元イエローハット社長の鍵山秀三郎さんの呼びかけからはじまった、「日本を美しくする会」が主催されている活動です。
さあ、掃除をするのですが、どこを掃除するのか、分かりますか?
もうご存知の方はよーくわかっていらっしゃると思いますが・・・・・そうですね。
トイレです。そして、この会は、トイレを素手で磨いていくんですね。もちろん、雑巾は必要ですが。
私も昔、ある研修に参加して、トイレを、3ヶ月間毎日素手で磨いておりました。トイレを素手で磨いていると、結構、いろいろなことに気づくんですね、汚れとともに。たとえば、どうやったら掃除を効率化できるだろうか、トイレの形状はこんな風になっているんだ、とか。
新しい発見があります。もちろん、自分自身の再発見も。
自分の意思の継続、行動力、克己心等々。
たかがトイレ掃除、されどトイレ掃除。日常の行動の先に、自己革新があります。不連続ではないんですね。当然のことですが、日常の連続が営みとなり、そして経営にも反映されてくる・・・・・・。
そして、「日本を美しくする会」で、よく言われていますが、こんな方もトイレ掃除をやってらっしゃるのですね。以下、引用です。
『実践した人だけが知っている!』
あるタレントがテレビでこう言っておられました。
自分は、くだらない番組をやっても視聴率があがる。自分では面白いと思わないのに、小説を書くと売れる。絵を描いても、いい絵だって評価されて、美術館だとかに収録されたりする。映画も自分の楽しみの一つとして創っていたら入賞してしまったり、グランプリで選ばれたりする。
自分としては好き勝手にやっているだけで、人よりも才能があるとは思えない。でも、何をやっても全部評価されてしまう。「おかしい」。よく考えてみても、自分の才能でそれらをやれるわけがない。ただ、心当たりは、たったひとつだけある。
それは、若いころ師匠に「トイレをきれいに掃除しろ。」と言われたから、三十年以上ずーっと掃除をやり続けてきた。ロケに行ったときなどは、公園のトイレがグチャグチャでも自分が使ったあとは、必ずきれいにする。ときには、隣のトイレまできれいにして出てくるときもある。もちろん、掃除用具をもって歩いているわけでもないので、トイレットペーパーがないトイレでは、素手でもやる、とのこと。
そういうのを三十年以上、ずーっとやり続けてきた。そこにだけ思い当たるふしがあるんだそうです。で、かれは今でもトイレ掃除をやり続けています。「自分は才能があるとは思わないのに、なぜかもてはやされる。何をやっても、それが評価を受けるのは、もしかしてトイレ掃除のせいかもしれない。」と言っていた。今のような話をテレビでたった一度しゃべった人がいます。
その人の名は、北野たけし、あのビートたけしさん、です。
ということで、私は今はほとんどやっていませんので、「富士掃除に学ぶ会」に出かけたわけです。会には200人くらい参加されておりました。(遠くは九州とか東北から駆けつけてきている人もいました。)
長泉北中学校のトイレも結構汚れていましたが、皆で3時間集中して一心不乱になってやりました。
本当に見違えるように、きれいになりました。トイレとは思えないほどです。すごいですね。(本当は写真があればよーくわかるんでしょうけど、あいにく撮るのをまったく忘れてやっていました。)
終わったあとは、皆で弁当を食べて、見ず知らずの人たちが楽しく会話を交わします。
大変気持ちのいい体験をさせていただきました。また、会が開催されるときは、このブログでご案内を差し上げます。皆さんもよろしかったらご参加されてはいかがでしょうか?
追伸:「人んちのトイレを掃除するより自分んちのトイレや庭を掃除しろよ」という妻の罵声をあびながら・・・・ヾ(´▽`;)ゝ
11月28日日経朝刊社説(観光振興について)
「よみがえれ地域経済」
社説「観光振興は「外からの目」を生かして
日本の地域経済は有力な資源を活用し切れていない。大都市にない豊かな自然や味わい深い文化であり、その有機的な結び付きが観光という産業の推進力となる。
北海道・釧路のさらに東に霧多布という国内三位の面積の湿原が広がる。ここで湿原保護と自然観察ツアーなどの活動をする特定非営利活動法人(NPO法人)、霧多布湿原トラストが今年、環境省のエコツーリズム大賞を受賞した。国土交通省からも地域づくりで表彰された。
自主的に収入再配分
霧多布の美しさに魅入られた東京の旅行者が勤め先を辞めて移住したのが始まりだ。若い猟師らとまちづくりに乗り出す。寄付を募り、民有の湿原を少しずつ買い上げた。今では修学旅行生や海外の自然愛好家を含め年間四十万人が訪れる。NPO法人の会員は約三千人に増えた。
行政の号令ではなく、主体になったのは普通の人々だ。そして発端は「よそ者」の目だった。
国内の観光は2005年度で二十四兆円と、国内総生産(GDP)の約5%にあたる一大産業だ。二百万人を超す雇用も生む。食や輸送など波及効果を含めると、市場規模は二倍を超す。ただし日本人の宿泊旅行の五五%、外国人旅行の七〇%が三大都市圏でおカネを落とす。
地方で観光を伸ばす余地は大いにある。都市の人たちが魅力ある地域で、楽しく、自主的に収入を再配分するのが観光の役割だ。税金という形でおカネだけが動くのと、どちらが望ましいか。明らかだろう。
北海道の倶知安は二年連続、住宅地の基準地価の上昇率が三割を超え日本一になった。パウダースノーという雪質の良さから豪州のスキー客が別荘を建て始めたからだ。富良野は脚本家の倉本聰氏、美瑛は写真家の前田真三氏と、新しい視点をきっかけに観光地へと変身した。
家庭に伝わる人形を展示し有名になった新潟県村上市。土塀や路地など伝統的な景観を復活させた長野県小布施。古民家を何軒も再生し、生活文化の伝承の場とし、世界遺産にもなった島根県の石見銀山。昭和三十年代の商店街を復活した大分県の豊後高田。いずれも外国人や大都市からのUターン組など、外からの目がうまく働いた。
対照的なのが、自治体と金融機関が主導し1990年代に各地に造られたテーマパークだ。第三セクターによる物まね施設で客は呼べない。
地域が個性を示すなら、「小京都」や「小銀座」を目指す必要はない。本土復帰ブームの後、いったん停滞した沖縄の人気が復活したのは「国内版ハワイ」を目指すことをやめ、テレビドラマなどを通じ、ゆったりと時間の流れる独自の生活文化が理解されたからだろう。北海道や東北は先住のアイヌ民族や縄文人の文化を掘り起こすことで、新たな観光客が足を運んでいる例もある。
インドネシアのバリ島では、棚田を望む高級ホテルが外国人の手で開発されリゾート地になった。日本では大分県の湯布院がこれに近い。
自治体や既存の観光業者は先例踏襲や横並びに陥りがちなので、支援に徹した方が良いだろう。案内業務や観光地図の作成は市町村ごとに手がけず、広域で協力すれば利用者に便利だし経費も削減できる。
外国人を待たせるな
日本を訪れる外国人が不便を感じないようにも、もっと努力したい。地方空港は出入国管理の職員や窓口が少ない。とくに国際定期便のない空港では、韓国、台湾などからの国際チャーター便の発着する観光シーズンには、出入国の長蛇の列ができる。心地よくはあるまい。
政府の観光立国推進基本計画では、全空港で待ち時間を二十分以下にするという目標を掲げている。ぜひ実現すべきであり、検疫、税関業務を含め人員配置を工夫し、地元の自治体職員の活用や権限委譲も検討すべきではないか。
今月発行の『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』の表紙を秋田県の田沢湖が飾った。本文中では近くの鶴の湯温泉の雪景色を「ただの温泉ではなくhitou(秘湯)」として詳しく紹介した。日本に目を向ける外国人の関心対象をいち早くつかみ、地方と協力し積極的に売り込むのも政府や関係機関の仕事だ。海外のテレビ放送網への印象的な広告やインターネットなどを使った情報発信ももっと充実すべきだろう。
競争相手は国内にとどまらない。中東、南アジアでは医療や美容、マカオではカジノを売り物に世界中から観光客を集める。これまでの常識にない案でも、まずやってみる。地方の観光の競争力を高めるには、そんなベンチャー精神が欠かせない。
以上です。この記事の中で「伊豆」が一言も触れられていないことに、大変な寂しさを感じます。もうそろそろ「伊豆」は目覚めなければならないのではないでしょうか?
社説「観光振興は「外からの目」を生かして
日本の地域経済は有力な資源を活用し切れていない。大都市にない豊かな自然や味わい深い文化であり、その有機的な結び付きが観光という産業の推進力となる。
北海道・釧路のさらに東に霧多布という国内三位の面積の湿原が広がる。ここで湿原保護と自然観察ツアーなどの活動をする特定非営利活動法人(NPO法人)、霧多布湿原トラストが今年、環境省のエコツーリズム大賞を受賞した。国土交通省からも地域づくりで表彰された。
自主的に収入再配分
霧多布の美しさに魅入られた東京の旅行者が勤め先を辞めて移住したのが始まりだ。若い猟師らとまちづくりに乗り出す。寄付を募り、民有の湿原を少しずつ買い上げた。今では修学旅行生や海外の自然愛好家を含め年間四十万人が訪れる。NPO法人の会員は約三千人に増えた。
行政の号令ではなく、主体になったのは普通の人々だ。そして発端は「よそ者」の目だった。
国内の観光は2005年度で二十四兆円と、国内総生産(GDP)の約5%にあたる一大産業だ。二百万人を超す雇用も生む。食や輸送など波及効果を含めると、市場規模は二倍を超す。ただし日本人の宿泊旅行の五五%、外国人旅行の七〇%が三大都市圏でおカネを落とす。
地方で観光を伸ばす余地は大いにある。都市の人たちが魅力ある地域で、楽しく、自主的に収入を再配分するのが観光の役割だ。税金という形でおカネだけが動くのと、どちらが望ましいか。明らかだろう。
北海道の倶知安は二年連続、住宅地の基準地価の上昇率が三割を超え日本一になった。パウダースノーという雪質の良さから豪州のスキー客が別荘を建て始めたからだ。富良野は脚本家の倉本聰氏、美瑛は写真家の前田真三氏と、新しい視点をきっかけに観光地へと変身した。
家庭に伝わる人形を展示し有名になった新潟県村上市。土塀や路地など伝統的な景観を復活させた長野県小布施。古民家を何軒も再生し、生活文化の伝承の場とし、世界遺産にもなった島根県の石見銀山。昭和三十年代の商店街を復活した大分県の豊後高田。いずれも外国人や大都市からのUターン組など、外からの目がうまく働いた。
対照的なのが、自治体と金融機関が主導し1990年代に各地に造られたテーマパークだ。第三セクターによる物まね施設で客は呼べない。
地域が個性を示すなら、「小京都」や「小銀座」を目指す必要はない。本土復帰ブームの後、いったん停滞した沖縄の人気が復活したのは「国内版ハワイ」を目指すことをやめ、テレビドラマなどを通じ、ゆったりと時間の流れる独自の生活文化が理解されたからだろう。北海道や東北は先住のアイヌ民族や縄文人の文化を掘り起こすことで、新たな観光客が足を運んでいる例もある。
インドネシアのバリ島では、棚田を望む高級ホテルが外国人の手で開発されリゾート地になった。日本では大分県の湯布院がこれに近い。
自治体や既存の観光業者は先例踏襲や横並びに陥りがちなので、支援に徹した方が良いだろう。案内業務や観光地図の作成は市町村ごとに手がけず、広域で協力すれば利用者に便利だし経費も削減できる。
外国人を待たせるな
日本を訪れる外国人が不便を感じないようにも、もっと努力したい。地方空港は出入国管理の職員や窓口が少ない。とくに国際定期便のない空港では、韓国、台湾などからの国際チャーター便の発着する観光シーズンには、出入国の長蛇の列ができる。心地よくはあるまい。
政府の観光立国推進基本計画では、全空港で待ち時間を二十分以下にするという目標を掲げている。ぜひ実現すべきであり、検疫、税関業務を含め人員配置を工夫し、地元の自治体職員の活用や権限委譲も検討すべきではないか。
今月発行の『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』の表紙を秋田県の田沢湖が飾った。本文中では近くの鶴の湯温泉の雪景色を「ただの温泉ではなくhitou(秘湯)」として詳しく紹介した。日本に目を向ける外国人の関心対象をいち早くつかみ、地方と協力し積極的に売り込むのも政府や関係機関の仕事だ。海外のテレビ放送網への印象的な広告やインターネットなどを使った情報発信ももっと充実すべきだろう。
競争相手は国内にとどまらない。中東、南アジアでは医療や美容、マカオではカジノを売り物に世界中から観光客を集める。これまでの常識にない案でも、まずやってみる。地方の観光の競争力を高めるには、そんなベンチャー精神が欠かせない。
以上です。この記事の中で「伊豆」が一言も触れられていないことに、大変な寂しさを感じます。もうそろそろ「伊豆」は目覚めなければならないのではないでしょうか?
椎間板ヘルニアの話
11月1日の私の記事に、腰痛のお話を載せておりました。
その際、腰痛の原因は、十二指腸潰瘍であり、ピロリ菌が見つかった話をしました。
ただ、どうもそれだけではなさそうだとも。
実はその後、すぐに整形外科に行き、腰痛の原因は、椎間板ヘルニアと診断されておりました。
皆さんの中でもやっている人いませんか?
結局、私の運動不足からきているんですよね。
椎間板ヘルニアを完治させるには、腹筋と背筋を鍛える以外にないということを、お医者様から言われました。
そして、その日以来、ほぼ1ヶ月ですが、毎日、腹筋と背筋を鍛えております。
11月1日の時には、歩くのままならなかったのですが、いまでは若干、左足を引きずるかなあくらいで、ほぼ元の状態に近づきました。
でもこうなってみるとありきたりの言葉で恐縮ですが、全てのことは体あってのことですね。
やはり日頃から体へのケアは入念にしておかないと、体は正直ですね。
皆さんも気をつけてくださいね。
腹筋・背筋も毎日鍛えていると、少しだけ引き締まってきたような・・・・気のせいかな?
では。
その際、腰痛の原因は、十二指腸潰瘍であり、ピロリ菌が見つかった話をしました。
ただ、どうもそれだけではなさそうだとも。
実はその後、すぐに整形外科に行き、腰痛の原因は、椎間板ヘルニアと診断されておりました。
皆さんの中でもやっている人いませんか?
結局、私の運動不足からきているんですよね。
椎間板ヘルニアを完治させるには、腹筋と背筋を鍛える以外にないということを、お医者様から言われました。
そして、その日以来、ほぼ1ヶ月ですが、毎日、腹筋と背筋を鍛えております。
11月1日の時には、歩くのままならなかったのですが、いまでは若干、左足を引きずるかなあくらいで、ほぼ元の状態に近づきました。
でもこうなってみるとありきたりの言葉で恐縮ですが、全てのことは体あってのことですね。
やはり日頃から体へのケアは入念にしておかないと、体は正直ですね。
皆さんも気をつけてくださいね。
腹筋・背筋も毎日鍛えていると、少しだけ引き締まってきたような・・・・気のせいかな?
では。
伊豆の観光について(私見)
前回の記事の続きですが、要するになぜ伊豆がないのかな?という素朴な疑問なんですね、私の違和感は。
「古湯」というカテゴリーがあり、特殊なのかもしれない、という思いもあるのですが、でもどうも釈然としないなあ、と思うわけです。箱根はランキングされていても伊豆はない。これはいったいどうしたことか。
伊豆だってかなり古くから温泉地として栄えていたわけで、熱海まで加えればこれは相当長い歴史があるはず・・・・。
が、どうしてか?
kiyoさんの記事のコメントにも書かせていただいたのですが、私は結局、伊豆のブランド化に失敗しているんだと思います。もっと言えば、伊豆は観光地として、ブランドにもなっていないのではないか。このことは8月30日の私の記事にも書きました。
伊豆は一つではありません。
私はこの地の観光振興を伊豆全域で、と考えた時点で、結局、どの施策も中途半端なものになってしまうと思います。
伊豆をブランド化するには、広すぎます。(もちろん、広域連携は十分にありえます。)
また、観光振興を行うには、その地がもっている、他の地にはない価値を際立たせていくことが、もっとも大事ではないか、と思います。
その点で、伊豆を眺めると、残念ながらこの地は、中途半端に東京に近かったことが、逆に大きなマイナス面になっていたのではないか、と思っています。
伊豆にとって、東京は大市場です。それは過去数十年をみれば、陰りをみせているとはいえ、今もなお大得意さんです。したがって東京を無視して伊豆観光は成立しません。これは当然のことです。
しかしながら、この事実が、現実が、伊豆(というか伊豆の各地域という意味合いで使っています)本来の、他地域にない価値創造の動きを阻んでいるのではないか、と思えてなりません。
では、伊豆本来の価値って、いったい何だろうか?
この問いにすぐに答えられないとすれば、これは大変大きな問題がそこに潜んでいるということになります。
実はこの問いがもっとも重要です。たとえば、伊豆が東京からこれほど近くに存在しなければ、果たして旅行客は訪れるでしょうか?
伊豆は東京の近くにあって交通の便がいいので・・・・・というのでは、そのお客様は真の意味で、「伊豆に訪れたくて来ている」というわけではないことになります。はたして?
かつて、「じゃらん」さんが持っている観光のマーケティングデータを見せてもらいました。
伊豆にくる観光客が、伊豆に求めているもの。
それは「癒し」であり「おいしい食べ物」であります。また、伊豆にくる観光客が、伊豆に落としていく一人当たりの金額は、2万円~3万円で、旅館・ホテルでの宿泊・食事以外には、数千円しかありません。これは他の観光地に比べて遥かに低い金額です。
皆さん、このデータの持つ意味がわかりますでしょうか?
「癒し」「おいしい食べ物」は伊豆に来なくても得られます。すなわち、このデータは「伊豆の代用」は十分他にある、ということを示しているのではないでしょうか。
これが、現時点での伊豆の置かれた、まぎれもない現実です。
すなわち、東京近郊であることからかろうじて観光地として成立している伊豆の姿を、そこにみます。
今まで、東京近郊であったがために、本来やらなければならなかった「伊豆本来の価値創造」の営みをなおざりにしてきたつけが、ここに回ってきています。
さて、そろそろ、皆さん、伊豆を心底愛している皆さんは、自分たちの地域に根ざしたものをベースに、新しい価値を創造する時期にきているのではないでしょうか?
まずは、自分たちが立脚しているこの地(地域だけでなく、自分の旅館・ホテルでもよいのです)が、他の地域にない魅力を、どんなことでもよいので、書き出してみることです。そして、その書き出したもので、この地域の方々が情報交換し、次第に共通的な価値観を醸成させ、その価値観を新しい視点(外部の視点、もっと言えば伊豆の外の人間の視点)で見返すことです。
そして、そこからブランド化のための戦略を立てていきます。
こういった自分たちの立脚点を明らかにし、新たな発見と創造の歩みがなく、ブランド化というのはありえませんので、まずはここから、ということ。
当然、ブログもこの歩みと寄り添いながら進めていくことになります。
まったく、観光の専門家でもない私がこんなことを言うのは失礼千万であると思いつつも、どうも昨今、この地の観光の方々とお話していると、もっとどうにかならないのかなあ、という思いが募り書いてしまった次第です。関係者の方、ごめんなさい。あくまでも私見ですので、気分を害した方はすみません。m( __ __ )m
この件に関して、皆さんのご意見はいかがでしょうか?
非難でも批判でも、どうぞご遠慮なくコメントにご記入ください。私の議論はかなり稚拙だと思いますので、皆さんにご指導賜りたいと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

「古湯」というカテゴリーがあり、特殊なのかもしれない、という思いもあるのですが、でもどうも釈然としないなあ、と思うわけです。箱根はランキングされていても伊豆はない。これはいったいどうしたことか。
伊豆だってかなり古くから温泉地として栄えていたわけで、熱海まで加えればこれは相当長い歴史があるはず・・・・。
が、どうしてか?
kiyoさんの記事のコメントにも書かせていただいたのですが、私は結局、伊豆のブランド化に失敗しているんだと思います。もっと言えば、伊豆は観光地として、ブランドにもなっていないのではないか。このことは8月30日の私の記事にも書きました。
伊豆は一つではありません。
私はこの地の観光振興を伊豆全域で、と考えた時点で、結局、どの施策も中途半端なものになってしまうと思います。
伊豆をブランド化するには、広すぎます。(もちろん、広域連携は十分にありえます。)
また、観光振興を行うには、その地がもっている、他の地にはない価値を際立たせていくことが、もっとも大事ではないか、と思います。
その点で、伊豆を眺めると、残念ながらこの地は、中途半端に東京に近かったことが、逆に大きなマイナス面になっていたのではないか、と思っています。
伊豆にとって、東京は大市場です。それは過去数十年をみれば、陰りをみせているとはいえ、今もなお大得意さんです。したがって東京を無視して伊豆観光は成立しません。これは当然のことです。
しかしながら、この事実が、現実が、伊豆(というか伊豆の各地域という意味合いで使っています)本来の、他地域にない価値創造の動きを阻んでいるのではないか、と思えてなりません。
では、伊豆本来の価値って、いったい何だろうか?
この問いにすぐに答えられないとすれば、これは大変大きな問題がそこに潜んでいるということになります。
実はこの問いがもっとも重要です。たとえば、伊豆が東京からこれほど近くに存在しなければ、果たして旅行客は訪れるでしょうか?
伊豆は東京の近くにあって交通の便がいいので・・・・・というのでは、そのお客様は真の意味で、「伊豆に訪れたくて来ている」というわけではないことになります。はたして?
かつて、「じゃらん」さんが持っている観光のマーケティングデータを見せてもらいました。
伊豆にくる観光客が、伊豆に求めているもの。
それは「癒し」であり「おいしい食べ物」であります。また、伊豆にくる観光客が、伊豆に落としていく一人当たりの金額は、2万円~3万円で、旅館・ホテルでの宿泊・食事以外には、数千円しかありません。これは他の観光地に比べて遥かに低い金額です。
皆さん、このデータの持つ意味がわかりますでしょうか?
「癒し」「おいしい食べ物」は伊豆に来なくても得られます。すなわち、このデータは「伊豆の代用」は十分他にある、ということを示しているのではないでしょうか。
これが、現時点での伊豆の置かれた、まぎれもない現実です。
すなわち、東京近郊であることからかろうじて観光地として成立している伊豆の姿を、そこにみます。
今まで、東京近郊であったがために、本来やらなければならなかった「伊豆本来の価値創造」の営みをなおざりにしてきたつけが、ここに回ってきています。
さて、そろそろ、皆さん、伊豆を心底愛している皆さんは、自分たちの地域に根ざしたものをベースに、新しい価値を創造する時期にきているのではないでしょうか?
まずは、自分たちが立脚しているこの地(地域だけでなく、自分の旅館・ホテルでもよいのです)が、他の地域にない魅力を、どんなことでもよいので、書き出してみることです。そして、その書き出したもので、この地域の方々が情報交換し、次第に共通的な価値観を醸成させ、その価値観を新しい視点(外部の視点、もっと言えば伊豆の外の人間の視点)で見返すことです。
そして、そこからブランド化のための戦略を立てていきます。
こういった自分たちの立脚点を明らかにし、新たな発見と創造の歩みがなく、ブランド化というのはありえませんので、まずはここから、ということ。
当然、ブログもこの歩みと寄り添いながら進めていくことになります。
まったく、観光の専門家でもない私がこんなことを言うのは失礼千万であると思いつつも、どうも昨今、この地の観光の方々とお話していると、もっとどうにかならないのかなあ、という思いが募り書いてしまった次第です。関係者の方、ごめんなさい。あくまでも私見ですので、気分を害した方はすみません。m( __ __ )m
この件に関して、皆さんのご意見はいかがでしょうか?
非難でも批判でも、どうぞご遠慮なくコメントにご記入ください。私の議論はかなり稚拙だと思いますので、皆さんにご指導賜りたいと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

行ってみたい古湯ランキング
昨日の日経新聞のNIKKEIプラス1から。
1面の「何でもランキング」はいつも楽しみに見ているのですが、今回は、「行ってみたい古湯ランキング」でした。
中・小規模温泉の部では、
第7位 別所温泉(長野県上田市) 111票
国宝の安楽寺八角三重塔など、古くから仏教や学問が盛んだった地域にわく。単純硫黄泉など
第6位 三朝(みさき)温泉(鳥取県三朝町) 174票
白狼により発見されたとの言い伝え。温泉街を流れる川の河原に露天風呂がある。放射能泉など
第5位 野沢温泉(長野県野沢温泉村) 177票
江戸初期からにぎわう古湯。源泉の数が多く、地元の人は野沢菜などを温泉でゆがく。硫黄泉など
第4位 大鰐(おおわに)温泉(青森県大鰐町) 213票
青森県の南部にあり、温泉の熱で栽培する温泉モヤシが有名。含石こう食塩泉など
これよりナンバー3の発表です。
第3位 ジャジャン!
嬉野温泉(佐賀県嬉野市) 234票
「美肌の湯」として女性に人気の含食塩重曹泉の温泉。名物の温泉湯豆腐はとろけるように軟らかい。
続いて第2位 ババーン!(ちょっと擬音語がダサイo(*^▽^*)o)
雲仙温泉(長崎県雲仙市) 246票
島原半島の中央、雲仙岳の中腹にある。夏でも涼しく、避暑地として早くから開けた。硫黄泉など
そして、そして・・・・・第1位 ・・・・・(うーん擬音語がみつからない ダッセー(◎_◎) ン?
蔵王温泉(山形市) 363票
ウィンターリゾート地としても有名な温泉。古くからの共同浴場が残る。含硫化水素強酸性明ばん泉など
さて、次は大規模温泉の部です。
第7位 箱根温泉郷(神奈川県箱根町) 315票
いわずと知れた箱根です。地域ごとに異なる種類の温泉を楽しめ、江戸時代から温泉客でにぎわった。アルカリ性単純泉など
第6位 有馬温泉(神戸市) 327票
坂の多い町にわく。近年、豊臣秀吉が造らせたとみられる岩風呂の遺構が発見された。含鉄強食塩泉など
第5位 下呂温泉(岐阜県下呂市) 396票
白鷺により発見されたとの言い伝え。飛騨川の河原に露天風呂あり。アルカリ性単純泉など
第4位 霧島温泉郷(鹿児島県霧島市) 447票
霧島連山の中腹にある温泉群。坂本竜馬、与謝野鉄幹などが訪れた。単純硫黄泉など
さあ、これよりナンバー3!!
第3位 道後温泉(松山市) 462票
夏目漱石の「坊ちゃん」の舞台として知られ、浴場で鳴らす太鼓が時を告げる。アリカリ性単純泉など
では、第2位 ジャン!(う、短い(! ──__──) )
別府温泉(大分県別府市) 675票
繁華街の中に共同浴場が混在する。明治時代以降に全国的に有名になった。重炭酸土類泉など
そしてそして、栄えある第1位!!!!(パンパカ・・・やめとこ・・・・・・・( ̄  ̄) )
草津温泉(群馬県草津市) 678票
もう別府と草津は解説の必要がない、とは思いますが・・・一応。
温泉街の湯畑が湯を噴き上げる。ここから江戸へ湯が運ばれた。含硫化水素強酸性明ばん緑ばん泉など
ということで、「行ってみたい古湯ランキング」、いかがでしたでしょうか?
皆さんも行ってみたいところありますか?という具合に終わりたいのですが、なんだか物足りないんですねーーーウーン (Θ_Θ;)
何か足りない想いがあるのは私だけでしょうか?
何か忘れられている気がして仕方ないのは私だけでしょうか?
ということで、少し心残りがある方は、この続きの記事を書きますので、そちらをご覧ください。
ではまた。

1面の「何でもランキング」はいつも楽しみに見ているのですが、今回は、「行ってみたい古湯ランキング」でした。
中・小規模温泉の部では、
第7位 別所温泉(長野県上田市) 111票
国宝の安楽寺八角三重塔など、古くから仏教や学問が盛んだった地域にわく。単純硫黄泉など
第6位 三朝(みさき)温泉(鳥取県三朝町) 174票
白狼により発見されたとの言い伝え。温泉街を流れる川の河原に露天風呂がある。放射能泉など
第5位 野沢温泉(長野県野沢温泉村) 177票
江戸初期からにぎわう古湯。源泉の数が多く、地元の人は野沢菜などを温泉でゆがく。硫黄泉など
第4位 大鰐(おおわに)温泉(青森県大鰐町) 213票
青森県の南部にあり、温泉の熱で栽培する温泉モヤシが有名。含石こう食塩泉など
これよりナンバー3の発表です。
第3位 ジャジャン!
嬉野温泉(佐賀県嬉野市) 234票
「美肌の湯」として女性に人気の含食塩重曹泉の温泉。名物の温泉湯豆腐はとろけるように軟らかい。
続いて第2位 ババーン!(ちょっと擬音語がダサイo(*^▽^*)o)
雲仙温泉(長崎県雲仙市) 246票
島原半島の中央、雲仙岳の中腹にある。夏でも涼しく、避暑地として早くから開けた。硫黄泉など
そして、そして・・・・・第1位 ・・・・・(うーん擬音語がみつからない ダッセー(◎_◎) ン?
蔵王温泉(山形市) 363票
ウィンターリゾート地としても有名な温泉。古くからの共同浴場が残る。含硫化水素強酸性明ばん泉など
さて、次は大規模温泉の部です。
第7位 箱根温泉郷(神奈川県箱根町) 315票
いわずと知れた箱根です。地域ごとに異なる種類の温泉を楽しめ、江戸時代から温泉客でにぎわった。アルカリ性単純泉など
第6位 有馬温泉(神戸市) 327票
坂の多い町にわく。近年、豊臣秀吉が造らせたとみられる岩風呂の遺構が発見された。含鉄強食塩泉など
第5位 下呂温泉(岐阜県下呂市) 396票
白鷺により発見されたとの言い伝え。飛騨川の河原に露天風呂あり。アルカリ性単純泉など
第4位 霧島温泉郷(鹿児島県霧島市) 447票
霧島連山の中腹にある温泉群。坂本竜馬、与謝野鉄幹などが訪れた。単純硫黄泉など
さあ、これよりナンバー3!!
第3位 道後温泉(松山市) 462票
夏目漱石の「坊ちゃん」の舞台として知られ、浴場で鳴らす太鼓が時を告げる。アリカリ性単純泉など
では、第2位 ジャン!(う、短い(! ──__──) )
別府温泉(大分県別府市) 675票
繁華街の中に共同浴場が混在する。明治時代以降に全国的に有名になった。重炭酸土類泉など
そしてそして、栄えある第1位!!!!(パンパカ・・・やめとこ・・・・・・・( ̄  ̄) )
草津温泉(群馬県草津市) 678票
もう別府と草津は解説の必要がない、とは思いますが・・・一応。
温泉街の湯畑が湯を噴き上げる。ここから江戸へ湯が運ばれた。含硫化水素強酸性明ばん緑ばん泉など
ということで、「行ってみたい古湯ランキング」、いかがでしたでしょうか?
皆さんも行ってみたいところありますか?という具合に終わりたいのですが、なんだか物足りないんですねーーーウーン (Θ_Θ;)
何か足りない想いがあるのは私だけでしょうか?
何か忘れられている気がして仕方ないのは私だけでしょうか?
ということで、少し心残りがある方は、この続きの記事を書きますので、そちらをご覧ください。
ではまた。
旅館の再生「女将力」がカギ
かなり前の日経新聞です。以前に書いた「菊屋」さんの記事も参考にしていただくと面白いかもしれません。
『女将になって今年で29年目の三宅美佐子さんは、旅館業界では知る人ぞ知る再建請負人。嫁いだ兵庫県・城崎温泉の旅館経営を立て直し、その手腕を買われて山口県の温泉などにも転戦、V字回復させた実績がある。
今は旅館やホテルの運営受託会社、女将塾(東京・豊島)で「大女将」のポストにあり、女将を志す若手の指導にあたりながら、彼女たちとチームを組んで旅館の経営刷新に取り組んでいる。
最近、活動の舞台にしているのが静岡県伊豆だ。買収や土地建物の長期賃借契約で温泉旅館経営を拡大中の共立メンテナンスに請われ、まず修善寺の老舗旅館「菊屋」でサービスやコストを改善。7月から伊東市の「米屋」に移った。
チームの陣容は三宅さんのほか、女将の佐野綾子さんら二十から三十歳代の6人。
「6ヶ月たつと(前からいる)従業員に情が移り、改革の障害になる」。
これまでの経験から三宅さんは、「改革は三ヶ月でやり遂げなければならない」が持論。菊屋の立て直しも三ヶ月でめどをつけ、米屋でもスピードを重視、「チーム三宅」は矢継ぎ早に手を打っている。
宿に着いた客にお茶を立ててもてなすカウンターと帳場の間を戸がふさぎ、人が行き来しにくかったので、迷わずぶち抜いた。製造現場の改革と同様、人の動線をスムーズにして生産性を高めるためだ。従業員が急に休むなど出勤日や勤務時間の管理にずさんな面があったため、人員シフト(交替)などの計画は女将が掌握、厳格に管理するようにした。
在庫管理も徹底。冷蔵庫のなかに古い牛乳が客に出せないまま眠っていることに三宅さんは驚いた。自動車工場の「ジャスト・イン・タイム」のように、食材や備品は数量を常時点検、必要なだけ調達するシステムに改めた。
こうした「チーム三宅」の改革を一言で言えば、限りある経営資源を最大限、有効に活用するということだ。ヒトの使い方やモノ(在庫)の無駄を排し、人件費や材料購入などのお金をできるだけ効率的に使う。
山口県・湯田温泉の「ホテル松政」など三宅さんが結果をだしてきた旅館の立て直しはいずれも、資源の最適配分を目指した業務改革が基本になっている。
「経営が悪化した旅館は原因が共通している。旅館経営のプロであるはずの女将にその力がなく、改革のけん引役がいないため」と三宅さんはいう。伊豆で不振旅館が目立つのも、景気低迷が続いて客数が減ったことが第一の理由ではないという。
「旅館は土地建物の資産を守ろうと身内に継がせるが、嫁に女将としての実力がない場合が多い。所有と経営を分離し、マネジメントができる人材を女将に起用すべき」。
現場での実践を通じて旅館経営のプロを養成する女将塾の設立は、女将を職業として確立することが狙いだった。
接客をはじめ旅館の仕事に「マニュアルはない」。一人前の女将になるには客の様子を見ながら的確に状況を判断、今すべきことを自ら考え出す訓練が欠かせないという。米屋で三宅さんは夕方五時半には帰るようにしている。引き連れてきたチームの面々に、「自分の頭で考えさせる」ためだ。
女将塾の塾生は現在二十人。女将に育て上げたのは三人で、当面、「十人に増やしたい」という。
兵庫・城崎を振り出しに各地の旅館をてこ入れしてきたが、「そろそろ一箇所に定着したい」と三宅さん。伊豆は有力な候補地という。女将の供給源が地域にできれば、伊豆の旅館にとって強力な援軍になるかもしれない。』
いかがでしょうか?
参考になる方は多いのでは。
女将がどんどん経営のプロとしてパワーアップし、そしてその美にさらに磨きがかかることになれば、われわれ男性軍としては旅の魅力がさらに増すわけですから大歓迎ですね。
また、弊社も女将にとっての援軍になれれば、と思っております。
ということで・・・・・女将さん、時間ですよ・・・・ちょっと古いかo(*^▽^*)oエヘヘ!分からない人はわからないだろうなあ、ではまた。これまでーよー。く、くどい(-_-メ;)

『女将になって今年で29年目の三宅美佐子さんは、旅館業界では知る人ぞ知る再建請負人。嫁いだ兵庫県・城崎温泉の旅館経営を立て直し、その手腕を買われて山口県の温泉などにも転戦、V字回復させた実績がある。
今は旅館やホテルの運営受託会社、女将塾(東京・豊島)で「大女将」のポストにあり、女将を志す若手の指導にあたりながら、彼女たちとチームを組んで旅館の経営刷新に取り組んでいる。
最近、活動の舞台にしているのが静岡県伊豆だ。買収や土地建物の長期賃借契約で温泉旅館経営を拡大中の共立メンテナンスに請われ、まず修善寺の老舗旅館「菊屋」でサービスやコストを改善。7月から伊東市の「米屋」に移った。
チームの陣容は三宅さんのほか、女将の佐野綾子さんら二十から三十歳代の6人。
「6ヶ月たつと(前からいる)従業員に情が移り、改革の障害になる」。
これまでの経験から三宅さんは、「改革は三ヶ月でやり遂げなければならない」が持論。菊屋の立て直しも三ヶ月でめどをつけ、米屋でもスピードを重視、「チーム三宅」は矢継ぎ早に手を打っている。
宿に着いた客にお茶を立ててもてなすカウンターと帳場の間を戸がふさぎ、人が行き来しにくかったので、迷わずぶち抜いた。製造現場の改革と同様、人の動線をスムーズにして生産性を高めるためだ。従業員が急に休むなど出勤日や勤務時間の管理にずさんな面があったため、人員シフト(交替)などの計画は女将が掌握、厳格に管理するようにした。
在庫管理も徹底。冷蔵庫のなかに古い牛乳が客に出せないまま眠っていることに三宅さんは驚いた。自動車工場の「ジャスト・イン・タイム」のように、食材や備品は数量を常時点検、必要なだけ調達するシステムに改めた。
こうした「チーム三宅」の改革を一言で言えば、限りある経営資源を最大限、有効に活用するということだ。ヒトの使い方やモノ(在庫)の無駄を排し、人件費や材料購入などのお金をできるだけ効率的に使う。
山口県・湯田温泉の「ホテル松政」など三宅さんが結果をだしてきた旅館の立て直しはいずれも、資源の最適配分を目指した業務改革が基本になっている。
「経営が悪化した旅館は原因が共通している。旅館経営のプロであるはずの女将にその力がなく、改革のけん引役がいないため」と三宅さんはいう。伊豆で不振旅館が目立つのも、景気低迷が続いて客数が減ったことが第一の理由ではないという。
「旅館は土地建物の資産を守ろうと身内に継がせるが、嫁に女将としての実力がない場合が多い。所有と経営を分離し、マネジメントができる人材を女将に起用すべき」。
現場での実践を通じて旅館経営のプロを養成する女将塾の設立は、女将を職業として確立することが狙いだった。
接客をはじめ旅館の仕事に「マニュアルはない」。一人前の女将になるには客の様子を見ながら的確に状況を判断、今すべきことを自ら考え出す訓練が欠かせないという。米屋で三宅さんは夕方五時半には帰るようにしている。引き連れてきたチームの面々に、「自分の頭で考えさせる」ためだ。
女将塾の塾生は現在二十人。女将に育て上げたのは三人で、当面、「十人に増やしたい」という。
兵庫・城崎を振り出しに各地の旅館をてこ入れしてきたが、「そろそろ一箇所に定着したい」と三宅さん。伊豆は有力な候補地という。女将の供給源が地域にできれば、伊豆の旅館にとって強力な援軍になるかもしれない。』
いかがでしょうか?
参考になる方は多いのでは。
女将がどんどん経営のプロとしてパワーアップし、そしてその美にさらに磨きがかかることになれば、われわれ男性軍としては旅の魅力がさらに増すわけですから大歓迎ですね。
また、弊社も女将にとっての援軍になれれば、と思っております。
ということで・・・・・女将さん、時間ですよ・・・・ちょっと古いかo(*^▽^*)oエヘヘ!分からない人はわからないだろうなあ、ではまた。これまでーよー。く、くどい(-_-メ;)
伊豆マラソンの話があまりにも少ないですね
漂琉者@所長さんのブログでは、結構掲載されていましたが、他のブログではあまり掲載されていませんね。
かくいう私も当日はずっと仕事で見ていなかったのですが。
でもこのイベントはかなり伊豆の活性化には寄与するのではないでしょうか?
「夢は下田へ」ということなので、うまく成長していき、そのうち伊豆を縦貫するマラソンになれば面白いですねえ。
ぜひ、イーラとしても応援していきませんか? ね☆^ヽ(-。・)ゝ
かくいう私も当日はずっと仕事で見ていなかったのですが。
でもこのイベントはかなり伊豆の活性化には寄与するのではないでしょうか?
「夢は下田へ」ということなので、うまく成長していき、そのうち伊豆を縦貫するマラソンになれば面白いですねえ。
ぜひ、イーラとしても応援していきませんか? ね☆^ヽ(-。・)ゝ